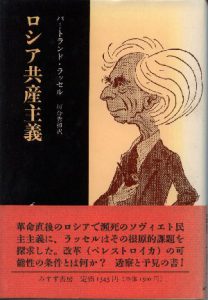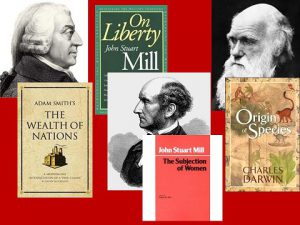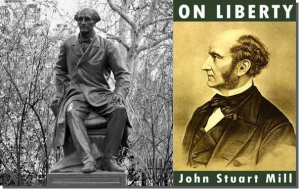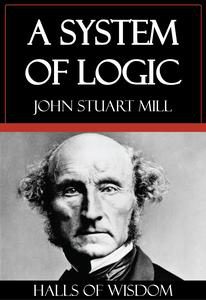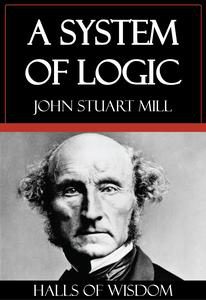 ミルの最初の重要な著作は,『論理学』である。それはアプリオリな方法ではなく,実験的な方法に対する弁明(抗弁)として執筆されたことは明らかであり,そうして,そのようなものとしてはそれほど独創的なものではないが有用なものであった。彼は,1854年に出版されたブール(著)『思考の法則』に始まった演繹論理の広大かつ驚くべき発展を予知できず,その重要性はかなり後になって明らかになったのである。彼が『論理学』のなかで帰納推理以外のことについて言っていることは,御座なりかつ伝統的なもの(従来の論理学に従ったもの)である。たとえば,命題は,一つは主語でもう一つは述語である名辞を組合せることによって構成される(作られる),と述べている。彼にとってこれは無害な自明の理にみえたのだと思われるが,実際は,これは過去二千年間続いた誤謬のもと(源泉)であった。
ミルの最初の重要な著作は,『論理学』である。それはアプリオリな方法ではなく,実験的な方法に対する弁明(抗弁)として執筆されたことは明らかであり,そうして,そのようなものとしてはそれほど独創的なものではないが有用なものであった。彼は,1854年に出版されたブール(著)『思考の法則』に始まった演繹論理の広大かつ驚くべき発展を予知できず,その重要性はかなり後になって明らかになったのである。彼が『論理学』のなかで帰納推理以外のことについて言っていることは,御座なりかつ伝統的なもの(従来の論理学に従ったもの)である。たとえば,命題は,一つは主語でもう一つは述語である名辞を組合せることによって構成される(作られる),と述べている。彼にとってこれは無害な自明の理にみえたのだと思われるが,実際は,これは過去二千年間続いた誤謬のもと(源泉)であった。
近代論理学が大いに関心を払ってきた名辞について彼が言っていることは,まったく不十分なものであり,事実,ドン・スコトゥス(Johannes Duns Scotus 1266-1308:中世ヨーロッパの神学者・哲学者)やウィリアム・オッカム(William of Ockham,1285-1347:節約の原理「オッカムの剃刀」の提唱者として有名)が言ったことよりも劣っている。バルバラ(Barbara)における三段論法は,一種の論点先取(注:前提において結論を仮定する論理的な誤り)であり,推論は実際は特称(特殊)から特称(特殊)へと行われているのだという彼の有名な主張(議論)は,一定の場合においてはいくらか真実を含んでいるが,一般的原理として受け入れることはできない【注:Barbara: 大前提:「全ての人間」は,「死ぬ存在」である。 (MaP) → 小前提:「全てのギリシア人」は,「人間」である。(SaM) → 結論:ゆえに(∴)「全てのギリシア人」は,「死ぬ存在」である。(SaP)】。たとえば,ミルの主張によれば,「あらゆる人間は死ぬ(べき存在である)」という命題は,その主張をする人がウェリントン公爵について聞いたことがなくても,「ウェリントン公爵は死ぬ(べき存在である)」を主張している。これは明らかに成り立たない。即ち,「人間」及び「死ぬ」という語の意味を知っている人は,「あらゆる人間は死ぬ」という陳述を理解できるが,聞いたことのない人についての推論をすることはできない。一方(しかるに),ウェリントン公爵について,ミルの言っていることが正しいと仮定すると,かつて生存し,あるいはこれから生存するだろうあらゆる人びとの一覧表を知らなければ(注:一覧表を持っていて,いざとなれば見ることが出来なければ),この陳述を理解することはできないことになる(注:ウェリントン公爵のことを知らなくても,「あらゆる人間は死ぬ(べき存在である)」と言えるためには,あらゆる人のリストを持っていなければならない。そういう場合に限り,ウェリントン公爵について知らなくとも,「ウェリントン公爵は死ぬ」と言える。実際はそんなことはないので,そういった「推論」は論理的にはできない。)。
推論は,特称(特殊)から特称(特殊)へとなされるものだという彼の(学)説は,私の言うところの「動物的帰納」に適用される場合には正しい心理学であるが,決して正しい論理学ではない。過去における人間の死から,まだ死んでいない人間の死を推論することは,帰納の一般的原理がある場合にのみ正当なものとなる。大雑把に言って,一般的な結論は一般的な前提がなければ決して引き出し得ないし,一般的前提のみが,事例の不完全な枚挙からの一般的結論を保証するだろう。
さらに,事例はひとつも与えられなくても,誰もその真理を疑うことのできない一般的命題が存在する。たとえば,次のような命題である。「西暦紀元二千年以前(注:この文章は1955年に発表されていることに注意)には誰も考えつかなかったすべての数は百万よりも大きい」という例をとろう。あなたは自己矛盾をおこさないで,その事例(注:考えつかなかった数)を与えることができないし,そのすべての数が誰かによって考えられたと言いはることもできない。
ロックの時代からずっと,英国の経験主義者たちは,数学に適用(応用)できない知識論をもっていた。一方,大陸の哲学者たちは,フランスの哲学者たちを例外として,数学に不当な強調点をおき,幻想的な形而上学の体系(体系的な哲学)を産みだしていた。経験主義の領域が,数学と論理学の領域からはっきりと切りはなされ(境界が設けられ),両者の平和的共存が可能となったのはミルの時代以後(になってのみ)のことである。
私は18歳の年にはじめて,ミルの『論理学』を読んだが,当時私は彼の考えに深い好意を寄せていた。しかし,その時でさえも,「2と2を加えると4になる」という命題を受け入れるのは経験からの一般化であると信ずることは出来なかった。私は,どのようにして我々がこの知識(2+2=4などの算術の知識)に達したのか,どう言ったらよいか途方に暮れた。しかし,その命題は,「あらゆる白鳥は白い(all swans are white)」というような命題 -経験が論破するかもしれないし,また事実論破した命題(注: black swan が発見された)- とは異なっていると思われた。2に2を加えると4になるというような新鮮な例がいかなる程度にも私の信念を強めるとは思えなかったが,私にこのような初期の感情を正当化し,数学と経験的知識をひとつの枠組みにぴったりはめ込むことを可能にしたのは,数理論理学の最近の発展だけである。
Mill’s first important book was his Logic, which no doubt presented itself in his mind as a plea for experimental rather than a priori methods, and, as such, it was useful though not very original. He could not foresee the immense and surprising development of deductive logic which began with Boole’s Laws of Thought in 1854, but only proved its importance at a considerably later date. Everything that Mill has to say in his Logic about matters other than inductive inference is perfunctory and conventional. He states, for example, that propositions are formed by putting together two names, one of which is the subject and the other the predicate. This, I am sure, appeared to him an innocuous truism; but it had been, in fact, the source of two thousand years of important error. On the subject of names, with which modern logic has been much concerned, what he has to say is totally inadequate, and is, in fact, not so good as what had been said by Duns Scotus and William of Occam. His famous contention that the syllogism in Barbara is a petitio principii, and that the argument is really from particulars to particulars, has a measure of truth in certain cases, but cannot be accepted as a general doctrine. He maintains, for example, that the proposition “all men are mortal” asserts “the Duke of Wellington is mortal” even if the person making the assertion has never heard of the Duke of Wellington. This is obviously untenable: a person who knows the meaning of the words “man” and “mortal” can understand the statement “all men are mortal” but can make no inference about a man he has never heard of; whereas, if Mill were right about the Duke of Wellington, a man could not understand this statement unless he knew the catalogue of all the men who ever have existed or ever will exist. His doctrine that inference is from particulars to particulars is correct psychology when applied to what I call “animal induction,” but is never correct logic. To infer, from the mortality of men in the past, the mortality of those not yet dead, can only be legitimate if there is a general principle of induction. Broadly speaking, no general conclusion can be drawn without a general premise, and only a general premise will warrant a general conclusion from an incomplete enumeration of instances. What is more, there are general propositions of which no one can doubt the truth, although not a single instance of them can be given. Take, for example, the following: “All the whole numbers which no one will have thought of before the year A.D. 2000, are greater than a million.” You cannot attempt to give me an instance without contradicting yourself, and you cannot pretend that all the whole numbers have been thought of by someone. From the time of Locke onward, British empiricists had had theories of knowledge which were inapplicable to mathematics; while Continental philosophers, with the exception of the French Philosophes, by an undue emphasis upon mathematics, had produced fantastic metaphysical systems. It was only after Mill’s time that the sphere of empiricism was clearly delimited from that of mathematics and logic so that peaceful co-existence became possible. I first read Mill’s Logic at the age of eighteen, and at that time I had a very strong bias in his favor; but even then I could not believe that our acceptance of the proposition “two and two are four” was a generalization from experience. I was quite at a loss to say how we arrived at this knowledge, but it felt quite different from such a proposition as “all swans are white”, which experience might, and in fact did, confute. It did not seem to me that a fresh instance of two and two being four in any degree strengthened my belief. But it is only the modern development of mathematical logic which has enabled me to justify these early feelings and to fit mathematics and empirical knowledge into a single framework.
出典: John Stuart Mill,1955.
詳細情報:https://russell-j.com/beginner/1097_JSM-020.HTM
<寸言>
人間は,人間や自分に都合のよい論理を信じやすいということ。従って,誰もが近代論理学(記号論理学)を学んだほうがよい。
 言葉の歴史は,好奇心を誘う(ものである)。可能性のある例外としてマルクスを除いて,ミルの時代においては,「共産主義」という言葉が労働者に彼らの暴力的反抗を防ぐのに必要な程度の生産物しか与えない(許さない)ような少数独裁政治の軍事的,行政的,及び司法的な専制を意味するようになることを(事前に)推測することは誰もできなかったであろう。マルクスは,ミルと同時代人としては最も影響力があった人物であると今日の我々は理解できるが,彼は,私の知り得たかぎりでは,ミルの著作ではまったく触れられておらず,ミルは彼のことをまったく知らなかった,ということは非常にありそうなことである。(マルクスとエンゲルスの)『共産党宣言』は,ミルの『政治経済学(原理)』と同じ年に出版されたが,(英国の)文化を代表した人たちは『共産党宣言』を知らなかった。現在全く未知の人物が,(今から)百年後に我々の時代の最重要人物だったということがわかるようになるのだろうか。
言葉の歴史は,好奇心を誘う(ものである)。可能性のある例外としてマルクスを除いて,ミルの時代においては,「共産主義」という言葉が労働者に彼らの暴力的反抗を防ぐのに必要な程度の生産物しか与えない(許さない)ような少数独裁政治の軍事的,行政的,及び司法的な専制を意味するようになることを(事前に)推測することは誰もできなかったであろう。マルクスは,ミルと同時代人としては最も影響力があった人物であると今日の我々は理解できるが,彼は,私の知り得たかぎりでは,ミルの著作ではまったく触れられておらず,ミルは彼のことをまったく知らなかった,ということは非常にありそうなことである。(マルクスとエンゲルスの)『共産党宣言』は,ミルの『政治経済学(原理)』と同じ年に出版されたが,(英国の)文化を代表した人たちは『共産党宣言』を知らなかった。現在全く未知の人物が,(今から)百年後に我々の時代の最重要人物だったということがわかるようになるのだろうか。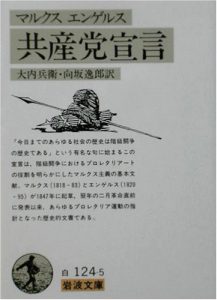 The history of words is curious. Nobody in Mill’s time, with the possible exception of Marx, could have guessed that the word “Communism” would come to denote the military, administrative, and judicial tyranny of an oligarchy, permitting to the workers only so much of the produce of their labor as might be necessary to keep them from violent revolt. Marx, whom we can now see to have been the most influential of Mill’s contemporaries, is, so far as I have been able to discover, not mentioned in any of Mill’s writings, and it is quite probable that Mill never heard of him. The Communist Manifesto was published in the same year as Mill’s Political Economy, but the men who represented culture did not know of it. I wonder what unknown person in the present day will prove, a hundred years hence, to have been the dominant figure of our time.
The history of words is curious. Nobody in Mill’s time, with the possible exception of Marx, could have guessed that the word “Communism” would come to denote the military, administrative, and judicial tyranny of an oligarchy, permitting to the workers only so much of the produce of their labor as might be necessary to keep them from violent revolt. Marx, whom we can now see to have been the most influential of Mill’s contemporaries, is, so far as I have been able to discover, not mentioned in any of Mill’s writings, and it is quite probable that Mill never heard of him. The Communist Manifesto was published in the same year as Mill’s Political Economy, but the men who represented culture did not know of it. I wonder what unknown person in the present day will prove, a hundred years hence, to have been the dominant figure of our time.