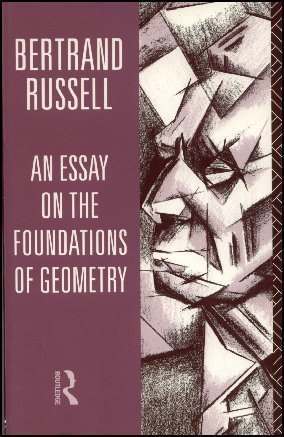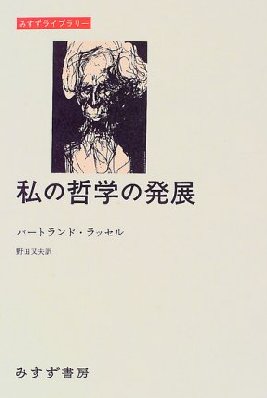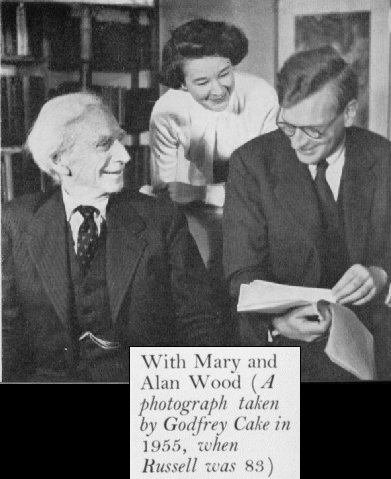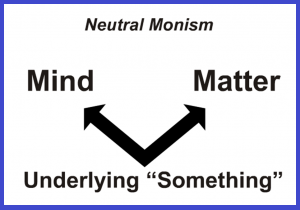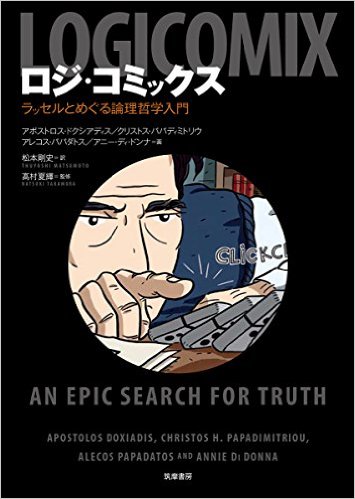
ラッセルの主要な目的は、宗教の真理、数学の真理、及び、科学の真理を確立することであった。彼自身、宗教と数学について、このことをはっきりと述べている。「私は哲学に宗教的満足を見い出そうと期待した。・・・」*1「私は数学を通して、あるいはむしろ、数学の真理を信じるための何らかの理由を見つけたいという願望を通して、哲学にいたった(たどりついた)。」*2 科学に関しては、この感情は恐らくそれほど強くはなかったであろう。結局のところ、科学は、ただ単に、「たまたま存在する世界(’the world that happens to exist’)」を扱うだけである(からである)。しかし、最も有能なラッセルの解説者のひとりであるワイツ教授は「ラッセルの第一の関心(事)は、科学の真理性を正当化する(正当である根拠を示す)試みであったと私には思われる」と断言している。*3 それゆえ、ある意味で、ラッセルのキャリア(専門的職業)は三重の失敗だったと言うこともできるだろう。即ち、 (a)彼は宗教を捨てねばならなかっただけでなく、客観的な倫理的知識をもまた捨てなければならなかった。 (b)彼は(自著の)『数学原理』の体系に十分には満足しなかった。また、ヴィトゲンシュタインは、いずれにせよ(in any case どうであろうと)数学的知識はトートロジー(訳注:同語反復:同じことを違った言い方をするテクニック)にすぎないことをラッセルに信ぜしめた、あるいは、ほとんど信ぜしめたのである*4 。 (c)(自著の)『人間の知識』における科学的知識の擁護は、それ以前に彼がさせたいと望んでいたような基準に合致していなかった。*5
*1 Review of Urmson’s Philosophical Analysis in The Hibbert Journal, July, 1956.
*2 Philosophy of Bertrand Russell (‘My Mental Development’).
*3 ‘Logical Atomism’ in Contemporary British Philosophy, Vol. I (Ed. J. H. Muirhead: Allen and Unwin, London).
*4 Philosophy of Bertrand Russell, page 102.
*5 An Introduction to Mathematical Philosophy, 1919, p.71
Summary and Introduction 04 Russell’s primary objects were to establish the truth of religion, the truth of mathematics, and the truth of science. He himself stated this explicitly in the case of religion and mathematics. ‘I hoped to find religious satisfaction in philosophy….” … ‘I came to philosophy through mathematics, or rather through the wish to find some reason to believe in the truth of mathematics.” With science the feeling was perhaps not quite so strong: after all, science merely deals with ‘the world that happens to exist’. But Professor Weitz, one of the ablest of commentators on Russell, declares that ‘Russell’s primary interest, it seems to me, has been the attempt to justify science’. In a sense, therefore, it could be said that Russell’s career was a threefold failure. (a) He not only had to abandon religion, but objective ethical knowledge as well. (b) He was not fully satisfied with the system of Principia Mathematica, and Wittgenstein convinced him – or almost convinced him – that in any case mathematical knowledge was only tautological. (c) His defence of scientific knowledge in Human Knowledge was not in accordance with the kind of standards he had hoped to satisfy earlier.
*1 Review of Urmson’s Philosophical Analysis in The Hibbert Journal, July, 1956.
*2 Philosophy of Bertrand Russell (‘My Mental Development’).
*3 ‘Logical Atomism’ in Contemporary British Philosophy, Vol. I (Ed. J. H. Muirhead: Allen and Unwin, London).
*4 Philosophy of Bertrand Russell, page 102.
*5 An Introduction to Mathematical Philosophy, 1919, p.71
Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell.
More info.: https://russell-j.com/beginner/wood_br_summary-and-introduction_04.html