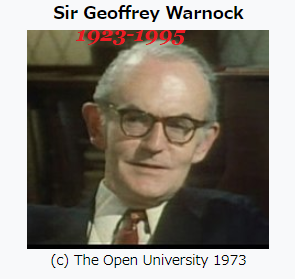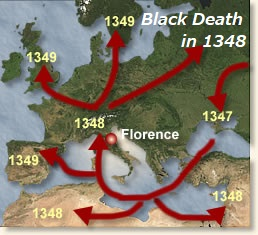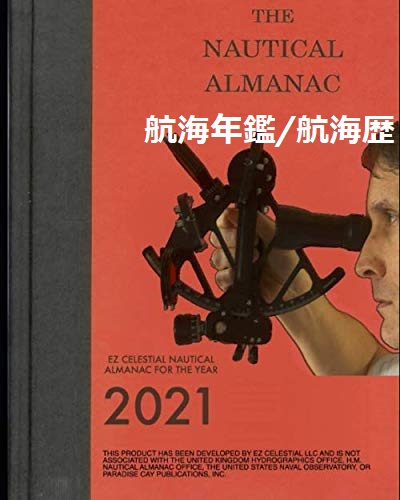昔々、とても遠い昔のことですが、ある川のほとりにある部族が住んでいました。ある人によれば、その川は「アイシス」 (The Isis) 、そのそばに住む人々は「アイシディアン」(The Isidians’)と呼ばれていたそうです。しかし、もしかすると、それは後になってもとの伝説に付加されたことかもしれません。その種族の言語には、「ひめはや(minnnow)」 「ます(trout)」「すずき(perch)」 「かわかます(pike)」 という語を含んでいましたが、「魚(fish)」という語(言葉)は含まれていませんでした。 イシディアンの一行があるときいつもよりも下流まで下り、我々(注:英国人)が「さけ」と呼ぶものを捕えました(ピーコックの小説 Crotchet Castle の第4章参照)。 するとたちまち喧々諤々の議論が起こりました。 ある人々はそれは「かわかます」の一種だと主張し、 他の人々はそれは不潔で厭うべきものものであり、その名を口にする者は部族から追放されるべきだと主張しました。そんな折(at this juncture この時点で)、一人の見知らぬ人がもうひとつの川の岸からやってきました。その川は流れがのろいという理由で軽蔑されていました。彼は言いました。
「私達の部族では、『魚』という語(言葉)があり、それは ひめはやにも、ますにも、すずきにも、かわかますにも、また、非常に大きな議論を引き起こしているこの生き物にも、ひとしく適用できます(あてはまります)」。
アインディアンは(これを聞いて)大いに腹を立てました。彼らは言いました。
「そういう妙な新語(such new-fangled words)の用法は何か。我々がこの川から捕るものは何であっても我々の言語で名付けることができます。 なぜなら、それは常に、ひめますか、ますか、すずきか、かわかますだからです。この見解に反対して あなたは、わが聖なる流れの下流におけるこの最近の出来事をもち出すかも知れないが、我々はこの出来事について語るべからずという法律をつくることを、言語の経済(節約)であると考えます。従って、我々はあなたの用いる『魚』という語(言葉)を、無用な衒学(学者ぶる態度)の一例であると考えます(みなします)」。
Chapter 18: Some Replies to Criticism, n.2_2
Once upon a time, a very long while ago, there was a tribe which lived upon the banks of a river. Some say that the river was called ‘The Isis’, and those who lived beside it, ‘The Isidians’, but perhaps this is a later accretion to the original legend. The language of the tribe contained the words ‘minnow’, ‘trout’, ‘perch’ and ‘pike’, but did not contain the word ‘fish’. A party of Isidians, proceeding down the river rather further than usual, caught what we call a salmon.(See Crotchet Castle, Chapter IV. ) Immediately, a furious debate broke out: one party maintained that the creature was a sort of pike ; the other party maintained that it was obscene and horrible, and that anybody who mentioned it should be banished from the tribe. At this juncture, a stranger arrived from the banks of another stream which was despised because it went footing slow. ‘In our tribe’, he said, ‘we have the word “fish” which applies equally to minnows, trout, perch and pike, and also to this creature which is causing so much debate.’ The Isidians were indignant. ‘What is the use’, they said, ‘of such new-fangled words. ‘Whatever we get out of the river can be named in our language, since it is always a minnow or a trout or a perch or a pike. You may advance against this view the supposed recent occurrence in the lower reaches of our sacred stream, but we think it a linguistic economy to make a law that this occurrence shall not be mentioned. We therefore regard your word “fish” as a piece of useless pedantry.’
Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell
More info.: https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_18-180.HTM