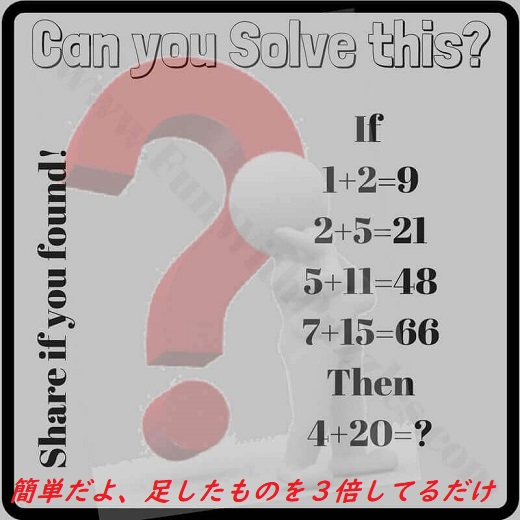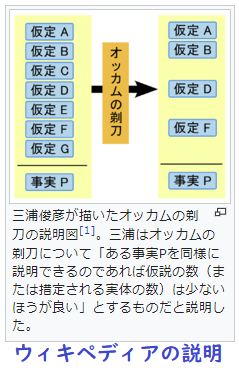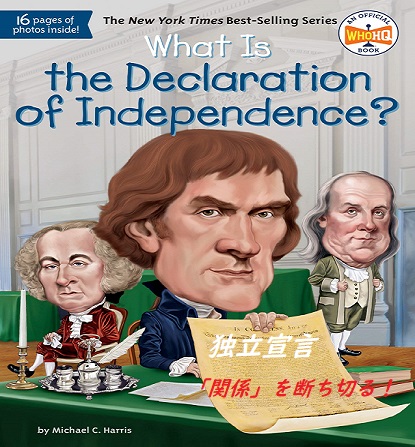数理論理学(数学的論理学)は、決して新しい研究主題(主題分野)ではなかった。すでにライプニッツはそれを幾分試みたが、アリストテレスに対する尊敬によってさまたげられていた。G. ブール(George Boole, 1815- 1864)は1854年に『思考の法則』を出版し、集合の包含関係(class-inclusion)を主として扱う算法(calculus)の全体を展開していた。またパース(Charles Sanders Peirce、1839-1914)は、関係の論理学を展開し、シュレーダーは、それまでになした全ての仕事(研究)を要約する3巻の大著を出していた。ホワイトヘッド(Alfred North Whitehead、1861-1947)は、彼の『普遍的代数学』の最初の部分をブールの算法に捧げた(=論じた)。以上の著作のたいていのものを私はすでによく知っていたが、私はそれらが算術の文法について何らかの新しい光(証明)をあてる(投げかける)とは認めていなかった。私は今でも、パリ(の国際哲学会議)ヘ行く直前にこの間題について私の書いた原稿をもっているが、今再読してみると、算術が論理学に提出する多くの問題の解決の糸口すらつかんでいないことがわかる。
Chapter 6: Logical Technique in Mathematics, n.2 Mathematical logic was by no means a new subject. Leibniz had made some attempts at it, but had been thwarted by respect for Aristotle. Boole had published his Laws of Thought in 1854 and had developed a whole calculus dealing mainly with class-inclusion. Pierce had developed a logic of relations, and Schreider had published a work in three big volumes summarizing all that had previously been done. Whitehead devoted the first portion of his Universal Algebra to Boole’s calculus. Most of the above works were already familiar to me, but I had not found that they threw any light on the grammar of arithmetic. I still have the MS. of what I wrote on this subject just before my visit to Paris and I find, on re-reading it, that it does not make even a beginning of solving the problems which arithmetic presents to logic.
Source: My Philosophical Development, chap. 6:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_06-020.HTM
月別アーカイブ: 2021年7月
バートランド・ラッセル『私の哲学の発展』第6章 「数学における論理的手法」 n1
大学を(種々の)部門に分けること(faculties 学部や学科)は必要だと思うが、,それによっていくつかの非常に不幸な結果を生んできた。(たとえば)論理学は哲学の一部門と考えられており,アリストテレスによって取り扱われたために、ギリシャ語に堪能な者によってのみ取り扱われる学科(主題)だと考えられてきた。数学は、その結果として、論理学を知らない者によってのみ扱われてきた。アリストテレスやユークリッドの時代から今世紀に至るまで、論理学と数学とのこの分離は、ひどい結果を引き起こしてきた。数学の哲学にとって論理学の改革が重要であることに私が気づいたのは、1900年、パリで開かれた国際哲学会においてであった。私がそのことに気づいたのは、トリノ大学のペアノ(Turin 英 = Torino 伊)とそこに集まった他の哲学者たちとの議論を聞いたことによってであった。私はそれ以前には、ペアノの著書を知らなかった。けれどもあらゆる議論において、ペアノが他の誰よりも正確さと論理的厳格さとを示したという事実から、私は強い印象を受けた。私はベアノのところに行って,こう言った、「私はあなたの書物をすべて読みたい。複本(copies)お持ちでしょうか?」 からは持っていた。そうして、私はすぐにそれらの本を全て読んだ。数学の原理についての私自身の見解を推し進める力を与えたものはこれらのペアノの著書であった。
Chapter 6: Logical Technique in Mathematics, n.1 The division of universities into faculties is, I suppose, necessary, but it has had some very unfortunate consequences. Logic, being considered to be a branch of philosophy and having been treated by Aristotle, has been considered to be a subject only to be treated by those who are proficient in Greek. Mathematics, as a consequence, has only been treated by those who knew no logic. From the time of Aristotle and Euclid to the present century, this divorce has been disastrous. It was at the International Congress of Philosophy in Paris in the year 1900 that I became aware of the importance of logical reform for the philosophy of mathematics. It was through hearing discussions between Peano of Turin and the other assembled philosophers that I became aware of this. I had not previously known his work, but I was impressed by the fact that, in every discussion, he showed more precision and more logical rigour than was shown by anybody else. I went to him and said, ‘I wish to read all your works. Have you got copies with you?’ He had, and I immediately read them all. It was they that gave the impetus to my own views on the principles of mathematics.
Source: My Philosophical Development, chap. 6:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_06-010.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n17
そういった(哲学に取り組み始めた)初期の時代以来、私は多様な問題について自分の意見を変えてきたけれども、現在同様当時、最重要だと思われた(いくつかの)点については(今にいたるまで)意見を変えてこなかった。私は今でも(still いまだ)、外的関係の学説(外的関係説)と,それと結びついている多元論(注:一元論に対立する考え方)とに固執している(hold to を固く信じている)。私は今でも、ひとつの孤立した真理が完全な意味で真でありうる、と信じている(注:部分的な真は本当の真ではなく、全体的な真のみが本当の真であるというヘーゲル的な考えたかに対抗する考え方)。私は今でも、分析は、ものをゆがめて見ること(falsification 歪曲/偽証)にはならない、と信じている(注:分析は部分しか見ていないので方法論として誤っているという批判に対する反論)。私は今でも(いまだ)、トートロジー(論理的真理)以外のいかなる命題も、もし仮にそれが真であるならば、事実への関係(注;事実の裏付けがあること)によって(in virtue of)真であるということ、また事実一般は経験から独立しているものである,と信じている。私は経験を欠いている宇宙(注;人間等の感覚器官を持っている生命体のいない宇宙など)において、不可能なものは何物も認めない(注:see nothing 何物も目に入らない)。反対に、経験は、宇宙の非常に小さな部分の、極めて狭く宇宙的には取るに足らない面(様相)であると考ぇる。これらすべての事柄(問題)に関して、カントとヘーゲルの教えを捨てて以来、私の見解は変わっていない(have not changed 変わってこなかった)。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.17
Although I have changed my opinion on various matters since those early days, I have not changed on points which, then as now, seemed of most importance. I still hold to the doctrine of external relations and to pluralism, which is bound up with it. I still hold that an isolated truth may be quite true. I still hold that analysis is not falsification. I still hold that any proposition other than a tautology, if it is true, is true in virtue of a relation to fact, and that facts in general are independent of experience. I see nothing impossible in a universe devoid of experience. On the contrary, I think that experience is a very restricted and cosmically trivial aspect of a very tiny portion of the universe. On all these matters my views have not changed since I abandoned the teachings of Kant and Hegel.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-170.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n16
新しい哲学を展開しつつあった初期の時期において、私は、主として言語上の諸問題に非常に専念した。私は、複合体/複合物を統一するものについて(注:いくつかのもので成っているものを一つの統一体にするものについて)、特に(more especially とりわけ)ひとつの文を統一するものについて、関心を持っていた(注:単語の集まりである一つの文を一体のものとして統合化するものは何か?)。(たとえば)一つの文と一つの語(単語)との違いが(何であるか)私を困惑させた(悩ませた/難問であった)。私は文の統一が、文が動詞を含むという事実に依存している(よっている)と理解した(I saw)。しかし,私には、動詞は --動名詞はもはや複合体の諸部分を結び合わせる能力をもたないけれども-- それに対応する動名詞(注:verbal noun 動詞的名詞)が意味するものと全く同じことを意味するように思われた。(注:たとえば、一つの文「Brutus killed Caesar.」は一つの統一のある文であるが、Bruths; killed; Caesar の語がめちゃめちゃの順番で並んでいると意味がなくなったり、意味が変わったりする。Caear killed Brutus. にすると意味が逆になってしまう。”kill”は前後の単語を結びつける力を持っているが、”killing”というように動名詞にすると前後を一体化する力を失う。) 私は「ある」(is)と「あること」(being)との相違について思い悩んだ。有名で気力に溢れた宗教的指導者であった義母(私の妻の母)は、哲学が難しいのはただ哲学が長い語(単語)を用いるからだと私に向って自信をもって主張した。私は、その日(当日)書きつけた覚え書きの中から、次の文(一文)を示して、彼女と対峙した(confronted her with)。その文は「“is (ある)の意味するものは is(ある)であり、従って、is (ある)の意味するものは is あるとは異なる。というのは(もし同一だとすると)”is is”(あるはある)はナンセンスであろうからである。あるの意味するものはある』、と言う代りに、『あるはある』と言えるはずだが〕、『あるはある』と言うのは無意味であろうから」(What is means is and therefore differs from is, for “is is” would be nonsense.) この文が難しいのは長い単語のせいであると言うことはできない。時が経つにつれて、私はそういった問題で悩まなくなった。そういう問題は、びとつの語が何らかの意味をもつ場合には、その語の意味する何ものかが存在しなければならない、という信念から生じたものである。1905年に私が到達した「記述の理論」は、上の信念が誤まっていることを明らかにし、他のやり方では解決不可能な問題の多くを一掃した。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.16 I was very much occupied, in the early days of developing the new philosophy, by questions which were largely linguistic. I was concerned with what makes the unity of a complex, and, more especially, the unity of a sentence. The difference between a sentence and a word puzzled me. I saw that the unity of a sentence depends upon the fact that it contains a verb, but it seemed to me that the verb means exactly the same thing as the corresponding verbal noun, although the verbal noun no longer possesses the capacity of binding together the parts of the complex. I worried about the difference between is and being. My mother-in-law, a famous and forceful religious leader, assured me that philosophy is only difficult because of the long words that it uses. I confronted her with the following sentence from notes I had made that day: ‘What is means is and therefore differs from is, for “is is” would be nonsense.’ It cannot be said that it is long words that make this sentence difficult. As time went on, I ceased to be troubled by such problems. They arose from the belief that, if a word means something, there must be some thing that it means. The theory of descriptions which I arrived at in 1905 showed that this was a mistake and swept away a host of otherwise insoluble problems.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-160.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n15
時が経過するにつれて、私の(想定する)宇宙はそれほど豊かでなくなって行った。ヘーゲルに反逆した当初は、もの(a thing)は存在できないというヘーゲルの証明が妥当でない場合には、ものは(当然)存在しなければならない、と私は信じた。(しかし)徐々に,オッカムの剃刀(注:「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とする格言/仮定は少なければ少ないほどよい)が、もっと綺麗に剃られた実在の姿を私に与えてくれた。(ただし)オッカムの剃刀が不必要であることを示した存在者(entities)が実在しないことを証明できた,と私は言うつもりほない。私はただ,オッカムの剃刀がそれら存在者を支持する議論を消滅させたと言っているだけである。私は今でも整数や点や瞬間やオリンボスの神々が実在しないことを証明することは不可能であると考えている。ひょっとすると(For aught I know)それらは全て、実在するかも知れないが、そう考えるべきかすかな理由もないのである。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.15
As time went on, my universe became less luxuriant. In my first rebellion against Hegel, I believed that a thing must exist if Hegel’s proof that it cannot is invalid. Gradually, Occam’s razor gave me a more clean-shaven picture of reality. I do not mean that it could prove the non-reality of entities which it showed to be unnecessary; I mean only that it abolished arguments in favour of their reality, I still think it impossible to disprove the existence of integers or points or instants or the Gods of Olympus. For aught I know these may all be real, but there is not the faintest reason to think so.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-150.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n14
<7月22,23日は振替休日のため、投稿を休止します。>
ヘーゲル主義者たちは、あれやこれやが「実在的」ではないことを証明しょうとする様々な議論(論証)を持っていた(持ち合わせていた)。数や空間や時間や物質は、すべて自己矛盾的であるということで,公然と(professedly)有罪判決を受けた(注:それらのものは「実在しない」と断罪された)。絶対者(神)以外は何ものも実在しないと、そのように我々は説得させられた。絶対者(神)は、それが他に考えるぺきものをもたずただ自己についてのみ考えうるだけであり、観念論哲学者たちが彼らの著書において考えたようなことを永遠に考えてきたのである。 ヘーゲル主義者たちが、数学や物理学によって扱われるものを非実在的であると有罪判決を下すために用いた議論(論証)は、全て内的関係の公理(内的関係説)に依拠していた。従って、私がこの公理をしりぞけたとき、私はへーゲル主義者たちが信じなかった全てのことを信じ始めた。これは私に非常に充実した宇宙を与えた(=物質が充満した宇宙)。私はあらゆる数がプラトン的天国で一列に並んで坐っている姿を想像した〔原注:私の(小説)『著名人の悪夢』の中の「数学者の悪夢」を参照)〕。私はまた、空間の(における)点や時間の(における)瞬間が、現実に存在しており、物質は物理学が(想定するのが)便利(都合がよい)と見出した実在の諸要素から構成されている可能性が非常に高い(might very well)、と考えた。私は大部分が動詞や前置詞によって意味されるもの(訳注:本書第14章で具体例が示されています。)で構成されてる普遍者の世界の存在を信じた。特に私は、数学が完全な意味では真ではない(not quite true)などともはや考える必要がなかった。ヘーゲル主義者たちは、2に2を加える(足すと)と4になるということは完全な意味では(完全には)真ではないと常に主張した。しかし彼らは、2に2を加えた(足した)結果は 4.000001 とかいった数であると言おうとしたのではない。彼らは実際には言わなかったけれども,言おうとしたことは、絶対者は、、加え算(足し算)などをするよりも、その心を向けるのにもっと良いものを見つけることができるということであった。しかし彼らはそのことをこのように単純な言葉で言い表わすのを好まなかったのである。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.14 Hegelians had all kinds of arguments to prove this or that not ‘real’. Number, space, time, matter, were all professedly convicted of being self-contradictory. Nothing was real, so we were assured, except the Absolute, which could think only of itself since there was nothing else for it to think of and which thought eternally the sort of things that idealist philosophers thought in their books. All the arguments used by Hegelians to condemn the sort of things dealt with by mathematics and physics depended upon the axiom of internal relations. Consequently, when I rejected this axiom, I began to believe everything the Hegelians disbelieved. This gave me a very full universe. I imagined all the numbers sitting in a row in a Platonic heaven. [“Cf. my Nightmares of Eminent Persons, “The Mathematician’s Nightmare”.] I thought that points of space and instants of time were actually existing entities, and that matter might very well be composed of actual elements such as physics found convenient. I believed in a world of universals, consisting mostly of what is meant by verbs and prepositions. Above all, I no longer had to think that mathematics is not quite true. Hegelians always maintained that it is not quite true that two and two are four, but they did not mean by this that two and two are 4.000001 or some such figure. What they did mean, though not what they said, was that the Absolute can find better things to occupy its mind than doing sums, but they did not like to put the matter in such simple language.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-140.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n13
私が関係の問題の重要性を初めて認識したのは、私がライプニッツを研究していた時であった。ライプニッツに関する多くの書物が明らかにしえなかったことであるが、ライプニッツの形而上学は明らかに、全ての命題(注:「AはBである」という真偽を判定できる陳述)は(命題は全て)一つの主語に一つの述語を帰属させるものであり、かつ(これはライプニッツにとってはほとんど同じことだと思われたようであるが)全ての事実は、ある特性をもつ実体(a substance)から成る、という学説(理論)を基礎としていることを私は発見した。私はまた、同じ学説(理論)が、スピノザやヘーゲルやブラッドリの体系の基礎にも存在することを発見した。実際,彼らはその学説をライプニッツによって示されたものよりももっと論理的に厳密に展開させたのである。 しかし、私が(自分の)新しい哲学を喜んだのは、これらのかなり無味乾燥な、論理説(論理上の学説)(doctrines”と複数形になっていることから、ラッセルの自分の学説ではなく、ヘーゲルやブラッドリなどの諸学説を指していると推定される。)のためだけではなかった(注:”rather”を野田氏はよくあるように「どちらかと言えば」と訳しているが、ここでは「かなり」と訳したほうがよいであろう。)。私は,実際,大いなる解放感をもったのであって、(生暖かい)温室(a hot-house)を脱出して、風に吹きさらされている岬に出たように感じた。私は空間及び時間は私の精神(心)の中にあるにすぎないという考えのもつ息苦しさ(stufiness 閉塞状態)が大変嫌であった(hated 憎んだ)。私は道徳律(moral law)よりも星空の方をいっそう好み(even better than)、私の一番好きな星空が主観の虚構物(figment 作り事)にすぎないというカントの見解には耐えられなかった。このように解放感にあふれていたはじめの頃、私は素朴実在論者となり、ロック以降の全ての哲学者たちの反対論にもかかわらず、草は本当に緑(色)である(自分の脳内の虚構ではない)という考えを楽しんだ。私はそれ以来この心地よい信念を、その最初の強さで保持し続けることはできなかったが、しかし再び主観という牢獄にわが身を閉じこめることは決してなかった。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.13
I first realized the importance of the question of relations when I was working on Leibniz. I found — what books on Leibniz failed to make clear — that his metaphysic was explicitly based upon the doctrine that every proposition attributes a predicate to a subject and (what seemed to him almost the same thing) that every fact consists of a substance having a property. I found that this same doctrine underlies the systems of Spinoza, Hegel and Bradley, who, in fact, all developed the doctrine with more logical rigour than is shown by Leibniz. But it was not only these rather dry, logical doctrines that made me rejoice in the new philosophy. I felt it, in fact, as a great liberation, as if I had escaped from a hot-house on to a wind-swept headland. I hated the stuffiness involved in supposing that space and time were only in my mind. I liked the starry heavens even better than the moral law, and could not bear Kant’s view that the one I liked best was only a subjective figment. In the first exuberance of liberation, I became a naive realist and rejoiced in the thought that grass is really green, in spite of the adverse opinion of all philosophers from Locke onwards. I have not been able to retain this pleasing faith in its pristine vigour, but I have never again shut myself up in a subjective prison.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-130.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n12
(続き) それゆえ、関係はそれらの諸項(=各項)の「本性(性質)」あるいは諸項からなる全体の「本性(性質)」に必然的に根拠づけられているという公理(注:axiom 最も基本的な仮定。ここでは「内面的関係説」)に反対すべき諸理由が存在しており、逆に賛成すべき理由はまったく存在していないように思われる。(そうして)この公理が拒否されるならば、ある関係項の「本性(性質)」について語ることは無意味になる。関係性(関係づけられていること)は、もはや複合性の証拠となるものではまったくなく、所与の関係は諸項の多くの異なる対(ペア)の間に成立することができ、また所与の項は異なった項への多くの異なる関係をもつことが可能である(注:複合体に対するものはライプニッツのモナド(単子)/モナドは部分を持たない単純な実体なので、複合的なもの同士が関係するような意味で「関係」することはできない。即ち、モナドには窓がない)。「差異における同一性」は消滅する(注:一元論の根拠の消滅)。(つまり)同一性があり、(また)差異があり、またいろいろな複合体(複合物)は同一の要素をもちうるとともに異なる要素をもちうるけれども、言及される対象のいかなる組合せについてもそれらの対象は「同一であるとともに異なっている」ということを余儀なくさせられることはもはやない。それは「ある意味で」そうであり(「同一であるとともに異なっている」のであり),未定義のままにしておくことが必須のものである。このようにして,多くのものからなる世界を手に入れ、それらの物(多くの物)の間の関係は、それらの物のもついわゆる「本性(性質)」、即ち,スコラ哲学的本質から演繹される必要がなくなる。この世界では、すべての複合物は、関係づけられた単純な事物から成り、もはや分析があらゆる段階で無限後退に直面することはなくなる。このような世界を前提として(想定して)して、真理の本性に関して我々は何を主張することができるかを尋ねることが(課題として)残っている。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.12
There would seem, therefore, to be reasons against the axiom that relations are necessarily grounded in the ‘nature’ of their terms or of the whole composed of the terms, and there would seem to be no reason in favour of this axiom. When the axiom is rejected, it becomes meaningless to speak of the ‘nature’ of the terms of a relation: relatedness is no longer a proof of complexity, a given relation may hold between many different pairs of terms, and a given term may have many different relations to different terms. ‘Identity in difference’ disappears: there is identity and there is difference, and complexes may have some elements identical and some different, but we are no longer obliged to say of any pair of objects that may be mentioned that they are both identical and different — ‘in a sense’, ‘this sense’ being something which it is vitally necessary to leave undefined. We thus get a world of many things, with relations which are not to be deduced from a supposed ‘nature’ or scholastic essence of the related things. In this world, whatever is complex is composed of related simple things, and analysis is no longer confronted at every step by an endless regress. Assuming this kind of world, it remains to ask what we are to say concerning the nature of truth.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-120.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n11
(続き) さらにまた、内的関係(内面的)の公理はあらゆる複合性(complexity 複雑性)とは両立しない(相容れない)。なぜなら、既に見たように、この公理(内的関係説)は厳格な一元論(monism)に導くからである。(即ち、)ただ一つのものだけが存在し、ただ一つの命題だけが存在する(ということになる)。その一つの命題(それはただ一つの真なる命題ではなく、ただ一つの命題である)は、一つの述語を一つの主語に帰属させる。しかしこのただ一つの命題は、主語から述語を区別することを(不可欠のものとして)含んでいるゆえに、必ずしも真ではない(not quite true)。しかし,その場合(then そうなると)(次のような)困難が生ずる。(即ち)もし叙述(predication :AはBである)が述語は主語とは異なるものであるということを(必然的に)含んでいるものであり、しかも(そのうえまた)唯一の述語が唯一の主語から区別されないものだとすると、その唯一の述語を唯一の主語に帰属させるところの命題なるものは、(真なる命題としてだけでなく)偽なる命題としてさえも存在することができない,と思うだろう。それゆえ、我々は、叙述(注:predecation 述語づけ/叙述付加)が、述語と主語との差別を含まず(伴わず)、またこの唯一の述語は唯一の主語と同一である(注:一体のものである)と想定(仮定)しなければならないであろう。しかし、我々がいま吟味している哲学(注:観念論哲学)にとっては、絶対的同一性を否定して「差異における同一性」を保持することが、必須である。そうでないとしたら,実在的世界の見かけ上の(apparent)多様性は説明不可能である(注:現実世界は多様かそうでないかは議論の対象/また観念論哲学では現実世界の多様性はあくまでも「現象」であり「実体ではない」と考えるので、「apparent」は「明らかに」ではなく「見かけ上は」と訳すべきであろう。因みに、みすず書房の野田訳では「明らかに」と訳されている)。しかし困難は、我々が厳密な一元論に固執すれば差異における同一性」は不可能である(不可能になる)ことである。なぜなら、「差異における同一性」は多くの部分的真理を含み(必然的に伴い)、それらの部分的真理は、一種の相互のギブ・アンド・テイクによって、一つの全体的真理を形成するからである。厳密な一元論においては、部分的真理は必ずしも真ではないというだけではない。(即ち厳密な一元論においては)そういう部分的真理なるものはまったく成立しない(のである)。真であるにせよ偽であるにせよ,仮にそういう諸命題が存在するとすれば 複合性(plurality 一つではなく多数であること)が存在することになるであろう。要するに、「差異における同一性」という考えは内的関係の公理(内的関係説)と両立しない(相容れない)のである。(そうして)しかも、この概念(「差異における同一性」)がなくては一元論は世界(の見かけ上の多様性)の説明を与えることができず、世界はオペラ用の帽子(opera-hat)のように突然つぶれてしまう。(そこで)私は、内的関係の公理(内的関係説)は偽であり、観念論の主張のうちこの公理に依存する部分は根拠がない、と結論する(しだいである)。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.11
Again, the axiom of internal relations is incompatible with all complexity. For this axiom leads, as we saw, to a rigid monism. There is only one thing, and only one proposition. The one proposition (which is not merely the only true proposition, but the only proposition) attributes a predicate to the one subject. But this one proposition is not quite true, because it involves distinguishing the predicate from the subject. But then arises the difficulty: if predication involves difference of the predicate from the subject, and if the one predicate is not distinct from the one subject, there cannot, even, one would suppose, be a false proposition attributing the one predicate to the one subject. We shall have to suppose, therefore, that predication does not involve difference of the predicate from the subject, and that the one predicate is identical with the one subject. But it is essential to the philosophy we are examining to deny absolute identity, and retain ‘identity in difference’. The apparent multiplicity of the real world is otherwise inexplicable. The difficulty is that ‘identity in difference’ is impossible, if we adhere to strict monism. For ‘identity in difference’ involves many partial truths, which combine, by a kind of mutual give and take, into the one whole of truth. But the partial truths, in a strict monism, are not merely not quite true: they do not subsist at all. If there were such propositions, whether true or false, that would give plurality. In short, the whole conception of ‘identity in difference’ is incompatible with the axiom of internal relations; yet without this conception, monism can give no account of the world, which suddenly collapses like an opera-hat. I conclude that the axiom is false, and that those parts of idealism which depend upon it are therefore groundless. Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959. More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-110.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n10
<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>
内的関係の公理(注:「内面的関係」を「内的関係」に変更/内的関係説)に反対するもっと綿密な議論(論証)(A more searching argument)は、ひとつの項(term)の「本性(性質)」は何を意味するか(項の「本性(性質)」の意味)について考察することに由来している。「項の本性(性質)」は、「項そのもの」と同一なのか、あるいは異なっているのか。もし異なっているとすればと本性(性質)は項に対してある関係をもたなければならないことになり、この関係は、無限後退におちいることなしに、関係以外の何ものかに還元することはできない。従って(thus こうして)この公理(内的関係説)が支持されるべきだとするなら、項がその本性(性質)と異なったものではない,と想定しなければならない。その場合には、(一つの)述語(a predicate)を(一つの)主語(a subject)に帰属させるあらゆる真なる命題は、純粋に分析的なもの(分析命題)となる。なぜなら、主語はそれ自身の全ての本性(性質)の全体(注:its own whole nature)であり、述語はその本性(性質)の部分(一部)であるからである。しかし、この場合、(いくつかの)述語を、一つの主語の(配下の)述語として結合させる接着剤は何であろうか? もしも主語が、それ自身の述語の体系そのものに他ならないとすれば、いくつかの述語の任意のいかなる集まり(集合体)でも、ひとつの主語を構成しうると考えられることになるであろう(注:倒置型になっている。/一般人の常識では主語と述語は別物であるが「主語=諸述語の集合体」だと考えることも可能)。もし一つの項の「本性(性質)」が多くの述語からなるものであり、そしてそれが同時に項そのものと同一のものであるならば、一体主語Sが述語Pを持つかどうかと問う場合に、その問いの意味を理解することが不可能であるように思われる。なぜなら、この問いは「Pは、Sの意味を説明する場合に枚挙される述語のうちの一つであるか」という意味ではもちろんありえないのであるが、上の見解によれば、そういう意味に取るより他ない(他の意味にとることができない)ように見えるからである。つまり今議論している(問題にしている)見解では --ある述語(predicates 述部)が一つの主語の述語であると言われるための根拠となるところの(in virtue of which they may be called predicates of one subject)-- いろいろの述語の間の「コヒーレンス」の関係(注:a relation of coherence 全体を貫く一つの関係/全体を束ねる一つの関係?)を導入しようとしてもできない。というのは、それは関係を述語に還元するのではなく、叙述(predications)を一つの関係に基礎づけることになるだろうからである。このようにして,我々は、主語がそれ自身の「本性(性質)」とは異なると考えてもまた異ならないと考えても、同様な困難に陥ることになる。〔「この点については私の著書『ライプニッツの哲学』第21節、24節、25節を参照〕
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.10
A more searching argument against the axiom of internal relations is derived from a consideration of what is meant by the ‘nature’ of a term. Is this the same as the term itself, or is it different? If it is different, it must be related to the term, and the relation of a term to its nature cannot, without an endless regress, be reduced to something other than a relation. Thus if the axiom is to be adhered to, we must suppose that a term is not other than its nature. In that case, every true proposition attributing a predicate to a subject is purely analytic, since the subject is its own whole nature, and the predicate is part of that nature. But in that case, what is the bond that unites predicates into predicates of one subject? Any casual collection of predicates might be supposed to compose a subject, if subjects are not other than the system of their own predicates. If the ‘nature’ of a term is to consist of predicates, and at the same time to be the same as the term itself, it seems impossible to understand what we mean when we ask whether S has the predicate P. For this cannot mean; ‘Is P one of the predicates enumerated in explaining what we mean by S?’ and it is hard to see what else, on the view in question, it could mean. We cannot attempt to introduce a relation of coherence between predicates, in virtue of which they may be called predicates of one subject; for this would base predication upon a relation, instead of reducing relations to predications. Thus we get into equal difficulties whether we affirm or deny that a subject is other than its ‘nature’. [[On this subject, cf. my Philosophy of Leibniz, §§ 21 , 24 , 25]
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-100.HTM