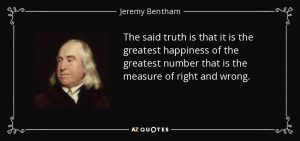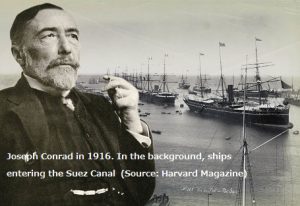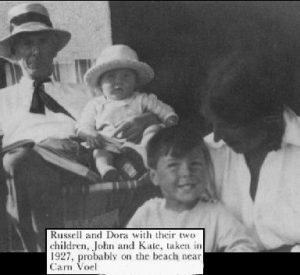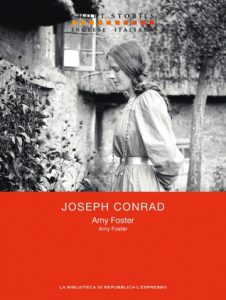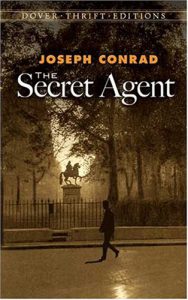伝統的道徳を擁護する人たちも,時には,伝統的道徳が完全なものでないことを認めるであろう。しかし,彼らは,道徳に対するいかなる批判も,道徳を全て壊してしまう,と強く主張する。このことは,道徳に対する批判が何らか積極的かつ建設的なものに基づいてなされているのなら当てはまらないであろうが,その批判が一時的な楽しみにすぎないものを目当てになされる時だけは当っている。
伝統的道徳を擁護する人たちも,時には,伝統的道徳が完全なものでないことを認めるであろう。しかし,彼らは,道徳に対するいかなる批判も,道徳を全て壊してしまう,と強く主張する。このことは,道徳に対する批判が何らか積極的かつ建設的なものに基づいてなされているのなら当てはまらないであろうが,その批判が一時的な楽しみにすぎないものを目当てになされる時だけは当っている。
べンサムに戻ろう。彼は,社会道徳(注:morals 複数形)の基盤として,「最大多数の最大幸福」を唱えた。この原理に基づいて行動する人は,単に因襲的な教えに従っているだけの人よりも,ずっと骨の折れる生涯を送るであろう。彼は必然的に抑圧された人たちのために闘う者(擁護者)となるであろうし,そのために偉い人たち(大物/権力者)の敵意を招くであろう。彼は,権力者が隠したいと望む事実を公表するであろう。彼は,同情を必要としている人々からその同情を遠ざける(同情がいかないようにする)意図を持った虚偽を否定するであろう(注:たとえば,困窮した人々に援助の手は必要ない,あるいはそんなことはその人たちのためにならない,といった嘘を虚偽だと否定する)。そのような生活様式は,本ものの道徳を破壊することにはならない(はずである)。官製(お上)の道徳は(これまで)いつも抑圧的,否定的なものであった。それは「汝・・・べからず」と言ってきたし,規則の禁じていない活動の結果を調べる労をとったことがない。この種の道徳に対して,神秘思想家や宗教関係の教師(導師)は皆抗議してきたけれども無駄であった(効果はなかった)。(即ち,)彼らに従う者たちは,彼らの最もはっきりした意見さえも無視した(のである)。それゆえ,彼らのやり方では,いかなる大規模な改善も生じそうにないように思われる。
Those who defend traditional morality will sometimes admit that it is not perfect, but contend that any criticism will make all morality crumble. This will not be the case if the criticism is based upon something positive and constructive, but only if it is conducted with a view to nothing more than momentary pleasure. To return to Bentham: he advocated, as the basis of morals, ‘the greatest happiness of the greatest number’. A man who acts upon this principle will have a much more arduous life than a man who merely obeys conventional precepts. He will necessarily make himself the champion of the oppressed, and so incur the enmity of the great. He will proclaim facts which the powers that be wish to conceal; he will deny falsehoods designed to alienate sympathy from those who need it. Such a mode of life does not lead to a collapse of genuine morality. Official morality has always been oppressive and negative: it has said ‘thou shalt not’, and has not troubled to investigate the effect of activities not forbidden by the code. Against this kind of morality all the great mystics and religious teachers have protested in vain: their followers ignored their most explicit pronouncements. It seems unlikely, therefore, that any large-scale improvements will come through their methods.
出典: The Harm That Good Men Do,1926.
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/0393_HGMD-140.HTM
<寸言>
「由らしむべし知らしむべからず」(一般大衆は愚かなので,説明しても理解しない。従って,社会秩序を保つためには,「余分なこと」は知らせない方がよい。)の精神で政治を行う保守政治家たち。つまり,自分たちは一般庶民とは違うと思っている。彼らは,選挙で落選すれば「タダの人」になってしまうが、国会に議席をもっていなくても,保守党に所属していれば(与党「関係者」であれば)一般国民の「上にたてる」と思っている人たちである。