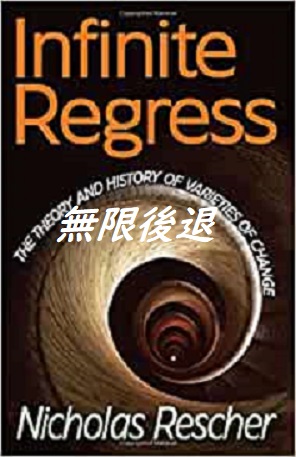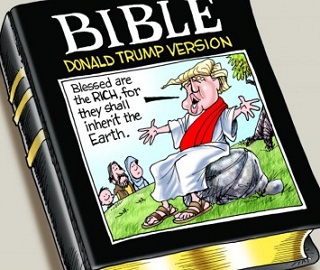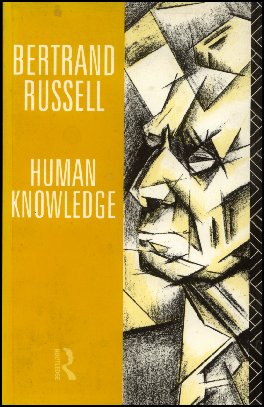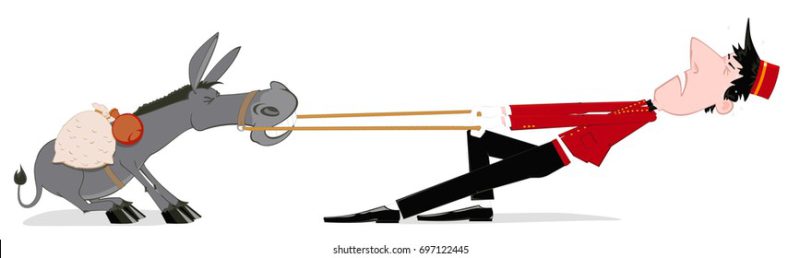プラグマティズム(実際主義/実用主義)に対する理論的反対とは別に、今から五十年前、世界大戦(第一次及び第二次)が起る以前に- その後の歴史によって確証されていることであるが- 哲学としてのプラグマティズムは理論的に誤っているだけでなく、社会的にも破壊的なもの(disastrous)であると,私は考えた。私は。当時、プラグマティズムに対する批評を次のように結論づけた。
国際平和の希望は、国内平和の達成と同様に、紛争における正・不正の評価にもとに形成される有効な世論を創り出すことにかかっている(依存している)。従って、力によって決着がをつけられるとだけ言って、力が正義に依存することをつけ加えなければ、人を誤り導くであろう。 しかし、そのような世論の可能性は、その社会の願望(wishes)の結果ではなくて原因であるところの、 正義の基準の可能性に依存している。 そうして、そのような正義(なるもの)は、プラグマティズムの哲学とは共存不可能であると(両立しないと)思われる。それゆえこの哲学は、自由と寛容(とを主張すること)から始めてはいるが、発展するにつれて、内的必然に(inherent necessity 固有の必要性)、力への訴えと大きな軍隊による裁決へと発展して行く。この発展によりそれは、国内における民主主義と国外に対する帝国主義とのいずれにも適応するものとなる。このようにして、この点においてもまた、この哲学は、いままで発明された他のどの哲学よりも、時代の要求にうまく適合しているのである。
要約しよう。プラグマティズムは、この惑星(地球)の表面のみに自らの想像の全ての材料を見出す精神的気質(the temper of mind)(の人)に対して訴えかける。即ち、進歩を確信し(confident of)、人間の力に対する非人間的な限界を意識しないという気質である。;あらゆる危険が伴う戦いを好むという気質である。なぜなら、自らが勝利を得るであろうことを真の意味で疑うということがないからである。 (また)それは、鉄道や電灯を欲する(欲求する)ように、世事(the affairs of this world)における慰めや助けるものとして宗教を欲する気質(の人)であり、、完全性や無条件に崇拝すべきものに対する飢えを満足させる非人間的対象を与えるものとして宗教を欲するのではない気質(の人)である。 しかし、この地球上の生(活)はもし地球を超えたより大きな世界がなければ牢獄の生であろうと感ずる人々、人間の全能を信ずることは傲慢であると思われ、この世の王国を自分の足元に見るところのナポレオン風の支配よりは、むしろ強い感情を支配することから生まれるストア的自由の方を欲する人々 つまり人間なるものを自らの十全な崇拝対象と見ない人々にとっては、プラグマティスト(実際主義者)達の世界は狭く卑小なものに見え、人生に価値を与える全てのものを奪い去り、人間の眺める宇宙からその光彩の全てを奪い取ることによって、人間自身を矮小化するものに見えるであろう(『哲学論文集』pp.125-126)
Chapter 15, n.06 Apart from theoretical objections to pragmatism, I thought, fifty years ago, before the era of the World Wars, what subsequent history has confirmed, that, in addition to being theoretically mistaken, pragmatism as a philosophy is socially disastrous. I concluded my criticism of pragmatism at that time as follows: The hopes of international peace, like the achievement of internal peace, depend upon the creation of an effective force of public opinion formed upon an estimate of the rights and wrongs of disputes. Thus it would be misleading to say that the dispute is decided by force, without adding that force is dependent upon justice. But the possibility of such a public opinion depends upon the possibility of a standard of justice which is a cause, not an effect, of the wishes of the community; and such a standard of Justice seems incompatible with the pragmatist philosophy. This philosophy, therefore, although it begins with liberty and toleration, develops, by inherent necessity, into the appeal to force and the arbitrament of the big battalions. By this development it becomes equally adapted to democracy at home and to imperialism abroad. Thus here, again, it is more delicately adjusted to the requirements of the time than any other philosophy which has hitherto been invented. To sum up: Pragmatism appeals to the temper of mind which finds on the surface of this planet the whole of its imaginative material; which feels confident of progress, and unaware of non-human limitations to human power; which loves battle, with all the attendant risks, because it has no real doubt that it will achieve victory; which desires religion, as it desires railways and electric light, as a comfort and a help in the affairs of this world, not as providing non-human objects to satisfy the hunger for perfection and for something to be worshipped without reserve. But for those who feel that life on this planet would be a life in prison if it were not for the windows into a greater world beyond ; for those to whom a belief in man’s omnipotence seems arrogant, who desire rather the Stoic freedom that comes of mastery over the passions than the Napoleonic domination that sees the kingdoms of this world at its feet — in a word, to men who do not find Man an adequate object of their worship, the pragmatist’s world will seem narrow and petty, robbing life of all that gives it value, and making Man himself smaller by depriving the universe which he contemplates of all its splendour (Philosophical Essays, 125 – 126 ).
Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell
More info. https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_15-060.HTM