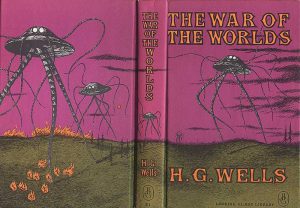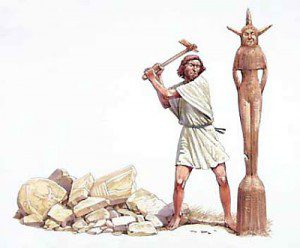ウェルズの重要性は,主として,思想と想像力の解放者としてであった。ウェルズは,彼が描かなければ若者たちが思いつかないだろういろいろな可能性を,若者たちが心に描くのを助長するような種類の,- 魅力的なあるいは魅力的でない- ありうる(実現可能性のある)社会の絵をつくり上げる(構成する)ことができた。彼は,時々,これをとても啓発的なやり方でやっている。『盲人の国』はプラトンの洞窟の寓話を現代の言葉でやや悲観主義的に言い直したものである。彼の(彼が描いた)多様なユートビアは,それ自身,それほど一様のもの(がんじょうなもの)ではないが,あとで実を結ぶ可能性のある思想の口火を切る(導火線に火をつける)ように意図されている。彼は常に合理主義的であり,現代人の心が陥りやすい(とりこになりやすい)多様な形態の迷信を回避している。彼の科学的方法への確信は,健全かつ人を元気づけるものである。彼の一般的な楽天主義(彼が概ね楽天的であること)は,世界の現状は楽天主義を維持することを難しくしているが,ごく普通なものになりつつあるやや怠惰な悲観主義よりも,もっとずっと良い結果に導きそうである。H. G. ウェルズは,いくらか留保すべき点(注:前述の「少し打算的な側面」など)があるにもかかわらず,社会制度や人間関係の双方について,正気かつ建設的な思考への重要なカであったとみなすべきであろう。私は現時点においてそれが誰になるかは知らないが,彼が後継者(たち)を持つことを期待する。
ウェルズの重要性は,主として,思想と想像力の解放者としてであった。ウェルズは,彼が描かなければ若者たちが思いつかないだろういろいろな可能性を,若者たちが心に描くのを助長するような種類の,- 魅力的なあるいは魅力的でない- ありうる(実現可能性のある)社会の絵をつくり上げる(構成する)ことができた。彼は,時々,これをとても啓発的なやり方でやっている。『盲人の国』はプラトンの洞窟の寓話を現代の言葉でやや悲観主義的に言い直したものである。彼の(彼が描いた)多様なユートビアは,それ自身,それほど一様のもの(がんじょうなもの)ではないが,あとで実を結ぶ可能性のある思想の口火を切る(導火線に火をつける)ように意図されている。彼は常に合理主義的であり,現代人の心が陥りやすい(とりこになりやすい)多様な形態の迷信を回避している。彼の科学的方法への確信は,健全かつ人を元気づけるものである。彼の一般的な楽天主義(彼が概ね楽天的であること)は,世界の現状は楽天主義を維持することを難しくしているが,ごく普通なものになりつつあるやや怠惰な悲観主義よりも,もっとずっと良い結果に導きそうである。H. G. ウェルズは,いくらか留保すべき点(注:前述の「少し打算的な側面」など)があるにもかかわらず,社会制度や人間関係の双方について,正気かつ建設的な思考への重要なカであったとみなすべきであろう。私は現時点においてそれが誰になるかは知らないが,彼が後継者(たち)を持つことを期待する。
Wells’s importance was primarily as a liberator of thought and imagination. He was able to construct pictures of possible societies, both attractive and unattractive, of a sort that encouraged the young to envisage possibilities which otherwise they would not have thought of. Sometimes he does this in a very illuminating way. His Country of the Blind is a somewhat pessimistic restatement in modern language of Plato’s allegory of the cave. His various Utopias, though perhaps not in themselves very solid, are calculated to start trains of thought which may prove fruitful. He is always rational, and avoids various forms of superstition to which modern minds are prone. His belief in scientific method is healthful and invigorating. His general optimism, although the state of the world makes it difficult to sustain, is much more likely to lead to good results than the somewhat lazy pessimism which is becoming all too common. In spite of some reservations, I think one should regard Wells as having been an important force toward sane and constructive thinking both as regards social systems and as regards personal relations. I hope he may have successors, though I do not at the moment know who they will be.
出典: Bertrand Russell: [On] H. G. Wells, 1953.
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/1037_WELLS-060.HTM
<寸言>
日常にかまけしぼみがちな想像力を(優れた)文学者や芸術家は解放してくれる。子どもの頃は皆想像力がたくましくても,分別がつく大人になるにつれ、想像力の「暴走」に自ら歯止めをかけるようになってしまう。そうしてしだいにコンピュータやロボットで代替可能にしていき、自分で自分の首をしめることになる。