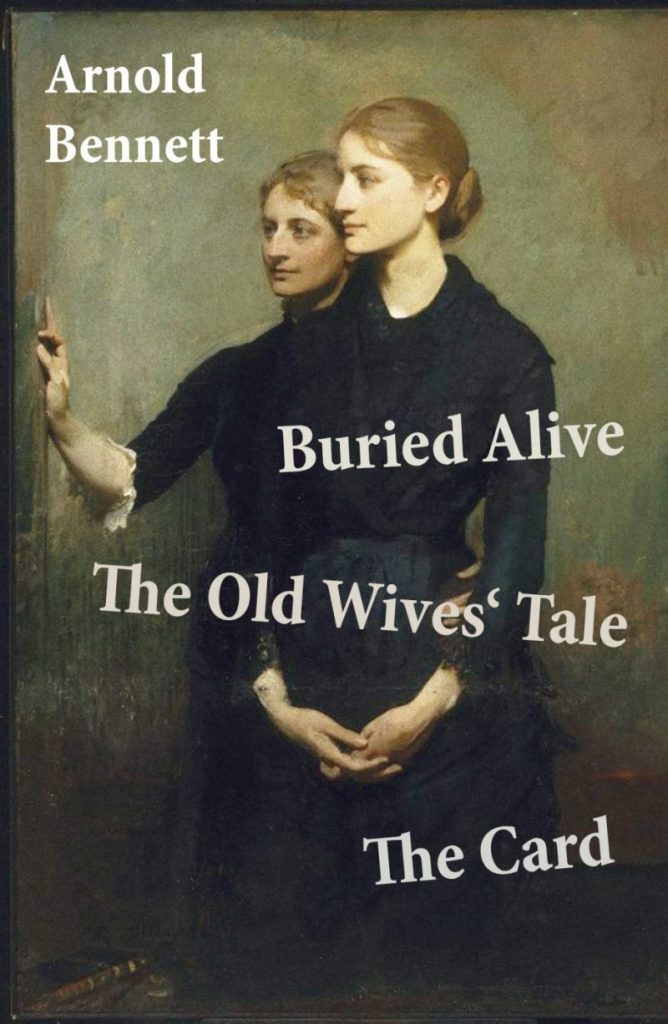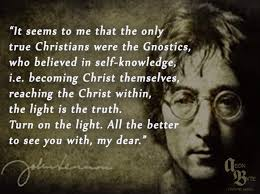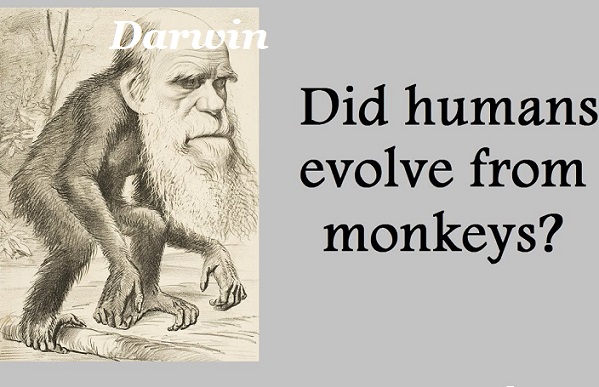
しかし、こういった事柄だけが唯一人間(彼/彼女)が自身を祝福しなければならない(has to congratulate himself)ものではない。というのは、人間はホモ・サピエンス(という高等な種)の一員ではなかったのか? 動物のなかで人間だけ不滅の魂を持っており、かつ、理性的である(はずだ)。即ち、人間は善悪の違いがわかり、九九の表も覚えている。神は神自身の像に似せて(in His own image)人間を創ったのではなかったか?。そうして、あらゆるものは人間の便宜のために創られたのではなかったのか? (たとえば)太陽は日中を照らすために、月は夜を照らすために創られた(のではないか)---ただし、月は何らかの手ぬかりのために(by some oversight)ただ夜間の半分の時間しか輝かないけれども。地上の生(なま)の(いろいろな)果物は人間の栄養のために創られた(のではないか?)。兎の白い尻尾でさえ、一部の神学者(達)によれば、一つの目的、即ち、狩人が兎を撃つのを容易にさせるという目的をもっている(そうである)。いくつか不便なものがあることも、確かである。(たとえば)ライオンや虎は獰猛すぎるし、 夏は暑すぎ、冬は寒すぎる。しかし、これらのことは、アダムがリンゴを食べた以降にのみ始まった(ことである)。 それ以前は、全ての動物は草食(ベジタリアン)であり、そうして、季節は常に春であった。 もしアダムが桃やブドウや西洋ナシやパインアップルだけで満足していたとしたら、これらの恩寵は依然として我々(人間)のものであるはずだろう。
Outline of Intellectual Rubbish (1943), n.18
But these are not the only matters on which he has to congratulate himself. For is he not an individual of the species homo sapiens? Alone among animals he has an immortal soul, and is rational; he knows the difference between good and evil, and has learnt the multiplication table. Did not God make him in His own image? And was not everything created for man’s convenience? The sun was made to light the day, and the moon to light the night — though the moon, by some oversight, only shines during half the nocturnal hours. The raw fruits of the earth were made for human sustenance. Even the white tails of rabbits, according to some theologians, have a purpose, namely to make it easier for sportsmen to shoot them. There are, it is true, some inconveniences: lions and tigers are too fierce, the summer is too hot, and the winter too cold. But these things only began after Adam ate the apple; before that, all animals were vegetarians, and the season was always spring. If only Adam had been content with peaches and nectarines, grapes and pears and pineapples, these blessings would still be ours.
Source: Bertrand Russell : An Outline of Intellectual Rubbish, 1943 Reprinted in: Unpopular Essays, 1950, chapter 7:
More info.: http://www.ditext.com/russell/rubbish.html https://russell-j.com/cool/UE_07-180.HTM