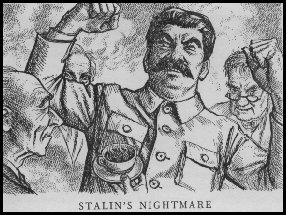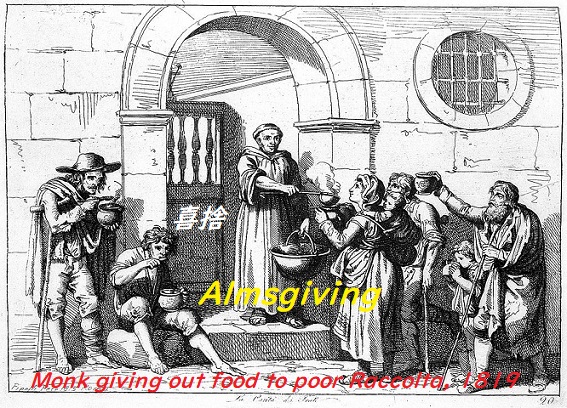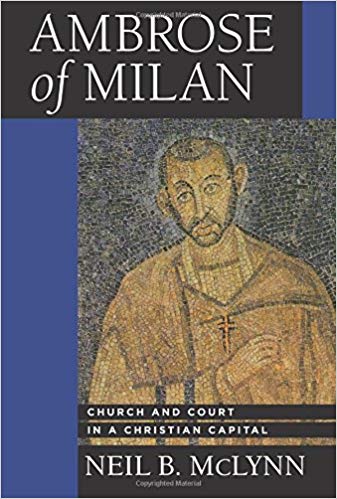===========================
◆8月10日(土)~8月18日(日)まで夏休み休刊とします。◆
===========================
(二)宗教改革(続き)
イングランドでは,ヘンリー八世は,彼らしい精力と冷酷さで(もって)この問題(注:教会の国家への服従)に自ら取り組んだ。彼は自らを英国教会の長であると宣言(布告)することによって,宗教を世俗的かつ国家的なものにする仕事にとりかかった。彼は,イングランドの宗教をもって,キリスト教界(全キリスト教徒)の普遍的宗教の一部でなければならないといった望みはまったく持っていなかった。彼は,イングランドの宗教を,神の栄光よりも自分(ヘンリー八世)の栄光の役に立つ(ものであること)を望んだ。彼は卑屈な議会によって(御用議会を利用して),カトリック教会公認の教義を彼が望むように改変することができた(注:as he chose 望むように/You may stay here if you choose お望みならここにお残りになってけっこうです)。また,そういった改変を嫌った者たちを苦もなく処刑することができた。僧院(修道院)の解散は彼(ヘンリー八世)に収入(歳入)をもたらし,それによって彼は,「恩寵の巡礼(の乱)」(注:the Pilgrimage of Grace 1536年にイングランドの北部で起こった,特に修道院解散に反対した反政府暴動)のようなカトリック教徒の反乱を容易に潰すことができた。火薬や薔薇戦争は,旧い封建的貴族階級を弱体化し,彼はその気になればいつでも,貴族の首を切ることが出来た。ウルジー(注: Thomas Wolsey, 1475-1530, イングランドの聖職者で枢機卿。ヘンリー8世治世の初期に信任を得ていたが後に失脚)は,昔ながらのカトリック教会の権力に頼り,失墜した。クロムウェルとクランマーは,ヘンリー王の御用道具であった。ヘンリー八世は,カトリック教会の失墜において,国家権力がどのようなものでありうるかということを世界に示した,先駆者であった。
Chapter VII: Revolutionary Power, n.12
II. The Reformation.(continued)
In England, Henry VIII took the matter in hand with characteristic vigour and ruthlessness. By declaring himself Head of the Church of England, he set to work to make religion secular and national. He had no wish that the religion of England should be part of the universal religion of Christendom ; he wished English religion to minister to his glory rather than to the glory of God. By means of subservient Parliaments, he could alter dogmas as he chose; and he had no difficulty in executing those who disliked his alterations. The dissolution of the monasteries brought him revenue, which enabled him easily to destroy such Catholic insurrections as the Pilgrimage of Grace. Gunpowder and the Wars of the Roses had weakened the old feudal aristocracy, whose heads he cut off whenever he felt so disposed. Wolsey, who relied upon the ancient power of the Church, fell ; Cromwell and Crammer were Henry’s subservient tools. Henry was a pioneer, who first showed the world what, in the eclipse of the Church, the power of the State could be.
出典: Power, 1938.
詳細情報:https://russell-j.com/beginner/POWER07_120.HTM