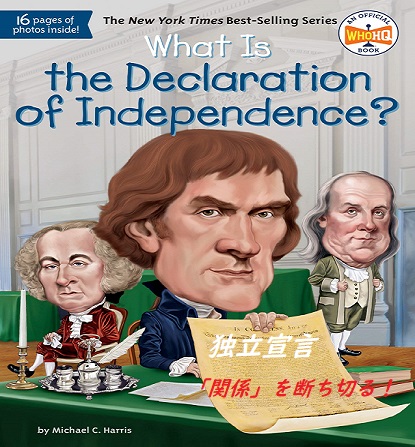私が関係の問題の重要性を初めて認識したのは、私がライプニッツを研究していた時であった。ライプニッツに関する多くの書物が明らかにしえなかったことであるが、ライプニッツの形而上学は明らかに、全ての命題(注:「AはBである」という真偽を判定できる陳述)は(命題は全て)一つの主語に一つの述語を帰属させるものであり、かつ(これはライプニッツにとってはほとんど同じことだと思われたようであるが)全ての事実は、ある特性をもつ実体(a substance)から成る、という学説(理論)を基礎としていることを私は発見した。私はまた、同じ学説(理論)が、スピノザやヘーゲルやブラッドリの体系の基礎にも存在することを発見した。実際,彼らはその学説をライプニッツによって示されたものよりももっと論理的に厳密に展開させたのである。 しかし、私が(自分の)新しい哲学を喜んだのは、これらのかなり無味乾燥な、論理説(論理上の学説)(doctrines”と複数形になっていることから、ラッセルの自分の学説ではなく、ヘーゲルやブラッドリなどの諸学説を指していると推定される。)のためだけではなかった(注:”rather”を野田氏はよくあるように「どちらかと言えば」と訳しているが、ここでは「かなり」と訳したほうがよいであろう。)。私は,実際,大いなる解放感をもったのであって、(生暖かい)温室(a hot-house)を脱出して、風に吹きさらされている岬に出たように感じた。私は空間及び時間は私の精神(心)の中にあるにすぎないという考えのもつ息苦しさ(stufiness 閉塞状態)が大変嫌であった(hated 憎んだ)。私は道徳律(moral law)よりも星空の方をいっそう好み(even better than)、私の一番好きな星空が主観の虚構物(figment 作り事)にすぎないというカントの見解には耐えられなかった。このように解放感にあふれていたはじめの頃、私は素朴実在論者となり、ロック以降の全ての哲学者たちの反対論にもかかわらず、草は本当に緑(色)である(自分の脳内の虚構ではない)という考えを楽しんだ。私はそれ以来この心地よい信念を、その最初の強さで保持し続けることはできなかったが、しかし再び主観という牢獄にわが身を閉じこめることは決してなかった。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.13
I first realized the importance of the question of relations when I was working on Leibniz. I found — what books on Leibniz failed to make clear — that his metaphysic was explicitly based upon the doctrine that every proposition attributes a predicate to a subject and (what seemed to him almost the same thing) that every fact consists of a substance having a property. I found that this same doctrine underlies the systems of Spinoza, Hegel and Bradley, who, in fact, all developed the doctrine with more logical rigour than is shown by Leibniz. But it was not only these rather dry, logical doctrines that made me rejoice in the new philosophy. I felt it, in fact, as a great liberation, as if I had escaped from a hot-house on to a wind-swept headland. I hated the stuffiness involved in supposing that space and time were only in my mind. I liked the starry heavens even better than the moral law, and could not bear Kant’s view that the one I liked best was only a subjective figment. In the first exuberance of liberation, I became a naive realist and rejoiced in the thought that grass is really green, in spite of the adverse opinion of all philosophers from Locke onwards. I have not been able to retain this pleasing faith in its pristine vigour, but I have never again shut myself up in a subjective prison.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-130.HTM
「未分類」カテゴリーアーカイブ
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n12
(続き) それゆえ、関係はそれらの諸項(=各項)の「本性(性質)」あるいは諸項からなる全体の「本性(性質)」に必然的に根拠づけられているという公理(注:axiom 最も基本的な仮定。ここでは「内面的関係説」)に反対すべき諸理由が存在しており、逆に賛成すべき理由はまったく存在していないように思われる。(そうして)この公理が拒否されるならば、ある関係項の「本性(性質)」について語ることは無意味になる。関係性(関係づけられていること)は、もはや複合性の証拠となるものではまったくなく、所与の関係は諸項の多くの異なる対(ペア)の間に成立することができ、また所与の項は異なった項への多くの異なる関係をもつことが可能である(注:複合体に対するものはライプニッツのモナド(単子)/モナドは部分を持たない単純な実体なので、複合的なもの同士が関係するような意味で「関係」することはできない。即ち、モナドには窓がない)。「差異における同一性」は消滅する(注:一元論の根拠の消滅)。(つまり)同一性があり、(また)差異があり、またいろいろな複合体(複合物)は同一の要素をもちうるとともに異なる要素をもちうるけれども、言及される対象のいかなる組合せについてもそれらの対象は「同一であるとともに異なっている」ということを余儀なくさせられることはもはやない。それは「ある意味で」そうであり(「同一であるとともに異なっている」のであり),未定義のままにしておくことが必須のものである。このようにして,多くのものからなる世界を手に入れ、それらの物(多くの物)の間の関係は、それらの物のもついわゆる「本性(性質)」、即ち,スコラ哲学的本質から演繹される必要がなくなる。この世界では、すべての複合物は、関係づけられた単純な事物から成り、もはや分析があらゆる段階で無限後退に直面することはなくなる。このような世界を前提として(想定して)して、真理の本性に関して我々は何を主張することができるかを尋ねることが(課題として)残っている。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.12
There would seem, therefore, to be reasons against the axiom that relations are necessarily grounded in the ‘nature’ of their terms or of the whole composed of the terms, and there would seem to be no reason in favour of this axiom. When the axiom is rejected, it becomes meaningless to speak of the ‘nature’ of the terms of a relation: relatedness is no longer a proof of complexity, a given relation may hold between many different pairs of terms, and a given term may have many different relations to different terms. ‘Identity in difference’ disappears: there is identity and there is difference, and complexes may have some elements identical and some different, but we are no longer obliged to say of any pair of objects that may be mentioned that they are both identical and different — ‘in a sense’, ‘this sense’ being something which it is vitally necessary to leave undefined. We thus get a world of many things, with relations which are not to be deduced from a supposed ‘nature’ or scholastic essence of the related things. In this world, whatever is complex is composed of related simple things, and analysis is no longer confronted at every step by an endless regress. Assuming this kind of world, it remains to ask what we are to say concerning the nature of truth.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-120.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n11
(続き) さらにまた、内的関係(内面的)の公理はあらゆる複合性(complexity 複雑性)とは両立しない(相容れない)。なぜなら、既に見たように、この公理(内的関係説)は厳格な一元論(monism)に導くからである。(即ち、)ただ一つのものだけが存在し、ただ一つの命題だけが存在する(ということになる)。その一つの命題(それはただ一つの真なる命題ではなく、ただ一つの命題である)は、一つの述語を一つの主語に帰属させる。しかしこのただ一つの命題は、主語から述語を区別することを(不可欠のものとして)含んでいるゆえに、必ずしも真ではない(not quite true)。しかし,その場合(then そうなると)(次のような)困難が生ずる。(即ち)もし叙述(predication :AはBである)が述語は主語とは異なるものであるということを(必然的に)含んでいるものであり、しかも(そのうえまた)唯一の述語が唯一の主語から区別されないものだとすると、その唯一の述語を唯一の主語に帰属させるところの命題なるものは、(真なる命題としてだけでなく)偽なる命題としてさえも存在することができない,と思うだろう。それゆえ、我々は、叙述(注:predecation 述語づけ/叙述付加)が、述語と主語との差別を含まず(伴わず)、またこの唯一の述語は唯一の主語と同一である(注:一体のものである)と想定(仮定)しなければならないであろう。しかし、我々がいま吟味している哲学(注:観念論哲学)にとっては、絶対的同一性を否定して「差異における同一性」を保持することが、必須である。そうでないとしたら,実在的世界の見かけ上の(apparent)多様性は説明不可能である(注:現実世界は多様かそうでないかは議論の対象/また観念論哲学では現実世界の多様性はあくまでも「現象」であり「実体ではない」と考えるので、「apparent」は「明らかに」ではなく「見かけ上は」と訳すべきであろう。因みに、みすず書房の野田訳では「明らかに」と訳されている)。しかし困難は、我々が厳密な一元論に固執すれば差異における同一性」は不可能である(不可能になる)ことである。なぜなら、「差異における同一性」は多くの部分的真理を含み(必然的に伴い)、それらの部分的真理は、一種の相互のギブ・アンド・テイクによって、一つの全体的真理を形成するからである。厳密な一元論においては、部分的真理は必ずしも真ではないというだけではない。(即ち厳密な一元論においては)そういう部分的真理なるものはまったく成立しない(のである)。真であるにせよ偽であるにせよ,仮にそういう諸命題が存在するとすれば 複合性(plurality 一つではなく多数であること)が存在することになるであろう。要するに、「差異における同一性」という考えは内的関係の公理(内的関係説)と両立しない(相容れない)のである。(そうして)しかも、この概念(「差異における同一性」)がなくては一元論は世界(の見かけ上の多様性)の説明を与えることができず、世界はオペラ用の帽子(opera-hat)のように突然つぶれてしまう。(そこで)私は、内的関係の公理(内的関係説)は偽であり、観念論の主張のうちこの公理に依存する部分は根拠がない、と結論する(しだいである)。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.11
Again, the axiom of internal relations is incompatible with all complexity. For this axiom leads, as we saw, to a rigid monism. There is only one thing, and only one proposition. The one proposition (which is not merely the only true proposition, but the only proposition) attributes a predicate to the one subject. But this one proposition is not quite true, because it involves distinguishing the predicate from the subject. But then arises the difficulty: if predication involves difference of the predicate from the subject, and if the one predicate is not distinct from the one subject, there cannot, even, one would suppose, be a false proposition attributing the one predicate to the one subject. We shall have to suppose, therefore, that predication does not involve difference of the predicate from the subject, and that the one predicate is identical with the one subject. But it is essential to the philosophy we are examining to deny absolute identity, and retain ‘identity in difference’. The apparent multiplicity of the real world is otherwise inexplicable. The difficulty is that ‘identity in difference’ is impossible, if we adhere to strict monism. For ‘identity in difference’ involves many partial truths, which combine, by a kind of mutual give and take, into the one whole of truth. But the partial truths, in a strict monism, are not merely not quite true: they do not subsist at all. If there were such propositions, whether true or false, that would give plurality. In short, the whole conception of ‘identity in difference’ is incompatible with the axiom of internal relations; yet without this conception, monism can give no account of the world, which suddenly collapses like an opera-hat. I conclude that the axiom is false, and that those parts of idealism which depend upon it are therefore groundless. Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959. More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-110.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n10
<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>
内的関係の公理(注:「内面的関係」を「内的関係」に変更/内的関係説)に反対するもっと綿密な議論(論証)(A more searching argument)は、ひとつの項(term)の「本性(性質)」は何を意味するか(項の「本性(性質)」の意味)について考察することに由来している。「項の本性(性質)」は、「項そのもの」と同一なのか、あるいは異なっているのか。もし異なっているとすればと本性(性質)は項に対してある関係をもたなければならないことになり、この関係は、無限後退におちいることなしに、関係以外の何ものかに還元することはできない。従って(thus こうして)この公理(内的関係説)が支持されるべきだとするなら、項がその本性(性質)と異なったものではない,と想定しなければならない。その場合には、(一つの)述語(a predicate)を(一つの)主語(a subject)に帰属させるあらゆる真なる命題は、純粋に分析的なもの(分析命題)となる。なぜなら、主語はそれ自身の全ての本性(性質)の全体(注:its own whole nature)であり、述語はその本性(性質)の部分(一部)であるからである。しかし、この場合、(いくつかの)述語を、一つの主語の(配下の)述語として結合させる接着剤は何であろうか? もしも主語が、それ自身の述語の体系そのものに他ならないとすれば、いくつかの述語の任意のいかなる集まり(集合体)でも、ひとつの主語を構成しうると考えられることになるであろう(注:倒置型になっている。/一般人の常識では主語と述語は別物であるが「主語=諸述語の集合体」だと考えることも可能)。もし一つの項の「本性(性質)」が多くの述語からなるものであり、そしてそれが同時に項そのものと同一のものであるならば、一体主語Sが述語Pを持つかどうかと問う場合に、その問いの意味を理解することが不可能であるように思われる。なぜなら、この問いは「Pは、Sの意味を説明する場合に枚挙される述語のうちの一つであるか」という意味ではもちろんありえないのであるが、上の見解によれば、そういう意味に取るより他ない(他の意味にとることができない)ように見えるからである。つまり今議論している(問題にしている)見解では --ある述語(predicates 述部)が一つの主語の述語であると言われるための根拠となるところの(in virtue of which they may be called predicates of one subject)-- いろいろの述語の間の「コヒーレンス」の関係(注:a relation of coherence 全体を貫く一つの関係/全体を束ねる一つの関係?)を導入しようとしてもできない。というのは、それは関係を述語に還元するのではなく、叙述(predications)を一つの関係に基礎づけることになるだろうからである。このようにして,我々は、主語がそれ自身の「本性(性質)」とは異なると考えてもまた異ならないと考えても、同様な困難に陥ることになる。〔「この点については私の著書『ライプニッツの哲学』第21節、24節、25節を参照〕
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.10
A more searching argument against the axiom of internal relations is derived from a consideration of what is meant by the ‘nature’ of a term. Is this the same as the term itself, or is it different? If it is different, it must be related to the term, and the relation of a term to its nature cannot, without an endless regress, be reduced to something other than a relation. Thus if the axiom is to be adhered to, we must suppose that a term is not other than its nature. In that case, every true proposition attributing a predicate to a subject is purely analytic, since the subject is its own whole nature, and the predicate is part of that nature. But in that case, what is the bond that unites predicates into predicates of one subject? Any casual collection of predicates might be supposed to compose a subject, if subjects are not other than the system of their own predicates. If the ‘nature’ of a term is to consist of predicates, and at the same time to be the same as the term itself, it seems impossible to understand what we mean when we ask whether S has the predicate P. For this cannot mean; ‘Is P one of the predicates enumerated in explaining what we mean by S?’ and it is hard to see what else, on the view in question, it could mean. We cannot attempt to introduce a relation of coherence between predicates, in virtue of which they may be called predicates of one subject; for this would base predication upon a relation, instead of reducing relations to predications. Thus we get into equal difficulties whether we affirm or deny that a subject is other than its ‘nature’. [[On this subject, cf. my Philosophy of Leibniz, §§ 21 , 24 , 25]
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-100.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n,9
<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>
(続き) (そこで)内面的関係の公理(内面的関係説)に反対する(否定する)何らかの根拠(理由)があるかどうかを尋ねること(仕事/作業)が残っている。この公理に反対する者の頭に(脳裏に)自然に思い浮ぶ第一の議論(論証)は、内面的関係の公理を現実に遂行することの困難さである。我々は(既に)異他性(diversity 多様性)についてその一例を示した。それ以外の多くの他の例では、困難はさらにあきらかである。たとえば、ある量(体積)が別の量(体積)よりも大(きい)としてみよう。これら二つの量(体積)の間の「より大きい」という関係を、-- 一方を”これこれの大きさの”(ものであり)、もう一方を”これこれの大きさの”(ものである)と言うことによって-- それぞれの量(体積)についての形容詞的規定に還元しようするかもしれない。。しかしその場合には(そう言ってもなおその上に)一方の大きさは他方の大きさよりも大である(より大きい)と言わなければならない。そこでさらに、この新たな関係〔二つの大きさの間の関係〕をも、二つの大きさがそれぞれにもつ形容詞的規定に還元しようと試みるならば、それら形容詞的規定がまたやはり、「より大」に対応する関係をもたなければならないことになり、以下同様である。従って無限後退を避けようとすれば、結局は関係項がそれぞれ持つ形容詞的規定に還元できないひとつの関係に至らざるをえないことを認めなければならない。この議論(論証)は特に、非対称的な関係、即ち、AとB(A→B)との間に成り立つならばBとAとの間(B→A)には成り立たないような関係、にあてはまる。〔上にただ示すのみにとどめた議論は、私の著書『数学の諸原理』(1903年刊)の第212節から216にわたって詳細に述べられている。〕
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.9
It remains to ask whether there are any grounds against the axiom of internal relations. The first argument that naturally occurs to an opponent of this axiom is the difficulty of actually carrying it out. We have had one instance of this as regards diversity; in many other instances, the difficulty is even more obvious. Suppose, for example, that one volume is greater than another. One may reduce the relation ‘greater than’ between the volumes to adjectives of the volumes, by saying that one is of such and such a size and the other of such and such another size. But then the one size must be greater than the other size. If we try to reduce this new relation to adjectives of the two sizes, the adjectives must still have a relation corresponding to ‘greater than’, and so on. Hence we cannot, without an endless regress, refuse to admit that sooner or later we come to a relation not reducible to adjectives of the related terms. This argument applies especially to all asymmetrical relations, i.e. to such as, when they hold between A and B, do not hold between B and A. [The argument which is merely indicated above, is set forth fully in my Principles of Mathematics, §§ 212-216 .]
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-090.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.,8
<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>
(続き) (2) この議論(論証の強さ(力)は主に誤まった陳述形式に依存している,と私は考える。(即ち=その誤った陳述形式とは)「もしAとBがある一定の関係にあるならば、次のように言ってよいであろう。即ち、もしそれらがそのように関係づけられていないとすると、それら(A及びBの2つの項)は、現にあるものとは違ったもの(other than they are)になるであろうと認めなければならず、またその結果、それらが現にあるように関係づけられている存在にとって本質的な何らかのものがそれら(A及びB)自身の中になければならない」。 ところで(Now)、二つの項が現にある一定の関係を持つ場合、それがそのように関係づけられていないとしたら、あらゆる結果が後に続くことになるであろう(ensue 続く)。なぜなら、それらが”現に”(実際に)そのように関係づけられているとすると、そのように関係づけられていないという仮定は偽であり、しかも偽なる仮定からは、いかなる命題でも演繹しうるからである(注:一つでも偽の命題を認めると、あらゆる命題も演繹できるというのは論理学の常識です)。従って(thus こうして)上記の陳述形式は変更されなければならない(ということになる)。そこで次のように言ってよいだろう。「AとBとがある一定の関係を持つならば、そのような関係を持たないいかなるものも、A及びB以外のもの(AとBとは違ったもの)でなければならない、云々。」 しかしこれは、AとBとの関係のように関係づけられていないものは,AあるいはBとは数的に異なっていなければならないということを証明するのみである(注:質の違いについては何も言うことができない)。それは、内面的関係の公理(内面的関係説)を仮定しないかぎり、形容詞的規定の相違を証明しない(のである)。前述の議論は、レトリックな議論であるのみであり、悪しき循環論に陥ることなくその結論を証明することはできないのである。(循環論法に陥ってしまって証明不可能,ということ)
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.8 (2)
The force of this argument depends in the main, I think, upon a fallacious form of statement. ‘If A and B are related in a certain way’, it may be said, ‘you must admit that if they were not so related they would be other than they are, and that consequently there must be something in them which is essential to their being related as they are.’ Now if two terms are related in a certain way, it follows that, if they were not so related, every imaginable consequence would ensue. For, if they are so related, the hypothesis that they are not so related is false, and from a false hypothesis anything can be deduced. Thus the above form of statement must be altered. We may say: ‘If A and B are related in a certain way, then anything not so related must be other than A and B, hence, etc.’ But this only proves that what is not related as A and B are must be numerically diverse from A or B; it will not prove difference of adjectives, unless we assume the axiom of internal relations. Hence the argument has only a rhetorical force, and cannot prove its conclusion without a vicious circle.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-080.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.7
<しばらく小難しい議論が続きます。わかりにくいとことは飛ばしてください。>
(続き) (1) 充足理由律を正確に述べることは難しい。それは,あらゆる真なる命題が他の何らかの真なる命題から論理的に演繹可能であるということ‘だけ’を意味するとは言えない。なぜなら、それは明らかな真理ではあるが、充足理由律に要求する結果を生まないからである。たとえば、2 + 2 = 4 は 4 + 4 = 8 から演繹可能であるが、だからといって、4 + 4 = 8 を 2 + 2 = 4 の理由(が正しい理由)とみなすことは馬鹿げているであろう。ある(一つの)命題が正しい理由は、その命題よりももっと単純な、一つまたは2つ以上の命題であると常に予想(期待)される。従って(Thus こうして)充足理由律はあらゆる命題は(その命題よりも)より単純な命題から演繹可能であるということを意味すべきであろう。これは明らかに偽である(間違っている)と思われるが、いずれにせよ、観念論を考える時、適切ではありえない。(なぜなら)観念論は、命題が単純であればあるほどそれだけ真でないと主張するものであり、従って、単純な命題を出発点とすべきだというのは(観念論の立場から言えば)不合理であろうからである。それゆえ、私は次のように結論を下す。もし充足理由律の任意の(何らかの)形態が適切であるとしたら、それは内面的関係の公理を肯定する(賛成する前述の)第二番目のもの(理由)、即ち、関係づけられた諸項は現にあるがごとくに関係づけられてあるよりほかはない(cannot but)、ということの吟味(点検)の中にむしろ見出されるべきである,と。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.7 (1) The law of sufficient reason is hard to formulate precisely. It cannot merely mean that every true proposition is logically deducible from some other true proposition, for this is an obvious truth which does not yield the consequences demanded of the law. For example, 2 + 2 = 4 can be deduced from 4 + 4 = 8, but it would be absurd to regard 4 + 4 = 8 as a reason for 2 + 2 = 4. The reason for a proposition is always expected to be one or more simpler propositions. Thus the law of sufficient reason should mean that every proposition can be deduced from simpler propositions. This seems obviously false, but in any case it cannot be relevant in considering idealism, which holds propositions to be less and less true the simpler they are, so that it would be absurd to insist on starting from simple propositions. I conclude, therefore, that, if any form of the law of sufficient reason is relevant, it is rather to be discovered by examining the second of the grounds in favour of the axiom of relations, namely, that related terms cannot but be related as they are.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-070.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.6
(煩瑣な議論がこのあと5,6回続きますが、飛ばしていただいてけっこうです。内面的関係の理論は間違いであり、外面的関係の理論の方が正しいというラッセルの考えがわかればOKです。)
内面的関係の公理(内面的関係説)に賛成する理由(根拠)が何であるかを自問する時、我々はその公理(の正しさ)を信ずる人々(の言うところ)によって、疑いを抱かされる(are left in question)。たとえばヨアキム氏(Harold Joachim, 1868-1938,ヨアヒムと表記している人もいる)は、終始この公理を前提としていて、しかも、それに賛成する議論(argument 論拠)をまったく提示しない。しかし, 我々が発見できる限りにおいて言えば、その理由(根拠)は二つあると思われる。ただし,これら二つの理由(根拠)は、恐らく、実際には(really)、区別できないものであろう。(即ち)第一に、充足理由律(the law of sufficient reason)があり、それによれば、いかなるものも単なる生の事実(注:just a brute fact:哲学の分野で使われる言葉で、それ以上基礎的な何かによっては説明されないような事実のこと)であるということはなく、そうであってそうでないことはないという(と言える)何らかの理由を有していなければならない。〔ブラッドリー『現象と実在』第二版 p.575に言う、「もし諸項(関係項)が、それ自身の内的本性(性質)からその関係に入っていくのでなければ、その場合は、それらの諸項(関係項)に関する限り、全く理由なしに関係づけられていると思われ、それらの諸項(関係項)に関する限り、関係は恣意的に作られていると思われる。」p.577も参照のこと〕 第二は、もし二つの項がある一定の関係を持つならば、それらの諸項(関係項)はその関係を持たざるをえないのであって、もしそれらがその関係を持たないとすれば、それら二つの項は、異なったものであるであろう、ということである。このことは、諸項(関係項)そのものの中に何かがあって、それが諸項(関係項)をして現在そうであるように関係づけられるように導くということを示しているように見える。
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.6 If we ask ourselves what are the grounds in favour of the axiom of internal relations, we are left in doubt by those who believe in it. Mr Joachim, for example, assumes it throughout, and advances no argument in its favour. So far as one can discover the grounds, they seem to be two, though these are perhaps really indistinguishable. There is first the law of sufficient reason, according to which nothing can be just a brute fact, but must have some reason for being thus and not otherwise. [Cf. Appearance and Reality, 2nd ed., p. 575: ‘If the terms from their own inner nature do not enter into the relation, then, so far as they are concerned, they seem related for no reason at all, and, so far as they are concerned, the relation seems arbitrarily made,’ cf. also p. 577.] Secondly, there is the fact that, if two terms have a certain relation, they cannot but have it, and if they did not have it they would be different; which seems to show that there is something in the terms themselves which leads to their being related as they are.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-060.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.5
従って(thus こうして),内面的関係の公理(内面的関係説)は、あらゆる命題は一つの主語と一つの述語とを持つという仮定に等しい(equivalent to 相当する)。なぜなら、一つの関係を主張する命題は、その関係の項に対して構成される全体(the whole composed to)に関する主語-述語命題に還元されるからである。このようにして、より大きな全体へと進んでゆくことにより、我々は徐々に当初のおおざっぱな(crude 粗野な)抽象的な判断を訂正し、全体についての一つの真理へと近づいてゆく。最終的かつ完全な一つの真理は、一つの主語,即ち,全体と一つの述語とで構成されていなければならない。しかし,これ(一つの主語述語命題)は(これも)、主語と述語との区別を伴っており(含んでおり)、両者が異なったものでありうるかのごとくであるゆえに、これさえも完全に真であるとは言えない。それについて言える最上のことは,それ(一つの主語述語命題)は「知性によって修正する」ことはできない( not ‘intellectually corrigible’),即ち、それは最高度に真である(it is as true as any truth can be)ということである。しかし,そのような絶対的真理でさえ、完全な真ではないままである(persist in being not quite true)。〔参照:ブラッドリー『現象と実在』第一版p.544 にあるように「こうして,(知的には)絶対的真理であってさえも、最終的には誤まっていることが明らかになるように思われる。そして.最終的には、いかなる真理も完全に真であることはないということを認めなければならない。それ(真理)は、それが丸ごと(bodily)示そうとするものの、部分的かつ不十分な翻訳(translation 移転)なのである。このような内面的分裂が、真理というものの本来の性質に属していて、除去できないのである。しかし,絶対的な真理と有限な真理との間の区別は、それにもかかわらず、維持されなければならない。なぜなら絶対的真理(のほう)は、要するに、知的見地から見て誤謬の余地がないものであるからである。」〕
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.5
The axiom of internal relations is thus equivalent to the assumption that every proposition has one subject and one predicate. For a proposition which asserts a relation must always be reduced to a subject-predicate proposition concerning the whole composed to the terms of the relation. Proceeding in this way to larger and larger wholes, we gradually correct our first crude abstract judgments, and approximate more and more to the one truth about the whole. The one final and complete truth must consist of a proposition with one subject, namely, the whole, and one predicate. But since this involves distinguishing subject from predicate, as though they could be diverse, even this is not quite true. The best we can say of it is, that it is not ‘intellectually corrigible’, i.e. it is as true as any truth can be; but even absolute truth persists in being not quite true. [Cf. Appearance and Reality, 1st ed., p. 544: ‘Even absolute truth seems thus to turn out in the end to be erroneous. And it must be admitted that, in the end, no possible truth is quite true. It is a partial and inadequate translation of that which it professes to give bodily. And this internal discrepancy belongs irremovably to truth’s proper character. Still, the difference, drawn between absolute and finite truth, must none the less be upheld. For the former, in a word, is not intellectually corrigible.’]
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-050.HTM
ラッセル『私の哲学の発展』第5章 「一元論にそむいて多元論へ」 n.4
(続き)内面的関係の公理(内面的関係説)は、(この/前述の)どちらの形態においても、 ブラッドリ氏が正しく(も)主張したように 〔参照:『現象と実在』第二版、p.519の,「実在(しているもの)は一(の全体)である。実在は単一でなければならない。なぜなら複数性(複数存在すること)は、それを実在的である(注:現実に存在する)と考えると(taken as real)、自己矛盾に陥るからである。複数性は、必然的に関係を含み(注:複数のものが存在すれば両者の間になんらかの関係が生じる/たとえばAはBの上に置かれている)、その関係によって、自らの意に反して(unwillingly)、より高い統一を常に主張する。」〕、 関係というものは(まったく)存在せずまた、複数のもの(多様なもの)は存在せず、ただ一つのもののみが存在する、という帰結を伴う。(観念論者たちは、「究極において(そう帰結する)」と(いう言葉を)常につけ加える。しかしそれ(究極においてという言い方)は、その帰結を忘れることがしばしば好都合であると言っているだけである。)この帰結は、多様性(diversity 異他性)という関係を考えてみることによって達せられる。なぜなら、もし本当に二つの異なるもの(別物)としてAとBとが存在するならば、この多様性(異他性)を、AとBとの(共通の一つの)形容詞的規定/表現に還元することはまったく不可能だからである(注: it is impossible wholly to reduce this diversity to adjectives:みすず書房の野田訳では「全てを還元することは不可能」と訳されているが、impossible wholly to reduce となっていることから誤訳)。この場合、AとBとがお互いに異なる形容詞的規定/表現を持つことが必要であるであろうが、これらの形容詞的規定/表現そのものの多様性/異他性は、 --無限後退の刑に処せられて(訳注:on pain of ~の刑に処すとい条件で/an endless regress 無限後退)-- 再びそれら形容詞的規定がまた,異なる形容詞的規定/表現をもつことを意味する、と解釈することはできない。即ち、AとBとが異なるのは、Aが「Bと異なる」という形容詞をもち、Bは「Aと異なる」という形容詞を持つ場合である、というならば、我々は、もちろんこの二つの形容詞的表現/規定そのものが相異なると想定しているのでなければならない。そうなると「Aと異なる」は「『Bと異なる』とは異なる」という形容詞的規定/表現を持たなければならず、また「Bと異なる」は、「『Aと異なる』とは異なる」のでなければならず,このようにして無限に(ad infinitum)進むことになる。(そうしてまた)我々は、「Bと異なる」をもはやそれ以上の還元を必要としない形容詞的規定/表現とみなすこともできない。なぜならば、「Bと異なる」という句において「異なる」とは何を意味するかを問わなければならず、しかもこの句は、そのままでは(as it stands)、関係(があること)から生まれた形容詞であって、形容詞から生まれた関係ではないからである。こうして,何らかの異他性/多様性があるべきであるならば、必然的に、形容詞的規定/表現の相違に還元できない異他性/多様性、すなわち相違している二つの項の「本性」(性質)に根拠づけられていないところの異他性、多様性がなければならないからである。従って、もし内面的関係の公理(内面的関係説)が真であるならば、異他性/多様性は存在しないということになり、存在するのはただ一つのものだけである、ということになる。こうして内面的関係の公理(内面的関係説)は、存在論的一元論の仮定、及び関係の存在の否定、に等しいのである。関係があるように見える場合,常に,それは,実はその関係の項より成る全体のもつ一つの形容詞的規定/表現にほかならないのである。(注:こうして,この後にラッセルは関係は存在するとしたら,外面的関係でなければならないと主張することになる。)
Chapter 5: Revolt into Pluralism, n.4 The axiom of internal relations in either form involves, as Mr Bradley has justly urged [“cf. Appearance and Reality, 2nd ed., p. 519: ‘Reality is one. It must be single because plurality, taken as real, contradicts itself. Plurality implies relations, and, through its relations it unwillingly asserts always a superior unity”], the conclusion that there are no relations and that there are not many things, but only one thing. (Idealists would add: in the end. But that only means that the consequence is one which it is often convenient to forget.) This conclusion is reached by considering the relation of diversity. For if there really are two things, A and B, which are diverse, it is impossible wholly to reduce this diversity to adjectives of A and B. It will be necessary that A and B should have different adjectives, and the diversity of these adjectives cannot, on pain of an endless regress, be interpreted as meaning that they in turn have different adjectives. For if we say that A and B differ when A has the adjective ‘different from B’ and B has the adjective ‘different from A’, we must suppose that these two adjectives differ. Then ‘different from A’ must have the adjective ‘different from “different from B”,’ which must differ from ‘different from “different from A”,’ and so on ad infinitum. We cannot take ‘different from B’ as an adjective requiring no further reduction, since we must ask what is meant by ‘different’ in this phrase, which, as it stands, derives an adjective from a relation, not a relation from an adjective. Thus, if there is to be any diversity, there must be a diversity not reducible to difference of adjectives, i.e. not grounded in the ‘natures’ of the diverse terms. Consequently, if the axiom of internal relations is true, it follows that there is no diversity, and that there is only one thing. Thus the axiom of internal relations is equivalent to the assumption of ontological monism and to the denial that there are any relations. Wherever we seem to have a relation, this is really an adjective of the whole composed of the terms of the supposed relation.
Source: My Philosophical Development, chap. 5:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_05-040.HTM