『ラッセル自伝』第3巻(1969年刊)への後書きに代えて(最後のところ)
私の仕事(活動)は終りに近づいており(1969年,ラッセル97歳),私の仕事(活動)を一つの全体として概観できる時がきている。私は,どれだけ成功したのか? またどれだけ失敗したのか?
 私は,若い時から,自分は人生を偉大かつ困難な仕事に捧げていると考えていた。ほぼ3/4世紀前(注:『ラッセル自伝』第3巻は1969年の出版。ラッセルがティーア・ガルテン(注:ベルリンの大公園=右写真:)を散策したのは1895年。従って正確にいうと74年前),冷たくきらきら光る3月の太陽のもとで融け始めた雪を踏んでティーアガルテンの中をひとりで歩きながら,私は二種類の系列の本を書こうと決意した。一つは抽象的なもので次第に具体的になってゆく系列の本,もう一つは具体的なもので次第に抽象的になってゆく系列の本である。それらは純粋理論を実際的な社会哲学と結びつけた一つの総合によって栄誉を与えられる(有終の美を飾る)予定であった。いまだ達成できていない最終的な総合を除けば,私はそれらの本をこれまで書いてきた。それらの本は,喝采を浴び,賞讃され,多くの男女の思考はそれらの本の影響を受けた。この程度まで,私は成功した。
私は,若い時から,自分は人生を偉大かつ困難な仕事に捧げていると考えていた。ほぼ3/4世紀前(注:『ラッセル自伝』第3巻は1969年の出版。ラッセルがティーア・ガルテン(注:ベルリンの大公園=右写真:)を散策したのは1895年。従って正確にいうと74年前),冷たくきらきら光る3月の太陽のもとで融け始めた雪を踏んでティーアガルテンの中をひとりで歩きながら,私は二種類の系列の本を書こうと決意した。一つは抽象的なもので次第に具体的になってゆく系列の本,もう一つは具体的なもので次第に抽象的になってゆく系列の本である。それらは純粋理論を実際的な社会哲学と結びつけた一つの総合によって栄誉を与えられる(有終の美を飾る)予定であった。いまだ達成できていない最終的な総合を除けば,私はそれらの本をこれまで書いてきた。それらの本は,喝采を浴び,賞讃され,多くの男女の思考はそれらの本の影響を受けた。この程度まで,私は成功した。
しかし,これに対し,二種類の失敗,即ち,外的な失敗と内的な失敗を対置しなければならない。
外的失敗から始めると,ティーアガルテンは荒れ果ててしまった。ティーアガルテンに入るために,当時の3月の朝,通り抜けたブランデンブルク門は二つの敵対する帝国(注:東側と西側)の境界になり,両者は障壁の向う側をお互いをにらみつけ,残忍にも人類の滅亡の準備をしている。共産主義者,ファシスト,ナチスは,相継いで私が良いと思った全てに挑戦して(正当性に異議を唱えて)成功し,それらを打ち負かす過程で,彼らの敵対者(注:連合国側)が保持しようとしたものの多くは失われつつある。自由(であること)は弱さ(である)と考えられるようになり,寛容は背信(裏切り)の衣装を身につけるように強いられてきた。古い理想は不適切(時代に合わない)と判断され,粗野でないいかなる教義も尊敬を払われない。
内的失敗は,--世界にとっては(私ラッセルは)ほとんど一瞬のことではあるが--,私の精神生活を絶えざる闘争へと化した。私は,プラトン的な永遠の世界への多少とも宗教的な信仰から出発(門出)したが,そこでは数学が(ダンテの)『神曲-天国篇』(Paradiso)の最後の篇におけるような美をもって輝いていた。だが永遠の世界はつまらないものであり,数学はたんに同じことを別の言葉で表現する技術にすぎないという結論に到達した。(また)自由で勇気を伴った愛は,闘わずして世界を克服できるという信念から出発した。(しかし)厳しくて恐ろしい戦争(注:第二次世界大戦)を支持するようになった。これは(内的)失敗であった。
しかし,このようなあらゆる失敗の重荷の下にあっても,私には勝利と感じられるいくらかのものをまだ意識している。私は理論的真理というものを間違ってとらえたかもしれないが,そのような真理が存在し,それらの真理は忠誠に値すると考えたことにおいて,間違ってはいなかった。私は自由と幸福な人間の世界への道(道程)が,現実に示されつつあるものよりもずっと短いと思ったかもしれないが,そのような世界が可能であり,そのような世界を我々のより身近なところにもたらそうという目的をもって生きることは価値あることであると考えたことにおいて,間違ってはいなかった。
私は,個人的にも社会的にも,ある夢想(vision)を追求しながら生きてきた。(即ち)個人的には,高貴なもの,美しいもの,優しいものを大切にし,より平凡な時代において,知恵を生み出すための内省的な時間を(自らに)与えることである。社会的には,創造されるべき社会を想像力によって見ることである。創造すべきは,個人が自由に成長し,憎悪や貪欲や妬みを育むものがないために,それらが死滅している社会である。これらのことを私は信じ,世界のあらゆる恐怖にもかかわらず,世界は私を動揺させなかったのである。(終)
Postscript (3/3)
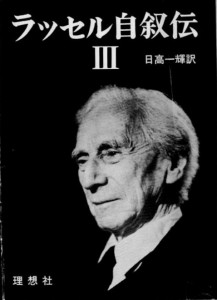 My work is near its end, and the time has come when I can survey it as a whole. How far have I succeeded, and how far have I failed ? From an early age I thought of myself as dedicated to great and arduous tasks. Nearly three-quarters of a century ago, walking alone in the Tiergarten through melting snow under the coldly glittering March sun, I determined to write two series of books: one abstract, growing gradually more concrete; the other concrete, growing gradually more abstract. They were to be crowned by a synthesis, combining pure theory with a practical social philosophy. Except for the final synthesis, which still eludes me, I have written these books. They have been acclaimed and praised, and the thoughts of many men and women have been affected by them. To this extent I have succeeded.
My work is near its end, and the time has come when I can survey it as a whole. How far have I succeeded, and how far have I failed ? From an early age I thought of myself as dedicated to great and arduous tasks. Nearly three-quarters of a century ago, walking alone in the Tiergarten through melting snow under the coldly glittering March sun, I determined to write two series of books: one abstract, growing gradually more concrete; the other concrete, growing gradually more abstract. They were to be crowned by a synthesis, combining pure theory with a practical social philosophy. Except for the final synthesis, which still eludes me, I have written these books. They have been acclaimed and praised, and the thoughts of many men and women have been affected by them. To this extent I have succeeded.
But as against this must be set two kinds of failure, one outward, one inward.
To begin wirh the outward failure: the Tiergarten has become a desert; the Brandenburger Tor, through which I entered it on that March morning, has become the boundary of two hostile empires, glaring at each other across a barrier, and grimly preparing the ruin of mankind. Communists, Fascists, and Nazis have successfully challenged all that I thought good, and in defeating them much of what their opponents have sought to preserve is being lost. Freedom has come to be thought weakness, and tolerance has been compelled to wear the garb of treachery. Old ideals are judged irrelevant, and no doctrine free from harshness commands respect.
The inner failure, though of little moment to the world, has made my mental life a perpetual battle. I set out with a more or less religious belief in a Platonic eternal world, in which mathematics shone with a beauty like that of the last Cantos of the Paradiso. I came to the conclusion that the eternal world is trivial, and that mathematics is only the art of saying the same thing in different words. I set out with a belief that love, free and courageous, could conquer the world without fighting. I came to support a bitter and terrible war. In these respect, there was failure.
But beneath all this load of failure I am still conscious of something that I feel to be victory. I may have conceived theoretical truth wrongly, but I was not wrong in thinking that there is such a thing, and that it deserves our allegiance. I may have thought the road to a world of free and happy human beings shorter than it is proving to be, but I was not wrong in thinking that such a world is possible, and that it is worth while to live with a view to bringing it nearer. I have lived in the pursuit of a vision, both personal and social. Personal: to care for what is noble, for what is beautiful, for what is gentle: to allow moments of insight to give wisdom at more mundane times. Social: to see in imagination the society that is to be created, where individuals grow freely, and where hate and greed and envy die because there is nothing to nourish them. These things I believe, and the world, for all its horrors, has left me unshaken.
出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.3:1944-1969 ,chap4:The Foundation,(1969)
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/AB-POST03.HTM
[寸言]
『ラッセル自伝』から多数抜粋してご紹介してきましたが、これで終了です。ラッセルのポータルサイトには、付録の書簡部分を除いて、全文(英文+邦訳)を掲載していますので、通してお読みに成ることをお勧めします。
http://russell-j.com/beginner/AUTOBIO.HTM
ご愛読ありがとうございました。
