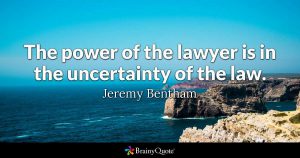第六章 ロマンティックな恋愛 n.2:聖職者の堕落の例
(以下,レッキーの著書からラッセルが引用したもの)
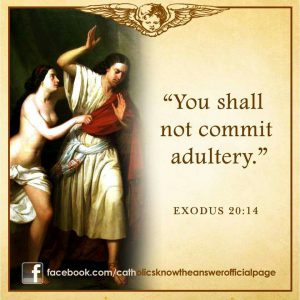 聖職者がひとたび誓いを破り,自らも常習的な罪の生活と考えている生活を送り始めたからには,すぐに,俗人よりもずっと下のレベルまで堕落してしまったのは,驚くべきことではない。堕落の個々の例をあまり強調してはいけないかもしれないが,堕落の例を挙げるなら,たとえば,他のかずかずの罪の中でも,近親相姦,及び姦淫(私通)のかどで断罪された教皇ヨハネス二十三世,あるいは,1171年に,調査の結果,ある一つの村で17人の私生児をもうけていた(産ませていた)ことがわかったカンタベリーの聖アウグステイン会の次期修道院長,あるいは1130年に,70人を下らない妾を囲っていたことが立証された,スペインの聖ベラヨ会の修道院長,あるいは65人の私生児を持っていたかどで1274年に退位させられた,リエージュの司教であるアンリ三世などである。
聖職者がひとたび誓いを破り,自らも常習的な罪の生活と考えている生活を送り始めたからには,すぐに,俗人よりもずっと下のレベルまで堕落してしまったのは,驚くべきことではない。堕落の個々の例をあまり強調してはいけないかもしれないが,堕落の例を挙げるなら,たとえば,他のかずかずの罪の中でも,近親相姦,及び姦淫(私通)のかどで断罪された教皇ヨハネス二十三世,あるいは,1171年に,調査の結果,ある一つの村で17人の私生児をもうけていた(産ませていた)ことがわかったカンタベリーの聖アウグステイン会の次期修道院長,あるいは1130年に,70人を下らない妾を囲っていたことが立証された,スペインの聖ベラヨ会の修道院長,あるいは65人の私生児を持っていたかどで1274年に退位させられた,リエージュの司教であるアンリ三世などである。
しかし,このような,長々と連鎖する教会会議や教会史の著者の挙げる証拠に抵抗することは不可能である。彼らは,単に妾を囲うことよりもずっと大きな害悪を描写している(からである)。司祭が現実に妻をめとった場合,この関係は不法であるという自覚がことに彼らの貞操(観念)にとって致命的であり,そのために重婚や極度の移り気(mobility of attachments)が,特に,彼らの間で一般的に見られたと言われている(It was obserbed that )。
中世の作家(の著作)は,売春宿のごとき女子修道院,女子修道院内でのおびただしい数の嬰児殺し,聖職者の間に常習的に蔓延していた近親相姦に関する記述に満ちあふれている。近親相姦のために,司祭は母や姉妹と同居してはいけないという,この上もなく厳しい条令を出すことが,くりかえし,必要となった。不倫の愛(unnatural love)をほとんどこの世から根絶したのは,キリスト教の偉大な功績の一つであったが,そうした愛が修道院の中にすたれずに残っている,と何度も(more than onde 一度ならず/くりかえし)うわさになった。そして,宗教改革の少し前には,告解場が誘惑の目的で使用されているという苦情が高まり,かつ,頻繁になった。(レッキー『ヨーロッパ道徳史』第二巻,pp.350-351)
It was not surprising that, having once broken their vows and begun to live what they deemed a life of habitual sin, the clergy should soon have sunk far below the level of the laity. We may not lay much stress on such isolated instances of depravity as that of Pope John XXIII, who was condemned for incest, among many other crimes, and for adultery; or the abbot-elect of St. Augustine, at Canterbury, who in 1171 was found, on investigation, to have seventeen illegitimate children in a single village; or an abbot of St. Pelayo, in Spain, who in 1130 was proved to have kept not less than seventy concubines ; or Henry III, Bishop of Liege, who was deposed in 1274 for having sixty-five illegitimate children ; but it is impossible to resist the evidence of a long chain of Councils and ecclesiastical writers, who conspire in depicting far greater evils than simple concubinage. It was observed that when the priests actually took wives, the knowledge that these connections were illegal was peculiarly fatal to their fidelity, and bigamy and extreme mobility of attachments were especially common among them. The writers of the Middle Ages are full of accounts of nunneries that were like brothels, of the vast multitude of infanticides within their walls, and of that inveterate prevalence of incest among the clergy, which rendered it necessary again and again to issue the most stringent enactments that priests should not be permitted to live with their mothers or sisters. Unnatural love, which it had been one of the great services of Christianity almost to eradicate from the world, is more than once spoken of as lingering in the monasteries; and shortly before the Reformation, complaints became loud and frequent of the employment of the confessional for the purposes of debauchery.(W. E. H. I.ecky, History of Europcan Morals, vol. ii, pp. 350, 351.)
出典: Marriage and Morals, 1929.
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/MM06-020.HTM
<寸言>
庶民には性道徳を強い、権力者(政治家、高位の聖職者、富豪など)は自らを例外として性的自由を謳歌する。権力や富を武器に自分よりも身分や生活程度の低い女性をかこったり慰みものにするのは、古今東西、権力者の役得のようなもの。