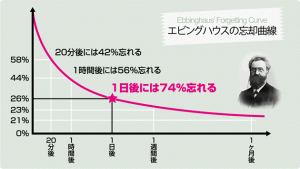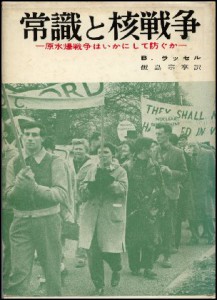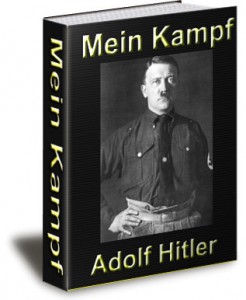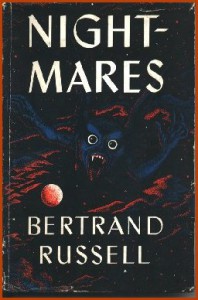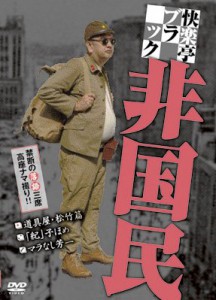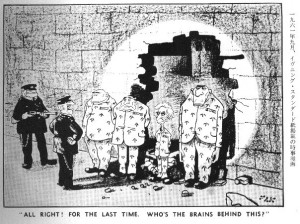私は,昔のベルリンをよく知っていた。それで,この時見たベルリンのぞっとするような見るも恐ろしい破壊(の光景)は,とてもショックだった。(ホテルの)部屋の窓からは,立っている家はほとんど一軒も見あたらなかった。(また)ドイツ人が住んでいるところを見つけ出すこともできなかった。この徹底的な破壊は,一部は英国人(軍)が行い,一部はロシア人(軍)が行ったものであって,極悪非道な行為だと思われた。
 (ベルリンの破壊よりも)いっそう弁解できない同国人(英国人)によるドレスデンの完全破壊(抹消)を熟視し,私は胸が悪くなった((YouTube 動画(ドレスデン空襲: http://youtu.be/SU3wkOGXlcY)。私は,ドイツが明らかに降伏しようとしていたのであるからそれで十分だと思うとともに,135,000人のドイツ人(注:ドレスデン市民)を殺すだけでなく,ドイツ人の住居全てと無数の財産を破壊することは野蛮行為であると思った。
(ベルリンの破壊よりも)いっそう弁解できない同国人(英国人)によるドレスデンの完全破壊(抹消)を熟視し,私は胸が悪くなった((YouTube 動画(ドレスデン空襲: http://youtu.be/SU3wkOGXlcY)。私は,ドイツが明らかに降伏しようとしていたのであるからそれで十分だと思うとともに,135,000人のドイツ人(注:ドレスデン市民)を殺すだけでなく,ドイツ人の住居全てと無数の財産を破壊することは野蛮行為であると思った。
私は,連合国によるドイツの取り扱い方は,ほとんど信じがたいほど愚かであると思った。勝利をおさめた国々の政府は,ドイツの一部をロシアに与え,一部を西側に与えることによって -特に,ベルリンが分割され,西側からベルリンの(西側の)部分(=西ベルリン)にアクセスするには空路によるほか何の保証もなかったので- 東西間の争いの継続を確かなものにした。彼らは,ロシアと西側の同盟国の間の平和的協力を想像していた。しかし,そんな結果は起こりそうもないことを予見すべきだった。感情面に限っても,実際に起こったのは,西側諸国の共通の敵としてのロシアとの戦いの継続ということであった。第三次世界大戦のための舞台が準備された。そしてそれは,諸政府の全く愚かな行為によって念入りになされたであった。
I had known Berlin well in the old days, and the hideous destruction that I saw at this time shocked me. From my window I could barely see one house standing. I could not discover where the Germans were living. This complete destruction was due partly to the English and partly to the Russians, and it seemed to me monstrous. Contemplation of the less accountable razing of Dresden by my own countrymen sickened me. I felt that when the Germans were obviously about to surrender that was enough, and that to destroy not only 135,000 Germans but also all their houses and countless treasures was barbarous.
I felt the treatment of Germany by the Allies to be almost incredibly foolish. By giving part of Germany to Russia and part to the West, the victorious Governments ensured the continuation of strife between East and West, particularly as Berlin was partitioned and there was no guarantee of access by the West to its part of Berlin except by air. They had imagined a peaceful co-operation between Russia and her Western allies, but they ought to have foreseen that this was not a likely outcome. As far as sentiment was concerned, what happened was a continuation of the war with Russia as the common enemy of the West. The stage was set for the Third World War, and this was done deliberately by the utter folly of Governments.
出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.3 chap. 1: Return to England, 1969]
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/AB31-070.HTM
[寸言}
二度と戦争を起こさせないようにしないといけないという口実で、敵国の領土や人々に対する徹底的な破壊が行われる。第一次世界大戦の時には、ドイツが支払いきれない天文学的な賠償金も課された。そういうことをすれば「いつかは見返してやる(やっつけてやる)」という気持ちが敗れた国民の間に広がってしまい、また新たな戦争の種となる。その反省で、第二次世界大戦は後は過大な賠償金を課さなかったのはよいが、ベルリンの分割統治や、中東に勝手に国境線を引くなどして、対立や戦争の種をまた作ってしまった。国力を強めるため(国益の確保!)にといって、他国(特に石油などのエネルギー資源)に対する利権をできるだけ確保しようとする愚かな政治家たち。