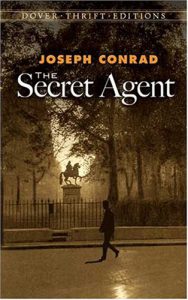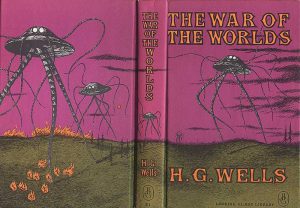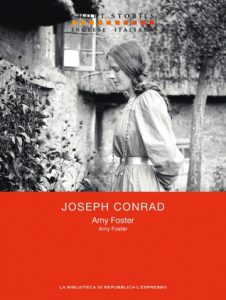 コンラッドの想像力の大部分を専有していると思われる二つのものは,孤独及び見慣れないものへの恐怖心である。『文化果つるところ』は『闇の奥』と同様に,見慣れない事物への恐怖心に係るもの(物語)である。両方(孤独と見慣れないものへの恐怖心)とも『(小説)エイミー・フォスター』という感動的な短編小説(物語)のなかに,一体となって出てきている。この短編小説(物語)のなかで,ある南スラブの小作人がアメリカに渡る中,船の遭難にあい,ただ一人生き残り,(英国の)ケント州のある村に放り出される。エイミー・フォスターを除く村中の人々が彼を恐れ,足蹴に取り扱う。彼女は,鈍感で飾りのない少女であり,彼が飢えている時にパンを持ってきて与え,ついには彼と結婚する。しかし,夫が熱病にうかされて母国語を口走った(母国語にもどった)時,彼女もまた彼に対する恐怖心(注:見慣れないものに対する恐怖心)にとらわれ,子供を奪いとって(ひっつかんで)彼のもとを去り,彼を棄てる。彼は,一人になり希望を失って,亡くなる。私は,作者であるコンラッドが,この男の寂蓼をどれほど英国人の中で感じ,強い意志のカ(努力)で抑圧したのだろうかと,時々,思案した。
コンラッドの想像力の大部分を専有していると思われる二つのものは,孤独及び見慣れないものへの恐怖心である。『文化果つるところ』は『闇の奥』と同様に,見慣れない事物への恐怖心に係るもの(物語)である。両方(孤独と見慣れないものへの恐怖心)とも『(小説)エイミー・フォスター』という感動的な短編小説(物語)のなかに,一体となって出てきている。この短編小説(物語)のなかで,ある南スラブの小作人がアメリカに渡る中,船の遭難にあい,ただ一人生き残り,(英国の)ケント州のある村に放り出される。エイミー・フォスターを除く村中の人々が彼を恐れ,足蹴に取り扱う。彼女は,鈍感で飾りのない少女であり,彼が飢えている時にパンを持ってきて与え,ついには彼と結婚する。しかし,夫が熱病にうかされて母国語を口走った(母国語にもどった)時,彼女もまた彼に対する恐怖心(注:見慣れないものに対する恐怖心)にとらわれ,子供を奪いとって(ひっつかんで)彼のもとを去り,彼を棄てる。彼は,一人になり希望を失って,亡くなる。私は,作者であるコンラッドが,この男の寂蓼をどれほど英国人の中で感じ,強い意志のカ(努力)で抑圧したのだろうかと,時々,思案した。
コンラッドの物の見方は,現代的な物の見方からはずっと離れたものであった。近代世界には二つの哲学がある。一つはルソーから出ているものであり,規律を不要なものとして払いのける(一蹴する)。もう一つはその完璧な表現を全体主義の中に見いだすことができ,規律を本質的には(本質上)外部から課せられる(課せられるべき)ものとして見なす。コンラッドは,規律は内部から生ずるべきであるという従来の伝統に固執する。彼は規律の無さを軽蔑し,また,単なる外的な(外部からの)規律を嫌った。
これら全ての点で,私は彼と非常に意見が一致していることがわかった。我々は,まさに最初の出会いにおいて,絶えず親しみが増し続ける状態で話し合った。皮相な面を一つひとつ通り抜けて深く沈んで行き,ついには二人とも心の奥底(central fire 心の中心の火炎)に到達したように思われた。それは,私がそれまでに経験したいかなるものとも異なった経験であった。我々はお互い目を見つめ合い,二人ともそのような領域にいるのを発見して,半ばぎょっとし,半ば陶酔した。それは情熱的な恋愛と同じように強烈であり,同時に,あらゆるものを包含するような感情であった。私は困惑しながら(彼のもとを)立ち去り,平常の仕事にほとんど手がつかなかった。
The two things that seem most to occupy Conrad’s imagination are loneliness and fear of what is strange. An Outcast of the Islands like The Heart of Darkness is concerned with fear of what is strange. Both come together in the extraordinarily moving story called Amy Foster. In this story a South Slav peasant, on his way to America, is the sole survivor of the wreck of his ship, and is cast away in a Kentish village. All the village fears and ill treats him, except Amy Foster, a dull, plain girl who brings him bread when he is starving and finally marries him. But she, too, when, in fever, her husband reverts to his native language, is seized with a fear of his strangeness, snatches up their child and abandons him. He dies alone and hopeless. I have wondered at times how much of this man’s loneliness Conrad had felt among the English and had suppressed by a stern effort of will.
Conrad’s point of view was far from modern. In the modern world there are two philosophies: the one, which stems from Rousseau, and sweeps aside discipline as unnecessary; the other, which finds its fullest. expression in totalitarianism, which thinks of discipline as essentially imposed from without. Conrad adhered to the older tradition, that discipline should come from within. He despised indiscipline, and hated discipline that was merely external.
In all this I found myself closely in agreement with him. At our very first meeting, we talked with continually increasing intimacy. We seemed to sink through layer after layer of what was superficial, till gradually both reached the central fire. It was an experience unlike any other that I have known. We looked into each other’s eyes, half appalled and half intoxicated to find ourselves together in such a region. The emotion was as intense as passionate love, and at the same time all-embracing. I came away bewildered, and hardly able to find my way among ordinary affairs.
出典: Joseph Conrad, 1953.
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/1040_CONRAD-040.HTM
<寸言>
ラッセルも大正時代に来日した時にコンラッドと同様な「見慣れないものへの恐怖心」を経験している。「ラッセル自伝」から以下、引用しておこう。
「私たちは,猛暑のなか京都から横浜まで(東海道線で) 10時間の旅 をした。暗くなってまもなくの頃,横浜に到着した。そうして,私たちはカメラマンたちが連続的にたくマグネシウムの爆発音で迎えられた。マグネシウムが一回爆発するごとにドーラはとび上がったので,流産するのではないかという心配が増した。私は’怒り’で我を失った。私がそんなふうになったのは,かつてフィッツジェラルドの首を絞めて殺しそうになった時以来,この時だけであった。私は,フラッシュライト(閃光灯)をもっている男性カメラマンたちを追いかけたが,’びっこ’をひいていたためにつかまえることができなかった。私は間違いなく殺人をおかしたであろうから,そのことは幸いであった。一人の冒険心のあるカメラマンが,怒りで眼が爛々としている私の写真を撮ることに成功した。私がそのように完璧に狂気じみて見えるようになるなどとは,この写真がなければついぞ知らなかったことである。この写真で私は東京に紹介された。
あの時の私の感情は,インド暴動(注:Mutiny 1857年のインドのベンガル地方のインド人傭兵が英国支配に対して起こした反乱)に際して,インド在住の英国人(Anglo-Indian)がもったにちがいない感情 -すなわち 有色人種の叛徒にとり囲まれた時の白人の感情- と同じ種類のものであった。・・・」