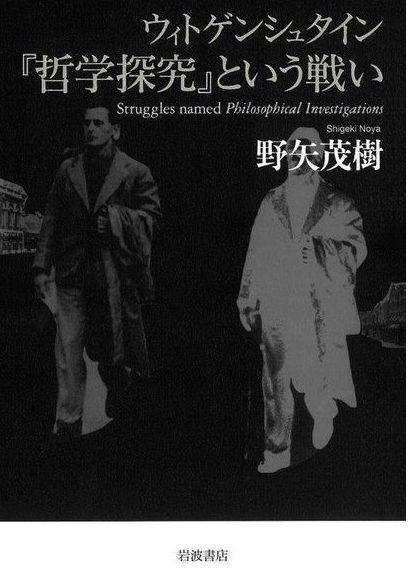
アームソン氏の私(の哲学)に対する(種々の)批判は、一部は誤解によるものであり、一部は真に(純粋な)哲学的不一致(哲学上の見解の相違)によるものである。そこで(前者の)誤解による批判を取り払うため(clear away)、私の哲学上の仕事をこれまで導いて来た目的と方法をできるかぎり簡潔に述べてみることにする。 WII(注:ウィトゲンシュタイン『哲学探究』)以前のあらゆる哲学者と共通して(同様に)、私の(哲学研究の)根本的な目標は、世界を可能な限りよく理解し(as well as may be)、知識として認めてよいものを、根拠なき意見として拒否すべきものから分離することであった。WII(ウィトゲンシュタイン『哲学探究』)がなければ、このような、当然認められるはずだと思われる目標を(改めて)述べる必要があるなどとは、私は考えなかったであろう(訳注:ウィトゲンシュタインが生前に出版したのは『論理哲学論考』だけです。『哲学探究』は、ウィトゲンシュタインのWIIの時期における主著とでもいうべき著作であり、ウィトゲンシュタインが亡くなった2年後の1953年に出版されています)。しかし、今や(今日では)、我々が理解するように努めなければならないのは(この)世界ではなく文(章)だけであり、しかも、哲学者の口にする文(章)以外の,いかなる文(章)も真と認められうると想定されている(訳注:オックスフォード学派は「日常言語学派」とも呼称され、哲学者の仕事は日常言語で話される言葉を批判的に分析することだと主張しています。オックスフォード学派は、ウィトゲンシュタインの「語り得ぬものは語るな」という言葉を金科玉条として、世界(全体)は「語り得ぬもの」であるので哲学探究の対象から外すべきだと主張しているという背景的知識が必要です)。けれども、これは言いすぎかも知れない。WIIの信奉者達(後期ウィトゲンシュタインの信奉者)は、文(章)が指示文(直説法の文)でありうるとともに、疑問文や命令文や願望文でもありうることを、 大した発見でもあるかのように、指摘するのを好みます。けれども、これでは文(章)の領域/範囲を越えることは(が)できない。言語の世界は事実の世界から全くきり離すことができるという奇妙な示唆(suggestions 暗示)が存在しており、それは既に論理実証主義者のなかに見出すことができる。そうして、もし仮に、語られた文(章)は物質の特定の動きからなる一つの物理的な出来事であり、書かれた文(章)はある色の背景の上にそれとは異なった色で記された印から成るなどと言えば、あなたは下品な人間であるとみなされる(訳注:論理実証主義に同意することが多いラッセルですが、これは同意できない考え方です)。我々は、人の言うことが非言語的な原因や非言語的な結果(effect 効果)とをもつこと、また、言語は歩いたり食べたりすることと全く同様にひとつの身体的活動であるといういことを忘れることが想定されている(忘れなければならないとされている)。論理実証主義者の中に既に見られる、論理実証主義者の中には、-特にノイラート (Neurath, 1873-1956) とヘンペル (Hempel, 1905-1997) - カルナップ (Carnap, 1891-1970) は一時期- 文(章)は事実とつきあわせてはならないと明確に主張した。彼らは、(論理的)主張は(論理的)主張とのみ比較されるべきであり、経験と比較されてはならず、我々は実在を命題と比較することは決してできないと断言する。ヘンペルの主張によれば、我々が真(である)と呼ぶところの体系は、「人類によって(現在)採用されている体系であり、特に我々自身の文化圏に属する科学者によって採用されている体系である、という歴史的事実によってのみ特徴づけられる」(とのことである)(訳注:野田氏は scientists を「学者」と訳しているが、ここはあくまでの学者の一部である「科学者」を指すと思われる)。私はこの見解を自著の『意味と真理との研究』のp.112以下で批判(批評)している。そこで、その批評の要点を繰り返すのみにする。その要点は、我々「文化圏」に属する科学者達の言うことは、それ自身ひとつの事実であるから、従って(主張と事実とをつきあわせてはならない、という考え方から)彼らが実際に言っていること(事実)は重要ではなく、彼らが言っているのだと我々の文化圏の(of your ‘culture circle’ )他の成員が言うことが重要である(ということになる)(”not … but (only)” の構文が隠れていることに注意)。これらの著者たち(ヘンペル他)は次のことに気づかなかったように思われる(←彼らに起こったとは思われない)。 私が本のあるページに印刷された文(章)を見る時に私はひとつの感覚的事実に対面しているのであるとは、彼らは思い至らなかったように思われる。また、もし彼らの学説が正しければ、そのページに印刷されているものについての真理はそのページを見ることによって確かめられるべきではなく、我々の友達に対して、あなた方はそこに何が印刷されていると言うかと尋ねることによってのみ確かめらるべきである、ということになること(になってしまうこと)に思い至らなかったように思われる。我々はヘンペルの立場をひとつの寓話によって例証することができるだろう。 彼の財産状態があまりよくなかった時分、あくまでも寓話ですが(so the fable avers その寓話ではそうなっているとします)、あるときヘンペルはパリの安食堂(大衆食堂)に入った(「寓話」です。)メニューを求めた。メニューを読み、牛肉を注文した。食堂に入ってからここのところまでは全て言語(に関するもの)だった。料理が出て来て彼はひと口食べた。これは事実との対面であった。彼は店の主人を呼びつけこう言った、「これは馬肉だ。牛肉じゃないぞ!」。主人は答えた、「すみません。ですが、私の文化圏の科学者達は『これは牛肉である』という文(章)を、彼らが受け入れる文(章)のなかに(ひとつに)含めています」と(訳注:事実との突き合わせは必要でなく、主張と主張との間で整合性が重要とのオックスフォード学派の人達へのからかい)。 ヘンペルは、自身の論証で(on his own showing)、これを平静に(with equanimity)受けいれざる得なくなるであろう。(もちろん)これは馬鹿げている。そうして、カルナップ(Rudolf Carnap, 1891-1970:論理実証主義の代表的論客)はやがてそのことに気づいたのであった。しかし、WII(後期ヴィトゲンシュタイン)の信奉者達はさらに一歩をすすめたのである。経験的陳述について(had been 過去に)二つの見解があった。(即ち)一つは、経験的陳述が事実への何らかの関係によって根拠づけられるというものであり、もう一つは、それら陳述は構文の規則(文法規則)に従うということによって根拠づけられるというものの2つであった。しかし、WII(後期ヴィトゲンシュタイン)の信奉者達はもはやいか なる種類の根拠づけ/正当化にも心を労することなく、従って言語がそれまでかつて享受したことのない無制限の(拘束されない)自由を、言語に対して保証する(secure 確保する)。世界を理解しようという望みは、時代遅れのだと彼ら(英国のオックスフォード学派)は考える。これが、彼らと私とが最も根本的に意見の相違する点である。
Chapter 18: Some Replies to Criticism, n.1_3
Mr Urmson’s criticisms of me are in part due to misunderstandings and in part to genuine philosophical disagreement. In order to clear away the former kind, I will try to state as concisely as I can the purpose and methods which have guided my work in philosophy. In common with all philosophers before WII, my fundamental aim has been to understand the world as well as may be, and to separate what may count as knowledge from what must be rejected as unfounded opinion. But for WII I should not have thought it worth while to state this aim, which I should have supposed could be taken for granted. But we are now told that it is not the world that we are to try to understand but only sentences, and it is assumed that all sentences can count as true except those uttered by philosophers. This, however is perhaps an overstatement. Adherents of WII are fond of pointing out, as if it were a discovery, that sentences may be interrogative, imperative or optative as well as indicative. This, however, docs not take us beyond the realm of sentences. There is a curious suggestion, already to be found among some Logical Positivists, that the world of language can be quite divorced from the world of fact. If you mention that a spoken sentence is a physical occurrence consisting of certain movements of matter and that a written sentence consists of marks of one colour on a background of another colour, you will be thought vulgar. You are supposed to forget that the things people say have non-linguistic causes and non-linguistic effects and that language is just as much a bodily activity as walking or eating. Some Logical Positivists — notably Neurath and Hempel, and Carnap at one time — maintained explicitly that sentences must not be confronted with fact. They maintain that assertions are compared with assertions, not with experiences, and that we can never compare reality with propositions. Hempel maintains that the system which we call true ‘may only be characterized by the historical fact, that it is the system which is actually adopted by mankind, and especially by the scientists of our culture circle’. I have criticized this view in An Inquiry into Meaning and Truth, page 142 ff., and will here only repeat the gist of the criticism, which is that what the scientists of your ‘culture circle’ say is a fact and therefore it does not matter what they say but only what other members of your culture circle say they say. It does not seem to have occurred to these authors that when I see a printed statement on a page I am confronted with a sensible fact and that, if they are right, the truth as to what is printed on the page is not to be ascertained by looking at the page but by asking our friends what they say is printed there. We may illustrate Hempel’s position by a fable: At a certain period, when his finances were not very flourishing (so the fable avers), he entered a cheap restaurant in Paris. He asked for the menu. He read it, and he ordered beef. All this since entering the restaurant was language. The food came and he took a mouthful. This was confrontation with facts. He summoned the restaurateur and said, ‘this is horse-flesh, not beef’. The restaurateur replied, ‘Pardon me, but the scientists of my culture circle include the sentence “this is beef” among those that they accept’. Hempel on his own showing would be obliged to accept this with equanimity. This is absurd, as Carnap in due course came to realize. But the adherents of WII go a step further. There had been two views about empirical statements: one that they were justified by some relation to facts; the other that they were justified by conformity to syntactical rules. But the adherents of WII do not bother with any kind of justification, and thus secure for language an untrammelled freedom which it has never hitherto enjoyed. The desire to understand the world is, they think, an outdated folly. This is my most fundamental point of disagreement with them.
Source: My Philosophical Development, 1959, by Bertrand Russell
More info.: https://russell-j.com/beginner//BR_MPD_18-050.HTM
