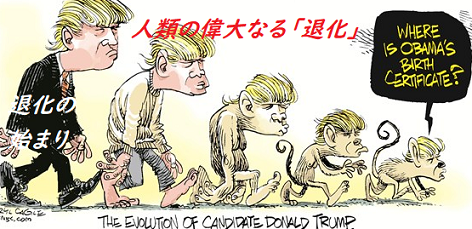
この研究(知識論の研究)の当初、私は定まった確信は何ももっておらず、ただいくつかの格率(注:maxims たとえばオッカムのカミソリなど)と先入見(注:prejudices 悪い意味での「偏見」ではなく、誰もが抱かないわけにはいかない先入見/先入観のこと)とを持っていたにすぎない。私は(主題に関連する)多くの本を読んだ。しかし結局のところ、(私が)『数学の諸原理』(1903年出版)を執筆する前に読んだ本の時( に思った)と同様、読んだ本の大部分は私の目的には無関係なものだということがわかった(気づいた)。 私が当初から持っていた先入見の中で特に重要なものとして以下の6つを列挙しておかなければならない。 その第一。(即ち)動物の心と人間の心との間の連続性を強調することが望ましいと私には思われた(注:人間の心はチンパンジーなどの動物の心とはまったく異なったものだという先入見はもたないでおこうという気持ち)。動物の行動を主知主義(者)的な観点で解釈することへの反対は普通のことであると気づいており、そういう反対に私も全体としては同意していた(注:Intellectualist interpretations:主知主義・知性主義者の観点での解釈。主知主義とは、「知性・理性」「意志・気概」「感情・欲望」に三分割する見方の中で、知性・理性の働きを重視する哲学・神学・心理学・文学上の立場。因みに、野田氏は「動物の行動を知的に解釈すること」と訳出/動物を人間よりに見るのはよくないが、人間を動物夜寄りに見た方がより有効だとラッセルは考えている)。しかし、動物の行動を解釈するにあたって採られる方法は、人間において「思考されたもの(thought 思想)」や「知識」や「推論」とみなされるところのものを解釈するにあたっても、通常認められているよりもずっと広い適用囲を持っていると私は考えた。こういった先入観を持っていたので、私は動物心理学の本を大量に読んだ。そうして -いくらか面白いことに- この分野には二つの学派があり、、それぞれの最も有力な代表者はアメリカのソーンダイク(注:Edward L. Thorndike, 1874-1949:アメリカの心理学者・教育学者でコロンビア大学教授/試行錯誤学習説で有名)とドイツのケーラー(注:W. Kohler, 1887-1967:、ドイツの心理学者で、ゲシュタルト心理学の創始者として有名)- であることを知った。動物たちは常に、動物たちを観察する人々が享受する哲学の正しさを示すように、行動する(かの)ように思われた。(devastating 何もかも台なしにしてしまうような)この破壊的な発見は、さらに広い範囲に適用される(hold over)。(即ち)17世紀において、動物たちは狂暴であったが、その後ルソーの影響のもと、ピーコック(注:Thomas Love Peacock, 1785-1866:イングランドの風刺小説家)がオランオトン卿(注:ピーコックが1817年に出版した2冊目の小説 Melincourt のなかの登場人物。この小説で、イングランド議会の議員候補として Sir Oran Haut-Ton という名のオランウータンが立候補する。)においてからかった「気高い野蛮人(the Noble Savage)」の崇拝を、動物たちは例示し始めた(例示となるように小説の中で行動した)。ビクトリア女王の統治期間はずっと、全ての猿は道徳的な一夫一婦主義者(猿)であったが、自堕落な1920年代には猿たちの道徳は破滅的な悪化を蒙った(ということらしい)。けれども、動物の行動のこの側面については、私の関心事項ではなかった。私が関心を持ったのは、動物の学習方法についての観察であった。アメリカ人の観察する動物は気が狂ったように走りまわり、偶然に解決につきあたる。ドイツ人の観察する動物は正座し頭をかきむしり、(ついには)彼らの内的意識から解決法を展開する(といったしだいである)。私は、どちらの観察結果も十分信頼できるものであり、動物のなすところは我々が動物に課する問題の種類に依存する、と信ずる。この問題について私が(関連文献の)読書で得た正味の結果は、いかなる理論でも、観察が確証した理論の範囲をこえて拡張させることにきわめて慎重にさせたことであった( make me very wary of )。 正確な実験的知識が相当多量に存在するびとつの領域(region)があった。それは犬の条件反射についてのパブロフの観察の領域であった。これらの実験は、行動主義(Behaviourism)という、かなり流行した哲学(行動主義哲学)を生み出した。この哲学の要点(gist)は、心理学においては全て外部観察(外部からの観察)に信頼を置くべきであり、その証拠がもっぱら内観に由来するいかなる事実を決して受け入れてはならないということである。私は哲学としてこの見解を受けいれたいという気をまったく起きなかったが、しかし、追求すべき一つの方法として、その価値があると感じた。この方法はきわめて明確な限界をもつことを信じつつも(while)それをできるかぎり広い範囲に適用して見ようと、私はあらかじめ(in advance)心に決めた。
Chapter 11 The Theory of Knowledge, n.2
At the beginning of this work I had no fixed convictions, but only a certain store of maxims and prejudices. I read widely and found, in the end, as I had with the reading that preceded the Principles of Mathematics, that a great part of what I had read was irrelevant to my purposes. Among the prejudices with which I had started, I should enumerate six as specially important: First. It seemed to me desirable to emphasize the continuity between animal and human minds. I found it common to protest against intellectualist interpretations of animal behaviour, and with these protests I was in broad agreement, but I thought that the methods adopted in interpreting animal behaviour have much more scope than is usually admitted in interpreting what in human beings would be regarded as ‘thought’ or ‘knowledge’ or ‘inference’. This preconception led me to read a great deal of animal psychology. I found, somewhat to my amusement, that there were two schools in this field, of whom the most important representatives were Thorndike, in America, and Kohler in Germany. It seemed that animals always behave in a manner showing the rightness of the philosophy entertained by the man who observes them. This devastating discovery holds over a wider field. In the seventeenth century, animals were ferocious, but under the influence of Rousseau they began to exemplify the cult of the Noble Savage which Peacock makes fun of in Sir Oran Haut-ton. Throughout the reign of Queen Victoria all apes were virtuous monogamists, but during the dissolute ‘twenties their morals underwent a disastrous deterioration. This aspect of animal behaviour, however, did not concern me. What concerned me were the observations on how animals learn. Animals observed by Americans rush about frantically until they hit upon the solution by chance. Animals observed by Germans sit still and scratch their heads until they evolve the solution out of their inner consciousness. I believe both sets of observations to be entirely reliable, and that what an animal will do depends upon the kind of problem that you set before it. The net result of my reading in this subject was to make me very wary of extending any theory beyond the region within which observation had confirmed it. There was one region where there was a very considerable body of precise experimental knowledge. It was the region of Pavlov’s observations on conditioned reflexes in dogs. These experiments led to a philosophy called Behaviourism which had a considerable vogue. The gist of this philosophy is that in psychology we are to rely wholly upon external observations and never to accept data for which the evidence is entirely derived from introspection. As a philosophy, I never felt any inclination to accept this view, but, as a method to be pursued as far as possible, I thought it valuable. I determined in advance that I would push it as far as possible while remaining persuaded that it had very definite limits.
Source: My Philosophical Development, chap. 11:1959.
More info.:https://russell-j.com/beginner/BR_MPD_11-020.HTM
