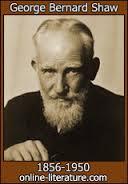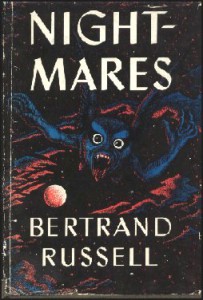【 バートランド・ラッセル(Bertrand Russell)の言葉 r366-c206】
その頃にはジョン(長男)はイギリスに戻り,英国海軍に入り,日本語の学習に従事させらていた。ケイト(長女)はラドクリフ女子大学で自活し,非常によく学業に励んでおり,ちょっとした教職の仕事を得ていた。従って,英国に渡航する許可を得ることは困難であることを除いて,私たち(自分と妻と次男コンラッド)がアメリカに留まっていなければならない理由はまったくなかった。けれども,その困難は,長い間乗り越えることができないように思われた。私は,英国上院における(私の)義務の遂行を認められなければならないということを主張するために,ワシントンに出かけ,そうしたいという私の欲求が非常に熱烈であるということを当局にわからせて説得しようと試みた。(注:ラッセルは伯爵なので,当時英国上院の議員だった。)ついに私は,(在米)英国大使館を納得させる論法を発見した。
私は彼らに言った。
「この戦争は,ファシズムに対する戦いであることを認めますね?」
「はい」
と,彼らは応えた。
私は続けて言った。
「ファシズムの本質は,’立法府’を’行政府’に従属させることにあるということも認めますね?」
彼らは,前よりもややためらい勝ちではあったが,「はい」と応えた。
私は続けて言った。
「さて,あなたがたは行政府(の人間)であり,私は立法府(の人間)です。もしあなたがたが,私の立法機能を,必要以上に一日でも長く阻害するようであれば,あなたがたはファシストです!」
一同爆笑のうちに,私の渡航許可が即座に認められた。
By this time John was back in England, having gone into the British Navy and been set to learn Japanese. Kate was self-sufficient at Radcliffe, having done extremely well in her work and acquired a small teaching job. There was therefore nothing to keep us in America except the difficulty of obtaining a passage to England. This difficulty, however, seemed for a long time insuperable. I went to Washington to argue that I must be allowed to perform my duties in the House of Lords, and tried to persuade the authorities that my desire to do so was very ardent. At last I discovered an argument which convinced the British Embassy. I said to them: ‘You will admit this is a war against Fascism. ‘ ‘Yes’, they said; ‘And’, I continued, ‘you will admit that the essence of Fascism consists in the subordination of the legislature to the executive’. ‘Yes’, they said, though with slightly more hesitation. ‘Now,’ I continued, ‘you are the executive and I am the legislature and if you keep me away from my legislative functions one day longer than is necessary, you are Fascists.’ Amid general laughter, my sailing permit was granted then and there.
出典: The Autobiography of Bertrand Russell,v.2,chap.6:America,1968]
詳細情報:http://russell-j.com/beginner/AB26-090.HTM#r366-c206