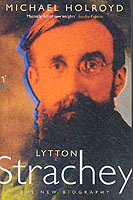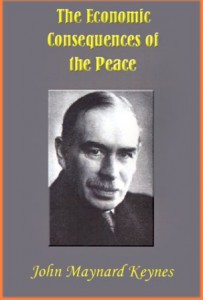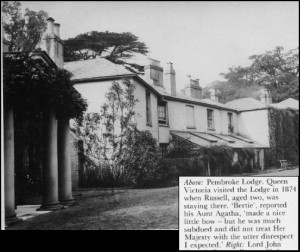【 バートランド・ラッセル(Bertrand Russell)の言葉 r366-c195】
彼(注:フランスの有名な論理学者ルイ・クーチュラ)の晩年には --彼は’国際語の問題’に没頭するようになったため-- 私は彼との接触は無くなった。彼はエスペラントよりもイド語(注:エスペラント語を一層簡易化したもの)を擁護した。彼の話によれば,人類の全歴史を通して,エスペランティストほど堕落した人間はなかった。彼は,イド語が,エスペランティスト同様の言葉の形成に向かわなかったこと(注:即ち,エスペラント語を使う人を’エスペランティスト’というように,ido 語を使う人を呼称する言葉が造語されなかったこと)を嘆き悲しんだ。私は,’idiot(ばか,まぬけ)’ という言葉を提案したが,彼は余り喜ばなかった(注:もちろん冗談)。
In the last years I had lost contact with him, because he became absorbed in the question of an international language. He advocated Ido rather than Esperanto. According to his conversation, no human beings in the whole previous history of the human race had ever been quite so depraved as the Esperantists. He lamented that the word Ido did not lend itself to the formation of a word similar to Esperantist. I suggested ‘idiot’, but he was not quite pleased.
出典: The Autobiography of Bertrand Russell, v.1, chap. 5: First marriage, 1967]
詳細情報: http://russell-j.com/beginner/AB15-170.HTM#r366-c195