バートランド・ラッセル関係文献紹介(2014)
索引(未作成)(-出版年順 著者名順 書名の五十音順)
|
|
(注意)「R落穂拾い」も「R関係文献紹介」も同様ですが,引用対象の文献は一部しか読んでないものが多いことをお断りしておきます。即ち,是非全部を読みたいと思った文献以外は,引用箇所の前後(と,まえがき・序文・あとがき+引用文が含まれている章)しか読んでいないものが多くあります。従って,付加する個人的なコメントは,そのような状況でも言うことができることや感想を述べることに限定されます。内容を的確につかみたい方は,興味を抱いた図書についてはご自分でお読みになることを勧めします。(M)
 ラッセル英単語・熟語1500 |
* この論文は,1992年1月16日に最終講義として著者が長野大学において話した内容に補足を加えてまとめられたもの。「III.感銘を受けた人物と著書」で,ラッセルの著書からの原文の引用と訳が収録されています。因みに,石井清氏は昭和24年9月に東大文学部を卒業し,同年10月に都立戸山高校に就職し,英語の授業を担当されたそうです。
(p.3)・・・。昭和30年代の後半あたり、難関といわれる東大等の入試にはラッセルやサマーセット・モー ム(SomersetMaugham-1874-1965)の著作からの出題が多かったと思う。だからという訳でもないが、ラッセルの作品は副教材として戸山高校の3年生には良く使われた。
・・・。
「以下、生徒と共に学んだいくつかの彼の著作に簡略にふれて見たい。」とあり, Portraits from Memory(1956); Has Man a Future?(1961); War Crimes in Vietnam(1967); Religion and Science (1935)からの抜粋及び邦訳が掲載されています。ここでは,Portraits from Memory(1956)からの抜粋(第一次世界大戦でのラッセルの経験)及び邦訳のみ転載させていただきます。なお, Portraits from Memory に収録された以下の部分は,『ラッセル自伝』第2巻第1章「第一次世界大戦」にそのまま転載されています。
(石井訳)- 時には私は懐疑のために正しい思考力を失うこともあった、 また時には人間の善意に対する不信にとらわれ、 さらにはまたどうでもいいやという気分になることもあった、 しかし戦争が起こったとき私は天の声を闘いたかのごとき感じであった。たとえ抗議がいかにむなしくとも、そうすることが私の任務であると知った。私の人格全体がこの任務にかかわった。真実を愛するものとしては、全交戦国の国家主義的宣伝に吐き気をもよおしたし、文明を愛するものとしては、(殺我の)野蛮時代への逆行は私を戦慄させた。 また子に対する親の愛を阻止されるものとして青年たちが大量に虐殺されることには胸をさかれる苦悩があった。
戦争に反対してもそこから大した効果が生じるとも思えなかったが、私は人間性の名誉のために、正気を失っていない人間達は、 自分たちは毅然として立っているということを示すべきだと思った。・・・。
1918年の4ヶ月半、平和主義宣伝活動の故に、私は獄につながれた。・・・中略・・・。
[... I have at times been paralysed by Scepticism, at times I have been cynical, at other times indifferent, but when the war came I felt as if I heard the voice of God. I knew that it was my business to protest, however futile protest might be. My whole nature was involved. As a lover of truth, the national propaganda of all the belligerent nations sickened me. As a lover of civilization, the return to barbarism appalled me. As a man of thwarted parental feeling, the massacre of the young wrung my heart. I hardly supposed that much good would come of opposing the war, but I felt that for the honour of human nature those who were not swept off their feet should show that they stood firm.
...中略...
For four and a half months in 1918 I was in prison for Pacifist propaganda, ...]
(★掲載サイトの紀要論文への直接リンク)
(石井氏付言)ラッセルの平和主義者としての毅然たる姿に、戦争体験の記憶をなまなましくもつ私たちは、教えるものも教えられる生徒も深く共感し、いかに生きるべきかの典型を見る思いがあった。
 ラッセルの言葉366 |
* 國分功一郎(こくぶん・こういちろう, 1974~ ):早稲田大学政経学部卒,東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。高崎経済大学経済学部准教授で哲学専攻。
本書は2011年度の「紀伊國屋じんぶん大賞」を受賞をしており,よく読まれているようです。私も興味深く読むことができました(1度目は速読し,2度目に精読しました)。ただし。ラッセルの著作(ここでは『幸福論』)に関する國分氏の誤解が少なくないように思われます。『暇と退屈の倫理学』の読者も多いことから,その点だけご紹介及びコメントをしておきたいと思います。
國分氏は,本書で,ハイデガーの思想,特に「退屈論」(「形而上学の根本概念」)を主な材料として評価・批判しながら自分の考えを順々に説き,著者が重要だと着眼した<暇と退屈の'倫理学'>について詳細に述べています。
ハイデッガーの次に引用が多いのは,ラッセル(の著書)からです(特に本書 pp.49-67)。ただし引用は,『幸福論』のみからであり,本書のテーマに直接関係のある,ラッセルの『怠惰への讃歌』からは皆無です。國分氏は,ラッセルの『幸福論』を評価もしていますが,この本の結論から考えれば,重要なのは批判しているところだと思われますので,ここではその部分についてのみとりあげてみます。
國分氏は,ラッセルの『幸福論』(あるいはラッセル思想や人間性)について,誤解や思い込み(なかには,意図しない?曲解)が少なくないように思われます。
まず一つ目の誤解(思い込み?)は,ラッセル『幸福論』に出てくる,幸福になるための条件の一つである「熱意」に関する國分氏のコメントです。(ちなみに,國分氏は,p49.で,ラッセルは「ノーベル平和賞を受賞した大知識人」と書いていますが,これはもちろん「ノーベル文学賞」の勘違いです。)
『暇と退屈の倫理学』の中の該当部分を少し長いですが,抜き出してみます。
(pp.14-30) 序章 「好きなこと」とは何かラッセルは,このようなこと(特に「打ち込むべき仕事を外から与えられない人間は不幸である」といったようなこと)は言っていないことは,先入観なしに『幸福論』を読めば,ほとんどの人が理解する思われますが,國分氏はなぜこのように読んでしまう,あるいは読めてしまうのでしょうか?(注:國分氏が好きなドゥルーズが大胆な解釈のためには「誤読」が必要だと述べているようですが,國分氏も「誤読」を気にしないためでしょうか?)
(p.14) イギリスの哲学者バートランド・ラッセル(1872-1970)は,一九三〇年に『幸福論』という書物を出版し,そのなかでこんなことを述べた(注:下線は,著者の國分氏が引いたもの)。いまの西欧諸国の若者たちは自分の才能を発揮する機会が得られないために不幸に陥りがちである。それに対し,東洋諸国ではそういうことはない。また共産主義革命が進行中のロシアでは,若者は世界中のどこよりも幸せであろう。なぜならそこには創造するべき新世界があるから・・・。
ラッセルが言っているのは簡単なことである。
二〇世紀初頭のヨーロッパでは,すでに多くのことが成し遂げられていた。これから若者たちが苦労してつくり上げねばならない新世界などもはや存在しないように思われた。したがって若者にはあまりやることがない。だから彼らは不幸である。
それに対し,ロシアや東洋諸国では,まだこれから新しい社会を作っていかねばならないから,若者たちが立ち上がって努力すべき課題が残されている。だからそこでは若者たちは幸福である。
彼の言うことは分からないではない。使命感に燃えて何かの仕事に打ち込むことはすばらしい。ならば,そのようなすばらしい状況にある人は「幸福」であろう。逆に,そうしたすばらしい状況にいない人々,打ち込むべき仕事をもたぬ人々は「不幸」であるのかもしれない。
しかし,何かおかしくないだろうか?本当にそれでいいのだろうか?
ある社会的な不正を正そうと人が立ち上がるのは,その社会をよりよいものに,より豊かなものにするためだ。ならば,社会が実際にそうなったのなら,人は喜ばねばならないはずだ。なのに,ラッセルによればそうではないのだ。人々の努力によって社会がよりよく,より豊かになると,人はやることがなくなって不幸になるというのだ。
もしラッセルの言うことが正しいのなら,これはなんとばかばかしいことであろうか。人々は社会をより豊かなものにしようと努力してきた。なのにそれが実現したら人は逆に不幸になる。それだったら,社会をより豊かなものにしようと努力する必要などない。社会的不正などそのままにしておけばいい。豊かさなど目指さず,惨めな生活を続けさせておけばいい。なぜと言って,不正をただそうとする営みが実現を見たら,結局人々は不幸になるというのだから。
なぜこんなことになってしまうのだろうか? 何かおかしいのではないか?
そう,ラッセルの述べていることは分からないではない。だが,やはり何かおかしい。そして,これをさも当然であるかのごとくに語るラッセルも,やはりどこかおかしいのである。
ラッセルが主張したように,打ち込むべき仕事を外から与えられない人間は不幸であると主張するなら,この事態はもうどうにもできないことになる。やはり私たちはここで,「何かがおかしい」と思うべきなのだ。
次のコメントも同様です。
(p.61) 熱意はおそらく幸福と関連している。だが,ラッセルはそこから「熱意があればよい」「熱意さえあれば幸せである」という結論に至ってしまった。「熱意があればよい」「熱意さえあれば幸せである」などと,ラッセル言っていません。また,「(ラッセルも)気づいていたようにも思われる」ではなく,最初から「熱意」は幸福になるための条件の「一つ」だと言っています。
実際,ラッセルはこの結論の問題点にも気づいていたようにも思われる。彼は熱意の傾けられる道楽や趣味が,大半の場合は根本的な幸福の源泉でなくて,現実からの逃避になっているとも指摘しているからである。
しかもラッセルは,本物の熱意とは,忘却をもとめない熱意であるとも述べている。彼は,「熱意」と見なされる現象が,単に現実から眼をそらす逃避や忘却のための「熱意」でありうる可能性にきづいているのだ。・・・。
ラッセルは,幸福になるための積極的条件として,熱意(Zest)だけではなく,愛情(Affection),家族(The family),仕事(Work),及び(外界に対する)非個人的な興味(Impersonal interests)をあげています。また,必要な努力をした後はどうしても達成できないことはあきらめることができること(Effort and resignation)などをあげています。
(下記のページにラッセル『幸福論』の目次をあげてあります。また,この目次経由で,ラッセル『幸福論』を対訳(松下訳)で全て読むことができますので,参照してみてください。
https://russell-j.com/beginner/KOFUKU.HTM
國分氏は,この思い込みのもと,さらに次のように書いています。
(p.62) したがって,当時のヨーロッパの青年たちを,当時のロシアや日本の青年たちと比べるという(ラッセル)の視点そのものが完全にまちがっていると言わねばならない。これは,現代のそれなりに裕福な日本社会を生きる若者を,発展途上国で汗水たらして働く若者たちと比べて,「後者の方が幸せだろう」と言うのに等しい。これはまちがっているどころか,倫理的に問題がある。なぜなら,それは不幸への憧れを生み出すからである。軽い気持ちで,ラッセルが一つの例としてあげた「ロシアの青年の熱意」を針小棒大にとりあげるのはどうでしょうか? ラッセルは,革命直後の(当時の)ロシアの青年は革命に対する熱意から幸福を感じているという「現象面」をとりあげているだけであり(幸福の「質」について客観的評価をしているわけではなく),それ以上でもそれ以下のものでもありません。(因みに,ラッセルは,1920年夏に,英国労働党代表団に随行し,革命直後のロシアを訪問し,帰国後の1922年に The Pracice and Theory of Bolshevism(邦訳書名:『ロシア共産主義』を執筆・出版し,ロシア共産主義に対するするどい批判を行っています。) 國分氏が,独自の<暇と退屈の倫理学>を構築したいのであれば,枝葉末節の記述を拡大解釈したり,針小棒大にとらないように,(國分氏が自ら言っているように)「大いに注意をせねばならない」のではないでしょうか?
不幸に憧れてはならない。したがって,不幸への憧れを作り出す幸福論はまちがっている。<暇と退屈の倫理学>の構想はこの点に大いに注意せねばならない。
このように「誤読」が多いと,他の著者の著作の引用・紹介も大丈夫だろうかと思われてきます。
もちろん,ラッセルの書き方にも原因はあります。
ラッセルの著書は,専門的な本(Aグループとします。)と一般向けの本(Bグループとします。/ popular books)の2つのグループに分けることができます。後者はさらに,教養のある知的な一般読者向けの本(B1グループ/『哲学入門』や『西洋哲学史』など)と,そういった制限があまりない一般読者向けの本(B2グループ/『幸福論』や『教育論』など)にわけることができます。
ラッセルは,著書の執筆において,「精確」であること(多義的であいまいにならないこと),読者に誤解を生じさせる余地を与えないことを重要と考え,そのためには文章の流麗さを犠牲にすることも気にしませんでした。
しかし,ラッセルは大学等の定職につくことはあまりなく,主に文筆によって,生計の糧を得て,家族を養っていましたので,B2グループの本の執筆においては,精確さを多少犠牲にして,面白おかしいエピソードやたとえ話をかなり挿入しました(注:既存の組織に定職を持つと言いたいことも言えなくなる恐れがあるため,ラッセルは若い時に,可能な限り,文筆業で生計をたてようと決意をします。ラッセルは貴族で財産がいっぱいあったからではありません。)。そのせいもあり,『結婚論』における「黒人の能力」に関する記述やキリスト「的な」愛(Christian love)の強調等々,たまにではありますが,世界の読者に誤解を与えてしまいました。
https://russell-j.com/beginner/AB31-220.HTM
ロシア革命前後においてロシアの青年は「熱意」を持つことができて幸福そうだというラッセルがあげた例 --私もあまり良い例だとは思いませんが-- について,,國分氏が,「(ラッセルが)熱意さえあれば幸福であると言っているのは間違いだ」として論じているのはいただけません。ラッセルの『幸福論』を先入観なしで読めば,「熱意」は,ラッセルがあげている,幸福になるための(有力な)条件の,あくまでも「一つ」であり,よほど不注意な読者でなければ,熱意「さえ」あれば幸福になれる,とは読まないと思われます。なぜそのように読んでしまう(読めてしまう)のでしょうか?
それに,ラッセルの『幸福論』の原書のタイトル The Conquest of Happiness(幸福の「克服」=幸福は棚からボタ餅のように,努力しないで落ちてくるものではなく,克己努力して勝ち得るものだという意味合いを含んだタイトル)にあるように,不幸の原因について徹底的に分析し,処方箋を提示した後に初めて幸福になるための積極的な条件についてふれる,という構成及びアプローチの仕方をとっていることを充分理解していないのではないか,と言いたくなります。
ラッセルはこの『幸福論』において,戦争や飢餓状態にあるなど,厳しい外的環境の中にいる人ではなく,一応世間一般の平均的な暮らしができる人々で,日常的な不幸に苦しんでいる人たちが,不幸の原因を知り,克服し,幸福になるための処方箋を書いた,とはっきり書いていることも,よく頭に入れておく必要があります。
それから,次の記述も気になりました。
(p.188) しかし,(ハンナ・アレントによるマルクスのテキストの改ざんについて)アレントを非難しても仕方がない。問題は,「欠乏と外的有用性によって決定される」という文句がアレントの目に入ってこないということだ。もうこうなると,読み間違いの問題ではない。アレントの欲望の問題である。アレントはマルクスのなかに労働廃棄の思想を読み取りたくて仕方ないのである。國分氏の指摘されるとおりかもしれないですが,しかし,これは「両刃の剣」ではないでしょうか?
即ち,國分氏も,ラッセル『幸福論』の中に,「ラッセルは,熱意さえもてれば人間は幸福になれる」と言っていると「読み取りたくて仕方がなかった」のではないか,と。
本書(『暇と退屈の倫理学』)の結論のところで,國分氏は次のような批判的なコメントも書いています。
(p.343) ラッセルはこんなことを言っている。「教育は以前,多分に楽しむ能力を訓練することだと考えられていた」。ラッセルがこう述べることの前提にあるのは,楽しむためには準備が不可欠だということ,楽しめるようになるには訓練が必要だということである。・・・。中略・・・。
「楽しむためには訓練が必要だ」と言うと,どうもハイカルチャーのことが想像されてしまうきらいがある。実際,ラッセルは食のような楽しみのことは考えていない。彼は上の引用文に付け加えて,訓練を必要とする楽しみとは,すなわち,「てんで教養のない人たちには縁のない繊細な楽しみである」と述べている。(こういうところがラッセルという哲学者の限界である。)
ラッセルは単純に,誰でもが素朴に楽しめるもの以外に,訓練や努力によって楽しむことができるようになるものがある,また興味を持てるものが多ければ多いほどその人はより幸福になれる「可能性」が増えると言っているにすぎません。「てんで教養のない人たちには縁のない」などという(國分氏の感情のこもった)表現の中に,偏見や思い込みがプンプン感じられます。
あと一つだけにしておきます。
國分氏は,本書の最後で以下のように書いています。ここに書かれている「労働時間の短縮」及び「余暇(時間)の有効活用」は,ラッセル(著)『怠惰への讃歌』における中心的な主張でもあり,本書でひとことも触れられていないのは残念です(國分氏は読んでいないのではないでしょうか!?)。
(p.356) マルクスは「自由の王国」の根本的条件は労働日の短縮であると言っていた。誰もが暇のある生活を享受する「王国」こそが「自由の王国」である。誰もがこの「王国」の根本的な条件にあずかることができる社会が作られねばならない。そして,物を受け取り,楽しむことが贅沢であるのなら,暇の「王国」を作るための第一日は,贅沢のなかからこそ始まるのだ。
最後に,ラッセル『幸福論』から,関係ありそうなところを少し引用しておきます。
私の目的は,文明国の大半の人びとが苦しんでいる普通の日常的な不幸に対して,一つの治療法を提案することにある。そういった不幸は,はっきりした外的原因がないため,逃れようがないように思われるために,それだけ耐えがたいものである。私の信じるところでは,こうした不幸は,大部分,間違った世界観,間違った倫理,間違った生活習慣によるものであり,人間であれ動物であれ,結局はその幸福のすべてがよっているところの実現可能な事柄に対する,あの自然な熱意と欲望を(そういった不幸は)打ちくだいてしまうのである。こういうことは,個人の力でなんとかなる事柄である。そこで,私は人並みの幸運さえあれば,幸福が達成できるような(生活の)改変を提案しようと思う。
https://russell-j.com/beginner/HA11-020.HTM
私の考えでは,'退屈'は,人間の行動における要因の1つとして,それに値する注意を払われていない(←注目を受けていない)。'退屈'は,有史時代を通じて大きな原動力の一つであったと信ずるが,現代においてもかつて以上にそうである。'退屈'は,人間特有の感情であるように思われる。・・・。 退屈の本質的要素の一つは,現在の状況と,想像せずにはいられない他のもっと快適な状況とを対比することにある。・・・。
'退屈'は,本質的には,事件を望む気持ちのくじかれた状態をいい,事件は必ずしも愉快なものでなくてもよく,'倦怠の犠牲者'にとっては,今日と昨日を区別してくれるような事件であればよい。退屈の反対は,ひと言で言えば,快楽ではなく興奮である。・・・。
https://russell-j.com/beginner/HA14-010.HTM
戦争,虐殺,迫害は,すべて退屈からの逃避の一部(→逃避から生まれたもの)であり,隣人とのけんかさえ,何もないよりはましだと感じられてきた(←経験して知る)。それゆえ退屈は,人類の罪の少なくとも半分は退屈を恐れることに起因していることから,モラリスト(道徳家)にとってきわめて重要な問題である。
https://russell-j.com/beginner/HA14-030.HTM
多少とも単調な生活に耐える能力は,幼少期に獲得されるべきものである。この点で,現代の親たちは大いに責任がある。・・・。
私は,単調さそのものに独自のメリットがあると主張しているわけではない。私はただ,ある種の良いものは,ある程度の単調さのあるところでなければ可能ではない,と言っているにすぎない。・・・。 退屈に耐えられない世代は,小人物の世代,即ち,自然のゆったりした過程から不当に切り離され,生き生きとした衝動が,花びんに生けられた切り花のように徐々にしなびていく世代となるだろう。
https://russell-j.com/beginner/HA14-060.HTM
現代の都市に住む人びとが苦しんでいる特別な種類の退屈は,彼らが「大地」の生から切り離されていることと密接に結びついている。そのことによって,生活は,砂漢の中の(孤独な)巡礼のように,暑く,ほこりっぼく,のどのかわくものになっている。自分のライフスタイルを選択できるほど裕福な人々の間において,特に彼らが苦しんでいる耐え難い退屈は,逆説的であるように思われるかもしれないが,退屈への恐れにその原因がある。実りある退屈から逃げることで,別の,より悪い種類の退屈の餌食になってしまう。幸福な生活は,大部分,静かな生活でなければならない。なぜなら,真の喜びは,静かな雰囲気の中でのみ,生きながらえることができるからである。
https://russell-j.com/beginner/HA14-070.HTM
しかしながら,(一時的な)流行追求や趣味は,多くの場合,多分大部分,根本的な幸福の源泉ではなく,現実からの逃避のための手段になっている。即ち,直視するには大きすぎる苦痛を当面の間忘れるための手段になっている。根本的な幸福は,ほかの何にもまして,人(間)や事物に対する'友好的'な関心とも言うべきものに依存しているのである。
https://russell-j.com/beginner/HA21-060.HTM
'幸福な人'とは,(できるだけ先入観を持たず)客観的に生き,自由な愛情と幅広い興味を持ち,またそういう興味と愛情を通して,今度は逆に,他の多くの人びとの興味と愛情の対象になるという事実を通して,自らの幸福を確保する人である。愛情の受け手になることは,幸福になるための有力な原因である。しかし,'愛情を要求する人'は,'愛情が与えられる人'ではない。愛情を受ける人は,大まかに言えば,愛情を与える人である。しかし,利子付きで金を貸すようなやり方で,愛情を打算で(計算づくで)与えようとすることは無益である。なぜなら,計算づくの愛情は本物ではないし,受け手からも本物とは思われないからである。
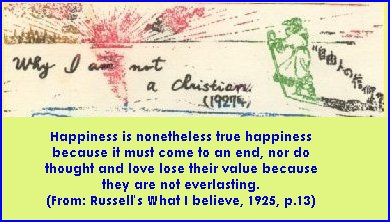
https://russell-j.com/beginner/HA28-010.HTM
* 柴田耕太郎(しばた・こうたろう, 1949~ ):翻訳仲介会社(株)アイディ代表取締役。
<著者の柴田耕太郎氏は,翻訳会社の(株)アイディの代表取締役で,翻訳者の紹介や翻訳者の養成を仕事とされているようです。本書は,受験参考書というより翻訳者になりたい人のための学習参考書といったところでしょうか。ラッセルの思想を扱ったものではないですが,広義の意味では「ラッセル関係文献」ですので,前回とりあげた『教養の場としての英文解釈』に続いて,ご紹介することにしました。「まえがき」には,次のように書かれています。
本書は,JR京浜東北線西川口駅前にあるBOOKOFFの英語の参考書コーナで見かけました。覗いてみたところ,英語の課題文が100題収録されており,ラッセルの英文も5つ含まれていました。しかし定価が約1万円であり,BOOKOFFでの売価も5,000円ほどしたため,購入する気にはなれず,公共図書館で借用しました。>
柴田氏も最近の会話中心の英語教育に不満や危機感を持っておられるようであり,事実,英語の受験教育の,というより英語教育の第一人者であった(故)伊藤和夫氏から大きな影響を受けたと,「あとがき」で書いておられます。
長年,翻訳者の選定を手がける立場として気になっていることがあります。訳文はうまい,でもよくチェックしないとこわい,という人が増えてきていることです。「役に立つ英語」の掛け声かまびすしい昨今,「重箱の隅をつつく」ような英語学習はやらないのかもしれません。しかし,精読の経験なしには,本当に英語を読むことなぞできないのも確かです。・・・。
「あとがき」には次のように書かれています。指南書三冊との巡り合いこれに続いて,世間では東南アジアの大学卒業者はみんな英語を流暢にしゃべれるのに日本人学卒者はしゃべれない,従って会話やコミュニケーション中心の実用的な英語教育に変えていかないといけないという声が強いことに対する,説得力のある反論が書かれています。
結局は「取り方」「解釈の違い」ということで済むのだろうか。そう悩んでいた矢先,伊藤和夫(著)『英文解釈教室』に巡りあった。「英語は構文で読め。言葉どうしの掛かり方が大切」との思想が全編を貫くこの指南書を読んだおかげで,ブラックボックスはない,構文を正しく取れば読み方は自ずとひとつに決まるのだと納得できた。この本を熟読してから,感覚はなく,論理的に訳文の是非を判断できるようになり,翻訳クレームへの対応が恐くなくなった。・・・。
日本語の英語教育を変えたい
この本は,近年の英語教育に対する私なりの異議申し立てです。「こんな簡単なことを何故学校で教えないのか」「文法こそ英語の基本である。」「論理的に考えることが大切」「きちんとした日本語にできて初めて英語が読めたことになる。」等のメッセージを込めたつもりです。流暢に話す英語と大意を掴む英語が,文部省(現・文部科学省)と国民一般のめざすところのようですが,硬質の文書を読み取る力もなく内容のないことをいくらペラペラやっても,教養あるネイティヴスピーカーからは軽んじられるばかり。 ・・・。
著者のご紹介はこれでやめておきます。
さて,本書には100の課題が載っており,ラッセルの英文も5つ収録されていますが,全て『幸福論』から採録されています。(注:残念ながら,100の英文についての出典は,著者名のみ,あるいはどこの大学の入試でだされたかといった情報しか載っていません。書名さえ載っていませんがなぜでしょうか? 翻訳者を養成している立場としては,適切な訳が載っている訳書を生徒に見られると勉強にならなくなるため,あえて載せていないのでしょうか!?)
今回は1つだけご紹介しておきます。他の4つについてご興味の有る方は,図書館で借りるなどしてお読みください。
「第五部 難解な文章を読む」の課題11「親である喜び」-著者の論理にのっかる」として,次の文章があがっています。(出典は Bertrand Russell としか書いてありませんが,これはラッセル『幸福論』第13章「家族」から採られたものであり,ラッセルのポータルサイトの次のページに掲載してあります。
https://russell-j.com/beginner/HA24-090.HTM)
The primitive root of the pleasure of parenthood is two-fold. On the one hand there is the feeling of part of one's own body externalised, prolonging its life beyond the death of the rest of one's body, and possibly in its turn externalising part of itself in the same fashion, and so securing the immortality of the germ-plasm. On the other hand there is an intimate blend of power and tenderness. The new creature is helpless, and there is an impulse to supply its needs, an impulse which gratifies not only the parent's love towards the child, but also the parent's desire for power.これに対し,<原文に則した訳>と<モデル訳文>として次の文章が収録されています。
* germ-plasm : 生殖細胞/
<原文に則した訳>訳し方は,好みの問題もありますが,<モデル訳文>のなかの,「客体化」及び「予感」という訳語と, 「not only, ... but also」 の部分の「それはもちろん・・・からだが」と not only の方を「断定的」に訳しているのは少し違和感を覚えました。(特に「客体化」というのは意訳のしすぎではないかと感じました。)
親であることの喜びの本源的な根は二つある。一方では自分の肉体の-部が外在化したという感じで,まず残りの肉体の死を超えて自分の生命が生き長らえてゆき,次にはそうして自分を引き継いだ肉体の-部の,また一部が同じようなやり方で外在化してゆき,そしてその結果生殖細胞の不死性が確保されるのではないか,といったものである。他方では力と優しさの親密な混合物がある。生まれたばかりの赤ん坊は無力であり,その必要とするものを供給してやろうという衝動があり,この衝動は子供に対する親の愛情を充足するだけでなく,親の子どもへの支配欲をも充足させるのである。
<モデル訳文>
親であることの喜びには,元々二つの要素がある。客体化された自分の身体の一部が,元の身体は死に絶えても自ずと永らえてゆき,こんどは同じようにしてその又一部を客体化し,遺伝子の不滅性が連綿とつづくという予感が一つ。もう一つは,いとしさと支配欲が微妙にない混ぜになった気持ち。生まれたばかりの子供は実に無力であり,何とかしてやらねばという内なる欲求が生じる。それはもちろん子供に惜しみなく愛を注いでやりたいからだが,子供を支配したいという願望のあらわれでもあるのだ。
下記の訳の方がよいということではないですが,参考まで松下訳をあげておきます。
<松下試訳>
親であることの喜びの根源は,二重にある。一方では,自分自身の肉体の一部(注:精確に言えば,受精によって精子と卵子が結合したもの)が外在化し,自分の肉体の死を越えて生命を延ばしていき,そして,おそらく,今度はその一部を同じようにして外在化し,そのようにして遺伝子(生殖質)の不滅が確保されるという感覚がある(これが喜びの根源のひとつ)。他方では,権力と優しさが密接に交じり合ったものがある(これがもう一つの喜びの根源)。生まれたばかりの赤ん坊(新生児)は無力なので,赤ん坊が必要とするものを与えたいという衝動がある。その衝動は,親の子供に対する愛情だけではなく,親の権力欲(支配欲)をも満足させるものである。


