

'Come unto these yellow sands, ...'退屈への恐れ(松下彰良 訳)
ロンドンを離れたことがなく,初めて緑の田舎の散歩に連れ出された2歳の男の子に,出会ったことがある。季節は冬で,何もかもが湿気を帯び,どろだらけだった。おとなの目には喜びをもたらすものは何もなかったが,男の子の心には,不思議なエクスタシーが湧き起こり,彼は,ぬれた地面にひざまずき,顔を草にうずめ,半ば言葉にならない歓喜の叫びをあげた。この男の子が経験していた歓喜は,原始的,単純,かつ大きなものだった。そのとき満たされつつあった生物的な(身体的)要求は,非常に深いものであり,その要求が満たされていない人びとは,正気であるとはほとんど言えない(ものである)。 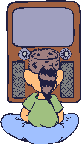 快楽の中には,たとえばギャンブルは好い例だが,こうした「大地」との接触の要素がまったくないものが多い。こうした快楽は,終わるやいなや,人を無味乾燥な気持ちや,欲求不満で,自分でも何がほしいのかよくわからないものを切望する'気持ち'にさせる。そのような快楽は,'歓喜'と言えるようなものは何ひとつもたらさない。これに対して,私たちを「大地」の生と接触させるような快楽は,その中に深い満足を与えるものを含んでいる。こうした快楽(の場合)は終わったとしても,その快楽が続いていたときの強さは,より興奮をもよおす娯楽の与える快楽の強さには及ばないだろうが,(「大地」の生と接触させるような)そのような快楽がもたらした幸福感は残り続ける。
快楽の中には,たとえばギャンブルは好い例だが,こうした「大地」との接触の要素がまったくないものが多い。こうした快楽は,終わるやいなや,人を無味乾燥な気持ちや,欲求不満で,自分でも何がほしいのかよくわからないものを切望する'気持ち'にさせる。そのような快楽は,'歓喜'と言えるようなものは何ひとつもたらさない。これに対して,私たちを「大地」の生と接触させるような快楽は,その中に深い満足を与えるものを含んでいる。こうした快楽(の場合)は終わったとしても,その快楽が続いていたときの強さは,より興奮をもよおす娯楽の与える快楽の強さには及ばないだろうが,(「大地」の生と接触させるような)そのような快楽がもたらした幸福感は残り続ける。私がいま考えている区別は,最も単純な'営み'(活動)から,最も洗練された'営み'(活動)までの全領域に行き渡っている。直前にふれた2歳の男の子は,「大地」の生との触れあいを最大限原始的かつ可能な形で表現した。しかし,より高度な形では,同じものが詩の中に見いだされる。シェイクスピアの叙情詩を最高のものたらしめているのは,2歳の男の子に草を抱きしめさせたものと同じ喜びが,それらの叙情詩に,溢れている点である。「聞け,聞け,ヒバリ」とか,「来たれ,この黄色い砂浜へ」といった詩を考えてみるといい。読者は,これらの詩の中に,先の2歳児には言葉にならない叫びでしか口に出せなかった感情の,洗練された表現を見いだすにちがいない。あるいはまた,愛(情)と単なる性的魅力との間の違いについて考えてみるとよい。草木が日照りの後の雨で生きかえるように,愛は,私たちの全存在を新しくよみがえらせ,生き生きとさせる1つの経験である。愛のない性交には,こういったものはまったく存在しない。つかの間の快楽が終われば,疲労,嫌悪,人生はむなしいという感じが残る。愛は「大地」の生の一部であるが,愛のないセックスはそうではない。 現代の都市に住む人びとが苦しんでいる特別な種類の退屈は,彼らが「大地」の生から切り離されていることと密接に結びついている。そのことによって,生活は,砂漢の中の(孤独な)巡礼(右下イラスト参照)のように,暑く,ほこりっぼく,のどのかわくものになっている。自分のライフスタイルを選択できるほど裕福な人々の間において,特に彼らが苦しんでいる耐え難い退屈は,逆説的であるように思われるかもしれないが,退屈への恐れにその原因がある。実りある退屈から逃げることで,別のより悪い種類の退屈の餌食になってしまう。幸福な生活は,かなりの程度まで,静かな生活でなければならない。なぜなら,真の喜びは,静かな雰囲気の中でのみ,生きながらえることができるからである。 |
 * From Free animation library https://www.animationlibrary.com/a-l/ I do not like mystical language, and yet I hardly knows how to express what I mean without employing phrases that sound poetic rather than scientific. Whatever we may wish to think, we are creatures of Earth; our life is part of the life of the Earth, and we draw our nourishment from it just as the plants and animals do. The rhythm of Earth life is slow; autumn and winter are as essential to it as spring and summer, the rest is as essential as motion. To the child, even more than to the man, it is necessary to preserve some contact with the ebb and flow of terrestrial life. The human body has been adapted through the ages to this rhythm, and religion has embodied something of it in the festival of Easter. I have seen a boy of two years old, who had been kept in London, taken out for the first time to walk in green country. The season was winter, and everything was wet and muddy. To the adult eye there was nothing to cause delight, but in the boy there sprang up a strange ecstasy; he kneeled in the wet ground and put his face in the grass, and gave utterance to half-articulate cries of delight. The joy that he was experiencing was primitive, simple and massive. The organic need that was being satisfied is so profound that those in whom it is starved are seldom completely sane. Many pleasures, of which we may take gambling as a good example, have in them no element of this contact with Earth. Such pleasures, in the instant when they cease, leave a man feeling dusty and dissatisfied, hungry for he knows not what. Such pleasures bring nothing that can be called joy. Those, on the other hand, that bring us into contact with the life of the Earth have something in them profoundly satisfying; when they cease, the happiness that they brought remains, although their intensity while they existed may have been less than that of more exciting dissipations. The distinction that I have in mind runs through the whole gamut from the simplest to the most civilised occupations. The two-year-old boy whom I spoke of a moment ago displayed the most primitive possible form of union with the life of Earth. But in a higher form the same thing is to be found in poetry. What makes Shakespeare's lyrics supreme is that they are filled with this same joy that made the two-year-old embrace the grass. Consider 'Hark, hark, the lark', or 'Come unto these yellow sands'; you will find in these poems the civilised expression of the same emotion that in our two-year-old could only find utterance in inarticulate cries. Or, again, consider the difference between love and mere sex attraction. Love is an experience in which our whole being is renewed and refreshed as is that of plants by rain after drought. In sex intercourse without love there is nothing of this. When the momentary pleasure is ended, there is fatigue, disgust, and a sense that life is hollow. Love is part of the life of Earth; sex without love is not. The special kind of boredom from which modern urban populations suffer is intimately bound up with their separation from the life of Earth. It makes life hot and dusty and thirsty, like a pilgrimage in the desert. Among those who are rich enough to choose their way of life, the particular brand of unendurable boredom from which they suffer is due, paradoxical as this may seem, to their fear of boredom. In flying from the fructifying kind of boredom, they fall a prey to the other far worse kind. A happy life must be to a great extent a quiet life, for it is only in an atmosphere of quiet that true joy can live. |