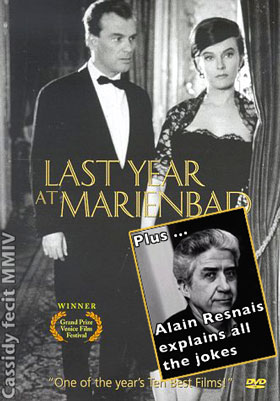* 右上写真出典:R. Clark's Bertrand Russell and His World, 1981.
スタッドランド以後,様々な困難(な事態)がトラブルをもたらし始めた。アリスはなおも怒り狂っており,アリスの兄のローガンも全く彼女同様激怒していた。ホワイトヘッド夫妻は,この時は,非常な親切を示してくれて,とうとう彼ら(アリスとローガン)を説得し,オットリンをまきこんでの離婚という考えを放棄させてくれた。アリスは,オットリンを巻き込まない場合には,離婚する意味はないという結論に達した。私は,オットリンがフィリップと離婚してくれることを望んだが,それは問題外だということが,間もなくわかった(松下注:オットリンは,夫のフィリップも心から愛しており,また娘 Julian のことも心配であった)。とかくするうちに,ローガンはフィリップのところにいき,いくつかの条件を課した。それをフィリップは,今度はオットリンに課さなければならなかった。それらの条件は,厄介なものであり,私たちの恋愛の幸福をひどく妨げた。それらの条件のなかで最悪なものは,私たちは一夜でも一緒に過ごしてはならないというものであった。私は,フィリップとローガンとアリスの3人が怒るのと同じように,激怒し,怒り狂った。オットリンは,すべてこうしたことを耐え難く思うようになり,そのことは,最初の時のあの精神的高揚を再体験することは難しいという気分を生み出した。私は,オットリンの人生の連帯性(彼女から切っても切れないもの)について,(即ち)夫と子供と財産は彼女にとって重要であるという事実について,気がつくようになった。私にとっては,彼女と比較して(同じように)重要なものは何もなかったので,この差異が,私を嫉妬にかりたて,つらいものとなった。(松下注:ラッセルのこのような体験が後に,『幸福論』に活かされることとなる。たとえば,ラッセルの「'ねたみ'や'嫉妬'」についての記述を参照)。けれども,最初の内は,私たちのお互いの情熱の単なる強さが,このようなあらゆる障害を克服した。
彼女は,チルターン(Chilterns:ロンドンから北西数キロのところにある丘陵地帯/右欄の地図参照)のペッパード(Peppard)に小さな家を所有しており,彼女はその年の7月そこで過ごした。私は,ペッパードから6マイルはなれたイプスデン(Ipsden/右欄の地図の西北にあり)に滞在し,毎日,そこから自転車で通い,正午頃ペッパードに到着し,午前零時頃ペッパードを去った。(松下注:ラッセルは,ここでは,オットリンと一夜をともにしてはいけないという条件を守ったことになるのか?)その夏は驚くべき暑さとなり,ある時のごときは,日陰でさえも華氏97度(摂氏36度/C=5/9(F-32)→C=5/9(97-32))に上った。私たちは,いつも昼食を持って,西洋ブナの林の中に行き,そしてお茶の時間よりすこし遅く帰宅した。その月(7月)は,オットリンの健康状態は悪かったけれども,最高に幸せな1ケ月であった。ついには,(温泉治療のため)彼女は,マリエンバート(Marienbad:旧チェコスロバキアの温泉地/マリエンバート=マリアーンスケー・ラーズニェ)に行かなければならなかった。しばらくしてから,私はマリエンバートの彼女のもとに行ったけれども,ホテルは別にとった。
秋の訪れとともに彼女はロンドンに戻った。私は,彼女が私に会いに来られるように,大英博物館の近くのベリー・ストリート(Bury Street)にフラットを借りた。私はその頃はずっとケンブリッジ大学で講義をしていたが,いつも朝ロンドンに上京し,午後5時半からの講義に間に合うようケンブリッジに戻った。当時彼女は,ひどい頭痛でずっと苦しんでいた(注:右欄上の写真参照:右手を頭にやっている写真がけっこうあるのは,頭痛のせいか? 前ページの写真も参照)。彼女の頭痛は,私たちの逢瀬をしばしば失望させるものとした。そうしてこのような時には,もっと思いやりをもつべきであったが,私は彼女に対しあまり思いやりがなかった。それにもかかわらず(そのような時には,思いやりを持って接すべきなのに),私たちは,重大な意見の不一致が生じたのは,彼女が宗教的であることを私が非難したことから生じたものだけであり,(大きな揉め事もなく)その冬を過ごした。けれども,徐々に,私が彼女のことを思うほど彼女は私のことを思っていないということを感じとり,私の感情はますますかき乱されていった。このような感情が全く消えてしまうことが時々あり,実際は,彼女の健康状態がよくなかったのが,彼女は私に対して冷淡であるとしばしば思われたのだと思う。しかし,確かにそれは,いつも事実であるというわけではなかった。自分では気づいていなかったが,私は歯槽膿漏をわずらっていた。また,それが私の息をひどいものにしていたがそのことにもまた私は気づいていなかったのである。彼女は私にそのことに言及する気になれなかった。そうしてそれが,どんなにひどく彼女の気持ちに影響したかを私に教えてくれたのは,私がこの病気のことを発見し,治療を終えた後のことであった。
|
 After Studland various difficulties began to cause trouble. Alys was still raging, and Logan was quite as furious as she was. The Whiteheads, who showed great kindness at this time, finally persuaded them to abandon the idea of a divorce involving Ottoline, and Alys decided that in that case a divorce was not worth having. I had wished Ottoline to leave Philip, but I soon saw that this was out of the question. Meanwhile, Logan went to Philip, and imposed conditions, which Philip in turn had to impose upon Ottoline. These conditions were onerous, and interfered seriously with the happiness of our love. The worst of them was that we should never spend a night together. I raged and stormed, along with Philip and Logan and Alys. Ottoline found all this very trying, and it produced an atmosphere in which it was difficult to recapture the first ecstasy. I became aware of the solidity of Ottoline's life, of the fact that her husband and her child and her possessions were important to her. To me nothing was important in comparison with her, and this inequality led me to become jealous and exacting. At first, however, the mere strength of our mutual passion overcame all these obstacles. After Studland various difficulties began to cause trouble. Alys was still raging, and Logan was quite as furious as she was. The Whiteheads, who showed great kindness at this time, finally persuaded them to abandon the idea of a divorce involving Ottoline, and Alys decided that in that case a divorce was not worth having. I had wished Ottoline to leave Philip, but I soon saw that this was out of the question. Meanwhile, Logan went to Philip, and imposed conditions, which Philip in turn had to impose upon Ottoline. These conditions were onerous, and interfered seriously with the happiness of our love. The worst of them was that we should never spend a night together. I raged and stormed, along with Philip and Logan and Alys. Ottoline found all this very trying, and it produced an atmosphere in which it was difficult to recapture the first ecstasy. I became aware of the solidity of Ottoline's life, of the fact that her husband and her child and her possessions were important to her. To me nothing was important in comparison with her, and this inequality led me to become jealous and exacting. At first, however, the mere strength of our mutual passion overcame all these obstacles.
She had a small house at Peppard in the Chilterns, where she spent the month of July. I stayed at Ipsden, six miles from Peppard, and bicycled over every day, arriving about noon, and leaving about midnight. The summer was extraordinarily hot, reaching on one occasion 97° in the shade. We used to take our lunch out into the beech-woods, and come home to late tea. That month was one of great happiness, though Ottoline's health was bad. Finally, she had to go to Marienbad, where I joined her after a while, staying, however, at a different hotel.
With the autumn she returned to London, and I took a flat in Bury Street, near the Museum, so that she could come and see me. I was lecturing at Cambridge all the time, but used to come up in the morning, and get back in time for my lecture, which was at 5.30. She used to suffer from terrible headaches, which often made our meetings disappointing, and on these occasions I was less considerate than I ought to have been. Nevertheless, we got through the winter with only one serious disagreement, arising out of the fact that I denounced her for being religious. Gradually, however, I became increasingly turbulent, because I felt that she did not care for me as much as I cared for her. There were moments when this feeling disappeared entirely, and I think that often what was really ill-health appeared to me as indifference, but this was certainly not always the case. I was suffering from pyorrhoea although I did not know it, and this caused my breath to be offensive, which also I did not know. She could not bring herself to mention it, and it was only after I had discovered the trouble and had it cured, that she let me know how much it had affected her.
(映画ポスター「去年マリエンバートにて」より)
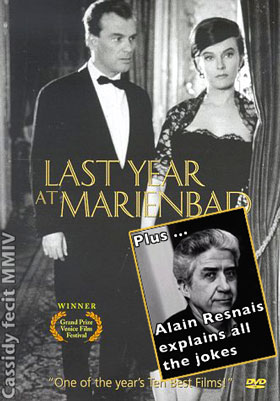
|


 After Studland various difficulties began to cause trouble. Alys was still raging, and Logan was quite as furious as she was. The Whiteheads, who showed great kindness at this time, finally persuaded them to abandon the idea of a divorce involving Ottoline, and Alys decided that in that case a divorce was not worth having. I had wished Ottoline to leave Philip, but I soon saw that this was out of the question. Meanwhile, Logan went to Philip, and imposed conditions, which Philip in turn had to impose upon Ottoline. These conditions were onerous, and interfered seriously with the happiness of our love. The worst of them was that we should never spend a night together. I raged and stormed, along with Philip and Logan and Alys. Ottoline found all this very trying, and it produced an atmosphere in which it was difficult to recapture the first ecstasy. I became aware of the solidity of Ottoline's life, of the fact that her husband and her child and her possessions were important to her. To me nothing was important in comparison with her, and this inequality led me to become jealous and exacting. At first, however, the mere strength of our mutual passion overcame all these obstacles.
After Studland various difficulties began to cause trouble. Alys was still raging, and Logan was quite as furious as she was. The Whiteheads, who showed great kindness at this time, finally persuaded them to abandon the idea of a divorce involving Ottoline, and Alys decided that in that case a divorce was not worth having. I had wished Ottoline to leave Philip, but I soon saw that this was out of the question. Meanwhile, Logan went to Philip, and imposed conditions, which Philip in turn had to impose upon Ottoline. These conditions were onerous, and interfered seriously with the happiness of our love. The worst of them was that we should never spend a night together. I raged and stormed, along with Philip and Logan and Alys. Ottoline found all this very trying, and it produced an atmosphere in which it was difficult to recapture the first ecstasy. I became aware of the solidity of Ottoline's life, of the fact that her husband and her child and her possessions were important to her. To me nothing was important in comparison with her, and this inequality led me to become jealous and exacting. At first, however, the mere strength of our mutual passion overcame all these obstacles.