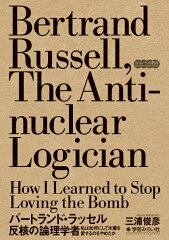「パグウオッシュ会議18年の歩み (3):理念から「現実」に変質(大国主義)
* 出典:『朝日新聞』1975年8月27日付夕刊第6面掲載* Pugwash Online: Conferences on Science and World Affairs
「悪魔が栄えるために必要なことは善良な人々が何もしないということだけだ。」
(All that is needed for evil to flourish is that good men do nothing about it.)」
ラッセル卿が辞任
「自己の良心のみを代表する」との基本精神が、大国の意志でゆらぎはじめていた。主唱者ラッセル卿がその現状に失望してこの会議の議長を辞任したことは、パグウォッシュ(会議)が10年目でひとつの曲がり角にきたことを象徴している。
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
「恐怖の均衡」を前提とする核抑止論をとる両大国。パグウォッシュが世論の支持で影響力をもちはじめると、米ソはここを核兵器の使用を制限しあう「軍備管理」の場へと傾斜させていく。核軍縮をかかげるラッセル=アインシュタイン宣言の理念から「現実主義」への変質である。
「政府代表」の学者
その米ソ出席者の顔ぶれもまったく「政府代義」。ソ連は、アカデミー副会長トプチェフ、宇宙開発の父ブラゴスラポフ、ノーベル物理学賞のタムらトップレベルをそろえる。「ストウの電話局が経験しなかった巨額の長距離電話料」と地元紙が報じたように、連日クレムリンと緊密な連絡をとりつつ会議にのぞむほどだ。
アメリカ側も、アイゼンハワーの軍事顧問でハーバード大学政治学教授キッシンジャー、原水爆開発の物理学者ベーテら、政府に影響力のある学者を動員。
「まだ無名のキッシンジャーが、会議声明案をめぐる議論の最中、多数(の)意見に対立するタカ派発言を続けてついに立ち上がって無言で退場したことを記憶している。」と豊田教授。
1970年、アメリカ・フォンタナでの第20回会議。それは息づまるような核兵器体系の開発競争をめぐる米ソ戦略兵器制限交渉(SALT)がはじまった年でもある。
「米ソが主役でそれ以外はワキ役。この両大国については互いにやりあわぬように気をくばり、会議は儀礼的、その裏で実質的な話し合いをしていた。」と坂本義和東大教授(国際政治)は緊張緩和(デタント)下での会議の印象を語っている。
つまりパグウォッシュは、東西冷戦からデタントへの歩みの中で、米ソ両政府が非公式に接触、打診する役割を果たしていたのだ。
「建前は学者の会だが、その実質は政治問題の解決の場。大変な政治的コミュニケーションを果たしていた。」と坂本教授。
芽生えてきた動き
だが、このことは「核保有国」と「非核保有国」のミゾを深める過程でもあった。実際、軍事技術開発にともなう米ソの「垂直的核軍拡」と核開発技術の普及によるインドなどへの「水平的核拡散」という現実に対して、新しい動きが芽生えている。
たとえば第17回会議で継続委員会にアフリカ、ラテンアメリカ代表が選ばれたことなど、いまやこれら非核保有国、第3世界の声を無視して議論できなくなりつつある。
この「断絶」をどのようにうめるのか--18年目のパグウォッシュがかかえる大きな課題といえよう。