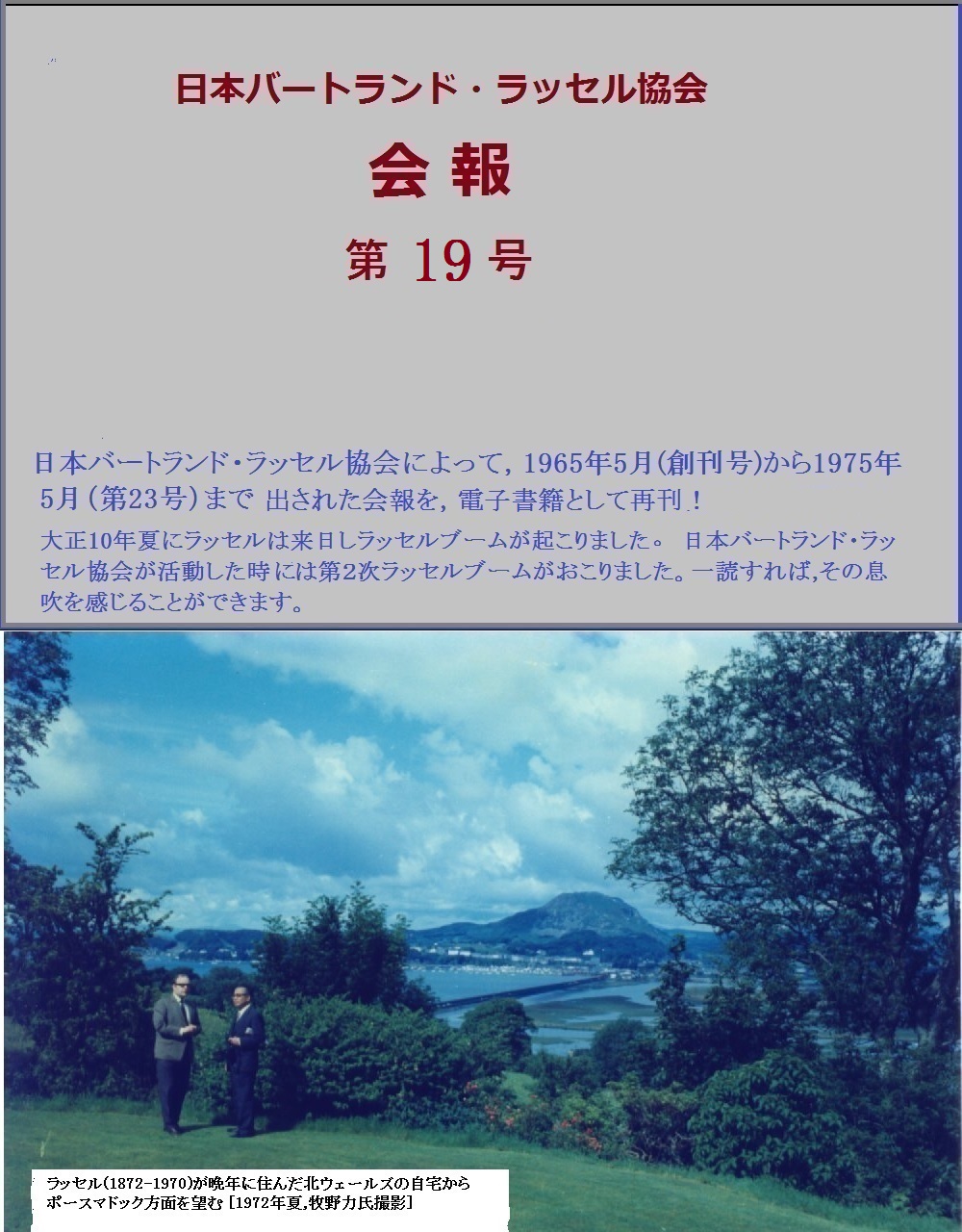
ラッセル協会会報_第19号
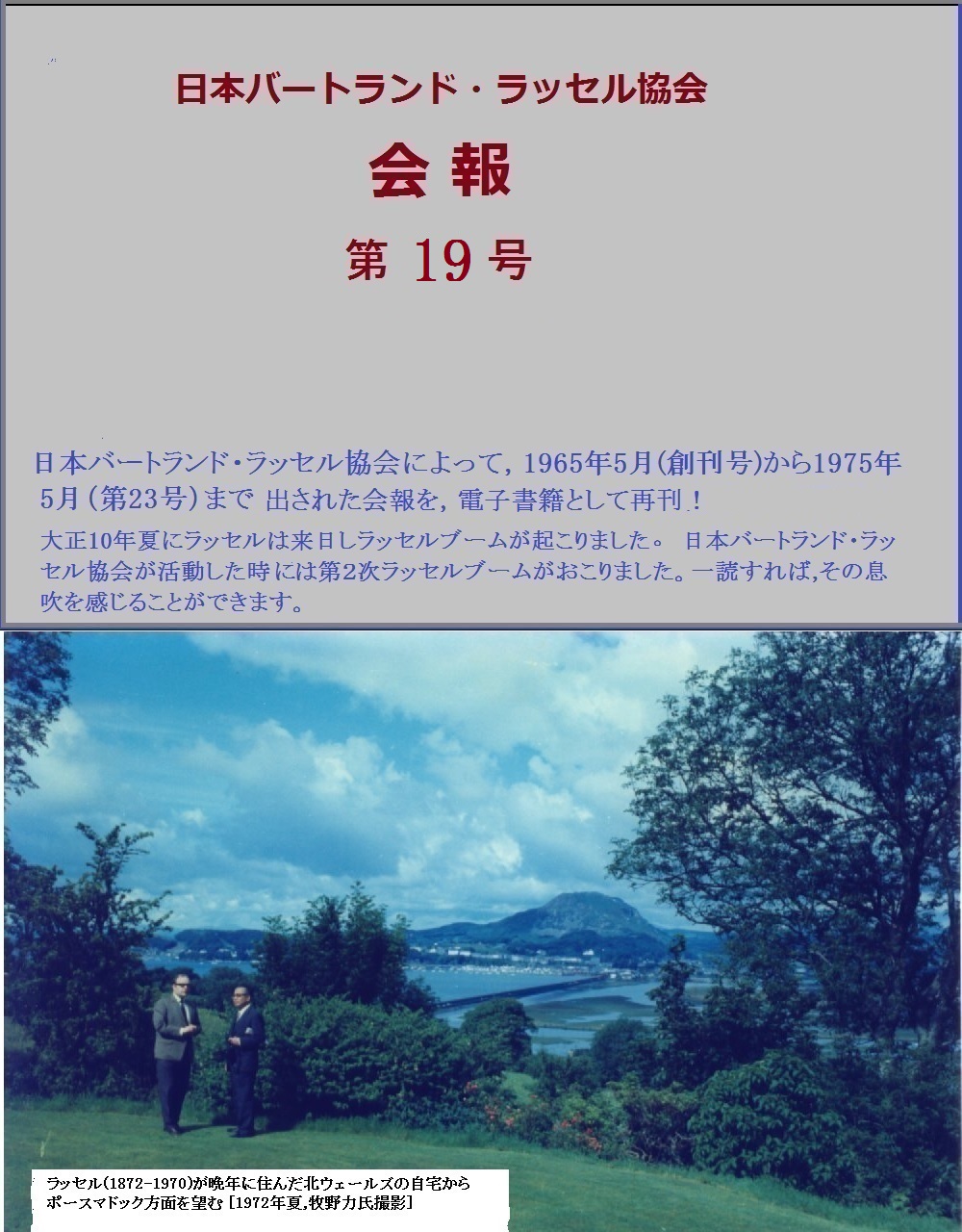 ラッセル協会会報_第19号 |
| I. | 彼女はとても清楚な感じの美人であった |
| II. | それまで知り合ったどの女性よりも解放的であった |
| III. | 親切心が深く積極的にもてなしてくれた |
| IV. | クェーカー教徒としての信仰の強さをもっていた |
| V. | 禁酒運動に参加するほどの行動的な迫力があった |
| VI. | 不思議な因縁めいたものを感じた-すなわち,自分が当時賛美してやまなかった米国の詩人ウォルト・ホイットマンとアリスが親友だったこと,それから,彼女と初めて逢ったその日の朝に読み終えたばかりのドイツ語の本「エックハルト」を,彼女と初対面の席でいままで読んだことがあるかとアリスにきかれたこと |
| VII. | 彼女も自分と同じ自由恋愛論者だった |
| VIII. | 自慰の悪癖に耽ったり,野蛮な性行為を夢みたりしていた自分を極度に恥じ,悔悛の情が深まっていたところへ,アリスの心境が,真実の愛のない性行為は不潔であり,男女の性交は男性の獣性の現われで好ましくないものであり,たとえ結婚をしたとしても子供はぜったいに生みたくないというところにあったので,それがむしろ崇高なものに思えた等々。 |
| 1. | 彼女が米国からの移住者の娘であるということ |
| II. | 英国の伝統を教育されていないということ |
| III. | 下層階級の山師の家庭で育って,作法を知らず,美しい感情を少しも持っていない |
| IV. | 未熟な青年をだまそうとする幼児誘拐魔にひとしい, 等々。 |
| 1. | 生活を共にしていくうちアリスの複雑な性格があらわになってくる |
| II. | アリスの心が,ラッセルに集中するよりは社会的な活動の方により傾いてきた。絶対禁酒運動や婦人参政権運動に熱中していて外出の機会が多い。ラッセルが初めて彼女に求婚した当日ですら,それにたいする諾否の意志を表明しないまま,たまたまその日届いた米国からのインヴィテーション・レターに応じて禁酒宣伝の会議に出席するためシカゴに発っていってしまったほどだった |
| III. | キリスト教にたいする二人の間の意見が対立して論争がたえなかった |
| IV. | ラッセルは子供がほしくてたまらなかった。けれどもアリスは欲しなかった。それに彼女は,セックスを不潔なものと考えて,女性はそれを憎悪すべきものとした。男性の獣的な色欲こそが結婚の幸福に対する大きな障害であるとした。事実アリスは石女(うまずめ)だった |
| V. | 二人の間の性生活が不調であった。初夜のときから困難を感じさせられていた。楽しいものではなくてだんだんと疲労感に悩まされ,やがて彼女に接することを嫌悪する情がつのってくる |
| VI. | アリスの嫉妬心の深さに苦しめられる。しばしば言い争いをしなければならなくなる。ラッセルがパリ駐在の大使館員を辞めてアリスの許に帰ってきた時ですら,パリ滞在中,アリスの妹とよく会っていたということを嫉妬して激しくラッセルをせめたほどであった |
| VII. | ラッセルは,自然を愛していたし,自分の研究と著述の能率をあげるためにも好ましいからというので田舎で暮すことを主張したが,アリスは徹頭徹尾それに反対した |
| VIII. | 妥協や粉飾を許さないラッセルの生一本な気質に反して,虚栄のとりことなるアリスの態度が彼にはとてもたまらないものになってくる。ラッセルの言によれば一「アリスは,人間としてはとても不可能なほど,一点の非のうちどころもないほど高潔だと人に思われようとする。そうして偽善に陥いる。自分の寛大さを賞賛させようとの下心から人をほめる。先方に向っては,そちらに諂おうとしてこちらの悪口を言い,当方にたいしてはこちらに良く思われようとして先方の悪口を言う癖がぬけなかった。平然と嘘を言うことがしばしばだった」と。 |
| IX. | とてもがまんがならなくなったのは,ラッセルが最も忌み嫌った彼女の母のいやな性癖がアリスにあらわれてきたことだった。自分の主人に話をするときにいかにも主人を軽蔑する口調でしたり,また,他人に主人のことを話すときに主人を侮蔑している態度をありありと示す性癖があった等々。 |

|
| I. | まじめではあるが型にははまらない |
| II. | 伝統的には貴族に属しているけれども,貴族特有の偏狭さと特権意識を嫌う |
| III. | 権力・暴力による支配や残虐さを許さない-弱者や虐げられたものの味方となる等々。そして,やさしくいたわってくれるオットリーンに何とも表現できないほどの心の安らぎをおぼえる。ラッセルは言う-「アリスとの結婚生活の何年間を通じて,少しも味うことのできなかったあるもの,飢えていた何ものかをオットリーンが与えてくれた」 |
 「わたしが彼女のことを思っているほどには彼女がわたしのことを思っていないということを感じた」 こうしてオットリーンの心が冷たくなっていった一九一三年(ラッセル四十一才)の夏,ラッセルは友人のサンガーと一緒にインスブルックからアルプス越えをしてイタリアのプント・サン・ヴィギリオに徒歩旅行をした。とあるレストランで他の一行と同じテーブルについた。その時,離れた他のテーブルに一人の若い女性が坐っているのが目についた。みんなはその女性を観察しているうちに彼女が結婚しているか未婚者であるかについて論じあうようになった。ラッセルは,彼女は既婚者だと断言した。けっきょくどちらの意見が正しいかを確かめることになって,ラッセルがその役を仰せつかった。それが縁で彼女と近づきになっているうち,だんだんと彼女にひきつけられていった。彼女の夫は精神分析家で二人の間には二児があったが,彼女は離婚してちょうどそこへ来たばかりであった。「彼女は若くてチャーミングだった。彼女が好きになって,彼女との子供をつくりたいという欲望にかりたてられた」-こうして急速に親しみが深まった。二人は一緒に遠くはなれた田舎を旅行した。けれどもこれは,旅での短い間の恋でしかなかった。そのとき以後は,二人はついに一度も会うことがなかった。ただ数年間のあいだは,よく彼女からのたよりが届いた。彼女はドイツ人であった。
「わたしが彼女のことを思っているほどには彼女がわたしのことを思っていないということを感じた」 こうしてオットリーンの心が冷たくなっていった一九一三年(ラッセル四十一才)の夏,ラッセルは友人のサンガーと一緒にインスブルックからアルプス越えをしてイタリアのプント・サン・ヴィギリオに徒歩旅行をした。とあるレストランで他の一行と同じテーブルについた。その時,離れた他のテーブルに一人の若い女性が坐っているのが目についた。みんなはその女性を観察しているうちに彼女が結婚しているか未婚者であるかについて論じあうようになった。ラッセルは,彼女は既婚者だと断言した。けっきょくどちらの意見が正しいかを確かめることになって,ラッセルがその役を仰せつかった。それが縁で彼女と近づきになっているうち,だんだんと彼女にひきつけられていった。彼女の夫は精神分析家で二人の間には二児があったが,彼女は離婚してちょうどそこへ来たばかりであった。「彼女は若くてチャーミングだった。彼女が好きになって,彼女との子供をつくりたいという欲望にかりたてられた」-こうして急速に親しみが深まった。二人は一緒に遠くはなれた田舎を旅行した。けれどもこれは,旅での短い間の恋でしかなかった。そのとき以後は,二人はついに一度も会うことがなかった。ただ数年間のあいだは,よく彼女からのたよりが届いた。彼女はドイツ人であった。 このようなことがあった翌年(一九一四年,ラッセル四十二才),ラッセルはハーヴァード大学からの招聘に応じて渡米した。同大学でのローウェル記念講義とアン・アーボァー大学での講義を終えてシカゴに赴いた時(シカゴ大学での講演のため),彼は或る著名な婦人科医の家に泊った。その婦人科医夫妻には四人の娘と一人の息子があった。その娘のうちの一人が,シカゴに来たらぜひ自分の家に泊ってくれるようにとラッセルに招待の手紙を出していた。その娘(松下注:Helen Dudley 右は Helen の肖像画)は,先にオックスフォード大学で,ラッセルの友人ギルバード・マーレイのもとでギリシァ語を学んでいるとき,ちょうどオックスフォード近郊のバグレイ・ウッドに住んでいたラッセルを二,三度訪問したことがあった。彼女は,ちょうどシカゴに帰っていたので,ラッセルの渡米を知るとすぐに手紙を書いてラッセルを招待したのだった。彼がシカゴの駅に降り立つと,彼女がちゃんと迎えに出ていた。彼は彼女を「何かしら印象に残る娘ではあった」とおぼえてはいたが,ここで再会するにおよんでさらに新たに自分をひきつける強い魅力を感じさせられた。「アメリカに来て会った他の誰よりも彼女との方がより親しみをおぼえ,ほんとうに心から寛いだ気持になれるのを感じた。気持がとてもやさしく,温い情で自分をつつんでくれた。美人という方ではなかったけれども愛矯があり,陽気で情熱的だった。詩をよくし,文学にたいする感情が凡庸でなかった。そうした反面,孤独の哀愁を漂わせるものがあった」。二日間ここに滞在するうち二人はすっかり恋しあうようになった。ラッセルはその二日目の夜,「彼女を得たいとおもう気持がつのって」彼女と肉体的に結ばれる。両親に気付かれないようにとの心くばりから,ほかの娘たちが廊下で二人の寝室の警戒に当るというエピソードもあった。ラッセルは,アリスとの正式離婚が成立次第,ロンドンで正式に結婚しようと彼女に約束をする。彼は英国への帰国の船中でオットリーンに手紙を書いてこのことを知らせる。ラッセルが帰英するとまもなく,彼女は父親を説得して英国に連れてきた。ちょうどその時,第一次世界大戦が勃発し,ラッセルの反戦運動が開始される。やがて彼は,ロンドン市庁での裁判で百ポンドの罰金刑に処されたり,ケムブリッジ大学から追放されたりした。ラッセルにとって悲惨な,そして暗澹たる時期がつづく。一九一八年には禁固刑に処されて,ブリックストン刑務所に投獄される。英国に渡った彼女は,突如として類例をみないほどの奇病にかかってしまう。麻痺状態,平静期そして発狂状態といった順序がくりかえされる一種の精神異常症であった。ラッセルは始終彼女を病院に見舞うこととなった。最後に会ったのが一九二四年,その後はついに彼女は正気に戻ることがなかった。そしてついに結婚にゴール・インすることもなくて終った。彼は言う-「発狂する以前は彼女はまれにみる優れた精神と愛すべき性質をもっていたから,もしも戦争の邪魔が入らなかったら二人がシカゴで作ったプランは,きっとわたしたち二人に大きな幸福をもたらしたことだろう。わたしはこの悲劇を悲しむ気持でいっぱいだ」
このようなことがあった翌年(一九一四年,ラッセル四十二才),ラッセルはハーヴァード大学からの招聘に応じて渡米した。同大学でのローウェル記念講義とアン・アーボァー大学での講義を終えてシカゴに赴いた時(シカゴ大学での講演のため),彼は或る著名な婦人科医の家に泊った。その婦人科医夫妻には四人の娘と一人の息子があった。その娘のうちの一人が,シカゴに来たらぜひ自分の家に泊ってくれるようにとラッセルに招待の手紙を出していた。その娘(松下注:Helen Dudley 右は Helen の肖像画)は,先にオックスフォード大学で,ラッセルの友人ギルバード・マーレイのもとでギリシァ語を学んでいるとき,ちょうどオックスフォード近郊のバグレイ・ウッドに住んでいたラッセルを二,三度訪問したことがあった。彼女は,ちょうどシカゴに帰っていたので,ラッセルの渡米を知るとすぐに手紙を書いてラッセルを招待したのだった。彼がシカゴの駅に降り立つと,彼女がちゃんと迎えに出ていた。彼は彼女を「何かしら印象に残る娘ではあった」とおぼえてはいたが,ここで再会するにおよんでさらに新たに自分をひきつける強い魅力を感じさせられた。「アメリカに来て会った他の誰よりも彼女との方がより親しみをおぼえ,ほんとうに心から寛いだ気持になれるのを感じた。気持がとてもやさしく,温い情で自分をつつんでくれた。美人という方ではなかったけれども愛矯があり,陽気で情熱的だった。詩をよくし,文学にたいする感情が凡庸でなかった。そうした反面,孤独の哀愁を漂わせるものがあった」。二日間ここに滞在するうち二人はすっかり恋しあうようになった。ラッセルはその二日目の夜,「彼女を得たいとおもう気持がつのって」彼女と肉体的に結ばれる。両親に気付かれないようにとの心くばりから,ほかの娘たちが廊下で二人の寝室の警戒に当るというエピソードもあった。ラッセルは,アリスとの正式離婚が成立次第,ロンドンで正式に結婚しようと彼女に約束をする。彼は英国への帰国の船中でオットリーンに手紙を書いてこのことを知らせる。ラッセルが帰英するとまもなく,彼女は父親を説得して英国に連れてきた。ちょうどその時,第一次世界大戦が勃発し,ラッセルの反戦運動が開始される。やがて彼は,ロンドン市庁での裁判で百ポンドの罰金刑に処されたり,ケムブリッジ大学から追放されたりした。ラッセルにとって悲惨な,そして暗澹たる時期がつづく。一九一八年には禁固刑に処されて,ブリックストン刑務所に投獄される。英国に渡った彼女は,突如として類例をみないほどの奇病にかかってしまう。麻痺状態,平静期そして発狂状態といった順序がくりかえされる一種の精神異常症であった。ラッセルは始終彼女を病院に見舞うこととなった。最後に会ったのが一九二四年,その後はついに彼女は正気に戻ることがなかった。そしてついに結婚にゴール・インすることもなくて終った。彼は言う-「発狂する以前は彼女はまれにみる優れた精神と愛すべき性質をもっていたから,もしも戦争の邪魔が入らなかったら二人がシカゴで作ったプランは,きっとわたしたち二人に大きな幸福をもたらしたことだろう。わたしはこの悲劇を悲しむ気持でいっぱいだ」 一九一六年,ラッセルは反戦運動で逆境に立たされ,孤独感にうちひしがれ,またオットリーンは彼を去り,結婚を約束したシカゴ娘が発狂して悲嘆のどん底にうちひしがれていた頃,彼の前に登場したのがレディ・コンスタンス・マリソン,すなわち女優コレッティ・オニール(Colette O'niel)であった。彼女は,俳優で劇作家のマイルズ・マリソンの夫人で,その頃人気上昇中の舞台女優だった。自由主義者で,純粋の平和主義者であった。ラッセルがよく面倒をみていたクリフォード・アレン(後の労働党議員,大臣,アレン・オブ・ハートウッド卿)の率いる徴兵反対同盟の事務所に毎日来ては封筒のアドレス書きをしたり,事務の手伝いをしていた。ラッセルはこのアレンの紹介でコレッティを知り,会議,演説会,晩餐会とつづくデートの機会を重ねるうちに恋人同志となった。二人の仲をラッセル自らこう説明する-「コレッティは非常に若くて美しい女優であった。そしてオットリーンと同じくらい素晴らしく落ち着いた勇気をもっていた。勇気こそが,わたしが真剣に愛そうとするほどの女性がもつべき不可欠な要素なのである。-わたしが初めてロンドンのホテルで彼女とベッドを共にしていた夜,外の街頭で突如として獣の咆哮するような叫び声が起こるのを聞いた。わたしはすぐさまベッドから飛び降りた。そして窓から,ドイツのツェッペリン飛行船が焔につつまれて墜落してくるのを見た。大衆は,勇敢な飛行士が苦悶しつつ死んでいく光景を頭に描きながらこの喚声を発しているのだった。
自分は戦争を憎悪し,大衆の犠牲を除こうとして反戦運動を展開しているのに,大衆自らは戦勝に踊り狂い,人の死に歓声をあげている。自分をおそう空虚感と大衆に対する失望感に苦悶した。その時,コレッティの愛こそがわたしの救いであった。頼りのないこの世で,コレッティの愛こそがわたしの支えであり,拠りどころだと思った。しかもそれは巌のように揺がない不動のものだった。当時としては計りがたい貴重なものだった……」
一九一六年,ラッセルは反戦運動で逆境に立たされ,孤独感にうちひしがれ,またオットリーンは彼を去り,結婚を約束したシカゴ娘が発狂して悲嘆のどん底にうちひしがれていた頃,彼の前に登場したのがレディ・コンスタンス・マリソン,すなわち女優コレッティ・オニール(Colette O'niel)であった。彼女は,俳優で劇作家のマイルズ・マリソンの夫人で,その頃人気上昇中の舞台女優だった。自由主義者で,純粋の平和主義者であった。ラッセルがよく面倒をみていたクリフォード・アレン(後の労働党議員,大臣,アレン・オブ・ハートウッド卿)の率いる徴兵反対同盟の事務所に毎日来ては封筒のアドレス書きをしたり,事務の手伝いをしていた。ラッセルはこのアレンの紹介でコレッティを知り,会議,演説会,晩餐会とつづくデートの機会を重ねるうちに恋人同志となった。二人の仲をラッセル自らこう説明する-「コレッティは非常に若くて美しい女優であった。そしてオットリーンと同じくらい素晴らしく落ち着いた勇気をもっていた。勇気こそが,わたしが真剣に愛そうとするほどの女性がもつべき不可欠な要素なのである。-わたしが初めてロンドンのホテルで彼女とベッドを共にしていた夜,外の街頭で突如として獣の咆哮するような叫び声が起こるのを聞いた。わたしはすぐさまベッドから飛び降りた。そして窓から,ドイツのツェッペリン飛行船が焔につつまれて墜落してくるのを見た。大衆は,勇敢な飛行士が苦悶しつつ死んでいく光景を頭に描きながらこの喚声を発しているのだった。
自分は戦争を憎悪し,大衆の犠牲を除こうとして反戦運動を展開しているのに,大衆自らは戦勝に踊り狂い,人の死に歓声をあげている。自分をおそう空虚感と大衆に対する失望感に苦悶した。その時,コレッティの愛こそがわたしの救いであった。頼りのないこの世で,コレッティの愛こそがわたしの支えであり,拠りどころだと思った。しかもそれは巌のように揺がない不動のものだった。当時としては計りがたい貴重なものだった……」| I. | ドーラは子供は自分だけのもので,父の権利は認めないと主張した |
| II. | ラッセルはロンア訪問の後,ロシアに対して批判的な論調を展開したが,ドーラの方はロシア崇拝,ボルシェヴィズム一辺倒を変えなかった |
| III. | ラッセルはどちらかというと内向的な性格だったが,ドーラは激情的で時には無軌道ぶりを発揮した-ラッセルは中国に赴く船中で「二人の間のトラブルを解決するためには,この船から大海に飛び込むほかは無い」とドーラに語ったほどだった |
| IV. | ラッセルが二階で著述に没頭しているのに,階下ではドーラがそこを「労働者産児制限協会」の事務所にしたり,社会運動や婦人運動の同志たちのたまり場にしたり,二回下院に立候補して選挙運動を展開するその事務所にした。 |
| V. | ドーラは別に二人の恋人をつくり,その恋人らとの間に二人の子供が出来る。ラッセルはドーラの恋人のうちの一人を家に同居させる。妻の恋愛の自由を認むべきであって嫉妬の感情をいだいてはならないというのが自分の理論であったが「しかし実際にはこのような環境に耐えきれなくなった」と言い出すラッセルだった |
| VI. | 一九二七年以来,ドーラと共同で実験学校を経営していたのであったが,教育の根本方針において,また経営の方針において本質的相異が二人の間にあり,それが二人の離別に拍車をかける。こうして一九三二年(ラッセル六十才),二人は別居生活に入る。離婚が正式に成立したのは一九三五年であった。 |
「今老いて,そして人生の終りに来て,わたしはあなたを知った。そうしてあたたを知って初めて喜びと平和を見出した。あの長い寂しい月日を経て,わたしはいまようやく安らぎを得ている。いま眠りにつくとすれば,わたしは心満たされて眠ることであろう」(出典)ラッセルは九十七才を一期として,その波乱にとんだ生涯を,エディス夫人にみとられつつ,心満たされつつ閉じたのである。
「恋愛は真実であり,真剣なものでなければならない。事実である恋愛の情を隠そうとするのも,またそれを認めようとしないのも,それは偽善である。たとえ結婚後といえども,真実の恋愛であるかぎり,それは認められなければならない-しかも夫婦の両方に平等に認められなければならない。それをもって離婚の理由にしてはならない」彼は,恋愛は高く評価されなければならないとした-
「恋愛は歓喜の源泉である。恋愛は,音楽とか,山頂の日の出とか,満月下の大海とかいったような最も良い快楽を一層大きくしてくれる。愛し合う幸福な者同志の深い親愛感と,強い共同意識を味わったことのない人たちは,人生にとって欠くことのできない最良のものを見失っている」