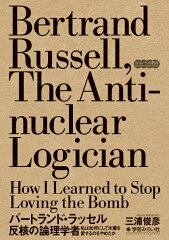横関愛造「バートランド・ラッセル-激しい原爆への憎悪
* 出典:横関愛造『思い出の作家たち』(法政大学出版局,1956年12月)pp.230-242.)* 横関愛造(1887~1969):長野県生。早大政経卒/東京毎日新聞編集長,『改造』初代編集長,後に改造社代表取締役。この間,外務省嘱託など/本書刊行当時,東京光機工業代表取締役。
*この回想記と,同氏が『日本バートランド・ラッセル協会会報』第2号(1965年9月)に発表した「日本に来たラッセル卿」とで,既述の重複が多い。
* 松岡正剛「松原一枝著『改造社と山本実彦』について」
「肉体的には,八十歳の老齢を思わせたが,その精神的な若々しさ,その思索の新鋭さは,年齢を超越しているように見受けました」とは,一九五二年,博士八十一歳のとき,親しくその別荘を訪ねた山川菊栄女史>(1890年生~1980年没。大正・昭和期の社会主義女性解放思想の代表的理論家。第二次大戦後は労働省婦人少年局初代局長に就任。/夫は山川均。)のおたより,である。(参考:山川菊栄文庫) 「曽遊の地日本について,かずかずの思い出を語り,いかにもなつかしそうであった」ということである。その折,日本語を話す博士の子息のひとりも同席した。大戦中,軍隊にいるとき日本語を修得したという話であった。(松下注:長男の John Russell と思われる。)いろいろ戦後の日本の現状を熱心に聞いていたそうである。日本に対する博士一家の愛情のほども想像される。そのなつかしい思い出の日本に,人類史上最初の原爆第一号が投下され,多数の惨害を被むったことについては,博士にとってまことに悲しむべきできことであったに違いない。ことに,非戦論者であり,絶対平和論者である博士にとって,これほど大きなショックを与えたものはなかったに相違ない。その顕著なあらわれこそ,一九五五年七月十日,博士の名において発せられた「核兵器の禁止,戦争絶対回避」の宣言である。この宣言は,アインシュタイン博士死去のニカ月前(松下注:ではなく,亡くなる2日前に署名),すでにラッセル博士との間に調印されたものである。この署名者は,世界におけるもっとも著名な科学者八名の賛成連署によるもので,それは次のひとびとである。
|
|
キユーリー博士も賛成であったが,発表当日までに署名が間に合わなかった。ラッセル博士の呼びかけによるこの宣言は,けだし,地球上の全人類を代表した,原爆への憎悪,人類絶滅への抗議にほかならぬ。「しかも,今や各国は更に強力な原水爆の製造を競い,その災いが,彼ら自身,その子,その孫にまで及ぶであろうことを悟っていないかのようである」と,この宣言は結んでいる。
( 松下注) この前後の記述は,少し不正確。署名者は以下の通り:
・マックス・ボルン教授(ノーベル物理学賞)
・P.W.ブリッジマン教授(ノーベル物理学賞)
・アルバート・アインシュタイン教授(ノーベル物理学賞)
・L.インフェルト教授(ノーベル物理学賞)
・F.J.ジョリオ・キュリー教授(ノーベル化学賞)
・H.J.ムラー教授(ノーベル生理学・医学賞)
・ライナス・ポーリング教授(ノーベル物理学賞)
・C.F.パウエル教授(ノーベル物理学賞)
・J.ロトブラット教授
・バートランド・ラッセル卿(ノーベル文学賞)
・湯川秀樹教授(ノーベル物理学賞)
ラッセル博士のこの原子戦争回避の勧告に対して,世界の著名な科学者九名が,その署名を拒否している。そのうち無視した科学者は,コンプトン,ユーリー(以上二名米国人,いずれもノーベル賞受賞者),李四光(中共)。拒否したもの,ハーン,ボルン(二名共西独),ボアー(デンマーク),パウリ(スイス),ジークバーン(スウェーデン),アドリアン卿(英)=以上六名いずれもノーベル賞受賞者,ハドフ(英),バーバー(印度),スコベルツィン(ソ連)。
この学者名は,声明の発表された前日,ラッセル博士によって公表されたもので,記者会見の席上,博士は「まことに遺憾なことを発表する」と前提して発言,不快な顔色がうかがわれたと報道された。
|
| |
|
アマゾンで購入 |
公使は,私の来意をジッと聞いていたが,やおら身をおこして,「君,軍部で上陸を拒否するかもしれないぞ,どうもその不安がある・・・」
と顔色をくもらせた。
「もちろん・・・その公算大いにありです」
「なにぶん博士は,第一次大戦中,非戦論者として,追放された人だからなア」
と,公使はますます暗い表情になる。
「しかし,もし通訳がいるようなら,僕の一存でだれか公使館から出してもいいよ」
「イヤ・それは辞退します。もし後日公使にまで累を及ぼすようなことが起ってはすみませんから・・・」
「そんなこと,どうでもいいさ」
と,公使はいっこうに意に介しないもののごとくに語をつぎ,
「心配するな,イギリスは,日本にとっては唯一の友好国だ。その友好国の学者にたいして,国際信義に反するようなことは,断じてすべきではない。わしから,適当に外務省へも連絡しておくよ」
公使はこういって,力強く私の肩をたたいた。
ラッセル博士は礼儀の正しい,純英国流の紳士であった。生活ぶりも,至って質素であった。北京には,六国飯店,北京飯店など,一流のホテルもあるのだが,これらのはなやかな旅館を敬遠して,東華門外の大陸飯店という,まことに質素なホテルに,こっそりと投宿した。「ラッセル来る」の報に,北京の報道陣は,駅頭に放列をしいて待ちかまえたが,その裏をかくように,裏門から抜け出して姿をかくした。その後,躍起となってその隠れ家をさがしまわったが,私が会見した後も,当分まだ新聞記者とは会わなかった。博士の新聞記者ぎらいは,かなり有名なものだ。日本に上陸したときも,それで問題をひきおこしたものだが,しかし,新聞記者を毛ぎらいしているのではなく,私生活を故なく無作法に乱されることを不快とする,英国流のエチケットからきているようである。あれほど物わかりのよさそうな,サバサバとした人間と思われているバーナード・ショウ翁でさえ,やはり新聞記者に対しては,無作法なやり方に不快な顔をした。日本にきたときも,新聞記者が同席すると,決して重要な意見は述べなかった。ただ,ラッセル博士のように,その不快さを端的に行動にあらわさないだけだった。写真班がカメラを向けると,きわめて自然な,おどけた身振りで,帽子で顔をかくしたり,手でさけたりする。英国流にいうと,失礼な行動に対する防禦なのかもしれない。
もっとも,ラッセル博士が,日本で新聞記者に特につらく当ったのには理由があった。それは,博士が北京滞在中のことである。当時の東京日日新聞上海特派員の村田君が,どこでどう早耳に聞いたのか,「ラッセル,北京において客死す」と電報をうってきた。(松下注:この報は,世界中に伝わった。)近く改造社の招待で日本に渡来することになっていた時のことであるから,相当センセーショナルな大見出しで報道された。この報道が,東京電報となって北京に逆輸入された。これには,さすがの北京人もおどろいて,あやうく弔間もしかねないところまでいったというから少々念入りであった。こんなことから,日本の新聞記者に対しては,一種の反感もあったのであろう。神戸に上陸するや,写真班がドッと押しかけて,その行く手に放列をしいた。これを見た博士は,俄然色をなして,「失礼だッ」と叫んで,ステッキをふりまわした。(松下注:このあたりの横関氏の記憶は心許ない。ラッセルがステッキを振り回したのは,横浜駅構内であり,妊娠していたドラ・ブラックがフラッシュの雨で流産しないかと恐れたためである。)おそらく日本の新聞史上,ステッキをふりまわして新聞記者を追いはらったのは,ラッセル,吉田茂のふたりきりだろう。
日本での正式の新聞記者会見では,機嫌よく話し,応答していたが,その時,
「日本にきているラッセルは,この世のものではない。ラッセルの幽霊だ」
と,謹厳な博士にしては,実に一世一代の皮肉をとばしてニヤッと笑った。心ある者は,思わず冷汗をかいたものである。
そこで私は,当時大阪毎日新聞北京特派員波多野幹一君(現在産経時事論説員)にその話を洩らしたところ,波多野君も,是非ラッセルに会いたいと思っていたとのことだったので,ともに連れ立って大陸飯店を訪れた。
「新聞記者には会わないことにしている。退席してもらいたい」 波多野君を見ると,博士はいきなりこういった。私も困った。通訳に当った陳博生氏は更に因惑したらしい。そこでともどもに,決して会ったということを発表しないから同席させてほしいとだのんで,やっと諒解してもらった。実は,新聞記者ぎらいもそれほど徹底しているとは想像していなかった。
「私の日本行きに政府が同意するか,日本では,政府が思想的にいろいろな圧迫を加えていると聞いているが・・・」
博士は開口一番こう切り出した。私は内心ギクッとした。それは,小幡公使と全く同じ意味を持っているからだ。そこで私はザックバランに,
「あるいはそうかもしれない。当ってくだけるよりほか道はないから,その覚悟できていただけないか」
と答えると,博士は,ニヤッとして,
「よろしい,よろしい,当ってくだけろ・・・,面白い言葉だ・・・」
と軽くうなずいて,まことに快く日本行きを承諾してくれたのだった。
「日本ではだれに会いたいか」
と私がたずねると,キョトンとした顔つきで,
「今のところ会って見たいと思っている人もない」
と,軽くあしらっていた。
日本に着いたのは一九二一年七月。当時,日本の思想界は,マルクス主義の勃興時代ではあったが,大学の教壇でも,社会主義の理論さえ遠慮がちに講義をしていた。ことに,社会革命などとは,口や筆にしてさえ,恐るべき危険思想と看做され,うっかり口をすべらせると,直にブタ箱に放り込まれる。わずかに,京都大学の河上肇博士が,気を吐いているにすぎなかった。ことに,博士来日の七月は,あたかも,神戸三菱,川崎両造船所職工三万八千名の大ストライキの起った時であり,当局の神経は極度に尖鋭化していた。他方,共産党員の大検挙などがあり,物情すこぶる騒然たるさなかだったので,果して無事上陸できるかどうか,われわれも内心警戒して,万一にそなえていた。しかし,小幡公使の進言なども効を奏したのであろう。何事もなく上陸することができた。
だが,上陸以来の警戒は,すこぶる厳重をきわめた。常に二名の尾行があとを追った。講演会は,どこもここも超満員の盛況で,入場のできない聴衆の列は,長蛇をなして,延々とつながっていた。講演会には,多数の私服のほか,検閲官が臨席して,一言一句を注意していたが,ついに一回も「弁士中止」を食ったことがなかった。
これについて,その講演を直接聞いていた,当時の内務省検閲官の宇野慎二氏は,こんなことをいっていた。
「ラッセル博士の数理哲学とか,新実在論哲学とかいう理論は,相当に予備知識がなくては,なかなか容易に理解のできるものでない。だから,急ごしらえの頭では検閲官が聞いたところで,正直なところ,どこまで日本流のいわゆる危険思想なのか,わかるものではない。それほどに難解のものであるから,実害が伴わないと見たので,中止命令は出なかったのだろう」
ということであった。この言葉を裏がえしにすると,結局,検閲官の頭では,ちんぷんかんぷんで,煙にまかれたかっこうだったということになるらしい。しかし博士の学説は,決して難解ではなかった。実にわかりやすい言葉で説かれた。知識階級にかぎられた聴講者は,咳一つさえしない静粛さであった。何事かさわぎでも起りはしないかと期待していたらしい取締当局も,いささか手持ぶさたの気味があったようだ。
講演会のひまひまには,箱根,日光,京都など,日本の風物,芸術を心ゆくまで鑑賞された。なにぶん,冗談もいわず,雑談もしない。汽車に乗っても,姿勢をくずさず,いつも何事かを思索しているといった風なので,お供をするわれわれは,さながら待従長のごとくシャチコ張っているので,肩のこることはなはだしい。ホテルに着いても,食事の時間以外は居室に引きこもって,思索するか,読書する。そのひまひまには,秘書の打つタイプの音が絶えない。アインシュタイン博士は,よく冗談もいう,軽口もたたく,夜になると,愛器のヴァイオリンを弾いてたのしむといった人だったが,ラッセル博士にいたっては,徹頭徹尾学究肌であった。一九五〇年,ノーベル文学賞を受けた博士は,その直後「原子力時代」という一書を公けにして,第二次世界大戦のもたらした,新らしい原子力戦争時代を警告した。博士はすでに八十五歳(一九五六年)の高齢である。しかし,年齢を超越した原子力戦争への憎悪は,おそらくその生涯を通じて戦いとる決心であろう。
日本滞在中,山川均,河上肇,大山郁夫,大杉栄氏などと会見してはどうかとすすめた人もあったが,公の席以外,私的会談はとうとう一度もしなかった。日本を去るにあたっては,心から日本での旅をよろこんでくれた。それ以来,博士の日本に対する愛情は,いろいろな形で表現された。四季おりおりの消息はもちろん,大正十二年大震災の時などは,わざわざ電報を寄せてわれわれ同人の安否を気づかってくれた。新らしい著書が出ると,必ず真ッ先に送ってくれた。大戦中,しばらく相互の音信が絶えていたが,平和回復とともに,すぐに安否を問う長文の書面を寄せられた。そして,われわれから紹介をした日本人には快く面会して,いろいろ日本の実状を聞くのをたのしみにされたらしい。
ラッセル博士百年の長寿を希ってこの一文を書く。