佐伯彰一「理性の王者の落とし穴 (バートランド・ラッセル)」(その1)
* 出典:『自伝の世紀』(講談社、1985年11月刊行)pp.270-300* 佐伯彰一氏(1922~20161.1):、東大英文科卒。文芸評論家、英文学者。米国留学を経て、都立大、東大、中央大学教授を歴任。著書は、『近代日本の自伝』(中公文庫、1990年)、『神童のこころ』(中公文庫、1992年)、その他多数。当時東大名誉教授。
1
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
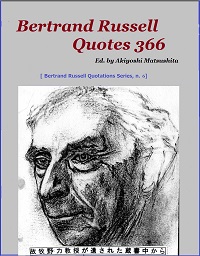 Kindle series |
さて、今しばらくクック記者の跡を追わせてもらうなら、一応の軽い挨拶をすませた後のラッセル卿は、まだ閉まったままの駅構内のキオスクの中を、ガラスごしにしきりとのぞきこんでいた。ここの係りの肥った男は、わきの方で悠々と朝食のコーヒーをすすっていて、お客のことなど歯牙にもかけない。ラッセル卿が、何度そちらにいら立たしげな視線を送っても、相手は素知らぬ顔であった。やがて、コーヒーを飲み終えて、店を開けにかかると、この男は、いかにもアメリカ人らしい率直さ、ぶしつけさで、じりじりしているラッセル卿に向ってこう言い放ったという。「どうかしたんかね、じいさん?」イギリスでも名だたる名門貴族のラッセル家の当主、そして輝かしいノーベル賞受賞者に対して、アメリカの庶民のこの天っ晴れな対応ぶりは、日ごろラッセルがイギリス貴族の美質としてあげる「大胆不敵さ、判断の独自性、群からの解放度」と、そして同時に「傲慢さ、同情の限界、お仲間以外に対する冷酷さ」というその弱点をも物の見事に体現して見せたあんばいの面白い取り合せと、クックはイギリス的ヒューモアをきかせたコメントを加えている。この際のラッセルは娘のケイトが住むワシントンヘ出かける所で、クックの同行を認めてくれたのだったが、キオスクでの彼は、新聞の日曜版などには眼もくれず、もっぱらペイパーバックの棚をあさって、探偵物を4冊ほど買いこんだ。そして、車中でのラッセルの読書ぶりがまた面白い。しばらく雑談してから、探偵小説を読み出すと、おどろくほどのスピードで、どしどし読み進む。明らかに斜め読みで、さっさっとページをひるがえしてゆく。1冊を読み上げるのが15分とはかからない。終ると、床下にぽんと投げ落す。すぐ2冊目、また3冊目と、1時間足らずのうちに、4冊を軽々と読み上げてしまった。探偵小説の作者、愛読者には叱られそうな、そっけない速読ぶりであったが、おそらくこの際にもラッセル一流の明晰にして合理的な方針と理由づけは一貫していたに違いない。探偵小説に自分の求める所は、犯罪の種類と経緯、そして解明の手続きいかんにあるのだから、それ以外の描写、もって廻った説明など、ただの余計物にすぎない。自分はひたすら探偵小説の本質的な部分をたどり、たしかめながら、読んでゆく。それだけで十分であり、十分に楽しんでもいるのだと。以上は、ぼくなりのさし出口の説明であるが、ラッセルの探偵小説愛好には、さらに重要な要素、動機が働いているらしい。つまり、彼は生涯一貫して徹底した合理主義者であり、世の不合理、不条理と暴力とを憎んでやまず、その廃棄・絶滅をめざして、大いにたたかいもした。しかし、じつの所、この相手はあまりに強大、執拗ともいうべく、せっかくのラッセル卿の批判、抵抗といえども、どこまで実効をおさめ得たかは、確言の限りでない。ところが、探偵小説というジャンルにおいては、とにかくある種の悪はその正体があばき立てられて、明瞭な解決にまで至りつかずにおかない。「勧善」はともかく、一種の「懲悪」のドラマが、判然たる手順で、展開されている。そこにラッセル卿は、いわば「現実補償」の快感を味わっていたのではないかというクックの解釈は、中々冴えた心理的探偵術とみとめていいだろう。
実際ぼくらの印象に残るラッセル像、とくに晩年の公人としての彼の活動ぶりは、何よりも老いの一徹、怒れる老人のイメージで、原爆反対のデモの先頭に立って逮捕されたり、ベトナム戦争批判の「国際法廷」が開かれたのも、彼のイニシャチヴによるものだった。一たん政治論争もしくは道徳的原理にかかわるトピックとなると、しばしば怒れるラッセル卿の姿と語調が現出することとなったとクックも書いている。ただし、彼の発言の内容、批判ぶりが、いかに手きびしく辛辣なものであろうとも、ラッセル卿の語りの調子とそして文体は(とほとんど言っていい)、「完壁に構成されたオペラのアリア」にも似た見事さで、「ただしスコットランドのバッグパイプさながら」、少少甲高く、かしましく響きわたるのだった。機嫌よく、愛想のいい時でも、彼の言葉は「一切頭の中で組み立てられ、メロディアスな -いくらか鼻声だが- 仕上りの確かさで発音された」。クックは、このラッセル論に「理性の王者」('The Lord of Reason')というタイトルをふっているのだが、いかにも終生一貫した理性の人、徹底した合理主義者の面目は、その語り口にまで及んでいたらしい。
しかし、クックが報告してくれるもう一つの特質は、いささか意外なものだ。この世の森羅万象を、人間にかかわる一切を、合理的な明晰さで割り切らずにおかなかったラッセル卿が、じつは並並ならぬ逸話ずき、それも会話の際のエピソードの語り口がまことに鮮やかだったという。2人の乗った汽車がニュージャージ州に入って、さびれた町外れに「ガラス工場」という剥げかけた看板が見えたとき、「ぼくの最初の妻の従兄が、このニュージャージーでガラス工場をやっていたんだ。その(妻の従兄の)妻君というのが、亡くなる最後の日までピストルを手放さなかった女でね」とラッセルは語り出した。アメリカ女とピストル-さてはおきまりの「銃砲取締り」の問題で、アメリカ社会の根深い暴力性の批判といった大議論かと身構えると、ラッセルは明るく軽やかな調子で、内輪話をやり出した。この女性が、「馬鹿げた文学的野心にとりつかれて、まるでまずい戯曲を次々と書きつづけたものだが、上演のあてなんて全くない。とうとう、彼女は大事に保存してきた、夫の自分あての恋文をかき集め、ブラウスの中につめこんでから、心臓目がけて、ピストルをぶっ放した-まず恋文を通って心臓まで貫通したという訳さ」、そういって話の落ちをつけた時の、老ラッセル卿は、まるで狐みたいにくしゃくしゃの満面の笑顔だったと、クックは書いていた。いかにも見事な語り口といっていいが、もとより無邪気なゴシップとは違い、面白おかしい滑稽談ともいい難い。一種グロテスクな結末という他なく、自殺するまで思いつめたご当人の大真面目、深刻な心境と現実との間に大きなギャップが、口を開いている。こちらも釣られて、笑いはするものの、何か嫌なおりのようなものが後に残る。残酷な寓話とでもいうか、にがい悪意の味わいが、いりまじらずにいない。しかし、これはしごく無雑作に語られながら、一度耳にしたら奇妙に忘れ難いような風刺的小話の傑作で、ディテールの選び方といい、端的な焦点のしぼり方といい、語り手としての手腕、才腕のほどには、誰しも舌をまかざるを得ないだろう。(続く)


