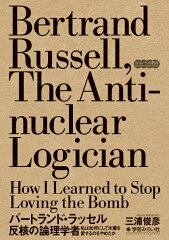小川岩雄「核軍縮をめざす科学者の役割 - パグウォッシュ京都シンポジウムの成果と今後の課題
* 出典:『朝日ジャーナル』(1975.09.12)pp.84-88,+90.*「パグウオッシュ京都会議開く、完全核軍縮求めて科学者ら36人が参加」
* ラッセル=アインシュタイン宣言の着想
5日間の白熱した討議を踏まえて、9月1日の午後、湯川秀樹博士とともに日本側の組織委員をつとめられた朝永振一郎博士が、ひとことひとことをいとおしむように閉会のことばを述べられるのを聴きながら、私の脳裡には、30年前に浴びた広島の青白い閃光やキノコ雲のピンクの輝きが、18年前はじめてこの会議が開かれたカナダの漁村バグウォッシュ(インディアン語で「深い水」の意味だという)の入り江の紺青のさざ波や、そこで各国のすぐれた科学者と深更まで額を集めて核の脅威を議論した帰途の夜道の暗さなどと重なり合って、走馬灯のようにかけめぐり、いいしれぬ感慨を抑えることができなかった。
すでに各国持ちまわりで24回もの大小さまざまの「本会議」と、ほぼ同数のシンポジウム、その他数多くの地域会議、研究会、国内グルーブの会合などを開いてきたパグウォッシュ会議が、こんどはじめて、とくに被爆国日本で、しかも広島・長崎の被爆からちょうど30年目、またこの会議のそもそもの発端となった「ラッセル=アインシュタイン宣言」の発表からちょうど20年目という、いろいろの意味で記念すべき年に、完全核軍縮、つまり日本人全部の悲願である核廃絶にテーマをしぼって、密度の高い(濃い)シンポジウムを開くことを決めたことについては、やはりそれだけのねらいと背景があった。
かねてからこうしたシンポジウムの日本での開催を熱望していたパグウォッシュ協議会議長 B.T.フェルド教授(米マサチューセッツ工科大学・核物理学)をはじめ、各実行委員にせよ、また多くの困難を承知の上であえてこの要請を受けて立たれた湯川・朝永両博士ら日本のバグウォッシュ・グループにせよ、こんどの企画には最初から並々ならぬ期待をかけ、意欲--というよりもほとんど執念に近いもの--を燃やしていたのである。
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
いまこそ初心に帰れ
「人類が直面している悲劇的な情勢の中で、私たちは科学者が会議に集まり、大量破壊兵器の発達の結果生じた危険を評価し、ここにそえられた草案の精神にしたがって決議を討議すべきである、と感じている。」バートランド・ラッセルが起草し、アルバート・アインシュタインが承諾したといわれる格調の高い文体で貫かれた宜言の、最初のこの一節ほど、パグウォッシュ会議の成立の背景と趣旨を端的にさし示しているものはない。
広島・長崎の悲劇を終止符として第2次大戦が終わってからわずか4年後にソ連も原爆を独自に完成し、アメリカの核独占は破れる。アメリカはただちに水爆の開発に乗り出してこれに対抗するが、ソ連もすかさずそれを追い、激しい核実験競争が東西間の冷戦や、極東での朝鮮戦争などを背景として進行する。
とくに1954年3月、南太平洋のビキニ環礁で行われた3F型超水爆の実験では、爆心から160キロも離れた海域で操業中の第5福竜丸の乗組員をはじめ、マーシャル群島の住民が重度の放射線障害をこうむり、無線長・久保山愛吉氏の死を招いたことはよく知られている。またその後の米・ソ・英の相つぐ核実験とともに全地球的な放射能汚染が生じ、これとならんで大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発達もめざましく、人びと、とくに科学者は核戦争の現実的可能性におののかないではいられなかった。
しかも東西の対立はいよいよきびしく、外交の面はいうまでもなく、科学者の自由な相互交流の道さえもほとんど途絶え、事態は異常に急迫していた。ラッセルがその解決の突破口を開く役割を、政治家や政府でなく、史上はじめて民間の、しかも科学者に委ねようとした発想の含蓄は深いものがあった。
その第1のポイントは、ことが人類全体の存亡にかかわるという認識であった。ラッセル宣言はその第2節にいう。
「私たちがいまここで発言しているのは、あれやこれやの国民や大陸、信条の一員としてではなく、その存続が疑問視されている人類、ヒトという種の一員としてである。」ここには人種や国籍をこえた客観的真理を求める共同作業を進めてきた科学者こそは、「人類の一員」という立場にもっとも立ちやすいであろう、との絶大な期待が読みとられる。
深まる科学者の憂慮
この呼びかけにこたえて1957年7月、第1回の科学者会議がはじめてカナダのパグウォッシュで誕生した。その陰には、故パウエル(英国)、故トプチェフ(ソ連)、故ラビノビッチ(米国)、ロートブラット(英国)の各博士ら数人の先進的科学者の精力的な準備活動や、アメリカの億万長者 C.イートン氏の物心両面にわたる貴重な援助があった。当時の平凡社社長・下中弥三郎氏の寄与も忘れることはできない。
第1回会議は、出席者も10カ国24人(わが国からは湯川・朝永両博士および筆者が参加)と少なく、会場も村の小さな公会堂を借り、参加者は民家やイートン氏の経営する私鉄の寝台車に泊まるなどごく質素なものであった。しかし会議の空気は終始きわめて真剣かつなごやかで、米国、ソ連、英国、中国、日本など立場のちがう国々の科学者、とくに東西両陣営の科学者がはじめて一堂に会したにもかかわらず、深刻な国際問題を冷静に議論できたばかりでなく、核実験・核戦争の影響や核兵器管理の必要性、科学者の社会的責任などについて、多くの重要な結論を一致して得ることができ、長文の声明まで出せたことは、予想以上の大成功であった。
これに力を得た関係者は、以後毎年1,2回ずつ、次々と会議を開き、その規模も、また各国(とくに米ソ)の政府や一般市民に対する影響力も次第に大きなものになっていった。たとえぱ翌1958年9月にオーストリアで開かれた第3回会議では、そこで採択された宣言が、首都ウィーンの大公会堂で、大統領以下1万人の市民を集めて発表されるなど、会議の発展には目を見はるものがあり、その結論は国連はもちろん、ときには米・ソの軍部の考え方にまで反映され、さらに会議の参加者が政府の顧問やブレーンに迎えられたり、逆に政府に近い自然科学者や社会科学者までが個人の資格でしばしば会議に参加するまでになってきた。たとえばキッシンジャー米国務長官さえも、就任前には数回出席している。
こうして、たとえば米ソ間のデタントの最初の表現ともいえる部分的核実験禁止条約(1963年)なども、キューバ危機その他の多角的な動因があるにせよ、ひとつにはパグウォッシュ運動が東西間のコミュニケーションを切り開いたことや、第1回会議がさし示した放射性降下物の危険性についての先進的結論が国連などを通じて国際的に定着したことなどが、この条約の成立に大きく寄与していたように思われる。
しかし、その後今日までの十数年間、米ソ間の政治的な強調体制が急速に確立されていったにもかかわらず、世界の情勢、とくに核をめぐる国際関係は--こんどのシンポジウムの報告書がその前文で悲痛な語調で指摘しているように--少しも好転しないばかりか、超大国間の核軍備競争は量・質の両面にわたってラッセル=アインシュタイン宜言の出された20年前をはるかに上まわるテンポと規模で激化し続けている。また、核保有国の数はすでに5カ国にふえ、潜在核保有国の数は、原子力平和利用の普及に伴って第3世界を含め爆発的に増加の傾向にある。さらに米ソ間の戦略兵器制限交渉(SALT)や、核拡散防止条約(NPT)の国際的な調印・批准や国連軍縮委員会(CCD)の軍縮努力なども核兵器の抑制・削減に向かってほとんど何らの実質的な成果を得ていないのが偽らぬ実情である。ラッセル=アインシュタイン宜言が戦争廃絶の第一歩としてしか位置付けなかった核兵器の放棄という課題が、ほとんど到達不可能な目標と見られるようになってしまった現状を前にパグウォッシュの科学者の憂慮は耐え難いまでに深まってきた。
絶対悪としての核兵器
だがこれと関連して、というよりもこれにもまして無視できないのは、この十数年間に見られるパグウォッシュ会議自体の変質の傾向である。初期にはかなり特殊な、ある意味できわめて個性的な個人提案ないしは少数意見に過ぎなかった2つの超大国間の相互核抑止の考え方が、その後、米ソの政府寄りの科学者の参加がふえるにつれて、むしろ有力な現実的アプローチの基盤とみなされるようになり、一時は、たとえば1964年の第12回会議の声明に見られるように、「核の傘の概念は・・・隠された兵器による侵略に対して、必要な保障となるという点できわめて重要である。」という見解に支配されるようにさえなってしまったのである。
こうした核抑止の考え方を認める限り、会議でどのような具体的な軍縮提案やその部分的措置が議論されたにしても、それはすべて米ソの2極体制を前提とするいわゆる軍備管理(arms control)の一環でしかなく、ラッセル=アインシュタイン宣言の指向した真の軍縮(disarmament)からほど遠いばかりか、核軍縮競争の現実をなんら変革する有効な手段とはなりえない。またかりに核抑止の教義を離れて部分的軍縮手段をひとつひとつ切り離して提案したり、検討したとしても、それだけでは必ずといっていいくらい各国(とくに核保有国側)の利害関係がからんできて、結局は受け入れられにくくなり、かりに受け入れられたとしても、それは核抑止戦略の再検討・否定に通ずるものではなく、せいぜい核軍縮にとって二義的な部分についての協定しか達成できなかった。
このような内外の傾向を何とかして転換すること--それは一方において活力を失いかけたパグウォッシュの「再生」(湯川博士はそれを「再構築」と呼び、今回エジプトから参加したマフーズ博士らはそれを「方向転換、reorientation」と呼んだ)であると同時に、他方において全世界に全面軍縮、とくに核軍縮への真の道を示すことでなければならない。
そのために、憂慮に沈むベテラン・パグウォッシャイトたちは、当面少なくとも次の3つの目標に執念を凝縮させることになった。
その第1は、いまこそラッセル=アインシュタイン宣言の「原点」に立ち返ろうということである。それは科学と倫理との深いかかわりを再認識することに当然つながる。
第2は、核抑止論を根本から再検討し、その破産を公然と確認しようという目標である。いいかえれば軍備管理の路線から真の軍縮の路線へと、基本的な軌道修正を行うということである。むろんその根底には湯川博士のいわれる核兵器の「絶対悪」性の認識がある。
第3は、B.T.フェルド教授のいわゆる「こま切れ軍備制限」(piecemeal arms-limitaton)に見切りをつけ、総合的な軍縮計画、とくに完全核軍縮に向けての全体的プログラムを組み立て上げることである。そのような全体計画の中でこそ、さまざまの部分的軍縮手段が互いに補強し合い、各国に受け入れやすいものともなるであろう。この構想は、その主唱者であるフェルド教授ばかりでなく、こんどのシンボジウムの事務局長をつとめられた豊田利幸名大教授をはじめ、海外からの多くの参加者、とくに西ドイツのすぐれた社会科学者ゼンハース教授や、アメリカのフォーク教授らによって、早くから独立に提起されてきた問題であった。
被爆国日本で初会合
ではだれがこういう「再生」の核となるのか。最大の期待は当然、数少ないラッセル=アインシュタイン宜言の存命の署名者(湯川、ポーリング、ロートブラットの2博士)のひとりである湯川博士と、第1回以来数年前まで、15年以上パグウォッシュ会議の事務局長をつとめられたロートブラット教授に寄せられる。また第1回会議以来、核抑止論について透微した理論的批判を続け、日本国内のパグウォッシュ・グルーブの育成にも献身された朝永博士や、会議に先立って「万国のハトよ団結せよ! 失うものは諸君の地球でしかない。」と、その論文(『ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスト』に掲載)の末尾で提唱されたフェルド教授も欠かせない中心的存在でなければならない。
そして被爆国日本、核兵器禁止運動のメッカともいえる広島・長崎のある唯一の被爆国日本こそは、ぜひともその再生の場でなければならない。しかも、日本でのパグウォッシュの会合は今回がはじめてである。その新鮮で強烈なインパクトは、核廃絶を願う世論の熱烈な支持をえて、国際世論を揺り動かす端緒ともなるだろう。
京都シンポジウムヘの期待は、開会が迫るにつれて関係者の間でいやましに高まっていった。国内での準備は周到をきわめ、6月にはすでに主だった参加者もきまり、すぐれた提出論文が次々と事前に配布された。参加者はあらかじめそのすべてを精読してから出席することが強く要請されていた。数多くの国際会議、いや過去のぱグウォッシュ会議ですら、この方式を貫徹した例はほとんどなかったのではなかろうか。そして、たとえば日本の参加者は、事務局員(そのほとんどが国内の中堅、または指導的な理論物理学者)ともども、8月中句、軽井沢に合宿して、シンポジウム開催に備えて核軍縮の構想を十分に練ったのである。
だが試練が次々に訪れた。そのひとつは、当の湯川博士の発病、入院である。博士がようやく小康を得られた時点で、こんどは日本シンぽジウムの提唱者であるフェルド教授が入院、手術で出席できなくなった。病床で一途に成功を祈られる両博士の痛切な激励を全身に感じつつ、朝永、ロートブラット両博士をはじめ、関係者は最後の仕上げに全精力を費やした。
8月28日、いよいよ開会の日がきた。病後の疲れをおして車イスで入場された湯川教授は、開会のことばの中で、声こそ物静かだが、激しい気迫をこめて、核兵器の「絶対悪」性と核抑止論の誤謬を鋭く論断された。博士は核抑止論のもとでの核軍備競争が激化する必然性を「正のフィード・バック」という電気工学の用語を借りて論証され、われわれは逆に「負のフィード・バック」をくりかえすことによって完全核軍縮を達成しなければならないことを、人類の名において全参加者に要請されたのである。ここで、5日問にわたって行われた膨大な討論の全容を紹介することはほとんど不可能に近い。しかし最終日にまとめられた報告書に沿って、その大要を紹介すれば、次のようになろう。
核抑止政策への強い批判
報告書はまずその前文で核兵器をめぐる現在の状況が、ラッセル=アインシュタイン宣言が発表された時点にもまして深刻化しており、人類が存続するためには核軍縮を達成することがぜひとも必要であること、それとても全面完全軍縮の一部にすぎないこと、最終的には軍備なしに各国の安全が保障されるような世界をつくり上げることこそ、われわれの目標であることを述べる。そして今日必要とされるものは、軍備競争の問題に対するあらたな道徳的・人道的アプローチと、人類の存続をおびやかす恐るべき情勢を終わらせるためのあらたな全体計画である、と結論する。
それに引き続く5章の各論の中で、最も注目されるのは、何といっても核抑止政策の有害性を明快に論証した第1章であろう。この政策は、米ソの2極体制だけを考え、核拡散を無視する場合でさえ、政治的には両陣営の構造的対立を固定化させ、軍事的にはデタントなどの国際関係の進行とは無関係に、自国の既得権益である優位さの追求を自己目的化する。そして、相手方の技術突破への恐怖は質的な核軍備競争を激化させ、自己運動化させる。その結果、抑止の安定性はもっぱら指導者の良識と正常さだけにゆだねられ、誤算や事故、狂気などによる核戦争発生を防ぐ保証はなにもない。
そればかりか、超大国が核抑止の考えを擁護すること自体が、他の国々に核武装への指向(水平核拡散)を促す。多くの国々が核を保有するようになった世界がはたして安定に保たれるかどうかはきわめて疑わしい。人類が存続し発展するためには、抑止政策はいまや正気で公平で、より確実な枠組みに席をゆずらなければならない。
抑止政策についてのこのような立ち入った批判が、核大国からの参加者を含む全員の合意を得たことは、こんどのシンポジウムの驚くべき成果といわなければなるまい。
むろんその背景には、ガラール、マフーズ両博士(エジブト)、スブラマニアム博士(インド)など、第三世界からの参加者の核問題への積極的な発言や、モーレ(デンマーク)「プラウ(オーストリア)両教授のような非同盟ないし中立諸国の科学者の徹底した平和主義的発想、そしてまたヨーク教授(米国)のように、かつて自分自身がたずさわった経験からミサイル開発競争の愚かさを知りぬいた科学者の証言などが、湯川、朝永両博士のするどい分析をゆたかに裏付け、強力に支持したという事情が大きく働いていた。
それとともに、エメリアノフ教授(ソ連)やマルコフ科学アカデミー会員(ソ連)、ラスチェンス博士(米国)のような核保有国の政府寄りの科学者が、あえて「人類の立場」に立って、共通の結論を追求された姿勢も高く評価されなければなるまい。筆者(小川)も核否定の立場から核拡散問題についてささやかなコメントを試みた。
|
|
第3章は、核および全面軍縮のひとつの具体的なプログラムを提起しているが、その作成には豊田利幸、坂本義和両教授のほか、もと国連軍縮局長のエプシュタイン教授(カナダ)らの論文が大いに寄与した。また第4章では、「完全核軍縮の前提条件とモデル」についての討論の結果がまとめられており、坂本、関寛治(東大)、西川潤(早大)、渡部経彦(阪大)各教授や、フォーク(米国)、ゼンハース(西独)両教授ら社会科学者の貢献が目立った。軍縮を他の国際問題との動的な関係でとらえる試みや、現在の核抑止体制や国家制度にかわるべき新しいシステムのあり方の追求は、パグウォッシュのこんごの重要な課題のひとつとなるであろう。
最後に第5章は、核問題をめぐる科学者の責任を強調している。飯島宗一(広島大)、野上茂吉郎(法政大)、モトレ、トルホック(オランダ)各教授をはじめ、第1回会議以来の「常連」のパブリチェンコ氏(ソ連)ら多くの参加者が、軍事研究を拒否する決意とともに、一般市民への警告や平和教育をいっそう強化する必要性を力説していたのは、感動的であるとともに、パグウォッシュのひとつの反省とも受け取れた。
この報告書が、来年1月、インドのマドラスで開かれる第25回パグウォッシュ会議で、はたしてどのように評価され、どのように定着するかが期待される。
なお、会期中、29日、30日の2晩にわたって、全参加者が故仁科芳雄博士らのつくられた広島・長崎の原爆被害調査の映画(例の「幻のフィルム」)全巻を見た。見終わった参加者の間に、声ひとつなかったのがひどく印象的であった。こんどのシンポジウムが、もしなんらかの成果をおさめえたとするならば、それは結局、何十万もの被爆者の地底からの叫びに支えられていたからだ、といえるのではなかろうか。(おがわいわお・立教大学教授=核物理学)