(リーフレット) 紀平英作「バートランド・ラッセルの警告」
* 出典:『歴史としての核時代』(山川出版社,1998月10月刊, 106pp. 世界史リブレットn.50) pp.1-3.
* 紀平英作(1946~ ):京都大学文学研究科教授。アメリカ現代史専攻。
 *「核」にはいろいろな側面(軍事利用,平和利用,その他)があり,時代によって人々が抱くイメージも変わって来ている。米ソ冷戦時代が終わり,あたかも核戦争の危険や核の脅威は過去の時代のものになった(それよりもテロの方が問題だ)と思われがちである。しかし,原子力発電所の事故の危険は減少しておらず,また広島級の核爆弾ならば肩にかついだ発射装置(バズーカ・タイプ)で使用できるほど「身近な」ものになってしまっている。先に核を保有した一部の国が既得権を持ち「核クラブ」をつくっているが,核後進国は核クラブに入ることは許されない。これ以上核を拡散させないためだとはいえ,現保有国の核保有が正当化されるわけではない。
*「核」にはいろいろな側面(軍事利用,平和利用,その他)があり,時代によって人々が抱くイメージも変わって来ている。米ソ冷戦時代が終わり,あたかも核戦争の危険や核の脅威は過去の時代のものになった(それよりもテロの方が問題だ)と思われがちである。しかし,原子力発電所の事故の危険は減少しておらず,また広島級の核爆弾ならば肩にかついだ発射装置(バズーカ・タイプ)で使用できるほど「身近な」ものになってしまっている。先に核を保有した一部の国が既得権を持ち「核クラブ」をつくっているが,核後進国は核クラブに入ることは許されない。これ以上核を拡散させないためだとはいえ,現保有国の核保有が正当化されるわけではない。
広島に原爆が投下されてから約60年が経過し,ようやく20世紀後半を「核時代」としてとらえることができるようになってきた。核兵器登場直後の「ラッセルの警告」の意味合いを今再考してみるのも無駄ではないだろう。(松下, 2004年6月19日)
以下の引用は,紀平氏の『歴史としての核時代』の冒頭部分
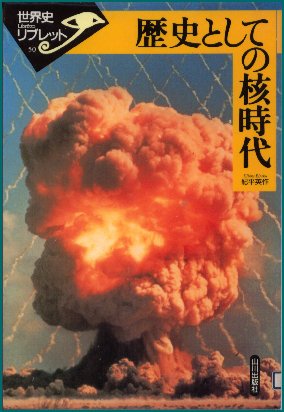
原爆が広島に投下されてから三カ月後の,一九四五年十一月二十八日のことである。哲学者ラッセルは,イギリス上院においてつぎのように警告していた。
(「(1945年11月28日)英国上院でのラッセルの演説」)
「まず私は,議員諸兄がよくご存じであろう二,三の技術的な問題を確認することから始めたい。第一に指摘したい点は,原爆は,現時点ではまだ初歩的段階にあり,将来の核兵器はさらに破壊的で,また手軽に生産が可能となるだろうという事実である。しかも極めて近い将来のうちに。……また第二の点は,そのような将来の核兵器がもし使用された場合には,広い地域におよんで人間ばかりか,小さな昆虫,つまり生きとし生けるすべての生き物を殺傷してしまうであろう放射性物質を含んだ爆発物として,この大地を襲うことが予想されるということである。そして,最後にお話しておきたい第三の点は,たぶんもう少しさきの問題であろう(が,つぎの点である。核エネルギーの放出には現在二つの方法が理論的に考えられているが,今日の原爆とは異なる核融合による方法も),私の考えでは,まもなく人類が開発するだろうということである。つまりより重い原子を作り出すための水素原子の融合という方法(松下注:水素爆弾)によって,さらに強大なエネルギーが,兵器に応用される可能性があるという事実なのである。(括弧内,筆者=紀平氏要約)」
偉大な先輩ラッセルの右の言葉を手がかりに,
「歴史としての核時代」の到来を私なりに,つぎのように考えてみたい。広島また長崎に投じられた二つの核爆弾。原子力と核の時代は,あの二つの事実が記憶に重々しく残る,一九四五年に開幕する。核エネルギーがもつ恐るべき威力,さらにはそれが人類と地球環境に与えるであろう深刻な脅威。その二つの未来を開幕時期の人間がすでに明確に認識していた事実を知ることは,この時代の歴史を考えるうえでやはり重要な出発点であろう。原爆へと到達する核エネルギーを人間が創造し確保しようとする理論と技術の成果は,十九世紀末からの理論物理学が行き着いた,きわだった科学上の進歩であった。しかし,その原子力という成果は,科学をこえた人類文明にとっては,やはりいくぶん別の意味をもった。優れた科学上の進歩であることを認めたとしても,その成果が「進歩」という名だけでは説明できない多くの犠牲をともなったことは,指摘せざるをえない重い事実であった。広島,長崎ばかりか,以後,中部太平洋あるいはセミパラチンスクなどにおいて,数限りなくおこなわれた核実験。原子力はまずもって核兵器として現れた。その核兵器が人間ばかりか環境に与えた暗い影響は,およそ進歩といえるものではなかった。
いかにしてこの五〇年間,人類は核と格闘してきたのか。また原子力との共存を求めてきたのか。以下,この小冊子が描こうとするのは,そのような歴史としての核時代の序幕である。この開幕の時点に,原子力のあり方を考え,また核の脅威や不安に立ち向かおうとした人びとの歴史は,挫折にみちていた。しかし,いかに苦悩や失望に満ちたものであったとしても,その足跡はまずもって歴史に書きとどめるに値する。そうした努力を洗い出すなかからしか,核問題へのわれわれの視野を切り開くことも,できないだろうからである。
(この続きは,興味のある方は,購入するか図書館で借りるかして読んでください。)



