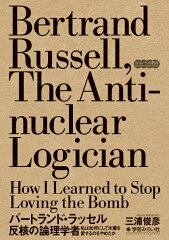金子光男(著)『ラッセル』へのまえがき
* 出典:金子光男(著)『ラッセル』(清水書院,1968年4月 225 p. 19cm. センチュリー・ブックス:人と思想シリーズ n.30)* 金子光男氏略歴:金子光男氏は、執筆当時、東京家政大学教授
*右下写真:バートランド・ラッセルから金子氏への手紙(1968年12月18日付)
ラッセルについて(本書のまえがき)
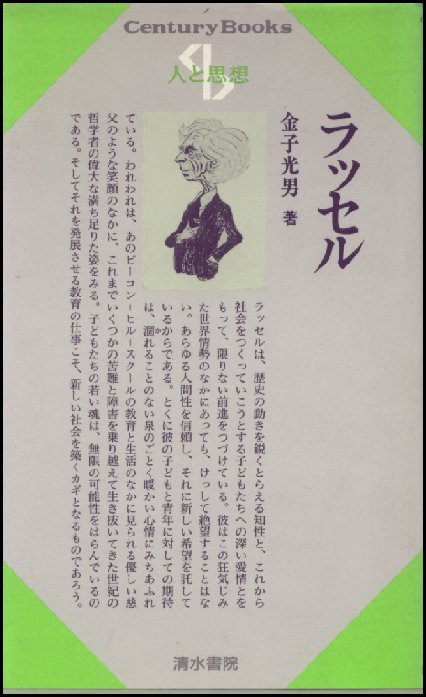 よみがえった歴史
よみがえった歴史わが国は、今年(1967年)で戦後22年目を迎えた。あの頃と比べてなんと見違えるほど復興し発展したことであろう。当時(=終戦時)はほとんど灰燼と化し去り、見る影もなかった東京には、ここかしこに大空高く高層ビルディングがそびえたち、はてしなく高速道路が続き、そしてそのなかにひしめくように密集して住宅が立ち並んでいる。われわれは、いまさらのようにその発展ぶりに目をみはるばかりである。
しかし、ひとたび夏を迎えると、蒸せかえるような炎熱下のなかで、日本人のだれもが、改めて一瞬の白い閃光で、20数万の生命とともにくずれ去った広島の聖域の悲惨な光景を想い出すことであろう。歴史は20年をさかいとしてよみがえるといわれる。1967年の8月5日、一段と緑の増した広島の平和記念公園にある原爆ドームは、新しい生命を吹きこまれ、よみがえった歴史の証人として、その補強工事の完工式が行なわれた。そして20年間の風雪のために、くずれかかったレンガ、折れかけた鉄骨は、そのままの姿を残して、改めて平和への道標としてつくり直されたのである。そこには、ドームの保存を通して、とこしえに平和を祈った国民の心からの悲願があり、ふたたび戦争の悲劇を繰り返してはならないという国民の非常な決意があった。平和の鐘が山にこだまし、合唱の歌が海を越えてひびくとき、われわれは、何千マイルもへだたった彼方から、核実験の被害を受けた日本に深い同情を示し、再武装をしないと誓った憲法の平和宣言は、じつにすばらしいものであるとほめたたえて、次のように呼びかける声を聞くことができる。
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
「われわれは、今日、いつ来るかも知れないこの人類の危機を、どんなことがあっても、取り除かなければならない。私はこのために全力を捧げている。この世界を廃墟にしてはならない。この人類を破滅させてはならない」と。その声は燃えるがごとく、祈るがごとく、切々としてわれわれの胸に迫ってくる。これこそ、人間の知性を絶対的に信頼してやまない哲学者バートランド・ラッセルの声であり、ことばなのである。
ラッセル峰登頂の試み
白髪の痩身で鶴のように、眼光炯々(けいけい)として鷲のように、つねにパイプをくわえて、壮者をも凌ぐ元気さをもったラッセルは、1967年の5月で、満95歳を数えることになった。ほとんど1世紀近くを生き抜いていることになる。彼は、いまは核兵器反対を叫んで、平和運動を実践している警世家としてその名を知られている人である。
しかしラッセルは、もともとは数学・論理学者であり、哲学者である。そしてまた彼の業績は、これだけにとどまらず、さらに広く政治、経済、社会、教育、倫理、芸術および宗教と、およそ人間が求めんとする思想上のあらゆる珠玉が、彼の著作のなかに散りばめられ、彼の行動としてあらわれている。その意味で、彼ほど多角的な思想家はいないということができるであろう。
ラッセルは、たしかに今世紀における思想界の巨峰である。しかし、それはエベレスト山のように、孤立してそびえ立つ巨峰ではなくして、アルプス連峰のように、いくつもの高山が並びそそり立つ連峰である。そのために、彼の思想を網羅的に解説した書物はほとんどなく、ましてや全面的な体系の研究は、おそらく至難の業であろう。彼の著作は、主要著書および論文その他を入れれば数百冊にものぼり、ことばだけでも2000万語に達するといわれる。
ラッセルは、イギリス経験主義の立場にたち、ヨーロッパの合理性にもとづいて、この現代社会が非合理的に動いてゆく動向と、そこから生ずる人物の愚かな行動の原因とを、冷静に分析して、少しずつでも人類の不幸を緩和してゆこうと努力している。そのために、彼は科学的精神を堅持して、ときには伝統的思想に反対し、ときには迷信倫理と対決して、つねに物事の真実の姿を追求してゆくのである。
かくして、彼は思想においては、独断や狂信やまやかしなどに対して、容赦なく批判のするどい刃をふるい、行動においては、あらゆる形の圧政や独裁や不寛容などに対して、身をもって抵抗の姿勢をとる。そして、それが寸鉄人を刺す皮肉や機智となり、また偶像破壊となってあらわれる。彼が「第2のソフィスト」といわれたり、「現代のボルテール」と呼ばれたりするのはこのためである。
現代社会において、ラッセルのように、真実と虚偽とを峻別して、自己の信ずるところに向かって、生き抜く不屈の人間はまれなのではないだろうか。たしかに彼は例外的存在者である。しかしそれだけ、善いにつけ悪いにつけ、彼は人間として魅力を持っているのではないだろうか。私は、今世紀に生きるひとりの人間として、ほんの些末でもよい、ラッセルにあやかりたいと思う。彼の発言と行動の意味するものに少しでもよい、接近したいと思う。
もとより、ラッセル巨峰を征服しようなどという望外の望みなどは持っていない。しかし何とかして登頂を試みてみたい。私は装備を厳重にし、着々と歩みを進めてみよう。その峰のけわしいところは、ピッケルを打ちこみ、ザイルを伝ってでも、できるかぎり登ってみようと思う。諸君たちとともに。登れば登るほど、その山容は明らかに、その展望はひらけてくることであろうから。
人間性の地平
人間は星を散りばめた天の子であるとともに、大地の子でもある。ラッセルは、われわれにとってはとても理解できないような偉大な思想家ではあるが、その彼の内面にあるものが、じつはきわめて優しい人間愛であり、せんさいな感受性であることを見逃してはならない。そして、ここにこそ、彼の人間としての秘密が存在しているのである。
人間はたしかに、宇宙全体からみれば、じつに微々たる存在である。しかしその微々たる人間は、逆に自分の心のなかにこの広大無辺なる宇宙を映し出す能力を持っているものである。ラッセルは、こうした能力を確信して、将来にはもっと想像や知識や共感のみなぎる人生の幸福が必ず訪れることを予言している。これが彼の人間尊重の考え方とむすびつき、人間性の信頼へと発展してゆく。彼が現代における貴重なるヒューマニストであることもそのためである。
そう考えるとき、われわれの容易にとどかざる雲上の巨峰は、一転してわれわれの眼前に広莫としてひろがる山裾として展開される。その意味で、われわれは、さきに登頂を試みたラッセルを、今度は人間性という地平に立ってとらえなおすことができる。どこまでも広がる裾野には、美しい花園もあり、緑の若草もあり、そしてまた清らかな渓流もあることであろう。われわれは、勇気を出して、この地平を踏破しよう。
ラッセルの文体はじつに論理明快であり、しかも内容の清新さは、読むものをして、ヨーロッパ文化全般をささえる素材にじかに触れることができるという感じを抱かせるものである。ここにわれわれは、人間としての共通の地盤であるヒューマニティを感得することができる。そして私は、諸君とともに、彼の著作や行動を通して、ラッセルと対話してゆこうと思うのである。
金子光男