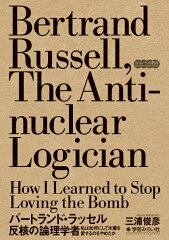『バートランド・ラッセル自叙伝』第3巻 - 訳者(日高一輝)解説
|
|
第1巻(1872-1914):1968年9月刊, 298+ 6 pp.
第2巻(1914-1944):1971年8月刊, 358+44pp.
第3巻(1944-1969):1973年2月刊, 282+19pp.
* 原著:The Autobiography of B. Russell, 3 vols., 1967-1969.
* 日高一輝氏略歴
『バートランド・ラッセル自叙伝』への訳者(日高一輝)解説
(邦訳書第3巻・巻末に収録/第1,2巻には「訳書あとがき」あり)
I
ラッセルは、ケンブリッジ大学に迎えられ、英国哲学界の代表的存在としてクローズアップされ、南欧、オーストラリア、米国の各大学にも特別講義に招待され、学者としても輝かしい栄誉が約束された。英国最高のメリット勲章を授与され、ノーベル文学賞をも受賞した。
ラッセルは、齢80に達してはじめて創作に着手した。『X嬢のコルシカ島探険』『郊外の悪魔』『著名人の悪夢』等、つぎつぎに短篇集を世に出した(松下注:The Corsican ordeal of Miss X は、Go誌, 1951年12月号(The Cristmas number)に掲載されたものであり、短編集ではなく、後に『郊外の悪魔』に収録)。世評が良かったので、ラッセルは気をよくした。そして、それからの文筆活動を創作一本にしぼろうかとさえ考えたほどだった。それに、思想や主張を一般に伝え、理解させるには、創作の形をとるのが一番いいとも語っていた。
それらと併行して、諸種の重要な国際問題の解決に寄与しようとするラッセルの尽力があった。キューバ危機、スエズ出兵、中印国境紛争等々。それに、現在の西独のブラント首相をはじめ、当時、不当に投獄されていた数々の政治犯を救出するための運動、ケネデイ大統領暗殺に関する真相究明のための運動等もあった。
ヴェトナム問題の発生とともに、米国の侵略と、その残虐行為を非とするラッセルの猛烈な世界的運動が展開された。バートランド・ラッセル平和財団、大西洋平和財団、ヴェトナム・ソリダリティ・キャンペーン、ヴェトナム戦争犯罪国際裁判(松下注:いわゆるラッセル法廷)等々。
ソ連軍のチェコ侵入が強行されると、ラッセルは即刻、それに抗議する世界的活動を展開した。ストックホルム世界大会、ロンドン世界大会等々であった。
II
ラッセルの運動の目標は、きわめて簡明直裁であった。「人類を滅ぼさないために!」であった。人類の存続こそすべてに優先する、と言っていた。Mankind should have a future! がスローガンであった。そのためには、人類破滅の危険性をはらむ核兵器を廃絶すべきであるし、戦争を放棄しなければならないとした。そうしたラッセル畢生の主張をかかげた代表的な論著として自ら推薦したのが、Has Man a Future? (『人類に未来はあるか』)であった。
ラッセルはどの国からでもよいから、率先して核兵器を撤廃 し、戦争否定の憲法をかかげるべきだとした。当然、彼は英国人として、それを英国政府に迫った。
ラッセルは、平和の原則を、自由、平等、正義、人道においていた。その原則に立つ個人や国は同志であり、それに背反するものはことごとく非難された。偏見や感情から発するものではなかった。彼は、英国を愛する英国人でありながら、英米を痛烈に批判した。英米が、自らを自由の国と呼称しながらも、他国の自由を侵害する行為は非であるとした。同時に、ハンガリーやチェコに対するソ連の侵略行為をも非難した。自由諸国はもとより、共産諸国、中国にいたるまで、すべての国の核政策を非とした。英米を糾弾したからといって、反米闘争でも共産主義でもない。ソ連、中国を批判したからといって、反共運動でも、英米一辺倒でもない。
ラッセルは、貴族の出でありながら、つねに貧しい者、虐げられた民族の味方であった。国内活動において、労働者、学生、大衆がつねに彼の同志であったとともに、国際的にも、ヴェトナム、インド、アラブ、アフリカ諸国の如く、白人の植民政策で痛めつけられた後進民族のために挺身した。
ラッセルは、事に当たって生命をかけた。信念に生き、志を遂げるのに、「生命がけで!」というのが、彼の信条であった。「真実に生き、真理を求めて!」というのが、そのモットーであった。
彼は、虚構と欺瞞を排した。そして、どこまでも、廉直に、合理的に、その主張と行動を貫くことを念とし、権力にも迫害にも屈しなかった。こうした革命的な性格と実践が、ラッセルの反骨精神と行動の本質であったが、それと同時に、彼は、法治主義と遵法精神の尊重すべきことを説いてやまなかった。
III
ラッセルの終戦後(第2次大戦後)の平和運動の基本理念と実践をみるとき、日本と深い縁で結ばれていることを思わないわけにはいかない。ラッセルは、ヒロシマ、ナガサキ(への原爆投下)の直後、国会の上院で演説して、「人類の危機」を警告し、つづいてBBC放送となり、世界連邦、世界科学者会議、核兵器撤廃等々の運動となって発展していくのである。彼は、日本の読者のためにと題して送ってくれたメッセージの中で、「ヒロシマ、ナガサキは、白人全体の罪であり、自分もその将外ではない。その罪は、ただいたずらに慰霊祭をくりかえすだけで償えるものではない。」と述べているし、彼が平和運動に挺身する心の奥底には、原爆の犠姓となった日本人への懺悔の気持が横たわっていたことは否めない。
ラッセルは、日本憲法の前文の精神と戦争放棄・軍備否定の第9条を高く評価し、これこそが、世界平和の基礎的要件であり、世界連邦への一里塚であるとも語っていた。
「この意味で、日本はまさに、世界平和の先駆的役割を果たしている。その日本に敬意を表しないではいられない。自分は、英国政府にも、これを見ならわせようと思って努力してきたが、いまだに成功しない。労働党内閣こそと思って望みをつないできたが、それにも裏切られた。わたしは、心から日本に希望を託している」ラッセルの周辺に最後に残ったのは、無名の青年たちだけであった。潔癖で純真なラッセルは、不純と妥協を嫌悪し、平和運動を政治的に利用したり、売名の具に供しようとした職業的運動家や政治家たちに失望して、自ら組織したCNDや百人委員会からすらもつぎつぎに離脱したほどであった。
「青年は純真である。そして生命をかけることができる。自分が共に語ることのできるのは、青年たちだけである」と、しみじみと語っていたラッセルである。ラッセルが心から頼みとしたのは、こうした青年学生たちだけだった。
だから、もし、日本の青年が、真にヒロシマ、ナガサキの意義を心にとめて、核兵器の廃絶、軍備撤廃、戦争放棄に挺身するならば、ラッセルの精神は、そこに共に生きつづけるのである。日本の憲法の平和精神、第9条には、ラッセルのたましいが寄せられている。だから、もし、日本の青年が、この平和憲法をどこまでも護持していくならば、そこにラッセルのたましいが生き続ける。もし日本の青年が、地球人・世界市民の自覚に立ち、人類の生存と、世界連邦の実現に献身するならぱ、ラッセルの理想は、日本青年の理念と実践のうちに成就されていくことになろう。(了)