バートランド・ラッセル『結婚論』への訳者(後藤宏行)あとがき
* 出典:バートランド・ラッセル(著),後藤宏行/しまねきよし(共訳)『結婚論』(みすず書房,1959年8月刊。252+iv pp)* 原著:Marriage and Morals, 1929
*(故)後藤宏行氏及び、しまねきよし氏略歴
「なんですって、ラッセルのものを訳すんですか。小説や文学論ならまだしも、結婚や道徳などという、いちばんたいせつな問題を、そうかるがるしく論じるのは、もっとも恐ろしい罪になります。貴男はなぜ、ラッセルなんかを訳すお友だちを知っていながら、その罪をおかそうとするお友だちの行為を止めてあげないんですか・・・。」このひとことに、気の弱い我らが信者君は、それ以上頼みこめなくなって引き退ってしまったそうである。
この神父氏のことばは、ラッセルがヨーロッパの因習的な道学者連中から、今(=1959年)なお、どのようなあつかいをうけているかを如実に物語っているようだ。すでに第1大戦中、参戦拒否運動のカドで投獄され、母校ケンブリッジ大学の講師の職を追われていたラッセルは、この書物の出版前にニューヨーク市立大学の教授の職が約束されていたにもかかわらず、ふたたびこの書物の急進的な主張のためにその実現がはばまれるにいたったという、いわくつきのエピソードをもっている。(松下注:1940年にニューヨーク市立大学教授のポストにつけなかったのは、1929年に出版されたこの Marriage and Morals が大きな原因の1つではあるが、その間に10年以上の開きがあり、「この書物の出版前にニューヨーク市立大学教授の職が約束されていた」というのは、後藤氏の勘違いと思われる。)その後のラッセルは、一貫して著述家としての生活をおくってきたが、彼の生涯や、さらに最近の動向については、このシリーズにも、第1巻の『自伝的回想』や、各巻の訳者たちによってものべられているので省略することにして、この書物から受けた私たち訳者の印象をつけくわえて、あとがきにかえたい。
 ラッセル関係電子書籍一覧 |
「わらはは、幸か不幸か御国ぶりの教へよりも、海のあなたの書どもを多く学びたりき。従ひて男女の関係につきても、こなたの古きならはしをいと飽かぬ事に思ふなり。妻は夫の所有物のやうにて、互の関係主従の如き奇観ありとは、かつて本社の社説にも見えたりし所にて、まことに、此一つは御国のためいともいとも口惜しき事に思ふものなり……到底楽しき家庭を作るべき見込なくして、漫りに結婚の大典をあぐることの一大不徳義なることも知れり…。」
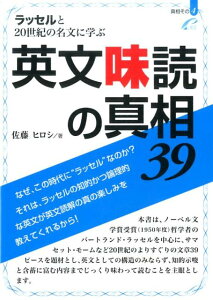 |
「いうまでなく、私たちは愛するもの同志なので、日本婚姻法に定められているような夫と妻との関係ではありませんし、また、あってはならないのです。自分が納得しえない法律で自分たちの共同生活を承認し、また保証してもらわなければならないなんて、そんな矛盾した、不合理なことができるでしょうか。私は、もし私が結婚届けをだせば、それは現行の結婚制度を私が認めたということになると思ったのです。法律結婚をしないことが、この時代として可能な唯一つの抵抗であったので、私は最初から規制観念の伴う結婚ということばを使うことさえ避け、とくに共同生活といって、はっきりそれを区別したのでした。」
ただひとつ、ラッセルに対する不満をのべておくと、彼の結婚観や性倫理の見通しが、あまりにも楽観的なことである。たとえば、彼は、これほど急進的な主張をしながらも、なお、子どものない夫婦は意味がないとまで断言してはばからない。しかし、われわれの世代の友人たちを見回してみると、結婚はするがこどもはうまないと宣言する人たちが、以外に多いことにおどろくのである。ラッセルは、子どものない男女は、本質的には社会にたいして責任を持てないと主張する。しかし、われわれの友人は、現代の社会状勢のもとでは、生れてくるこどもに責任を持てないと主張するのだ。(松下注:FAQのページに書いたように、後藤氏を始め、少なからぬ読者が誤読していると思われる。詳細は、FAQ回答を参照)現在のラッセルは、原水爆禁止運動の強力な推進者としても有名だが、そのラッセルが、1920年代の楽観的な立場とどうつながっているのかは、興味のある問題だが、しかし、責任を持てないから、子どもを生まないという論理は、ある意味で、明治の女性たちが、男性の横暴にたいして不婚宣言をしたように、ある種の消極的な抵抗の手段であるかもしれない。こうした考え方もまた、古い時代のほほえましい語り草にされてしまうような社会を、私たちはつくらねばなるまい、
本書は、序文~第13章を後藤が、第14~21章をしまね・きよしが担当した。
なお、私たちと編集部の間にたって、種々御心労をわずらわした市井三郎氏には、ここでお詫びをしておきたいと思います。もちろん、この仕事は氏のおすすめによるものです。
最後に、キリスト教の諸行事については、牧師、伊藤啓次氏にいろいろと教えをいただいた。また、カトリックの行事については前述のカトリック信者の友人から種々の教唆をうけたことは、立場をこえた思想の理解につとめようとする、若い日本のキリスト者一般の名誉のためにも、つけくわえておかなねばなるまい。
1959年7月 訳者
