バートランド・ラッセル(著),竹尾治一郎(訳)『心の分析』訳者(竹尾治一郎)解説
* 出典:バートランド・ラッセル(著),竹尾治一郎(訳)『心の分析(勁草書房,1993年3月。ix+394+x pp.)
* 原著:The Analysis of Mind, 1921.
*
竹尾治一郎氏(1926~ )略歴
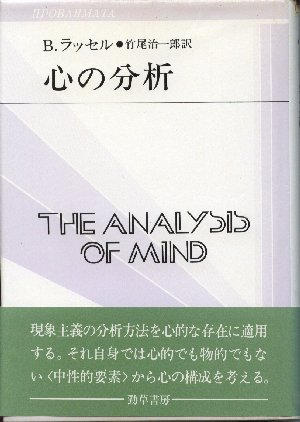 本書『心の分析』(The Analysis of Mind)は、ラッセルの中期の哲学の重要な著作であるが、それが彼の哲学全体のなかでどのような位置を占めるかを、以下にみておくこととしたい。そのために私は、著作の上に示されたかぎりでの、彼の全哲学を適当な数の時期に分け、本書がそのおのおのの時期の仕事とどのような関係をもっているかが分かるようにすることに努めたい。
本書『心の分析』(The Analysis of Mind)は、ラッセルの中期の哲学の重要な著作であるが、それが彼の哲学全体のなかでどのような位置を占めるかを、以下にみておくこととしたい。そのために私は、著作の上に示されたかぎりでの、彼の全哲学を適当な数の時期に分け、本書がそのおのおのの時期の仕事とどのような関係をもっているかが分かるようにすることに努めたい。
かつてC.D.ブロードは、「ラッセル氏は毎年のように新しい哲学の体系を生み出し、……」
(1)という辛辣な批評を加えたことがあるが、私にはそうは思えない。同じように誤解を導きやすい言い方かも知れないが、私にはむしろ、ラッセルは終始1つの哲学についてしか語ろうとしなかったように思われる。
ラッセルは1890年からケンブリッジ大学で数学を学んだが、
1893年に学位試験に合格の後は、哲学の研究に専念するようになった。それ以後、『私の哲学的発展』(1959)を出版するまでを,彼が哲学者として活動する期間とみると、それ五つの時期に分けて解説することができるであろう(2)。
まず、
第1期は,1893~1899年で、この時期を通じて彼は、カントならびに、当時のケンブリッジにおける先輩哲学者たち(本書に名前の出てくる、スタウトなどもその1人である)が解釈したかぎりでの、
ドイツ観念論の哲学の影響下にあった。この時期の重要な仕事としては、『幾何学の基礎』(
An Essay on the Foundations of Geometry, 1897)と『ライプニッツ哲学の批判的解説』(
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, 1900)が挙げられる。よく知られているように、1899年に、ラッセルはムーアとともに'
(ドイツ)>観念論に対する反抗'を開始することになる。それ以後、すなわち第2期からのラッセルの哲学は実在論であるが、ただ、
現象主義および中性的一元論というかたちでの、バークリ、ヒューム、J.S.ミルに代表されるような英国の観念論は、本書が書かれた第4期のラッセルの哲学にもはっきりと受け継がれていることに注意する必要があろう。
次に、
第2期は、1900~1910年で、この時期に彼は基礎論
(ただし、この名称は後のものである/松下注」「数学基礎論」のことか?)および数理論理学の仕事に没頭している。
論理学からの古典数学の導出、そしてそれに必要な数理論理学を作り上げること、がその仕事の目標であるが、この構想は1900年にパリで行われた国際学会で、イタリアの数学者、ジュゼッペ・ペアーノに会ったときに生まれたのである。(
その少し前までは、彼は『英国百科大事典(Encyclopaedia Britannica)』の「記号論理学」の項目の執筆依頼を、この主題についてはよく知らないからという理由で断っているほどである。)その構想は、『数学の原理』(
The Principles of Mathematics,1903)にスケッチされている。1902年(松下注:1901年春のまちがい)には、有名な「ラッセルのパラドックス」の発見があり、その解決(ないしは回避)のために、彼は
創始者のあらゆる苦心を経験している。そしてようやく得られた解決が「タイプ(の)理論」であり、その考えは有用な論文、「タイプの理論に基づく数理論理学」(1908)に述べられている。タイプの理論に基づく、論理学からの数学の導出という構想は、ホワイトヘッドの協力のもとに、『数学原理』全3巻(
Principia Mathematica, v.1, 1910; v.2: 1912; v.3: 1913)に詳しく展開されている。現在、多くの人々が認めるところであるが、この『数学原理』こそ、ラッセルが哲学に与えた最も重要な貢献であり、また「これまでのところ、おそらく20世紀の最も重要な哲学の業績」であろうとも言われる
(3)。いずれにしても、事実としてラッセルの初期の分析哲学は、この時期における『数学原理』の技術的な論理学の確立と同時並行的に始まったのであり、そして、以下にいくらかでも事情を明らかにすることが試みられるであろうが、
彼の哲学の発展は、その論理分析の適用範囲を逐次その当時の基礎的科学の間に拡張していくことにあったのである。この時期に書かれた彼の重要な論文は、現在2冊の論集(R.C.Marsh (ed.),
Logic and Knowledge, 1956 / D.P. Lackey (ed.),
Essays in Analysis, 1973)に収められている。前者には、ラッセルの仕事としては最もよく話題になる、
「指示について」('On Denoting'[1905]: 清水義夫訳、坂本百大編、『現代哲学基本論文集I』[1986]所収)なども含まれている。なおここで、1905年にはアインシュタインが特殊相対性理論を発表していることも付記しておくべきであろう。
 第3期は、1911~1918年で、ラッセルはこの時期に、第2期の論理学の仕事から彼の分析および総合の方法を取り出し、それによって彼の知識の理論、ならびにそれと結びついた形而上学を発展させる仕事にとりかかる。
第3期は、1911~1918年で、ラッセルはこの時期に、第2期の論理学の仕事から彼の分析および総合の方法を取り出し、それによって彼の知識の理論、ならびにそれと結びついた形而上学を発展させる仕事にとりかかる。本書が書かれたのもこの仕事の一環としてであり、従ってこのあたりから、本書のテーマとも直接関係のある問題が現れ始めるのである。まず最初のスケッチが『哲学の諸問題』(
The Problems of Philosophy, 1912: 中村秀吉(訳)『哲学入門』(1964))において与えられる。ここでは、「見知り」(acqaintance)による知識」と「記述による知識」とが区別される。人が対象を見知るとき、その対象は実際に存在し、また実際にそれがもっていると理解される性質をもっている。他方、記述によってのみ知られるものについては、その存在と性質は不確実である。それでは、どのようなものが見知られるのであろうか。そのようにし見知られるものとしては、われわれ自身の
私的なセンス・データ、イメージ、思考、および感情(
記憶は直接知の一種だから、それ以外の過去および未来の感情が含まれる)の他、
めいめいの人の「自已」(self)、さらに
抽象的な普遍(universals)もが含まれる。ラッセルは普遍の存在がこのような形で知られると考えることを明らかに好まなかったが、
普遍をなしですます方法を考えつかなかった。(つまり、普遍は類似性によって定義できるとも考えられるが、そうすると今度は類似性という普遍を認めなければならなくなる、と彼は考えた。)その他の存在物は、記述によって知られうるだけである。従って、
物理的対象は記述によって知られるのであり、その存在が
センス・データの原因として要請されるのである。『哲学の諸問題』はすぐれた哲学入門書ではあるが、『家庭大学叢書』という(ウィトゲンシュタインが大層嫌った)一般読者むけ廉価本叢書の1点であり、主要概念の定義などには精密さを分かりやすさの犠牲にする場合もある。実際、
ラッセルはこれとは別に1913年春、この本の理論を発展させた『知識の理論』(Theory of Knowledge)を書いたのであるが、その原稿を読んだウィトゲンシュタインの手厳しい反論にあい、それの出版を差し控えたのである。(この本の最初の6章は当時、雑誌論文として発表されたが、本の全体は1984年になって、遺稿に基づいて出版された。)
この時期を代表する、最も重要な仕事である『外部世界はいかにして知られうるか』(
Our Knowledge of the External World, 1914 (第2版は1922年刊)/石本新訳(1971))は、1912年以来の知識の理論を発展させ、これを物理学の哲学に結びつけようとしたものである。しかしこの画期的な意義は,
『数学原理』の論理学が哲学の問題に適用できることを具体的に示した最初の業績であるということにある。知識の理論としては、この本は、『神秘主義と論理』(
Mysticism and Logic, 1918)に収められた、「センス・データの物理学に対する関係」('The relation of sense-data to physics', 1914)などとともに、物理的対象についての言明がセンス・データについての言明に忠実に翻訳できることを主張する
現象主義の立場をめざしている。その場合、この哲学は物理学の扱う世界をどのように解釈するかが問題である。
任意の与えられた瞬間に、おのおのの観測者は、自分自身の私的空間(視覚ならびに触覚空間)をもつ、私的三次元世界を知覚する。このような私的世界のことを、パースペクティヴとよぶ。しかしパースペクティブとしては、知覚されるパースペクティヴの他に、無限個の(連続の濃度をもつ)知覚されないパースペクティヴがあることを認める。後者に含まれる個物(あるいは個別者)は、現実のセンス・データではなく、可能なセンス・データであり、「センシビリア」(sensibilia)ともよばれる。
ラッセルはこの理論を完成していないのであるが、しかしここで現象主義にはすでに原理的な困難が現れていると思われる。この時期にはまた、ラッセルの分析哲学の方法を古典的な形で示している「論理的原子論の哲学」('The philosophy of logical positivism')が書かれている。論理的原子論については、ラッセルはウィトゲンシュタインの影響を認めている。なお、第1次世界大戦(1914~1918)当時、ラッセルは戦闘的平和主義者として論陣を張ったが、新聞に寄稿した論説が英国政府および米国陸軍に対する誹謗にあたるとして、1918年、6カ月の禁固刑を言い渡された。よく知られていることであるが、彼はこの服役中に、『数理哲学序説』(
Introduction to Mathematical Philosophy, 1918(松下注:1919年の誤り): 平野智治訳[1954])を書き上げ、さらに本書『心の分析』の執筆にもとりかかっている。なお、前者は、非専門家のための『数学原理』の概説であり、同時にまた、有名な「記述の理論」の解説をも含む、『数学原理(Principia Mathematica)』の哲学的側面を扱った入門書である、なお、1915年は、当時もまた近頃も科学哲学の主要話題の1つである、アインシュタインの一般相対性理論(特殊相対性理論と矛盾しない重力理論)が発表された年である。
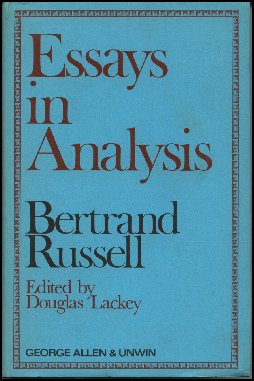 第4期は、1919~1927年
第4期は、1919~1927年で、本書『心の分析』が書かれたのはこの時期にあたる。ラッセルはこの時期、本書の他に『物質の分析』(
The Analysis of Matter, をも書いており、また2冊のセミ・ポピュラーな新物理学の解説書、『原子のABC』(
The ABC of Atoms, 1923)と『相対性(理論)のABC』(
The ABC of Relativity, 1925: 金子務、佐竹誠也(訳)『相対性理論への認識』[1971])をも公けにしている。『心の分析』、『物質の分析』において、ラッセルは、前の時期に物理学に対して適用された彼の現象主義的な分析をより完全なものにしようと努めるとともに、さらに前者では、その適用を心理学に拡張しようと試みているのである。ただし、これらの仕事においては、1914年の『外部世界はいかにして知られうるか』にみられたような、論理学の技術の直接の応用はまったく考えられておらず、その点では一歩後退と言わなければならないであろう。それはともかくとして、
彼が打ち立てようと望んだのは、知識の基礎に関しては経験主義の伝統を引き継ぎ、方法的基準としては『数学原理』の普遍的な論理を背景にもち、その結果として、それ自身として整合的な体系的理論であるとともに、同時代の最も先端的な物理学ならびに心理学の諸理論とも両立しうるような哲学であった。ラッセルが要求したような哲学(とくに知識の理論)は、特殊科学に同等の資格でならぶ「自然化された認識論」(クワイン)ではない。従って、その点ではラッセルの知識の理論は伝統的ではあるが、他方それは、同時代の第一線の科学をほぼ全面的に受け容れる用意がある哲学なのである。ここではラッセルは、『数学原理』の論理学を実際的な分析の道具として用い、彼が受け容れようとする科学的理論を懐疑のテストにかけ、その内部から、彼自身に納得のいくまで綿密に調べ上げることによって、それの根拠を見出そうと努力しているのである。
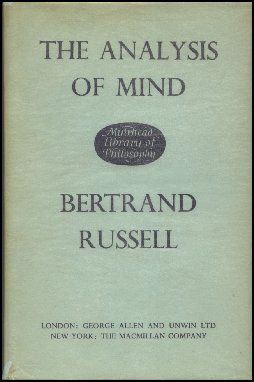
話を『心の分析』に戻すならば、これは、
1914年の仕事においては物質に対して適用された現象主義的分析の方法を、今度は心的存在に対して適用しようと試みたものである。その際、ヒューム、ウィリアム・ジェイムズ、マッハ、およびアメリカの新実在論者たちの例にならって、
心と物質のいずれをも、それ自身では心的でも物的でもない、感覚(的要素)の集まりに還元しようとする着想が踏襲された。ラッセルの意味での「中性的一元論」においては、感覚の他に、(心の構成にのみ関係する)イメージ、感情なども「要素」に数えられる。こうして
同じ感覚(的要素)が、物理的因果法則に従って関係づけらるときには物質が構成され、原因が心理学的な因果法則に従って関係づけられるときには心が構成される、と考えるのである。その結果として要素の集合には属さない、主体(subject)とか意識とかいったものを,実体的な存在者として認めることは不可能となる。また
これに伴って、主体が意識する対象として、センス・データが存在すると考える必要もないことになる。つまり、感覚やイメージだけからなる要素が、センス・データに代わって登場するのである。上にみたように、物理的対象とは何かという問題に関しては、1914年の仕事では、原理的には(現実のセンス・データヘの)還元主義が放棄された。しかし、心に関してはどうするのか、これまではっきりとは言われなかった。しかるに、本書でのように、
意識や主体を自立的な実体とみなすことを拒否するかぎりでは、心に関しては還元主義が保存されることになる。(
一般的に言えば知識のあり方を考える際に、自然を人間化することは慎み、人間を自然化することに努める、というのがラッセルの態度であると言ってよい。この態度は現代では、アメリカの哲学者クワインに最もよく承継されているように思われる。)
物質と心とを構成するにあたって従われるべき因果法則は、全体の構想が単なる形而上学的空想に終わるのでないならば、それぞれ、実際に物理学の法則であり、また、とくに本書の場合には、心理学の法則(と考えられるもの)でなければならない。しかし、
心理学の「法則」には物理学の法則とは非常に違う特徴がある。たとえば、経験がそれ以後の記憶-イメージを生み出すような原因作用は、ラッセルが(ゼーモンに従って)「ムネメ」とよぶ一種の「遠隔作用」なのである。彼は行動主義の心理学に従って、行けるところまでは行こうとするのではあるが、物理学的(ないしは生理学的)には定義することができない意識の状態が存在することをも、決して否定しないのである。
この時期の最後に現れる『物質の分析』(1927)では、力、物質、空間、時間といった、物理学の基本概念が「出来事」(events)に分析される。また出来事はセンス・データとセンシビリアを包含するものと考えられる。従って、原理的に知覚可能でない出来事が存在することをも認めるのである。この本での形而上学的立場は、(物理主義までは行かないが)概して実在論的になっていて、
物理空間と知覚空間との間には構造上の対応が与えられるだけで、それ以上に進んで、物理的対象に固有の性質を知覚することは、われわれにはできないと考えられている。(この見解は、初期のM.シュリックの『一般認識論』(
Allgemeine Erkenntnislehre, 1918)のそれと非常に近いといえる。ただし、(シュリックの)知識と見知りを区別するような考えは、もちろんラッセルとは違う。さらに、シュリックの論理学の理解はまったく前近代的である(たとえば、同書、第2部参照〕)。さらに、物理的対象と知覚との関係については、ラッセルはここでふたたび1912年当時の、知覚の因果説に戻ったと考えられる。
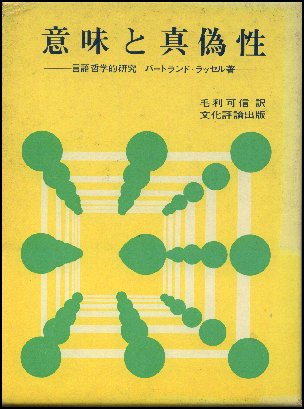
最後の
第5期は1928~1959年で、
この最後の時期にラッセルは、それ以前の時期の研究の過程で、繰り延べになっていた問題のうちの主要なものを取り上げている。『心の分析』との関連でいえば、たとえば、彼は、信念の分析(講義12)において、人が何かを信じているという状態は、信じられる内容(=「命題」、つまり、語またはイメージの列)に、或る感情あるいは感覚の複合が加わってできた状態だと考えた。この付随する感情あるいは感覚における差異から、信念(感情)の分類(記憶、期待、ただの同意)が行われた。しかしその際重要なことは、
信念の内容と信念感情との関係が、単なる併存という以上の、特に緊密な結びつきでなければならない、ということである。ところが、それがどういう結びつきなのかについては、本書では問題の指摘があるだけで(
ibid.)、詳しい説明が与えられていない。けれども、命題に同意することは、語やイメージの列に対してただ何かの感情をもつこととは同じではない。つまりこの場合、語やイメージは何か「の」(of)記号でなければならないのである。すると、すでにその死が宣告されたはずの
志向対象の古い亡霊が、またぞろ出現するであろう。しかし、志向対象の復活を許さないためには、命題に現れる記号を単なる音ないしはマークとみなした上で、そのような命題に同意するということを、単にそれらの記号を肯定的に受け容れるというだけのことであると解釈する道もあるであろう。だが、そのためにはまず、記号が何かの記号であるということを、志向性の概念によらないで説明しておくことが必要である。『意味と真理の研究』(
An Inquiry into Meaning and Truth, 1940: 毛利可信(訳)『言語哲学的研究――意味と真偽性』(1973))での、記号の代償刺激による定義、命題の心理的概念への還元、信念の因果的定義などは、そのような要求に応えようとした努力なのであった。また、ラッセルの最後の重要な哲学書である『人間の知識』(
Human Knowledge, its scope and limits, 1948: 鎮目恭夫訳(1987)においても、やはりそれまで繰り延べになっていた
帰納法の問題が取り上げられている。(もっとも、『哲学の諸問題』(1912)第6章にも、帰納法についての短い説明がある。)現在のこの瞬間に起こる感覚やイメージという直接の証拠を越えた経験的命題の真理は、不確実なものと考えられる。その種のすべての命題に対するわれわれの信念は、帰納推理の結果である。そして帰納推理の特徴は、前提よりも結論の方が確実性に乏しいことである。『人間の知識』では、ラッセルは(2部分から成る)このような
帰納推理の一般的原理を述べている。しかしそのような原理は、ラッセル自身が与える理由によって、不十分なものであることが示される。(そのことを示す理由に対応するものを、彼は『人間の知識』の確率について論じた箇所でも論じている。それは後に、ネルソン・グッドマンが「帰納法の新しい謎」とよんだものと同種の問題である(『事実・虚構・予言』(
Fact, Fiction and Forecast, 1954: 雨宮民雄訳(1987)第3章))。そして、
ラッセル自身の手になる、彼の哲学の最終的な要約と解説が、『私の哲学の発展』(
My Philosophical Development, 1959: 野田又夫訳(1960))において与えられている。
以上が、本書(『心の分析』)が占める位置、および本書で扱われている問題に主眼をおいた、
ラッセルの哲学全体の概観である。(なお、
哲学的にみた場合、倫理学や社会・政治哲学の分野でのラッセルの仕事は、論理学と知識の理論における彼の仕事に比較できるほどの興味のあるものではない。)
最後に、ラッセルの哲学の発展の上で、同時代の哲学者の仕事との間に生じた関係、ならびにラッセルの哲学が同時代ひいては現代の哲学に与えた基本的な影響について、ごく簡単に言及しておきたい。まず、彼とホワイトヘッドとの協同研究について言えば、純粋に論理学的な仕事においては、ラッセルの方がより多くの興味ぶかいアイデアをもっていたと思われる。たとえば、タイプの理論も記述の理論もラッセルが考え出したものであった。しかし、後にその種の技術を哲学の問題に適用することになったとき、今度はホワイトヘッドの方が先導するかたちになった。たとえば、『外部世界はいかにして知られうるか』(
第2版、1922、第4講を参照)における「抽象化の原理」、ならびにそれに基づいて、点や瞬間のような抽象的概念を観察語句に還元する技術は、ホワイトヘッドの独創であった。ラッセルはまた、上の第1期において、マクタガートの新へーゲル主義的観念論から癒されるにあたって、G.E.ムーアから決定的な影響を受けた。さらに、1912年からラッセルのもとで研究を始めたウィトゲンシュタインとの交渉も見逃すことができない。後者がモンテ・カッシーノの捕虜収容所からその原稿を送ってきた、『論理学哲学論考』(
Tractatus Logico-philosophicus(1922に英国で出版)にみられる、ラッセルの「論理学」に対するウィトゲンシュタインの批判は、いま読んでも興味ふかいものである。著者は『数学原理』の(従ってまた、フレーゲの『概念文字』[
Begriffsschrift, 1887?の)論理的真理が、論理定項の
「意味」によって真であることを否定する。それらの真理は、それらの
「論理形式」によって真なのである(とくに、5.4~5.476)。論理学は事実の上に立っているのではなく、従って、言語の意味あるいは用法についての事実の上に立っているのではない。従ってまた、いかなる「意味の理論」に支えられているのでもない。論理学はすべての言語に共通な「論理形式」に支えられているのである。『論考』の著者が考えていたような立場を、論理主義者の言うような意味での論理学として実現するとすれば、それはほぼ『数学原理』から無限公理と還元公理を切り棄て、論理学から導出される数学としては、原始帰納的算術だけを認めるようなものになることであろう。このようにして、『論考』の著者は、
絶対的に無仮定で、普遍的で自立自存の論理学とはどんなものかをはっきりさせ、ラッセルの「論理学」がいかにそれから遠いかを示し、それとともに、論理主義の元来の動機であった、数学の論理学への還元という問題を完全にとらえそこなったのであった
(4)。ラッセルは『論考』には非常な関心を示したが、これに反して後期のウィトゲンシュタインの『哲学探究』や、その影響を受けた日常言語学派の仕事には全然何の興味をももたなかった。ラッセルは彼らとは違って、哲学の問題には解答がありうると確信していたからである。
第3期のラッセルの哲学がわれわれに与えた影響について、クワインは次のように述べている。「……ラッセルが今世紀の2番目の10年間に提示した哲学的諸学説――感覚されないセンサ(sensa)とパースペクティヴ、論理的構成物と原始的事実――においては、新しい論理学が1つの役割を果たした。これらの学説は今日のわれわれの思考に、直接に、また予想もしない思想の学派の出現を通じて、影響を及ぼした。今日の哲学への論理経験主義の衝撃が、重要な程度にまで、ラッセルの衝撃と紙一重であることは、カルナップの著作やまた他の著作における参照文献が十分に証言していることである。その上、ウィトゲンシュタインの哲学は、ラッセルと若いウィトゲンシュタインとが共有した見解から発展してきたのであった。オックスフォードの日常言語の哲学は、その起源にラッセルの強い血統をもつことを、どれほど物悲しくはあろうとも、認めなければならないのである」
(5)。私は、ラッセルの知識の理論と論理経験主義とが、認識論的にまったく同じ立場であったとは思わないが、その点を別とすれば、私はこのクワインの観察があたっていると考える。『外部世界はいかにして知られうるか』(1914)の続編とみるべきものは、たしかにカルナップの『世界の論理的構築』(
Der logische Aufbau der Welt, 1928)でなければならないであろう。たとえば、「抽象化の原理」が初めてはっきりと定式化されたのもこの本においてであった。第4期のラッセル自身の哲学について言えば、それはこれらの仕事の間に介在する時期の仕事であった。そしてとくに『心の分析』については、それなしにはありえなかったであろうと思われるような仕事を、その後の哲学に見出すことができないことはたしかであろう。しかしながら、「日常生活の知識のすべてを批判することができる立場をわれわれに与えることができるような、哲学者によって得られうる、極上の種類の知識は存在しない。われわれにできることはせいぜい、われわれの共通の知識を、それが得られるための規範を仮定しながら、内部での綿密な調査によって検討し、純化することだけである」。もしこの『外部世界はいかにして知られうるか』の一般方針
(6)を基準として、そこからそれ以後の彼の一連の仕事をながめるとするならば、『心の分析』その他の彼の哲学的著作が、この基準をみたす実行であることを疑いうるどのような理由があるのか、私には分からない。
[注]
(1) Broad, C. D., 'Critical and Speculative Philosophy.' In: J. H. Muirhead (ed.),
Contemporary British Philosophy: Personal Statement, 1st series (London, 1924), pp. 75-lOO.
なお、「・・・」の部分は、「そして G.E.ムーア氏は、まったく何1つ生み出さない」と読まれる(?)。
(2) ラッセルの仕事を5つの時期に区分することは、次に負う。
Savage, C. Wade and C. Anthony Anderson (eds.) ,
Rereading Russell(Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol.12(Minneapolis, 1989)), Introduction.
(3) Savage and Anderson,
Ibid, p.5.
(4) この見方については、次に負う。 Friedman, Michael, 'Logical Truth and Analyticity in Carnap's
Logical Syntax of Languqge.' In: Aspray, William and Philip Kitcher (eds.) ,
History and Philosophy of Modern Mathematics(Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Vol. 11 (Minneapolis, 1988)), pp. 90ff. なお、次を参照。Goldfarb, Warren D., 'Logic in the Twenties: The Nature of the Quantifier,' In:
Journal of Symbolic Logic, Vol. 44, No. 3 (1979).
(5) Quine, W. V., 'Russell's Ontological Development.' In: Ralph Schoenman (ed.),
Bertrand Russell: Philosopher of the Century (London, 1967) , p. 304.
この論文は次に再録されている。 Quine,
Theories and Things(Cambridge, Mass., 1981),pp.73-85. なお、引用文中の「センサ」(sensa)とは、公共的に存在し、現実に知覚されるものからは区別された、単に感じられる、そして存在したり、何かの特定の性質をもったりすることを含意しないものを一般的に表す語である。たとえば、ロックの感覚の観念、バークリの観念、ヒュームの印象、ムーアやラッセルのセンス・データなども、多くの場合、センサの例にあたる。
(6) Russell, B.,
Our Knowledge of the External World, p. 71. クワインの上掲論文の末尾に引用されている。


