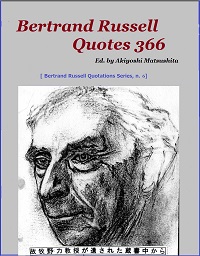志村武「バートランド・ラッセル」
* 出典:『思想家への招待』(大阪教育図書,1964年1月。256pp.)pp.227-246.
*  初心者用コンテンツ
初心者用コンテンツ
不正確な記述や、通俗的すぎる、時代感覚がずれていると思われる文章(書き方)が散見されるが、40年ほど前の、中・高校生向きの文章だということを念頭において読んでください。(本書は、当時の全国学校図書館協議会の推薦図書に指定されています。)
* 志村武(1922?~1988?):武蔵野女子大学教授(哲学)。66歳で死亡と新聞記事の切り抜きにあり(自宅は杉並区)。
1.核兵器反対運動の旗手
バートランド・ラッセルといえば、おそらくどなたも、相当程度のことをすでにご存じのことと思う。
1950年にノーベル文学賞を受けた彼は、タイムズの文芸付録で、「合理主義者、不可知論者、政治学者、社会学者、オールド・リベラリスト、進歩主義者、天才的で光のひらめくような独創的思想家」と評されている。
著書の邦訳もかなりあって、わが国にも広く知られているが、彼の名前が一般の人びとの間に強い印象をとどめているのは、その断固とした核兵器反対運動のためであろう。
ご承知のとおり、思索型の人間はとかく行動力にとぼしい。そしてまた、行動力に富む人は、がいして思索する力を欠くうらみがある。バートランド・ラッセルのようにこの2つの力を十二分に兼ね備えている人物は、まことに珍しいといえよう。
今日では、よほどのバカか気ちがい(松下注:後者の表現は現在ではさけるのが普通だが・・・。)でもないかぎり、核戦争に賛成する者はひとりもおるまい。ほかのことでなら意見が分かれても、核戦争反対だけは、人類がひとしく支持していることと思う。しかし、いざ実際に反対運動を始めるとなると、自分が先頭に立ってやろうとする人はめったにいない。大切なことはよくわかっていても、「誰かがやってくれるだろう」で、私たちはなかなか腰をあげないものだ。
ところがラッセルは、ジュネーブ巨頭会談開催に当たって、アインシュタイン、湯川秀樹ら8名の著名な科学者とともに、米・ソなどの6か国の元首または首相に書簡を送り、強硬な核兵器反対運動の口火をきった。
彼のこういう積極的な平和主義は、このときはじめて実行されたのではない。すでに第1次大戦のさいには、戦乱に勇みたつ政府に正面から反抗し、投獄されたことさえある。「戦争は、それはつまるところ無益な殺し合いだ。'よい戦争' とか '悪い平和' なんてものはない。あるのはただ、'悪い戦争' と 'よい平和' だけだ」(松下注:核兵器出現後は、ラッセルは、「実質的な」絶対平和主義者と言ってよいと思われる。しかしラッセルは、自分は「理論的な」絶対平和主義者であったころは一度もない、と何度か言っている。)
これがラッセルの信念だった。この信念は投獄されても少しもゆるがなかった。
 「牢獄は肉体の自由を奪うことはできるが、精神の自由まで奪うことはできない」(右図:第97回「ラッセルを読む会」案内状挿絵)
「牢獄は肉体の自由を奪うことはできるが、精神の自由まで奪うことはできない」(右図:第97回「ラッセルを読む会」案内状挿絵)
自分のこの言葉のとおり、彼は人類最大の危機に直面して再びたちあがったのである。
「これまで人類が生き残ってこれた理由は、人類の目的がどんなに愚かなものであったとしても、彼らはそれを成就するのに必要な知識をもっていなかったからである。ところが、今日ではその知識が得られるにいたったのであるから、人生の目的については、今までよりはるかに大きな聡明さがどうしても必要とされるようになってきた。しかし、この'気ちがいざた'ともいうべき時代にあって、どこにそのようなすぐれた知識が見いだされるであろうか」
ラッセルのこの憂いは、皆さんのひとりひとりの胸のうちにもきっとひそんでいるにちがいない。ひとたびボタンがおされてしまえば、もう決して取りかえしはつかないのだ。彼はすでに90歳に近い老体でありながら、みずから進んで平和運動の先頭にたった。しかし、その必死の努力にもかかわらず、世界の情勢は刻々と、核兵器の改善・準備に向かって進展していく。
ついに、1961年の秋には、ソ連は超大型の核実験の再開を発表、かくして、東西両陣営の接点ベルリンはにわかに暗雲にとざされ、核戦争の危険は倍増の一途をたどりはじめた。
この急激な事態の悪化に対応すべく、ラッセルは、ロンドンのトラファルガー広場と議会広場に、1万人の市民を集めて核兵器反対の集会を開く計画をたてた。ところが英国の官憲は、治安を乱すという理由のもとにこの集会を禁止し、彼に裁判所出頭を命じたのである。
「大衆を違法行為にかりたてるようなことは、今後やらないと誓いますか」
判事の問いは、満場をうずめる人びとの胸につきささるように響いてきた。まさに、ソクラテスの裁判を思わせる一瞬である。「ノー」といえば、人類の悲願をになうこの平和の旗手は、再び投獄のうき目を見なければならない。はたして「イエス」か「ノー」か……。人びとの絶大な信頼・尊敬のうちにも一抹の不安がまじる。水をうったように静まりかえった法廷。その静寂をやぶって、ラッセルは力強く、
「ノー」
と答えた。
判決は2か月の禁固刑(健康状態に対する考慮から7日間に減刑)だった。彼は世界中の人びとの尊敬と共感に送られて、再びブリクストソ監獄の門をくぐったのである。(松下注:実際は刑務所ではなく、病院に収容され、1週間拘束されただけで終わった。)
2.「不可能ではないのだ」
フルシチョフは、「たとえ水爆を落とされても、わが国は広大だから、恐るるにはたりない」という意味のことを公言したことがある。そしてアメリカでは、核戦争に備えて防空壕づくりが大流行しているという。
ラッセルが投獄を承知の上で「ノー」と答えたのには、それだけの根拠があるのだ。核戦争は決して単なる夢ではない。私たちのすぐ目の前にある何よりも恐ろしい現実なのである。彼は、この人類全滅の危機について、次のような見解をのべている。
「オセロはデスデモナを殺そうとするときに、『しかしそれはあんまりだ、イヤゴオ! イヤゴオ!、あんまりだ!』という。ソ連の支配者やその反対派が人類の絶滅を準備するとき、この叫びを発するだけの、あるいはせめて自分がしていることの性質をわきまえるだけのあわれみの情が、彼らの性格のうちにあるかどうか、私は疑問たと思うし……彼らの心は、わずかの期間しか続かない権力のための偏狭な争いのなかで、行きあたりばったりの、刹那的便宜主義以上に高まったことがないのだ。しかし、どこの国にも、もっと広い視野に立てる人間がたくさんいるにちがいない。どこの国の人間であれ、そういう能力をもった人びとにこそ、人間(人類)に味方しようとするものは呼びかけるべきである。人間(人類)の将来は危険にさらされている。そして、もし多くの人びとがそのことに目ざめるなら、その将来は確固たるものになる。世界をその苦悩から救い出そうとする者は・勇気・希望・愛をもたねばならない。…
世界が現在の苦悩から脱却し、また、事態の処理を残忍な山師にまかせず、真の知恵と勇気とをもつ人間にまかせることを知る日のくることを私は期待している。そのとき、私の目の前には明るい想像世界が浮かんでくる。すなわち、飢えた者のいない世界、親切な感情がゆきわたり、不安から解放された精神が、目と耳と心を楽しますものを創造する世界である。それは不可能だ、などといってはいけない。不可能ではないのだ。それがあすにでも実現されるとは私もいわないが、人間が人間に固有の幸福の実現に心を傾けるならば、千年以内には実現される、と私はあえていいたい」
ラッセルはここで、人類の運命を「もっと広い視野に立てる人」、「真の知恵と勇気をもつ人間」にまかせよ、と語っている。それは、具体的にはどんな人物を意味するのであろうか。
私たちはそのひとつの理想的なタイプを、ラッセル自身の生涯と思想のうちに、最も明白に見いだすことができるのである。
3.不死鳥のごとく
1872年(明治5年)5月18日、イギリスきっての名門ラッセル家に、鼻すじの通った、二重まぶたの目の大きな、かわいらしい男の子が誕生した。(松下注:この辺の記述は著者の「創作」に過ぎない。生まれた頃は、自叙伝によれば、なんて不器量な子供だろうと母親は思った由)父ラッセル伯は、自由思想家として名のある人であり、祖父は、ビクトリア女王の下で2度も首相をつとめた大政治家である。バートランド・ラッセルは、この誇り高い名家に生まれたが、不幸にして、2歳で母を、3歳で父を失った。ひき続いて(ラッセル6歳の時に)祖父をも失った彼は、祖母の手ひとつで育てられ、小・中学校には行かず、家庭教師について勉強、そして18歳のときにケンブリッジ大学に入学した。好きな科目は数学で、その成績はずばぬけていた。
めきめきと頭角をあらわしたラッセルは、早くも28歳のときに母校の講師に迎えられた。その3年後には、画期的著作『数学の原理』(1903年)を出版し、記号論理学に新風を吹きこんで、世界の学界から注目されるにいたった。それから約10年間の生涯は、研究につぐ研究の生活で、名門の秀才にふさわしい学究のコースを順調に歩んでいった。
この平穏な前半生にピリオドをうったのは、第1次世界大戦の勃発(1914年)であった。彼は平和に対する燃えるような情熱にかられて、敢然として雑踏の街頭に立った。徴兵反対運動に参加して、政府攻撃のビラをくばり歩いたのである。
このために、彼は100ポンド(約10万円)(松下注:当時の物価に換算する必要あり)の罰金を課され、(ケンブリッジ大学の)講師の職を免じられてしまった。その上、アメリカのハーバード大学が彼を教授に迎えようとしたのに、政府によって旅券の発行を停止され、赴任を禁じられるというひどいめにまであわされた。
しかし、ラッセルは少しも屈しなかった。1918年には、平和主義につらぬかれた論文を堂々と発表、戦争反対の論陣を鋭く展開した。この論文がもととなって、前に述べた最初の禁固刑(6か月)に処せられたのである。
「出るクギは打たれる」というたとえの通り、この名門の秀才は寄ってたかって打ちさいなまれたわけである。たいていの人ならば、このへんで気も心もくじけてしまう。ところが、彼はくじけるどころか、不死鳥のようにたちあがり、さらにたくましく活躍しはじめたのである。
ラッセルは、血なまぐさい闘争を徹底的に嫌悪した。彼には、1帝国(大英帝国)の利益などは、戦線に送り出される若人たちの生命に、決して価いしないと思われたのである。やがて、彼は戦争による大虐殺の原因を探り出すことに着手し、その原因を私有財産に見いだした。
「土地を私有させていたのでは、共同体にはいかなる種類の利益も生じない。もし人間が理性的であるならば、土地の私有は明日から停止し、現在の所有者には代償として適度の年金を与える、と布告するであろう」
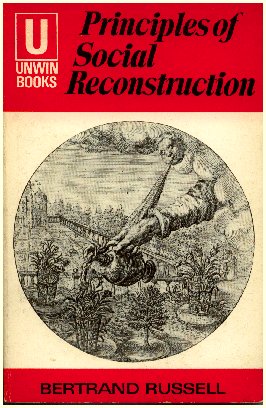 彼は、財産とはすべて(松下注:「莫大な財産の多くは・・・」というべき)、その起源は暴力行為と窃盗にあると考えたのである。そして、私有財産が国家によって保護され、財産の原因である強奪が法律によって認められ、国際間に戦争が強行される以上、国家というものはひとつの大きな禍悪でしかないと主張した。(松下注:このあたりはラッセルの主張を単純化しすぎている。)歴史的に考えると、たしかにそういうこともいえるだろう。現代でさえも、しばしば一部の私有財産は、「広い意味での」暴力・強奪によってきずかれているのだ。まして未開の時代においては、ほとんど万事が「強いもの勝ち」で左右されてしまったのである。
彼は、財産とはすべて(松下注:「莫大な財産の多くは・・・」というべき)、その起源は暴力行為と窃盗にあると考えたのである。そして、私有財産が国家によって保護され、財産の原因である強奪が法律によって認められ、国際間に戦争が強行される以上、国家というものはひとつの大きな禍悪でしかないと主張した。(松下注:このあたりはラッセルの主張を単純化しすぎている。)歴史的に考えると、たしかにそういうこともいえるだろう。現代でさえも、しばしば一部の私有財産は、「広い意味での」暴力・強奪によってきずかれているのだ。まして未開の時代においては、ほとんど万事が「強いもの勝ち」で左右されてしまったのである。
一方には先祖伝来の広大な私有地をもつ富裕な人びと、そして一方には住む場所にも窮する貧しい人びとの群れ、どこの国にも、いつの時代にも見られる矛盾といえよう。ラッセルはこの種の不合理の解決策を共産主義(松下注:「(ロシア)共産主義」ではなく「社会主義」と書かなければ誤解を与える。/参照:The Practice and Theory of Bloshevism の1948年版への序文)に見いだした。かつての数学的論理学者は、社会の圧迫をはねのけて、共産主義者(松下注:社会主義者)として再起したのである。
4.社会の革命よりセックスの革命へ
1920年、ラッセルは希望にもえてソ連を訪問した。彼はそこで、共産主義的社会を建設しようとする努力を直接見聞した。その結果はどうであったか……。言論および出版の自由の抑圧、あらゆる宣伝手段の思いきった独占とその組織的使用など、現実は彼の期待にまったく反するものであった。しかも皮肉なことに、ひとつだけ彼を喜ばせたのは、ソ連人民のほとんど全般的な文盲であった。なぜ、そんなことが彼を喜ばせたのであろうか。人民に読む力がないかぎり、彼らが一方的なゆがめられた新聞の報道に接しなくてもすむと思ったからである。また、彼は土地の国有化が私有に譲歩せざるを得なくなっている実情をまのあたりに見て、「人間は今日のところでは、自分の土地を自分が加えた改良ぐるみ、自分の子どもらに伝えることが当てにできないかぎり、それを本気には耕作しないものだ」ということをハッキリと思い知らされ、深い失望の念をいだいて帰国した。
この同じ年に、彼は招かれて中国に渡り、帰途には日本にも立ちよって各地で講演し(松下注:これも著者の「創作」。ラッセルは、短いスピーチは2,3回行ったが、講演は、慶應大学大講堂で行った1回のみ)、帰国後まもなく、労働党から下院に立侯補したが、不幸にも落選してしまった。
このように広く世界をまわり、いろいろな社会の現実に接したラッセルは、世界は自分の念願している目標へ急速に近づくには、あまりにも大きく重いことを次第に深く理解するにいたった。しかし、決して妥協的になったわけではない。その思想はいよいよみがかれ、何ものにもとらわれない公正な輝きを一段と増すにいたったのである。
かぎりない勇気に満ちたこのヒューマニティの熱愛者ラッセルの思想は、1940年、今度は『結婚と道徳』をテーマとする論陣をはり、セックスをめぐる風雲をまきおこした。(松下注:Marriage and Morals 自体は、1929年に出版されたもの)
「子どもを扱う伝統的な指針は、両親と教師ができるだけ子どもを無知にしておくことであった。……性に関する質問への答えはすべて、ぎくりとした調子の『しっ、しっ』という言葉であった。彼らは子どもはコウノトリが運んできたのだとか、スグリのやぶの中から掘り出されたのだとか教えられた。しかし、おそかれ早かれ子どもたちは、他の子どもからたいてい多少ゆがめられた形で事実を知る。言うほうはコッソリと話すし、そうして、自分が両親からそう教えられているので、事実を『不潔』なものと考えている」
ラッセルはこれがいかんというのである。こういう誤った、ゴマカシの指導と教育が、セックスは悪であるという考えをうえつけ、幸福な恋愛を不可能にし、女性を軽蔑し、しばしば残酷なしうちをする衝動を呼びおこすのであると説いた。彼は、「性には何も悪いところはない。この問題についての因習的な態度は病的である」とし、
「性本能は妨害するよりはむしろ訓練すべきものである。・・・。
たいていの男女が、幼年期をあれほどまでに禁制に取り囲まれて週ごさなかったとしたら、もっと真心のこもった、もっと寛大な夫婦愛を経験できるはずだが、今のところはそれが不可能なのである。彼らは必要な経験を欠いているか、さもなければ、ひそかな好ましくないやり方でそれを得ている」
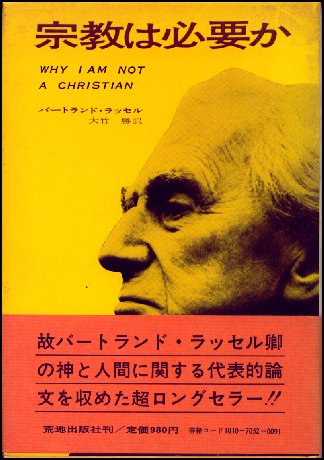 このように、セックスをゆがんだ禁制の中にとじこめ、その行為を暗い影でおおったのは、キリスト教の倫理思想であるとして、「教会は、すべて肉体を魅力的にするものは、人を罪に導きやすいという根拠から、入浴の習慣を攻撃した」などとのべて、彼はキリスト教の倫理に対する正反対の議論を展開した。この点、皆さんはどう思うだろう。日ごろ関心をもたざるを得ない問題だけに、それぞれ自分なりのご意見をお持ちではあるまいか。なかには、深刻な悩みにおちいっているかたもあるかもしれない。
このように、セックスをゆがんだ禁制の中にとじこめ、その行為を暗い影でおおったのは、キリスト教の倫理思想であるとして、「教会は、すべて肉体を魅力的にするものは、人を罪に導きやすいという根拠から、入浴の習慣を攻撃した」などとのべて、彼はキリスト教の倫理に対する正反対の議論を展開した。この点、皆さんはどう思うだろう。日ごろ関心をもたざるを得ない問題だけに、それぞれ自分なりのご意見をお持ちではあるまいか。なかには、深刻な悩みにおちいっているかたもあるかもしれない。
ラッセルのこの思想には多くのむずかしい問題がふくまれており、是非の判断はにわかには下しがたい。彼は「性本能は訓練すべきものである」というが、どんなふうに訓練するにせよ、やはりいろいろな問題が起こるであろうと考えられる。いったい、どうすればこの泥沼を解消できるのであろうか。私たちはしばしば、「この道ばかりは別だ」といって、セックスを特別扱いする。その力を何か絶対的なものであるかのように思いこんでいる人が多いのだ。セックスに関するかぎり、人間をじゅっぱひとからげにしてしまうこと、つまり、人格を否定してしまうこと、これはまともな見方だといえるだろうか。それほどセックスは強力なものなのだろうか。
ラッセルとともに、私たちもこの強敵に挑戦してみよう。彼ひとりにまかせておける問題ではないのだから。
5.挑戦
ラッセルは、「愛を恐れることは、人生を恐れることである。そして、人生を恐れる者は、すでに十中八、九は死んだも同然である」
と説き、男女間の愛にともなうセックスの問題を次のように論じている。
「自然は人間を孤独に耐えるようにはつくらなかった。というのは、人間は他に助けられないでは、自然の命ずる生物学的目的を達成できないからである。そうして、文明人は愛をともなわないでは、性的本能を十分に満足しえないからである。本能は、人間の全存在が肉体的にも精神的にも、この関係を結んではじめて完全に満足されるのである。
幸福な愛し合うもの同志の深い親愛感と強い共同意識を味わったことのない人は、人生になくてはならない最良のものを見失っているのである。意識的ではないにしても、無意識的に彼らはこれを感じる。そしてその結果がもたらす失望は、彼らを嫉妬・圧迫・残酷へと誘う。したがって、情熱的な愛に正当な場所を与えることは、社会学者の関心事であるべきである。なぜかというと、もしこの経験に恵まれない場合には、男性も女性も円満な精神的成長をとげ得ないし、世間一般に対しておおらかな暖かい気持をもつことができないため、彼らの社会活動は有害なものになる恐れが多分にあるからである」
このように彼は、愛の価値を論じ、セックスの解放を叫んで、従来の因習的な道徳の教えに正面から挑戦した。
「幼年時代から思春期・青年期を経て結婚にはいるまで、旧来の道徳律はほしいままに愛を毒し、憂欝、恐怖、相互の誤解・侮恨・それに神経の緊張でもって愛を満たし、性の肉体的衝動と理想的恋愛の精神的衝動との2つの領域にわけて、前者を獣的に、後者を無為におわらせる。しかし、人生をこのように生きねばならぬ理由はない。獣的な性質と精神的な性質とは、相争うべきではない。どちらも他と矛盾するものではなく、どちらも他と結合しなければ完全には成熟しない。最良の男女間の愛は、自由でものおじをしない、肉体と精神とが等しい割合で合一したものである。肉体的基礎があるから理想化を妨げはしまいかという懸念もないのである。愛は、大地に深く根をはりながらも、枝は天に向かって広がる樹であるべきだ」(江上昭彦氏訳参照)
かくして、ラッセルはセックスをおおっているうす黒いベールを徹底的に取りのぞき、セックスは決してそれ自体では悪いものではない、セックスにまつわる悪の根源は、旧来の不当な道徳的教えと因習にある、と断言したのである。こういう大胆な思想の説かれている彼の著書『結婚と道徳』が、世の人びとの注目をあびないはずがなかった。世論の大半はごうごうたる非難の声となって、彼の身辺に津波のようにおしよせた。そして、ニューヨーク市立大学の哲学教授に迎えられるさいにも、「ラッセルは、宗教や道徳をないがしろにする無法者だ。大学教授にするなどとは、もってのほかだ」「彼は、青少年を腐敗させる宣伝屋にすぎない」などの投書がニューヨーク中の新聞に殺到した。一方、アインシュタインやジョン・デューイなどのような世界的な学者たちの支持もあったが、ついに、彼の任命は取り消されるにいたったのである。彼は、徹底的平和論を主張して刑に服した場合と同様に、その思想と信念のために、今度は社会の「格子なき牢獄」にいさぎよく下ったのである。これは恐るべき事件であるといえるだろう。いわゆる「お上品な人びと」はセックスを徹底的に忌みきらう。少くとも、そういうポーズをとる。それらの人びとにこの革命の旗手は追放されてしまったのだ。知らぬ顔で見すごせる問題だろうか。私たちにとっても、セックスは当面の大問題である。彼の思想をたどることによって、この問題に関する私たち自身の迷いや悩みを、このさい一層深く検討してみようではないか。
6.「お上品な人びと」の基盤
ラッセルは『何を信ずるか』というエッセイのなかで、
「中世紀には、ある国に疫病がおこると、聖者が住民たちに向かって、教会に集合して助かるためのお祈りをするようにと勧告したものである。その結果、疫病は救いを求める群集の間に、猛烈に、しかも急速なスピードで伝染していった。これは知識のない愛の1例である」
と述べている。これに類する決定的なミステイクを、私たちはセックスに関する考えかたの面で、20世紀の今日もなお犯し続けているのではないだろうか。昭和20年の敗戦をさかいとして、たしかに、セックスに関する知識は飛躍的に普及するにいたった。しかし、それは興味本位な末梢的・技術的な知識たるにすぎない。セックスそのものに対する根本的な見解に、画期的発展を見たわけではないのである。その本質に関してのみは、昔からの迷信・偏見・無知がいぜんとして解消されず、私たちの大半は、セックスをいまだに「オゲレツなもの」であると見る習慣から脱け出していない。
「性は罪ではない、けっして! 性は罪ではない、それは汚れたものではない、たしかに汚れた精神がはいりこまないうちは」
と、D.H.ロレンスはいっているが、残念ながら、私たちにはその「汚れた精神」をセックスに入りこませてしまう傾向が多分にある。「どうしてこうエゲツナイんだろう」と、私たちは脳裡にうごめく泥沼的情念にしばしば長嘆息する。またときには、「この道ばかりはしかたがないさ。上品面した人だって同じなんだ」と、あきらめに似た気持で肯定することもある。ところが意外なことに、ラッセルをしていわしめれば、この傾向はいわゆる「上品な人びと」にこそ一層いちじるしいというのである。その1例として、彼は次のような話を挙げている。
「わたしは現にロンドンに住んでいるある外国婦人で、相愛のある男性と幸福な、しかし法律外の結婚をしている人を知っている。不幸にして、彼女の政治に関する意見は、望ましほどには保守的ではない。もっともそれは単なる意見だけのことで、それにもとづいて彼女が実際的にどうしようというものではないのだ。ところが、上品な人びとはこの口実を利用して、ロンドン警視庁に事情を探らせたのである。このために彼女は自分の生まれた国に追い帰されることになっている……」
これに類する話は、私たちの周囲でもよく聞かされる。そして、正式の結婚によらない男女の同棲は、上品な人びとによって断固として排撃される。だが、本質的に考えれば、エレン・ケイのいうように、
「恋愛のともなわない結婚は、結婚のともなわない恋愛よりも不道徳である」
といえるのではなかろうか。結婚とは単なる制度であり、法律によって権利・義務を設定されたものである。が、愛情というものはまったく個人的なものだ。愛情にともなうセックスも、当人どおしのプライベイトな問題であり、権利や義務をとやかく論じ合わせるべきものではなかろう。
「とんでもない話だ。そんなことをいって、人間を野放しのような状態においたら、世のなかの秩序がメチャクチャになってしまう」 上品な人びとはそういって、結婚という免許証のない男女の愛情生活を決して認めようとはしないだろう。たしかに、彼らのいうことにも一理はある。だが問題なのは、そういう上品で秩序を重んじる考えかたが、真に品性の優雅さから出てくるのかどうかという点にある。
ラッセルは、その点について次のような例をあげ、「上品さ」というものの本質を徹底的に追求しているo
「例えば、たくさんの黒人の労働者を輸送している大西洋航路の船の難破の場合を想像してみよう。1等の婦人船客――おそらくみな上品な婦人たちであろう――がまず救助されるが、これを可能にするためには、黒人の労働者でボートを一杯にさせないように監督している人びとがいなければならない。そしてこういった人びとは上品なやりかたでは成功はとうてい望みえない。救助された婦人たちは、溺死した哀れな黒人たちに対して、自分たちが安全になるやいなや同情しはじめるだろうが、彼女たちの心の優しさは彼女たちを護った荒々しい連中のおかげで可能にされたのである」
ラッセルはこのように「上品な人びと」の基盤にメスを入れたのち、「上品な人びとの主な特質は、現実を改善しようというほむ(ほめる)べき慣習である。神は世界を創造したが、上品な人びとはもっとよい仕事ができるものと感じている」と、皮肉タップリな口調で一応ほめたたえ、次の段階では、彼らの仮面を見事にひっぱがしてしまっている。ラッセルがその仮面の下に見いだしたものは、いったいどんなものであったろうか。
7.下品な精神の持ち主
ラッセルによれば、上品な人びとは、セックスがこっそりと、または冷たく実践されることに万全を期している。そして、それをこっそりと実践している人びとが発見されたときには、くすくす笑って下劣なこととして済まさないで、発表しようとする本や劇を検閲しようと試みる。上品な人びとがなぜそんな態度をとるかについてラッセルは次のようにズバリといっている
「『赤裸の真実』という言葉づかいをはじめた人は、ひとつの重大な関係を見てとったのである。裸であることは正気の人びとにはショックを与えるが、真理もまたそうである。どの部門のことに関心を持っていようと、それはほとんど問題ではない。人はまもなく真理というものが、上品な人びとが意識のなかに入れたがらないものであることを知る」
つまり上品な人びとは、たとえそれが真理であろうとも、あまり恰好のよくない部分には何らかの衣をいつも着せたがるというのである。このむきだしの真実を避けたがる傾向が、しばしば「偉大な人間像」をつくりあげてしまう。「もしも誰かが、ある上品な人に、彼の政党のある政治家は庶民大衆と少しもかわらない普通の人間だといって説得しようとするならば、上品な人は憤慨してその示唆に反対することだろう。このために、政治家としては非のうちどころがない様子をしなければならなくなる。……このようにして、上品な人びとは、国の大人物についての彼らの夢想する姿を保つことができるし、小学校の子どもたちは、有名になるということは最善の徳によってのみ獲得できるものであると信じこまされる……」 この点について、鈴木大拙先生は、
「自分も子どものときには、昔からのいいぐせで.『名を青史に垂れる』とか『虎は死して皮を留める』など、口にしたこともあったと思ふ。実に馬鹿なはなしだ。こんなことを考えて、育てられたかと思ふと、実にそのころの教育のくだらなさを痛感する。人間はえらくならなくてもよい、評判に上下しなくてもよい。一個の正直な人間となって、信用のできるものとなれば、それで結構だ」
と、序文のなかでいっている。しかし、いわゆる上品な人びとは決してそうは考えない。「どういう人間であるか」よりも、「どういう人間に見えるか」に重点を充き、世間的評判を何よりも気にかける。それだけではない。
「上品な人びとは、極めてもっともなことながら、見つけしだい快楽に疑惑をもつ。……たとえば、彼らは自分たちが慈善事業家的だと自分にいい聞かせるために、子どもたちのために公共運動場を作ってやる。しかし、そのあとで使用についてあまりたくさんの規則をもうけるので、子どもたちは誰も往来で遊ぶほどは楽しむことができなくなってしまう。……就職している若い女性は、若い男性とできるだけ話しができないようにさせられている。わたしが知っている最も上品な人びとは、この態度を家庭のなかにまで持ちこんできて、子どもたちに教訓的な遊戯しかさせなかった……」
ラッセルはこのように述べて、上品な人びとの不動の道徳的確信は因襲的なおきてや財産の防禦と密接に連結しているとし、次のような大胆な結論をくだしている。
「上品な人びとの本質は、協調の傾向とか、子どものかしましさとか、わけてもセックスに見られる生活を彼らが嫌っているということであって、セックスについてはむしろ病的に憑かれているのである。一言にしていうならば、上品な人びとは下品な精神の持ち主である」――(大竹勝氏訳参照)
ときめつけているが、はたしてどんなものだろう。ラッセルが「上品さ」という仮面の下に見たものは、「赤裸な真実」から目をそむける下品な精神であったのだ。私たちならば何をその仮面の下に見いだすであろうか。
8.自由人の信仰
さて、ラッセルは一時は「格子なき牢獄」にくだったが、やがて再ぴケンブリッジ大学に迎えられ、今日では90歳の高令に達している。この尖鋭で勇敢な老哲学者は、81歳のときにラジオ放送で次のように語った。
「世界の災いのひとつは、なにか特定のことを独断的に信ずる習慣である、と私は思う。そして、それらはすべて疑問に満ちており、理性的な人間なら、自分が絶対に正しいなどとむやみに信じたりはしないだろう。私たちは、常に、私たちの意見に、ある程度の疑いをまじえなければいけないと思う。」
たしかに、教養がなく知識にとぼしい人間ほど、自分の意見を強引に押し通そうとして、はたの者に迷惑をかける。その傾向の特にいちじるしい例を、私たちはしばしば、何かを熱烈に信仰している人に見いだすことができる。
「人類は黄金時代の入口にいるともいえよう。しかし、もしそうだとするならば、まず第1にその扉を守っている竜を殺す必要がある。この竜の名は宗教である」
とラッセルはいっているが、ピンとこないかたは、あらためて周囲を見まわしていただきたい。世の中には、何かをかたく信じて少しもゆずろうとしない人がどれほどいることか。金銭や名誉を絶対視する者、世間体を何よりも尊ぶ者、縁起ばかりをかついで、ツイテイル、ツイテナイと一喜一憂する者。それぞれのものに不動の信念をもつかぎり、彼らはいずれも宗教の信者と変わりはしない。核兵器の改善や製造に狂奔する政治家たちも、やはりその威力を最高絶対と信じる熱烈な信者であるといえよう。
それではいったい、私たちは何を目標に、どのように生きるべきなのであろう。ラッセルは、
「よい生活とは愛に力づけられ、知識によって導かれた生活のことである(The good life is one inspired by love and guided by knowledge.")」
とし、
「知識と愛とは、両者ともはてしなく延長できるものであるから、それゆえ、生活がいくらよくとも、もっとよい生活を想像することができる。知識のない愛も、愛のない知識も、よい生活をつくりだすことはできない」
と説き、さらに、
「個人的な幸福のための努力を放棄し、一時的な欲望に対する熱意のすべてを追放し、永遠なものに対する情熱に燃えること――これが解放であり、これが自由人の信仰である」
といい、その思想を生活の上にきびしく実行している。
今日もなお、彼はいよいよ高遠な思索にふけり、人類に対するかぎりない愛に満たされて、著作や核兵器の禁止運動に一身をささげている。彼のその一貫した平和主義が、核停会議その他にジカに生かされることを心からねがってやまない。

 初心者用コンテンツ
初心者用コンテンツ