バートランド・ラッセル著書解題12:ラッセル『懐疑論集』(東宮隆・解題)
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第13号(1969年8月)pp.4-6.* 東宮隆氏は当時,東工大教授,ラッセル協会理事
* 『懐疑論集』への訳者あとがき
本書(Sceptical Essays)は,一九二八年の出版で,それぞれ独立のエッセー十七篇から成っている。その章立ては以下のごとくである。
01.序説:懐疑主義の価値について/ 02.夢と現実/ 03.科学は迷信的か/ 04.人々は合理的になりうるか/ 05.二十世紀の哲学/ 06.機械と感情/ 07.行動主義と価値/ 08.東西の幸福の理想/ 09.善人の及ほす害/ 10.ピューリタニズムの再燃/ 11.政治的懐疑主義の必要/ 12.自由思想と官製宣伝/ 13.社会の自由/ 14.教育の権威対自由/ 15.人間心理と政治/ 16.信条戦の危険/ 17.若干の展望-明暗とりどり
これらの各章を通じて著者の言おうとしていることは,世界の真の進歩が理論と実際双方の上での合理性の増大にかかっているということである。
進歩といい合理性と言い,さほど目新しい概念ではない。それどころか,二十世紀初頭からこんにちに至るまで,進歩と合理性の破産を宣告する思想や事件はむしろ多過ぎるくらいであったとも言えるほどである。それにもかかわらす,いやそれだからこそ,著者は,どこまでも,悔い改めざる一個の合理主義者として,自己を主張しているのである。
「序説:懐疑主義の価値について」で,著者はつぎのような簡単明瞭な提言をしている。
「一つの命題を正しいと考えるべきなんの根拠もない場合,これを信ずることは望ましいことではない。」
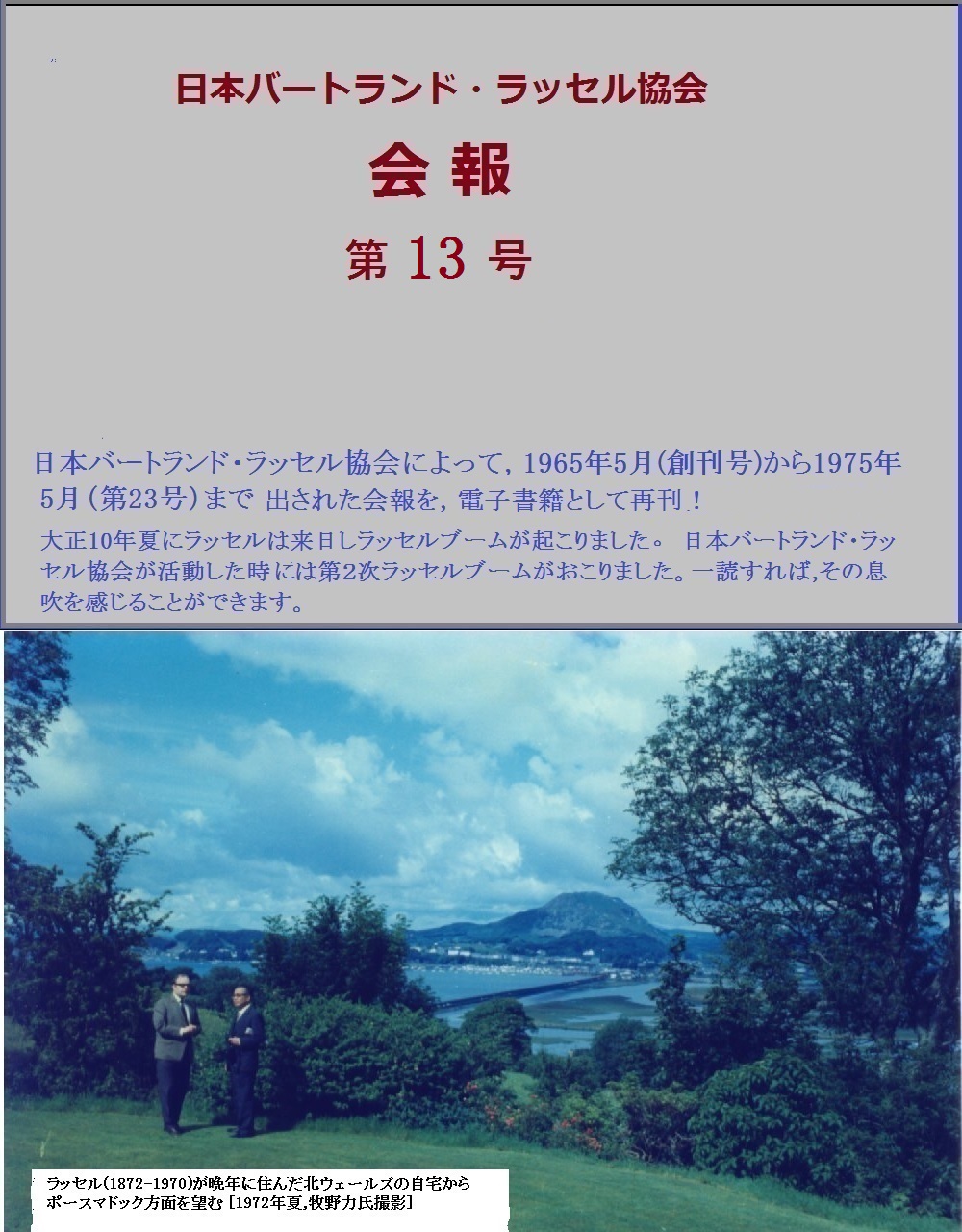 ラッセル協会会報_第13号 |
しかし,私は,この言い方そのものにもまた著者の面目がうかがえるように考える。それというのが,右の提言にもとづく改革案で,本書全体に説かれているものを,ひとたび実行に移したとすれは,破壊的とさえおもわれるほど激しいものが出てこないわけにいかぬからである。それは常識的中道主義と言っただけで片付くものではなさそうである。では,なぜそのようなことが起こってくるのであろうか。それは,ラッセルが,或る意味で単純な論理を,澄ましてそのまま,錯雑した現実に当てはめるところから,生じてくるもののように,私にはおもわれるのである。
懐疑主義は,古代のソフィスト辺に始まり,ルネサンスをへて,デカルト,ヒュームにまで及ぶ系譜を持っている。ラッセルを懐疑主義の系譜に位置づけるとすれば,どのあたりにすべきか,それは一つの問題かも知れない。ともかく,哲学の上で,ラッセルは誰に近いかと言って一番ヒュームに近い。それは,ラッセルみずからが好んで指摘しているところである。本書でも,科学の正当づけに関連しての因果性と帰納法に対するあの有名な懐疑の故に,ヒュームは取り上げられている。それは,ラッセルが,科学の理論的正当化を通じて,科学的発見への衝動の根を何とか枯らせまいとする意味でである。ところで,「バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家-」の著者,アラン・ウッドに従えば,「ギルバート・マレーもラッセルも共に懐疑主義と合理主義を奉じ,伝来の慣習やしきたりはみなまちがっていると推定する点で一致していた。」(碧海純一氏訳) そうだとすれば,ラッセルの懐疑主義は,ひとり哲学だけでなく,政治や社会にも関連するものとなる。ラッセルにおける論理分析と,政治思想や実践活動との関係-あるいは無関係-に,一つの照明を与えるものは,かれの懐疑主義ではなかろうか。
人々がいろいろな意見のために戦争や迫害をも辞さぬかのような勢いは,右の懐疑主義からは,狂気の沙汰としか見えない。「熱情をもって意見を懐くのは,いつも,この意見に然るべき根拠の欠けているときのことである。」 「序説」に見られるこの言葉は,現代世界の病弊に対しても,適切な処方を与えるものであろう。
失業問題,婚姻,社会主義,ナショナリズム等をめぐっての信念には,どれも,疑わしい事柄に対する強烈な信念が含まれている。ラッセルは,これらに対して,合理的態度をすすめる。つまり,われわれの行動の結果を予測する上での科学的な精神習慣とでも言うべきものを,静かにすすめるのである。それは,科学に普通な態度を,政治社会等の問題にも適用しようとするものである。この態度を宗教に注入すれば,原罪の教えは,おせっかいとなり,自由の干渉につながるものとなる。この合理的態度を倫理問題に注入すれば,道徳的戒律は,厳格に過ぎてかえって守りにくいものとなり,東洋的な仁義礼智信のほうが望ましいものとなるばかりか,今までの善は一転して悪となり,逆に,悪は善となる。このような眼で,第一次世界大戦後の二十年代の世界を眺めたとき,とくにラッセルの眼に映る非合理のあらわれの第一は,戦争の危険を孕むナショナリズムの信念であり,第二は,プラグマティズムとベルグソン哲学に見られる真理即効用説と神秘主義的な考えかたである。
ラッセルが今日,この新哲学に示されたような立場に多くの修正を加えていることは,よく知られた事実である。同時に,大陸の哲学一般に対して-実存主義にも,伝統的宗教の論証法を授けようとする哲学にもあまり重要なものはないという見かたに立っていることも,よく知られた事実である。ラッセルが,基本的には,ルネサンス以来の近代化を是認する立場に立脚することは,今さら言うまでもないが,ラッセル哲学の根幹にある科学観は,本書で,決して無条件な科学過信とはなってない。「(科学の)パイオニアをささえている単純な信仰は中心がくさりかけている。中心から遠い諸国家は,たとえばロシア人や日本人や若き中国の人々のように,いまだに十七世紀的な熱をこめて科学を歓迎する。西方諸国家の人々もまた同様である。しかしながら,(科学の)大司祭たちは,公式に自分らに捧げられている崇拝にいや気がさしかけている。」 このように指摘しながら,ラッセルは,科学的信条に逆らう幾つかの主張を検討した後,前にも触れたように,科学的発見に対する衝動の根を枯らすことのないようにとの希望を表明するのである。
順序は逆になったが,前に触れたナショナリズムの危険については,著者は,我々と我々の愛するものとの関係ならば,本能にまかせておいても安全であろうが,我々の憎しみの対象となる人々と我々との関係は,理性の支配下に置くべきであるとする。ここから,政治的懐疑主義の必要が生ずる。
最初にも述べたように,私は,ラッセルの哲学と政治思想との関連の問題を解く一つの手がかりが,かれの懐疑主義にあるであろうと考えている。私は,ここで,本書の扉の次にある題辞をあらためて想いおこす。それは,「愛し,かつ考えること-それこそ人間精神の真の生活だ」となっている。これはヴォルテールの言葉である。かつて,私は,この題辞を引用した著者の意図をそんたくして,現代世界に絶望しかけた著者が,その絶望の淵から身をひるがえそうとする際の拠りどころとしたものではないかと考えたことがある。しかし,ここに言う「考えること」こそ,まさに懐疑精神ではあるまいか。「考えること」は,「愛すること」と,結びついたものではなく,「愛すること」と「考えること」は,相互に矛盾するものであるかも知れない。「愛すること」は無意識なものでありえても,「考えること」は意識的でなくてはならないであろうからである。そうだとすれば,ラッセルは,右の題辞によって,ヴォルテールのような情熱的懐疑精神を理想としたのだと言えるかも知れない。
ラッセル自身が比較的最近に語ったところによれば,かれの哲学は,分析を主としながらも,正しい行動だという絶対の自信の持てない場合にも力強く行動させてくれる哲学である。すべての信念を懐くにあたって何らかの疑いの要素をもってすべきだとしながらも,その疑いをものともせず力強く行動しなくてはだめだとする哲学である。或る程度の不安は精神の鍛錬に必要であり,その場合,科学知識があれば,疑いのためにすっかり動顛することを避けうる落ちつきが出てくるはずだとする哲学である。これらから,ただちに,ラッセルの哲学と実践活動との関連は出てこない。ラッセルもまた,イギリス哲学の伝統に従って,概念によって経験を説明しようとするのでなく,経験によって概念を説明しようとしているかのようである。
 ラッセル著書解題 |
最後に,ラッセルとヒュームの類似性についてひとこと触れれば,ヒュームは,日常生活の上で私たちがもちろんのこととしている若干の事柄に,少しも正当な理由が付けられぬという結論に達しながら,それによって,生きてゆく上で直面する当面の問題について決心ができぬということになるのでなく,「自然は,手に負えぬ絶対の必然性によって,私たちに呼吸したり感じたりするように判断する決意までさせてきた」というように考えた。ヒュームがこのあたりから習慣という概念を持ち出してきていることは,これまたよく知られた事実である。ラッセルが,自分の哲学と政治思想とは無関係だとしてそのままで済ませている態度には,ヒュームの「習慣」概念にちかいものの実際のあらわれさえ感ぜられるほどである。
本書は,ラッセルが持前の懐疑的態度を,哲学のみか社会政治にも適用した,合理主義の勧めである。(当時,東工大教授,協会理事)
Portal Site for Russellian in Japan
Designed by Akiyoshi Matsushita
* PC site: https://russell-j.com/index.htm
Designed by Akiyoshi Matsushita
* PC site: https://russell-j.com/index.htm
