(巻頭言) 江上照彦「私の三題噺」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第21号(1972年4月刊)pp.1-2.
* 江上照彦(1910~1990)は当時,相模女子大学教授,ラッセル協会理事
私は宗教もイデオロギーも恋愛も,あんまり信用しない。いずれにも,どうも眉唾な感じがぬぐいきれない。と,やにわにこんなふうに言うと,何のことかと読者は小首を傾けられるに違いない。で,そのわけは――
 さて,僧正や聖人たちが衆生を済度したり,悩める魂にやすらい(ぎ)を与えたりといったぐあいの,宗教の効能を認めることに私は決して吝(やぶさか)ではないが,半面,そのゆえに多くの流血と殺戮が生じたことも明らかだ。十字軍の遠征はじめ,歴史にのこる数々の宗教戦争はもちろん,今もたとえば,北アイルランドでカトリックとプロテスタントが,また,ベンガルでは回教徒とヒンズー教徒が,血で血を洗う修羅場を作り出しているではないか。ということであってみると,御利益よりむしろ禍いの種になるのが宗教,というふうに私には見えるのである。先年,ヨーロッパ旅行をした折に,ふとチューリッヒの空港で出会ったのが縁で,同じ宿に泊り,同じ食卓で飯を喰ったある画伯 ―とうとう名前を教えてくれなかったから,いささか変人のようにも思える― が,口をきわめて宗教,ことにカトリックを罵った言葉が,今も私の記憶に残っている。
さて,僧正や聖人たちが衆生を済度したり,悩める魂にやすらい(ぎ)を与えたりといったぐあいの,宗教の効能を認めることに私は決して吝(やぶさか)ではないが,半面,そのゆえに多くの流血と殺戮が生じたことも明らかだ。十字軍の遠征はじめ,歴史にのこる数々の宗教戦争はもちろん,今もたとえば,北アイルランドでカトリックとプロテスタントが,また,ベンガルでは回教徒とヒンズー教徒が,血で血を洗う修羅場を作り出しているではないか。ということであってみると,御利益よりむしろ禍いの種になるのが宗教,というふうに私には見えるのである。先年,ヨーロッパ旅行をした折に,ふとチューリッヒの空港で出会ったのが縁で,同じ宿に泊り,同じ食卓で飯を喰ったある画伯 ―とうとう名前を教えてくれなかったから,いささか変人のようにも思える― が,口をきわめて宗教,ことにカトリックを罵った言葉が,今も私の記憶に残っている。
「ヨーロッパじゅう,どこもかしこも宗教の残虐性の遺蹟みたいなものですよ,やれ宗教裁判,やれ魔女狩り。そのため,どんなに多くの罪もない人間が殺されたことか!」

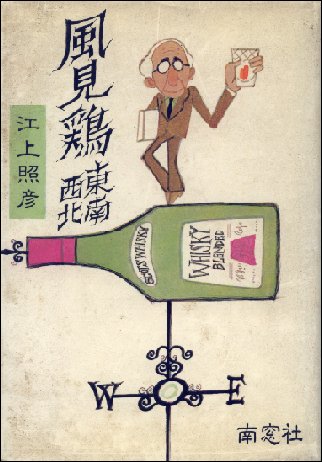 ところで(次に)イデオロギー,すなわち政治的信条というのも,これと一脈相通ずる性質をもっている。たとえば,共産主義の他に対する態度には,独善的で狭量で,わが仏尊しとして,他のいっさいを否定するようなところがあるが,その点では宗教と似たり寄ったりだ。こんなことは今さら私が言うまでもないことで,ラッセルがもうずっと以前に,「ボルシェビズムは宗教である」と言っている。彼によると,宗教とは信念の塊りであり,生活行動を支配するドグマであって,証拠や証明を排斥して,知的でない,情緒的または権威的方法で教えたりさとしたりするものなのだ。だから,「私(=ラッセル)のように自由な知性こそ人間進歩のおもな手段と信ずる者は,ローマ教会についてと同様に,ボルシェビズムにも根本的に反対せざるをえない」という次第だから,私が宗教もイデオロギーも信用できないなどと変な見栄をきっても,つまりはラッセルのうけ売り,物真似をしたことになるだろう。
ところで(次に)イデオロギー,すなわち政治的信条というのも,これと一脈相通ずる性質をもっている。たとえば,共産主義の他に対する態度には,独善的で狭量で,わが仏尊しとして,他のいっさいを否定するようなところがあるが,その点では宗教と似たり寄ったりだ。こんなことは今さら私が言うまでもないことで,ラッセルがもうずっと以前に,「ボルシェビズムは宗教である」と言っている。彼によると,宗教とは信念の塊りであり,生活行動を支配するドグマであって,証拠や証明を排斥して,知的でない,情緒的または権威的方法で教えたりさとしたりするものなのだ。だから,「私(=ラッセル)のように自由な知性こそ人間進歩のおもな手段と信ずる者は,ローマ教会についてと同様に,ボルシェビズムにも根本的に反対せざるをえない」という次第だから,私が宗教もイデオロギーも信用できないなどと変な見栄をきっても,つまりはラッセルのうけ売り,物真似をしたことになるだろう。
しかし,私が今,事新しくこんなことを言うのは,最近ますますその感じを深くする場合が多いからである。なにしろ,共産主義国家のドグマ一点張りが何よりいやである。ソビエトでは,芸術家でさえ政府の気に入らない限り,たとえばソルジェニーツィンの場合のように,ノーベル賞を受け取ることさえできない。反政府的芸術家たちには常に精神病院に送りこまれる危険が待っているのだから,おぞましい限りである。かたわら,中国では,文化革命以来毛沢東語録が国民みんなに拝跪拝誦されることが,住年のわが国の教育勅語の幾層倍だったように見えていたところ,それがこの頃いっせいに書店から影を没したとか。なんのことだかわからない。権力構造のひそかな変化にゆらいすることに違いないが,いずれにしても国民の知るべきことではないのである。
さらにおかしいのは,かって一枚岩の団結を誇った共産主義国のソビエトと中国とが,今では犬猿の仲であることだ。同一宗門内の争いというべきか。そこでまた奇怪なのが,中国がソビエトのやりかたを,'社会帝国主義' と罵っていることである。レーニンによれば,帝国主義とは,資本主義の究極の段階における政策だから,資本主義国特有のものであらねばならない。その帝国主義が,俄然共産国家に現われたのだから,為五郎ならずともアッと驚いたわけだった。主義と称するものの当てにならない一見本がこれである。かつて,小田原の八旬荘に長谷川如是閑先生をおたずねした折に,こんなことを承った。やはり賢人・哲人の言葉だった。

「あたしのことを自由主義者などと人は言うけど,実は主義をもたないのがあたしの主義なんだ。どうしてもってんなら,無主義主義者とでもしておくか・・・。」
最後に,私が恋愛に疑問をもつというのは?……これまたラッセルにかかわりがある。本会会報第十九号に日高一輝氏が「ラッセルの恋愛と結婚」という題で書かれた記事が,私にはたいへんおもしろかった。これによると,ラッセルが結婚または結婚同様の深みにはまった女性は,最初のアリスから最後のエディスまで八人に達する。いかに長命のラッセルとはいえ,これはちと多すぎる感じだが,それはさて,きわめて印象的なのは,ラッセルが決してドン・ファンではなく,その都度至極まじめで真剣だったことである。彼の心をとらえたのは,相手の清楚な美しさ,親切さ,信仰心,知性,行動力,情熱,愛敬,誠実,奔放さ,まじめさなどの彼女らそれぞれのもつメリットで,ラッセルはこれらを材料にすぐさますばらしい女神像を造りあげて愛の讃歌をささげる。こうして恋の虜になって結婚するのだが,するとやがて,これらの女神たちが,彼の肉体をきらったり,ひどく嫉妬深かったり,たいへん浮気だったりで,実はおぞましい女どもだった,というふうになってしまう。仮のいう「歓喜の源泉である恋愛」のもたらしたもののほとんどが,恐ろしい幻滅に変り,耐え難い苦痛に化けるのだ。
世紀最高の知性人であるラッセルにしてからが,恋愛にたぶらかされることかくの如しである。ましてわれわれ凡俗としては,やたら恋の闇に踏み迷わぬ用心の肝要なことはもちろん,恋愛こそが結婚の必然の不可欠の前提のように考えるにも及ぶまい,と覚るわけである。しかし,そんなかたわら,「恋は曲者」というではないか,えたいの知れないのが恋の恋たるゆえんで,そこにこそそのおもしろみも効用もあるのだ,というような意見も出そうだが…。
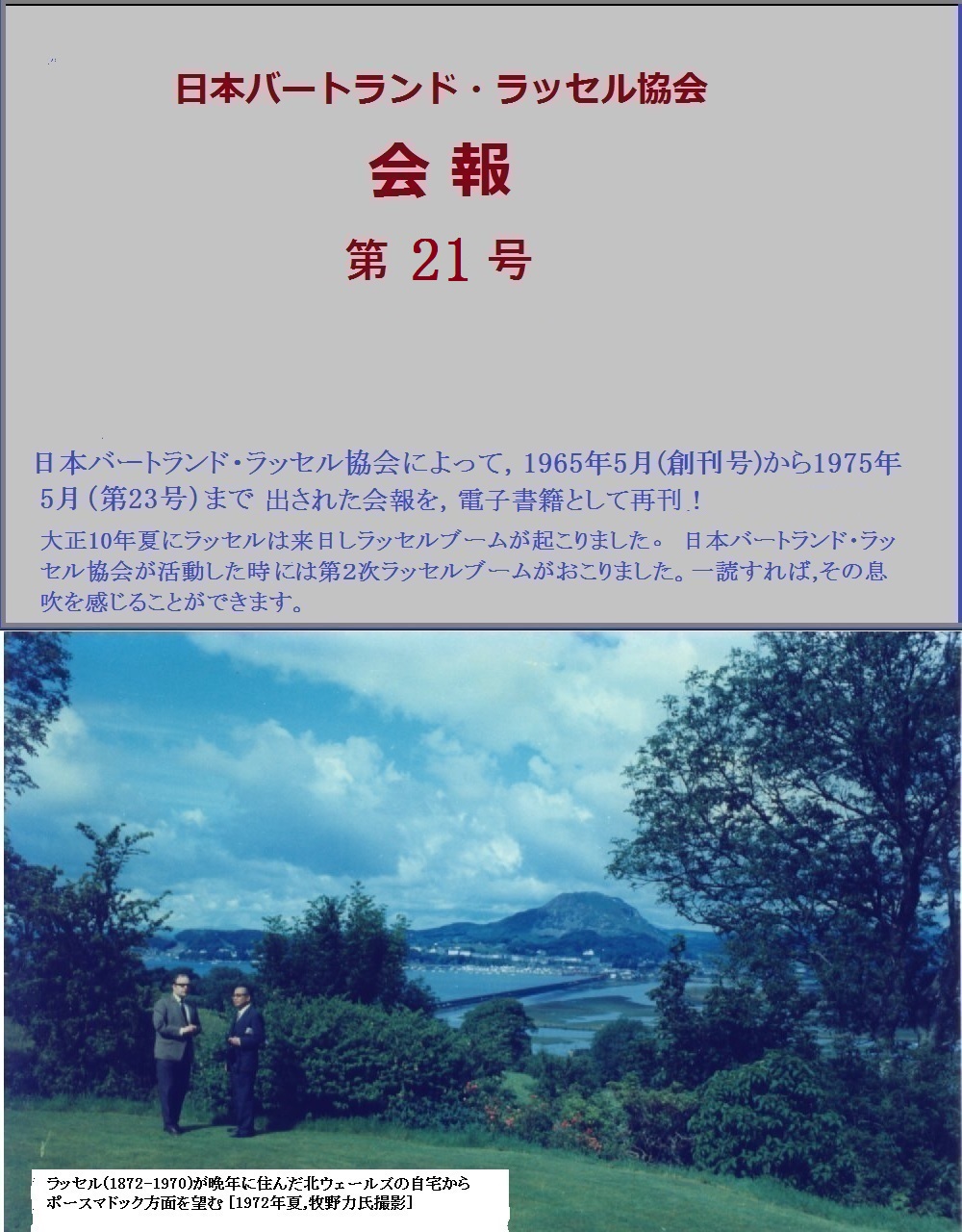
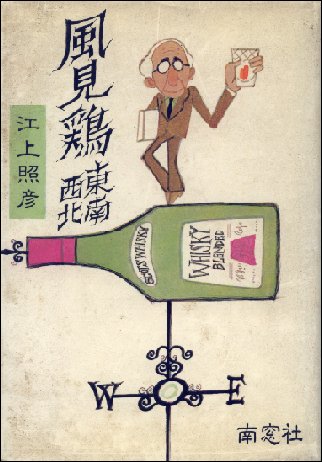 ところで(次に)イデオロギー,すなわち政治的信条というのも,これと一脈相通ずる性質をもっている。たとえば,共産主義の他に対する態度には,独善的で狭量で,わが仏尊しとして,他のいっさいを否定するようなところがあるが,その点では宗教と似たり寄ったりだ。こんなことは今さら私が言うまでもないことで,ラッセルがもうずっと以前に,「ボルシェビズムは宗教である」と言っている。彼によると,宗教とは信念の塊りであり,生活行動を支配するドグマであって,証拠や証明を排斥して,知的でない,情緒的または権威的方法で教えたりさとしたりするものなのだ。だから,「私(=ラッセル)のように自由な知性こそ人間進歩のおもな手段と信ずる者は,ローマ教会についてと同様に,ボルシェビズムにも根本的に反対せざるをえない」という次第だから,私が宗教もイデオロギーも信用できないなどと変な見栄をきっても,つまりはラッセルのうけ売り,物真似をしたことになるだろう。
ところで(次に)イデオロギー,すなわち政治的信条というのも,これと一脈相通ずる性質をもっている。たとえば,共産主義の他に対する態度には,独善的で狭量で,わが仏尊しとして,他のいっさいを否定するようなところがあるが,その点では宗教と似たり寄ったりだ。こんなことは今さら私が言うまでもないことで,ラッセルがもうずっと以前に,「ボルシェビズムは宗教である」と言っている。彼によると,宗教とは信念の塊りであり,生活行動を支配するドグマであって,証拠や証明を排斥して,知的でない,情緒的または権威的方法で教えたりさとしたりするものなのだ。だから,「私(=ラッセル)のように自由な知性こそ人間進歩のおもな手段と信ずる者は,ローマ教会についてと同様に,ボルシェビズムにも根本的に反対せざるをえない」という次第だから,私が宗教もイデオロギーも信用できないなどと変な見栄をきっても,つまりはラッセルのうけ売り,物真似をしたことになるだろう。