杖下隆英「Bertrand Russell の思想の位置と特質-現代思想圏・英国思想史における」(1968年2月)
* 出典:(ラッセル関係語学テキス)杖下隆英・島秀夫(編) Philosophy and Politics(栄光社, 1968年3月刊。95pp.)
* 杖下隆英(つえした・りゅうえい 1929~2017.11.21:東京大学教養学部教授を務める。
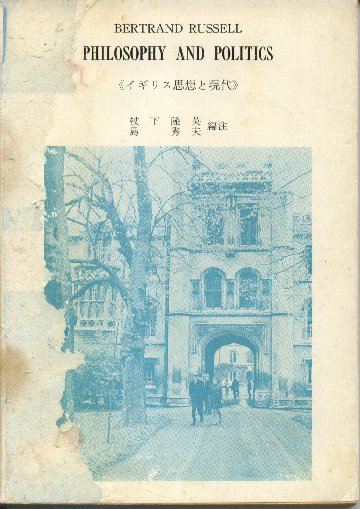 Bertrand Arthur William Russell は,わが国でも周知の現代イギリス思想家といえよう.邦書や邦訳を含めて,彼の自伝や伝記の類も決して少ないとはいえない。したがって,ここでは彼の伝記や数多くの著作への言及は必要な最少限度にとどめ,きわめて多角的で多年にわたる彼の活動を論理学者・哲学者・政治思想家の三側面に大別し,限られた範囲においてではあるが,現代思想圏ならびにイギリス思想史における Russell の見解の位置と特質にふれたいと思う.
Bertrand Arthur William Russell は,わが国でも周知の現代イギリス思想家といえよう.邦書や邦訳を含めて,彼の自伝や伝記の類も決して少ないとはいえない。したがって,ここでは彼の伝記や数多くの著作への言及は必要な最少限度にとどめ,きわめて多角的で多年にわたる彼の活動を論理学者・哲学者・政治思想家の三側面に大別し,限られた範囲においてではあるが,現代思想圏ならびにイギリス思想史における Russell の見解の位置と特質にふれたいと思う.
1) Bertrand Russell は1872年5月18日,イギリス南西岸,Bristol Channel に面する Monmouthshire の Trellock(松下注:正しくは ウェールズ語の Trellech で「トレスレクク」と発音)に次男として生まれた.祖父は Lord John Russell,両親は Viscount and Lady Amberley というRussellの家系はイギリス貴族の名門に属する. だが,3歳の幼少で両親と死別した彼は(London 郊外の Richmond Park 内にある) Pembroke の祖父母の家にひきとられ,18歳で Cambridge 大学の Trinity College に入学するまで(1890年まで)そこで少年時代を過した. Russell の数学的あるいは数理哲学的関心や才能にはこの Pembroke 時代にも特筆すべきものがみられるが, Cambridge 時代におけるその現われはいっそう顕著であった. そして,知的成長と思想形成という点で彼に無上の喜びを与えた Cambridge において彼が知るようになった多くのすぐれた人々のうちでも, Alfred N. Whitehead との邂逅とその後の共同研究は,1910年以後に両者の共著で刊行された全3巻の大著 Principia Mathematica に結実した.
|
| |
|
アマゾンで購入 |
 ラッセルの言葉366 |
理論哲学,そしてそのうちでも知識論のひとつを例にとっても,Russell の哲学は年代による見解の変化のために要約は困難である.一時期ではあるが,彼もイギリス・へ一ゲル学派の影響下にあり,また,プラトン的な概念実在論の傾向を示し(Problems of Philosophy, 1912),さらに--いわゆる phenomenalism を想わせるかのように--物質と精神,主観と客観の区分を感覚的知覚によって一元化する neutral monism (中立一元論)の立場をみせるが(The Analysis of Mind, 1921),後に再びその困難を認めてより常識的な二元的立場に復帰している. だが,第一に,これらの変遷を貫流する彼の認識論や存在論の基調が,一方では彼の大きな哲学的背景をなす,既述の論理学の素材・方法・理論に支えられ,他方では英国固有の経験論の伝統にねざすものであること,そして第二に,哲学の仕事を唯一絶対の全体者との関わりに求める Hegel 流の全体主義に対して, Russell に顕著な傾向は,思想表現およびそれと対応する実在の理論的単位を設定し,それへの論理的な還元や分析を重視する atomistic な個別主義・分析的立場にほかならず,また,思弁的観念論に対する経験的実在論の主張であるということは否定できまい.その基底にはさらに,哲学的思索を能うかぎり科学的な実証性・明晰性・実験的操作に裏づけられた普遍的な知的活動と考える傾向がある. Russell 自ら語っているように,それは無条件にイギリス古典哲学やウィーン学派の主張に左祖するものではないが,いわば同族的類似性という点でそれらと種々の共通性・親近性を示す思想であることに疑いはない.
この Text に収録の2論文,特に Philosophy and Politics (1946年の講演で後に Unpopular Essays, 1950 に所収)は,以上の第三の面における彼の政治思想の一般的見解をもっとも端的な形で,しかも明快な論旨と定評ある単純明断な文体で述べたものである.それは,イデオロギーの時代とよばれる現代において哲学と政治との関係はどのようなものであり,またあるべきかを説く. 極度に要約すれば Russell の主旨は,英国民主主義の確立やアメリカ合衆国の独立に決定的影響を与えた,17世紀イギリスの J. Locke の政治思想のあらわれと Locke の理論哲学としての経験論との結合こそが理想的な政治と哲学との連関である,ということに尽きる. Locke 的経験哲学こそは人々の幸福に資する政治のあり方をつねに実証的論拠に照らして判定し,必要とあれば既成の偏見や教条にとらわれずに改正・進展させる科学的態度とそれに裏づけられた自由および寛容の精神とを助成し,また怠惰な懐疑主義と非合理的な権威や独断からの開放を促す思想だからである.通常の哲学史の評価とは対照的に,Russellは古代ギリシアの Democritus を Locke とともに称揚し,Plato とドイツ観念論の哲学,特に Hegel の絶対的観念論をそれらに対立する反民主主義的哲学として痛烈に批判する. のみならず, Catholicism も Marxism も Nazism も Russell にとっては後者と共通の dogma と偏見にほかならない.
Russell の有名な大著 A History of Western Philosophy, 1945 が功罪と褒貶相半ばする書の典型であるのと同様の意味で,他の思想や思想家に対する,以上の Russell の評価には大きな問題があろう.また, Russell の政治・社会思想上の見解や態度にも時代による変遷がある。たとえば,初期の Russell は処女作においてすでに Marxism の理論的欠陥をつき、それに批判的であったが,全般的にははるかに同調的であった.しかし,ロシア訪問(1920)で革命の実状に接し,当時のロシアの指導者たちと会見したことは,現実の Marxism に対して Russell をすこぶる批判的にしたといえよう. だが,以上のような問題を離れて, Philosophy and Politics のうちには,彼自身の体験に裏づけられた政治思想史の理解,左右いずれの偏狭な dogma や権威・権力をも拒絶する不屈の自律的個性,それに支えられ,西欧的自由を基礎とする社会民主主義的な政治理念,強固冷徹な知性の蔭に秘められた実践的情熱,民主主義がけっきょくは政治的 fanaticism にまさるという彼の歴史哲学的考察と確信等々を読みとることができる.その背後にはさらに,彼自身の既述の哲学的傾向と政治的見解との連関がおのずと看取されるであろう.
Philosophy for Laymen は,上記の講演と共通の論旨を宿しながら,一段と平明に一般市民に対する哲学の意味を論じてる.一言にして言えば,単なる技術(skill)では解決しえない哲学的問題に対して,権威に頼らぬ自由な関心と普遍的な知恵(wisdom)を不断に深め保ち続けてゆくことが,実利的関心を離れて人生を豊かにし,政治的狂信や独断からの解放にも必要である,というのが Russell の主張である.


