バートランド・ラッセル『ライプニッツの哲学』への序(山内得立)
* 出典:バートランド・ラッセル『ライプニッツの哲学』(弘文堂,1959年10月刊。5+3+5+8+287+6pp.)
* 原著:A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz,
1900.(ラッセルが28歳の時に出した著書)
・
邦訳書『ライプニッツの哲学』目次
*
山内得立(YAMAUCHI, Tokuryu, 1890.6.12~1982.09.19):京大教授、京都学芸大学(現・京都教育大学)学長を歴任。1973年に京都市名誉市民となる。1974年に文化功労者。
序(山内得立)

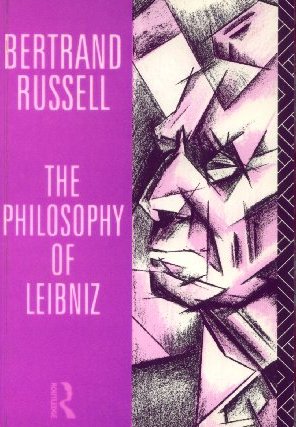 近代思想の主軸は「個性」の問題にある。西洋古代にあっては個体はあったが、個性はなかった。中世の哲学に於ては凡てが神性に覆われて人間の個性は、あるかなきかの状態に置かれていた。ルネィサンスはその字義の示すように、人間が人間として再び生誕することを意味し、神に対して自然を、自然に対して人間を取りもどす運動として起ったことは周知のことである。デカルトは「我思う」ことから出発しようとした。そこに個性の発見があり、近世哲学はここから始まるといわれるのであるが、しかしデカルトやスピノザには未だ多くの中世的残照が尾を曳いていたことはジルソン等の研究によりても明らかである。(Gilson, Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation du systeme Cartesien)。真に個性の問題に目覚め、それの追究を自己の課題とした人はライプニッツであり、その意味に於て近代思想の濫觴(らんしょう)はむしろライプニッツに求めらるべきであるといわねばならない。
近代思想の主軸は「個性」の問題にある。西洋古代にあっては個体はあったが、個性はなかった。中世の哲学に於ては凡てが神性に覆われて人間の個性は、あるかなきかの状態に置かれていた。ルネィサンスはその字義の示すように、人間が人間として再び生誕することを意味し、神に対して自然を、自然に対して人間を取りもどす運動として起ったことは周知のことである。デカルトは「我思う」ことから出発しようとした。そこに個性の発見があり、近世哲学はここから始まるといわれるのであるが、しかしデカルトやスピノザには未だ多くの中世的残照が尾を曳いていたことはジルソン等の研究によりても明らかである。(Gilson, Etudes sur le role de la pensee medievale dans la formation du systeme Cartesien)。真に個性の問題に目覚め、それの追究を自己の課題とした人はライプニッツであり、その意味に於て近代思想の濫觴(らんしょう)はむしろライプニッツに求めらるべきであるといわねばならない。
もとより個性の問題は彼によって正しく全き解決を得たとは言い難いのであるが、少くともこれを主題とした人は彼を措いて外にはなかったことだけは認められてよいであろう。
個性を発見することは人間を見出すことであり、そして人間を見出すことが近代思想を形づくる所以であるとするならば、近代から現代に到る哲学思想の源は正にライプニッツにあると言わねばならない。古代に於てアリストテレスが、中世に於てアウグスチヌスが占めた位置を、近代に於て有するものが正にライプニッツの哲学であったというべきである。
ラッセルのライプニッツ研究はしかし以上の観点からなされたものではなかった。むしろそれとは反対な立場に立って試みられたものであるが、しかし叉1つの別の意味に於て現代思想の濫觴をなしているのである。此書の第1版序文にあるように、ラッセルにとってはモナドロジーは「まるで勝手なお伽噺の一種」とさえ感ぜられたほどである。モナドは1つの個体であるが、これを個性として把握するにはラッセルの立場は余りに非人間的であった。ライプニッツのモナドは、ラッセルによって、アトムとして把握せられた。存在的なアトムとしてではなく論理的なアトムとして把握せられた。しかもそれが現代思想の一つの出発点となったわけである。
ラッセルの此の書の第1版が出たのは1900年であるが、それにつづいて、1910年にはホワイトヘッドとの共著になる「数学原理」(Principia Mathematica)が著作せられている。この浩瀚(こうかん)にして劃期的な大著は、現代の論理実証主義の先駆をなしたものであって、敢えて私事を語ることが許されるならば、私が京都大学に提出した卒業論文「級数と範疇(1914年)も実はこの書の新刊に刺戟せられる所多かったのである。「数学原理」の第2巻は1912年に、第3巻は1913年に出たが、爾来、ラッセルの学的活躍はめざましきものがあり、単に哲学の問題のみならず政治、経済、人倫に亘り、文芸作品さえ匿名によって書かれたようであるが、哲学者としての価値は現代英米のセマンティクに先鞭をつけた点にあることは争われない。それはカント的なる価値の哲学に対して、新しき「意味」の哲学の樹立であった。「意味」を記号として取扱い、思想の技術学を大成した功績は遂に彼をして英米哲学の王座を占むるまでに到らしめた。しかも此等の大業の淵源は実にこの「ライププニッツ研究」にあったのである。従ってこの書の価値は単に過去の一哲学者ライプニッツの歴史的研究にあるのではない。ラッセルは近時厖大なる「(西洋)哲学史」を書いたが、明断にして犀利なる叙述にも拘らず歴史書としては尚一抹のもの足らなさを感ぜしめる。彼は恐らく歴史家ではあるまい。ライプニッツの哲学の研究によって彼の得たものは単に此の哲学者の思想の開明にでなく、そこからして現代の1つの新しき哲学を樹立した点にある。ライプニッツが近代思想の先駆者であるように、この研究書は現代思想の先鞭をなしたものである。現代の論理実証主義を正しく理解するためにはこの「ライプニッツ研究」から始められねばならない。久しく忘れられた此の書が、今、新しく邦訳せられ、しかも訳者に、その人を得たことは、我々の最も喜びとする所であるといわなければならない。敢えて一言を序する所以である。
1959年7月 京都にて 山内得立

