湯川秀樹「『バートランド・ラッセル放談録』について」
* 出典:湯川著『本の中の世界』(岩波書店、1963年年7月刊。岩波新書 n.493)pp.125-133.
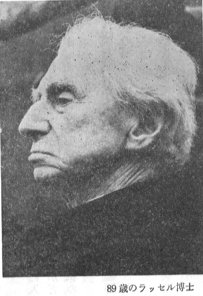 今からもう10年以上も前になるが、私がプリンストンの高等学術研究所に滞在していたあいだの或る日、バートランド・ラッセルが研究所を訪れた。それが初対面であったが、話合う機会はなかった。それから1、2年後、私がコロンビア大学に移ってからの或る日、ラッセルが講演をするという掲示を見た。出かけてみると、会場は超満員で、とても入れそうもないということだったので、講演を聞かずじまいになった。
今からもう10年以上も前になるが、私がプリンストンの高等学術研究所に滞在していたあいだの或る日、バートランド・ラッセルが研究所を訪れた。それが初対面であったが、話合う機会はなかった。それから1、2年後、私がコロンビア大学に移ってからの或る日、ラッセルが講演をするという掲示を見た。出かけてみると、会場は超満員で、とても入れそうもないということだったので、講演を聞かずじまいになった。
ラッセルの名前はひじょうに早くから、日本でもよく知られていた。たしか私が中学校に入る前後のころに、ラッセルが日本に立ち寄って、講演をしたことがあった。当時の私は彼がどういう人か、ほとんど何も知ってはいなかったが、ただ、彼の名前だけは、そのころから私の記憶の中に刻みつけられていたのである。
その後、彼の数多くの著書の中のいくつかは読む機会があった。哲学者の書くものは、難解なのが通例であるが、私が読んだ限りでは、彼の場合にはひじょうにわかりやすく、また、共鳴する点がひじょうに多かった。
そんなわけで、長い間ラッセルに対して親近感をもっていたが、彼と直接交渉をもつようになったのは、1955年以来のことである。それは、いわゆる「ラッセル=アインシュタイン声明」に関係してであった。今日ではこの声明はあまりにも有名であり、それについては今までに何度か書いたから、ここでは繰り返さない。
昨年(1962年)の8月から9月にかけての3週問、ケンブリッジとロンドンで開かれた、第9回、第10回のパグウォッシュ会議に出席するために、イギリスヘ行ったが、この会議のそもそものはじまりは、ラッセルが執筆した上記の声明である。この旅行の直前に私は、彼とワイヤットという人とのテレビでの問答をそのまま記録した 'Bertrand Russell Speaks His Mind, 1960' という本を手に入れた。「ラッセル放談録」とでも訳したらよかろうか。この本をカバンに入れておいたので、ケンブリッジの会議の合間をみて読み出したが、面白くてなかなかやめられない。つい夜中すぎまで読みふけって、翌日の会議に遅刻することもあった。
この一問一答は、1959年の春、4日半にわたってテレビ(BBC)で放送されたのを、そのまま活字にしたものである。「哲学とは何か」からはじまって、「人類の可能な未来」で終る13章からなっている。問答は生き生きとしていて、いたるところにラッセルらしい警句が見出される。どんな調子の問答かを知ってもらうために、いちばんはじめのところを、少しばかり直訳してみよう。(Bard Books 版、p.9)
ワイヤット「ラッセル卿、哲学とは何でしょうか」
ラッセル「そうですね、それはひじょうに異論の多い問題です。あなたに同じ答えを与える哲学者は2人といないだろう、と私は思います。私自身の見解は「哲学とは、正確な知識がまだ得られない事柄についての、思弁から成るものである、」というのです。それは私だけの答えであって、他の誰の答えでもないでしょう。」
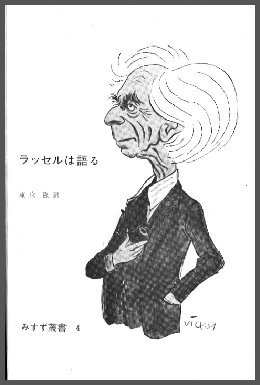 ワイヤット「哲学と科学との違いはなんですか。」
ワイヤット「哲学と科学との違いはなんですか。」
ラッセル「そうですね、大ざっぱにいって、科学とは私たちが知っているところのものであり、哲学とは私たちが知らないところのものである、といってよいでしょう。それは簡単な定義であり、また、そういう理由によって、知識が進むにつれて、いろいろな問題がつぎつぎと哲学から科学へ移されてゆきます。」
ワイヤット「それなら、何事かが確立されたり、発見されたりすると、それはもはや哲学ではなくなり、科学になるのですか。」
ラッセル「そうです。そして、哲学というレッテルがはられてきた、いろいろの種類の問題に対して、今日はもはや、そういうレッテルははられなくなっています。」
ワイヤット「哲学にはどういう効用がありますか。」
ラッセル「哲学には、実際、2つの効用があると私は思います。1つはまだ科学知識にまでなり得ない事柄についての、生き生きとした思弁をつづけることです。結局のところ、科学知識は人類が興味をもち、また、持つべき事柄のごく小さな部分しかカバーしていません。とにかく現在のところ、科学はそれについて、ほとんど知っていないが、しかし、ひじょうに興味のあることが、ひじょうにたくさんあります。そして、私は、人々の想像力が、現在知り得ることだけに限定されるのを望みません。世界についての想像的見解を、仮説的領域にまで拡大させるのが、哲学の効用の一つだと私は思います。しかし、これと同じくらい重要な、もう一つの効用があると思います。それは、私たちが知っていると思っていて、実は知らない事柄があるということを示すという効用です。一方では、哲学とは将来、私たちが知ることになるかもしれない事柄について、私たちに考えつづけさせることであり、他方では、知識らしく見えるもののどんなに多くが、本当は知識ではないということを私たちに気づかせることです。」
こういう調子で問答は進んでゆくのであるが、ここでまず私が感じたことが2つある。第1は、彼がいうところの哲学の定義が、科学について私が考えていることと、ほとんど違わないということである。私は最近10年間、基礎物理学研究所の面倒を見ているが、人から「基礎物理学とは何ですか」と聞かれたら、いつも「それは基礎のはっきりしていないところを研究するのが基礎物理学です」と答えることにしている。ラッセルによれば、それはむしろ哲学に属することになるかも知れない。実際、物理学の最も基礎的な部分と、哲学のある部分とは重なりあっているのであろう。私など自分で知らぬ間に哲学の領域に足を踏み入れ、素人の哲学談義をやって、哲学者のヒンシュクを買っているのかも知れない。
いずれにせよ、科学と哲学とは連続的につながっており、その間にはっきりした一線がひけないし、また私自身も、そういう境界線をつくりたくないのであるが、私の感じた第2の点も、このことと関連している。それは彼によれぱ、科学と連続的につながり得るような領域の全体が哲学であるという点にある。科学と全く性格を異にし、科学と全く独立な学問としての哲学の存在を、少なくとも強くは主張していない。そしてまた、少し後の方で「哲学者の仕事は世界を変えることではなく、それを理解することだ」(同書p.12)ともいっている。そういう意味でも彼は、自然科学者、特に私たち理論物理学者と比較的近いところに立っているように見える。彼が科学者に呼びかけてパグウォッシュ会議を開き、それが数年の間に大きく発展し得たのも、彼の哲学に科学者の共感を呼ぶ要素が多かったからでもあろう。
このことは、彼が合理主義者であると同時に、イギリスの経験主義的伝統を受けついでいることとも関係している。ワイヤットの「今日の哲学の主な傾向は何ですか」という質問に対して大体次のような答えを彼はあたえている。(同書p.12-13)
「それについては英語を話す国々とヨーロッパ大陸の国々とを区別する必要がある。現在はその違いが特に著しい。特にイギリスには新らしい哲学が現われている。そしてそれは、哲学として他から分離された領域を見出そうとする欲求によるものであるように私には思われる。私が前にいった限りでは、哲学は不完全な科学にすぎないように見えよう。そういう見解を好まぬ人たちがある。彼等は言語哲学とも称すべきものを考え出した。それによると、哲学者にとって大切なのは問題に答えることではなく、問題の意味を明らかにすることである。私はこの見解に同意しないが、一つ実例をあげよう。」
というところから、話は俄然面白くなる。
「私は以前、自転車でウィンチェスターに行こうとしたことがある。途中で道に迷ったので、とある村の店へ行って聞いた。
『ウィンチェスターヘの近道を教えてくれませんか。』
聞かれた人は、'奥の間'にいる別の人に呼びかけた。
『客人がウィンチェスターへの一番近道を知りたいとおっしゃる。』
奥から声が聞えてきた。
『ウィンチェスターか』
『そうよ』
『ウィンチェスターへ行く道か』
『そうよ』
『一番近道か』
『そうよ』
『知らない。』
というわけで何の答えも得られず、私は先へ行くほかなかった。まあ、これがオックスフォード哲学というものだ。
そのあと、これとは全く性格の違うヨーロッパ大陸の哲学についての問答あり、この章の最後は「世界を理解することは、長くかかる困難な仕事で、私たちは独断的になってはいけない」という言葉で結ばれている。
次の章は「宗教」についてであるが、ここでは彼の反宗教的な傾向が強くあらわれている。しかし、もしも彼が日本か中国かに生れていたら、特に宗教的か反宗教的かの強い傾向を示すことはなかったのではないかと想像される。その次に「戦争と平和主義」「共産主義と資本主義」など11章がつづくが、その中の「権力」という章の中で、こんなことを言っている。(p.65)
「悪い行動に関しては能率が悪いほどよい。…能率が悪かったために、人類は生き長らえてきた。近頃、非能率性が減ってきたために、人類は絶滅のおそれを生じた。」「あなたが'馬鹿な'殺人者なら捕えられてしまう。不幸にして殺人者はだんだん賢くなってきた。」
こんな調子の問答を読みながら、私はおのずと、昔読んだ中国の古典を思い出していた。実際、『論語』などは孔子と弟子たちの問答の形になっている。しかしラッセルの思想は、ある点では老荘思想に近いという印象を受ける。次の言葉(p.80)など、実に老荘的である。
「ある薬の販売人が、髪が黒くなる薬を私にすすめた。私は彼のすすめに従ってよいという確信が持てなかった。何故かといえば、私の髪が白くなればなるほど、人々は私のいうことをより容易に信じるようになるのだから。」
この問答が行なわれた時に、彼は87歳であった。こんな高齢になっても、こんなに頭がはっきりしており、しかも人間として円熟してくるとは、本当に羨ましいことである。1962年9月のロンドン会議に姿を現わしたラッセル氏は、90歳とは見えない元気さであった。鋭さは消えて、もっと安定した英知が彼の風貌から感じられた。彼は「世界を理解するのが哲学の仕事だ」と定義した。しかし、皮肉にも彼は世界を理解しようとするだけでなく、それをより望ましい方向へ動かそうと、長い間、努力しつづけた。パグウォッシュ運動の発展は、彼の努力が空しくなかったことを、はっきりと示している。この点では、彼の心は老荘思想と全く反対の方向を向いていたのである。
