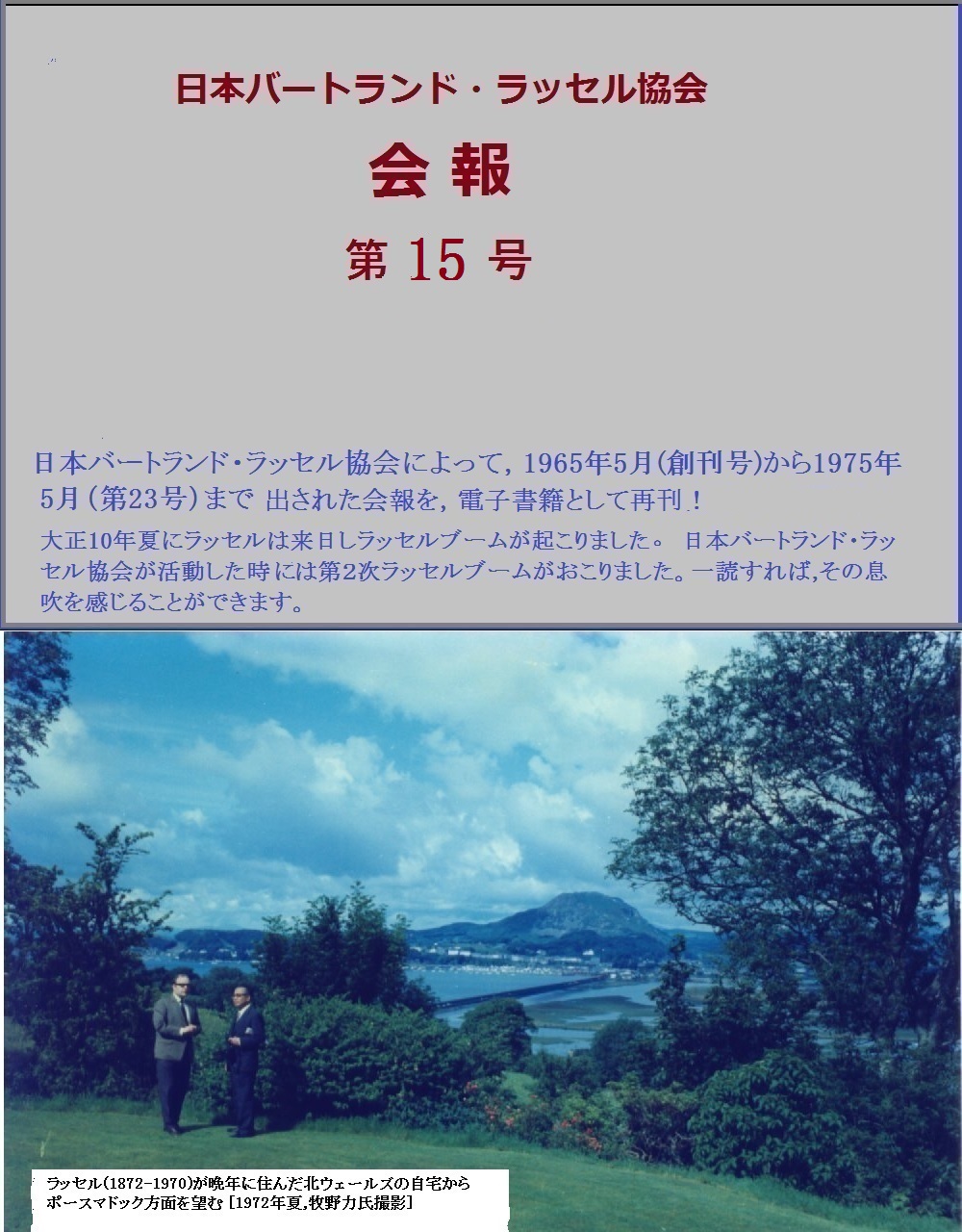柳田謙十郎「バートランド・ラッセルの『愛国心の功過』について」
* 出典:『日本バートランドラッセル協会会報』第15号(ラッセル卿追悼号:1970年5月)pp.3-4.
* (故)柳田謙十郎氏(1893~1983)は,「唯物論」哲学者、文学博士。日中友好協会会長、労働者教育協会会長等を歴任。『柳田謙十郎著作集』全8冊がある。
たしか一九二〇年代,大正の末期のことであったと思う。当時の日本の学界(哲学)はドイツ西南学派,とくにリッケルトの全盛時代で,彼の著『認識の対象』(Gegenstand der Erkenntnis)などは,たんに哲学研究者ばかりでなく,一般の青年学生たちの間にひろくよまれて,異常な売れ行きを示していた。その中で機に敏な改造社(中央公論社とともに,当時の二大総合雑誌社の一つ)では,記者を募集するのに,リッケルトにかんする研究論文をかいてだすことを条件としていたことなどをおぼえている。バートランド・ラッセルが日本に紹介されて「愛国心の功過」(pros and cons of patriorism)という彼の論文が雑誌『改造』の巻頭をはなばなしくかざったのはそのころのことであったと思うが,当時「愛国心」といえば,ひとえにその積極的な肯定面のみが主張され讃美されて,それがもつところの限界=否定面にとき及ぶものはほとんどなかった中にあって,ひとりラッセルが観念論者でありながらも,その長短両面をあわせ論じたということは,わが国の思想界――否,国家権力そのものにたいする重大な警告として,かなり大きな歴史的意義をもった文章であったと思う。(松下注:人によって意味合いがことなるので、注意が必要/ウィキペディアより:「Idealism という言葉は多義的であり、かつて日本では'存在論'については唯心論、認識論については'観念論'、倫理学説については'理想主義'と訳しわけられていた。しかし、現在多く使われるのは、存在論についてであるにもかかわらず、観念論と呼ばれており、物質よりも精神、理性、言葉に優位性を置く理論のことである。)
 この論文は私も少なくとも一応通読したはずであるが,残念なことには(すでに五十年前後も前のこととて)その内容がどんなものであったかはほとんどおぼえていない。しかし「功過」というその題目からおしてもおよそ推量できるように,そのねらいはブルジョア民族主義がともすれば排外主義――偏狭な民族的利己主義につっぱしる危険をもつものであることを,日本人民,とくに日本の天皇制支配層にむかって警戒したものであったように思われる。このことには今日のマルクス・レーニン主義理論の立場からすれば当然すぎるほど当然のことであって,別にとりたてていうほどのことでもないのであるが,彼が英国貴族出身の観念論哲学者であるにもかかわらず,いまから五十年前後も昔の時代に,このことに着目して,しかもこれを日本のもっとも有力な大衆雑誌にかいたということは十分注目に価することと思う。ラッセルのその後の思想と行動は,端的にいえばこの論文の中に脈々として息づいていた,抵抗の精神の一貫した延長であり,発展であったということができるように思われるのである。
この論文は私も少なくとも一応通読したはずであるが,残念なことには(すでに五十年前後も前のこととて)その内容がどんなものであったかはほとんどおぼえていない。しかし「功過」というその題目からおしてもおよそ推量できるように,そのねらいはブルジョア民族主義がともすれば排外主義――偏狭な民族的利己主義につっぱしる危険をもつものであることを,日本人民,とくに日本の天皇制支配層にむかって警戒したものであったように思われる。このことには今日のマルクス・レーニン主義理論の立場からすれば当然すぎるほど当然のことであって,別にとりたてていうほどのことでもないのであるが,彼が英国貴族出身の観念論哲学者であるにもかかわらず,いまから五十年前後も昔の時代に,このことに着目して,しかもこれを日本のもっとも有力な大衆雑誌にかいたということは十分注目に価することと思う。ラッセルのその後の思想と行動は,端的にいえばこの論文の中に脈々として息づいていた,抵抗の精神の一貫した延長であり,発展であったということができるように思われるのである。
今も昔もかわりないことであるが,哲学の歴史はいつも観念論と唯物論の二大陣営に分れて階級的な思想的対決の中で発展してきた。然し唯物論者かならずしも真のマルクス・レーニン主義者とはかぎらないように,観念論者かならずしも資本主義・帝国主義の味方とのみ断ずることができないばあいがある。日本の大塩平八郎の如きは,観念論中の観念論,まぎれもない陽明学の信奉者であったが,彼は人民の味方となって,おのが生命を賭して当時の支配階級の支配政治に反逆した。ラッセルもまた核兵器時代の世界帝国主義のまっただ中に身をおきながら,唯物論者にまけないような強靱な抵抗力をもって戦争と侵略の政治に抗議した。しかも彼は年九十才をこえてもついにその最後にいたるまで一歩もたじろぐことなくその節をまげなかった。
彼をしてこのような道を進むに至らしめたものは何であったであろうか? それは彼が現実を,いかなる偏見や先入見によってゆがめることなしに,正しく客観的に認識する科学的理性と良心の持主であったことに由来するのではなかろうか? 現代は宗教家の中からさえも反体制的な解放運動や反戦運動の味方があとからあとからと続出して来る時代である。観念論哲学者から平和の味方,民族解放戦線の味方が出たからといって別に異とするには足らない。その意味で私は彼の観念論哲学に対しては共鳴も同調もしようとは思わないが,彼の正義と真理にたいする良心的かつ非妥協な行動に対しては深い尊敬を禁ずることができない。
いまソ連のモスクワ大学で現代日本の哲学の講義をうけもっているエリ・シャフナザロワ女史という人があるが,この人の前半世はバートランド・ラッセルの熱心な研究者であった。それが十数年前私の著書をよんでそのロシア語訳をはじめてから,急に方向転換をして私を中心に現代日本の哲学の研究にその生涯をささげるようになってしまった。彼女はこうして人生の途上に牛を馬にのりかえたわけであるが,残念なことには彼女がのりかえたものが(柳田にかんするかぎり)馬でなくてロバか犬にすぎなかったとすればまことに申しわけない次第であると思っている。