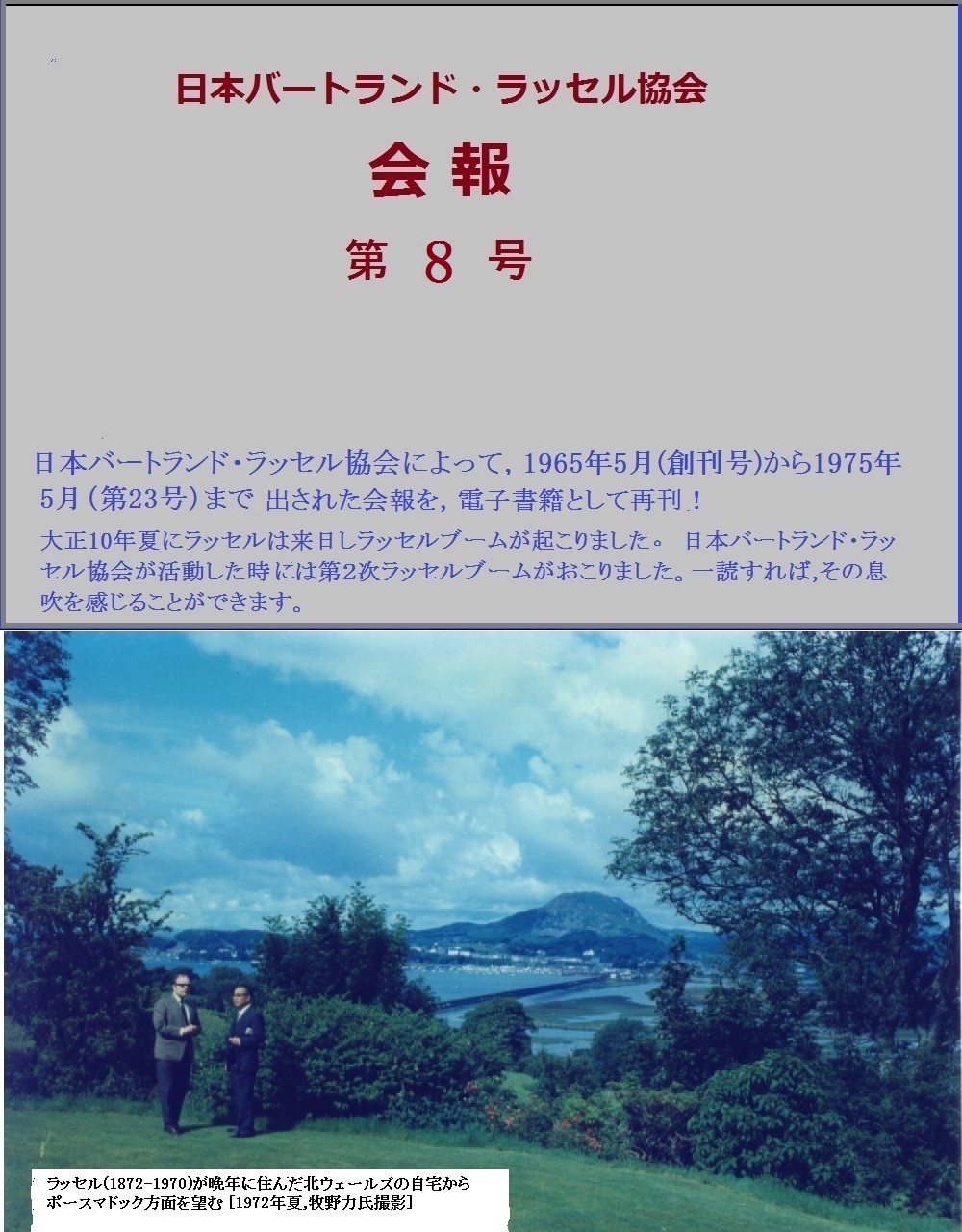バートランド・ラッセル生誕95年記念講演 - 浦松佐美太郎「人間の幸福について」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第8号(1967年7月)p.2
* 1967年5月18日、朝日新聞社講堂で開催された「ラッセル生誕95年記念講演会要旨。浦松氏(1901-1987)は、評論家。
私がラッセルを知ったのは大正年間、第一次大戦後、レーニンやトロツキーの論文が雑誌に載った頃であった。(ラッセルの)「自由への道」(The Road to Freedom, 1918)を読んで、わかったような気分でいたが、今からみると、ほんとに分っていたのではない。学生時代は数行よんで共鳴すると、もう全部わかったような気になるものである。
次のラッセルとの出合いは、昭和6年(1931)、The Conquest of Happiness, 1930 を読んだ時で、私はこれから強い印象を受け、考えさせられた。
この本は、ラッセルが57,8才頃の著述である。円熟した思想をわかり易く楽に書いたものである。
その中で、幸福の条件は、貧困根絶と平和実現の2つであると述べている。ところがそれからずっと後、10年程前、再読したい気持を抱いた。そしてラッセルが30年前に書いたことが、予言的に、今日(1967年)の日本人に考えるべきことを示唆していることに敬服した次第である。
先ず、「幸福の征服」という訳名の「征服(Conquest)」の意味に問題がある。私は山がすきで、山によく登った。最近、山の遭難が多くなると、山を征服するということを、勘違いして、「西洋風な考え方で、山の征服を考えるのはケシカラン、だから遭難者が頻出する。東洋思想は自然を愛し、自然に和する。これでなくてはいけない。」という調子の発言を聞くのである。しかし、これはおかしい。
元来、征服とは、「自分の力で努力して、かちとる」の意味である。(松下注:そのような誤解が生じないように、『幸福の獲得』を訳している訳者もいる。) 登山も然り。それを遭難と結びつけるのがおかしい。正確な意味で、考えたり、話したりしない悪い傾向が、今日ある。これが大会社の経営者までそうである。"合理化"をいい加減な意味に使う。掘り下げて考えない風潮がある。
ラッセルは、「自分は疑わしい(dubious)概念や語では考えない。誰にもわかる言葉で、自分にもわかっていることでしか考えない。」と言っている。
さて、The Conquest of Happiness で、忘れられないところがある。それは、「1920年代のアメリカでは、(それに英国でも)物質面で生活が向上し、自家用車もふえてきた。しかし、道を歩く人々の顔には一人として幸福な顔は見られず、退屈した顔である。果して、これで幸福と言えるだろうか」というところである。
高度成長を云々する日本。電気洗濯機、自家用車、レジャー・ブームの日本は正に30年前のアメリカに似ている。
「これで果して幸福か」というラッセルの予言的な言葉が骨身にしみる! これは、幸福論だけに限らない。ラッセルの反戦論についても同様である。
この前の戦争中、京大の歴史の主任教授が「戦争は文明の母なり」という千頁余の本を一番権威のある本として、一番権威のある書店から出版し、皆読んだ。
ところが、30年前、ラッセルとウェルズは、戦争の愚劣さを説いた。戦争でなければ、発明や改良をしない国家の金の使い方にウェルズも憤慨した。30年たって、その意味が身にしみてわかることを30年前に言ったことに先見の明がある。ラッセルにそういうところがある。幸福論だけではない。
幸福を月賦で買えるように思うところに不幸がある。かつて extrovert, introvert という言葉が使われた。
自分のことしか考えないのはイントロヴァート、社会に思いを向けて考えるのはエクストロヴァートである。教育ママ、立身出世主義はイントロヴァートの例である。大学へ行かないでもえらくなれる。尊敬する人物になれる。ラッセルは、邸内の植木職人に、幸福の姿を見て、称讃している。これでいいのだ。
観光ブームの日本ではどこへ行っても海に近いと、イルカが飛び上っている。それから、自然を汚している。ニューヨークの街では大空の星はみえない。日本では、スモッグの幕が張ってある。
 人間は自然を愛すべきである。自然を理解することこそ、幸福の源泉である。文明の発達、機械化が人間の創意を生かす機会を少なくする。しかし、自分の時間は増加する。その中で、幸福は、自己を離れて存在せず、幸福は自ら努力して求めるものである。また、幸福は次から次へと移っていく。次の幸福の目標を追求し、これを自らの努力で求めなければならない。幸福は与えられたり、そこいらにころがっているものではない、つかむものである。
人間は自然を愛すべきである。自然を理解することこそ、幸福の源泉である。文明の発達、機械化が人間の創意を生かす機会を少なくする。しかし、自分の時間は増加する。その中で、幸福は、自己を離れて存在せず、幸福は自ら努力して求めるものである。また、幸福は次から次へと移っていく。次の幸福の目標を追求し、これを自らの努力で求めなければならない。幸福は与えられたり、そこいらにころがっているものではない、つかむものである。
ラッセルは15才で人生に絶望し、自殺を望んだ。しかし数学を発見し、救われた。数学に没頭し、人生をながめた。人生に絶望した時、"自分は何を求めるか?" その時どうなるかが問題である。自分の一生の仕事に没頭できれば幸福である。
怒れる世代、ビート族、原宿族など、誤れる例であろう。
自己を凝視し、社会へ眼を向けよ。
ラッセルの反戦論も、15才の絶望から始まっている。
ラッセルは先を読んだ。これが思想家の真価である。今日、日本の思想家は、観念体系、建築物のように見事に組み立てられたものを思想とみる悪い傾向がある。知識としての概念を手玉にとって、思弁しているに過ぎない。
ラッセルは具体的な身近なものから始めて、これらを分析、綜合、組み立て、それから、生の人間に密着した生きた物の考え方をしている。これに反し、今日の日本の思想家は、観念的で、紙に書いたものを思想とみて、人間と密着しないので生きたものにならない。
読んでいくうちに、いろいろの印象と感銘をうけることは、ラッセルの本の力である。(文責・事務局)