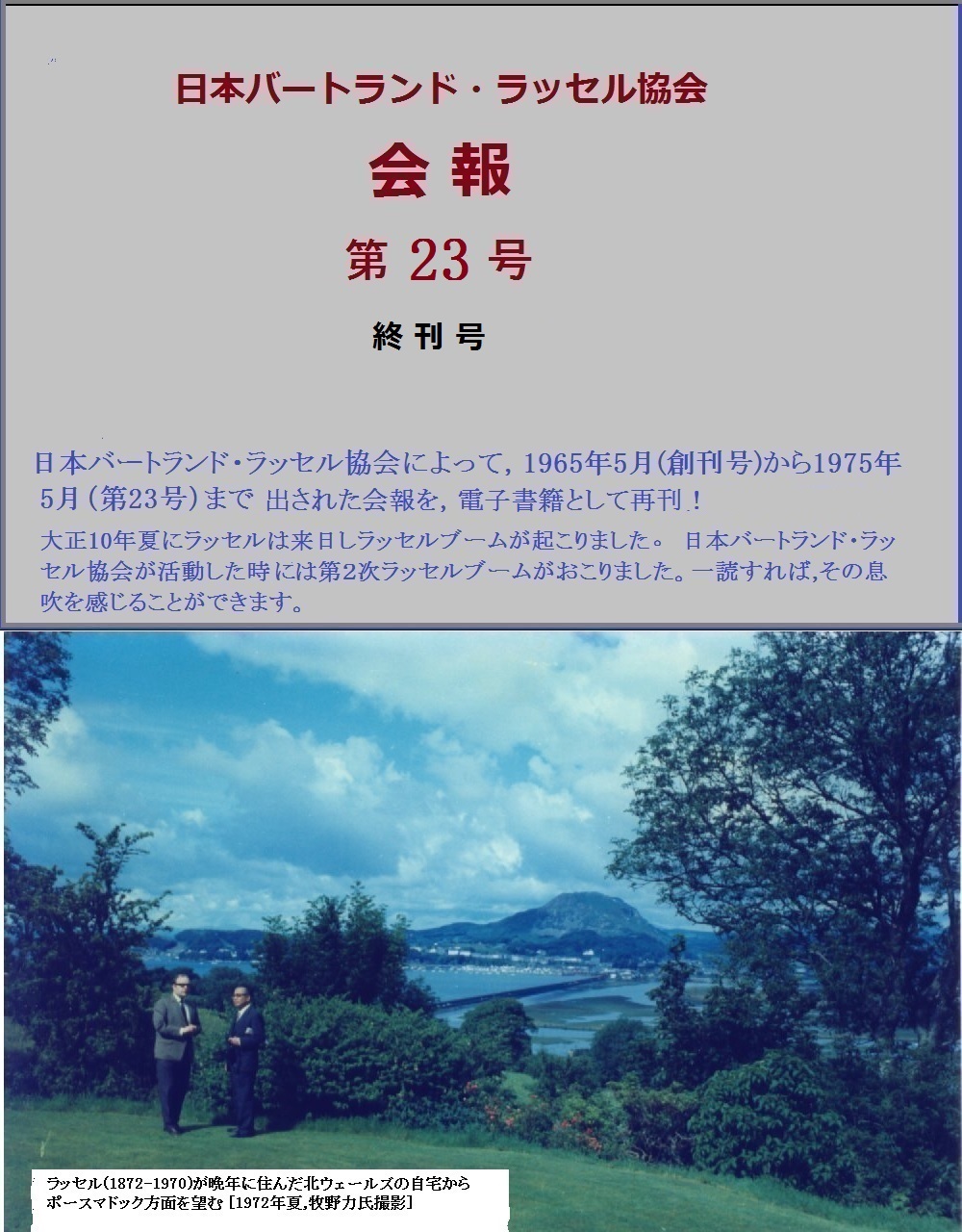鵜木奎治郎「バートランド・ラッセルとプラグマティックな倫理学」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第23号(1975年5月)p.5.
* 鵜木奎治郎(ウノキ, ケイジロウ)氏は当時,信州大学助教授(後に千葉大学に異動されたようである。
ラッセルは『西洋哲学史』(1945年刊)においてデューイの哲学を数学的思惟というより生物学的思惟であると判断している。この判断の当否が最も大きな意味を持って来るのは倫理的判断の場面である。人間を一つの生物と見た時に,生物としての行動がそのまま善につながるかどうか。ラッセルの批判もこの点に集中する。彼はデューイの学説を紹介して「ある信念の善悪は,その信念を持つ有機体にその信念がおこせる諸活動が,その有機体にとって満足すべき(下線は鵜木,以下同様)帰結を持つか,不満足な帰結を持つか,ということに依存する」と言及する。その結果,ラッセルとデューイの見解の相違は「デューイは信念をその帰結によって判断するが,わたしはその原因-過去の出来事に関した信念である場合-によって判断している点」(市井三郎氏の訳)にあるとされる。どうしてラッセルは過去の出来事に,つまりラッセル的に言えば数学的原因だけに,信念を限定したのだろうか。信念は未知の未来を志向して行動を起こす時にこそ必要であり,その時は人は若干非合理的な目的論的思考にとらわれざるを得ないのだ。あれ程現実的な生物学的図式に拘泥したデューイの思考の中にへーゲル的な神秘的永遠的世界像がちらつく理由はここにある。多くの人が(ラッセルを含めて)プラグマティズムの主潮を汎生物学主義ととらえたのは全く正しい。然しその主役である有機体の構造を,環境にたえず恒常的に反応する硬い構造を持った単純な機械と考えるのなら誤っている。生物特に人間は恣意的であり,時には生物学的にみると満足すべき結果が得られぬということがあらかじめ判っていても行動を起こすのである。逆説的に言えば不満足に満足することがあるのだ。こうしてラッセルはサンタヤナのデューイ批判に全く同意し,得々として彼の文章を引用するのである。「現代の科学や倫理学におけると同じようにデューイにおいては,擬似へーゲル的傾向がびまんしている。即ち実体的で現実的なすべてのものを相対的で過渡的な何ものかに解消するばかりではなく,個人というものをその社会的諸機能に解消させてしまう傾向である。」(市井氏訳)
ところがこのサンタヤナは,実はラッセルの批判者でもあったのだ。モートン・ホワイトは近著『アメリカに於ける科学と感性』において縷々として説明する。「サンタヤナの著作のある部分では道徳的な陳述というものはその性格上,経験的であると主張しており,その結果彼は『プリキピア・エチカ』における G.E.ムーアの善に関する見解,即ち善とはその性格上経験的でない陳述に現れた事物に付与された一種の非自然的な性質であるとする見解に断乎として反対するのである。この反対はラッセルが(一時期)ムーアの見解に盲従した時,ラッセルの実体的倫理学と呼んだサンタヤナの批判の中に登場する。そしてこのことは(サンタヤナ著)『理性の生活』において一層鮮明になる。「・・・進歩をテストする普通の方法はいろんな衝動の調和がとれて協力しているかいないかを調べることだというのであり,その結果我々の行為によって影響を受けた精神のすべての共同体のかち得る限り最大限の満足感に導いていく」のである。この満足感は単純な有機体の満足というようなものではない。
そして満足感に一言でも触れない倫理学は単なる饒舌であり脆弁であるとサンタヤナは断罪しているのだが,この満足感こそラッセルがデューイ批判の根拠としたものであった。ラッセル自身の経歴をみてみると,数学,哲学,社会科学,文学とその興味は二転三転しているが,その変遷の最大の根拠は彼自身の満足感ではなかったか(松下注:ラッセルの著作が,数学や哲学を中心としたものから,社会科学関係のものが多くなり,晩年には小説も出したとしても,ラッセルの興味がそのように「二転三転している」というのは非常に短絡的な見方といわなければならない。『ラッセル自伝』は鵜木氏も読んでいるだろうが,精読すればそのような言い方はしないだろうと思われる。)。晩年核文明の脅威について彼は警鐘を鳴らし続けて,その脅威を少しでもまぬかれる為とあらば,彼の嫌悪する教条的マルクス主義の軍門に降るも止むなしと述べたが,これは彼自身がデューイを批判して「力の哲学」というレッテルをはりつけた精神と矛盾するものではなかったか。もしそうなら数学者としての立場から演繹された数学者としては満足すべきこの結論に,非合理的な生物学的人間としての彼は満足できなかった筈である。
(松下注:会報 号に掲載された永井成男「理論と実践」と,第 号に掲載された碧海純一「」を併読することをお勧めします。ラッセルは,「・・・その脅威を'★少しでも★'まぬかれる為とあらば,嫌悪する教条的マルクス主義の軍門に降るも止むなし」などとは述べていません。また,「人類の存続のため,即ち,核戦争を回避するためには,必要とあらば(自分の嫌う)共産主義に譲歩するのもやむをえない」というラッセルの言動がなぜ(ラッセルの)デューイ批判と矛盾するのか,また,それがどうして「数学者としての立場から演繹された,数学者としては満足すべき結論」なのか,私には理解出来ません。ラッセルの主張の反対(一部の偏狭は「自由」主義者の主張)は単純であり,「共産主義に屈するくらいならば人類の絶滅の方を私はえらびたい」という主張です。)