鶴見俊輔「バートランド・ラッセルについて」(1959.7)
* 出典:みすず書房版「ラッセル著作集・月報」より(第5回配本付録)
 バートランド・ラッセルという名前をはじめて知ったのは、昭和十一年に室伏高信(むろふせ・こうしん、1892-1970:「時事新報」「読売新聞」の記者を経て評論家・著述家として活躍。戦時中は軍部批判をし、小田原に隠棲)の本(たしか『青年の書』、『現代文明批判』の合本)を読んだときだった。室伏高信とか、土田杏村、倉田百三のエッセイを通して私は哲学に入っていったので、これらの人々に多くをおうている。室伏の文章は人をひきつける力をもっており、この中に同時代の世界の最もあたらしい思想家達の名前がきらびやかにちりばめられていた。その中にラッセルについての紹介があり、彼がイギリスに行ったときラッセルに会って、フランスに行ったらベルグソンに会いたいと思うが、ベルグソンあての紹介状を書いてくれとたのむ。ラッセルは、ベルグソンとは思想的立場が違うので、紹介状を書きにくいという意味のことを手紙で返事してきた。このラッセルの自筆書簡を室伏は著書の巻頭にファクシミリ版でかかげていた。それからその著書の中では、ラッセルの思想は通俗的なものでおもしろいけれど浅薄であると批判していた。
バートランド・ラッセルという名前をはじめて知ったのは、昭和十一年に室伏高信(むろふせ・こうしん、1892-1970:「時事新報」「読売新聞」の記者を経て評論家・著述家として活躍。戦時中は軍部批判をし、小田原に隠棲)の本(たしか『青年の書』、『現代文明批判』の合本)を読んだときだった。室伏高信とか、土田杏村、倉田百三のエッセイを通して私は哲学に入っていったので、これらの人々に多くをおうている。室伏の文章は人をひきつける力をもっており、この中に同時代の世界の最もあたらしい思想家達の名前がきらびやかにちりばめられていた。その中にラッセルについての紹介があり、彼がイギリスに行ったときラッセルに会って、フランスに行ったらベルグソンに会いたいと思うが、ベルグソンあての紹介状を書いてくれとたのむ。ラッセルは、ベルグソンとは思想的立場が違うので、紹介状を書きにくいという意味のことを手紙で返事してきた。このラッセルの自筆書簡を室伏は著書の巻頭にファクシミリ版でかかげていた。それからその著書の中では、ラッセルの思想は通俗的なものでおもしろいけれど浅薄であると批判していた。
私は室伏から多くのものをまなんだし、彼の著書はおもしろいと思っているが、いまここにあげたようなラッセルについての彼のあつかい方の中に、われわれ日本人が西洋思想に対してとっている典型的な態度をみる心持がする。世界の最新の思想家をもっとも早く紹介しようとし、イギリスならばラッセル、フランスならばベルグソンが一流ときめて会見を申しこみ、文通したりしようと努力し、その仕事を紹介するときにも、少しけなしながら紹介してみることでこれら世界の一流よりすこし高いところに自分をおくことができると信じている。おそらく室伏はラッセルの主な著作を読んだことはないであろう。浅薄だがおもしろいという評価を昭和十年ころの日本で室伏高信がラッセルについてするということに、われわれは近代日本思想史上の一つの里程標としての意味をみる。
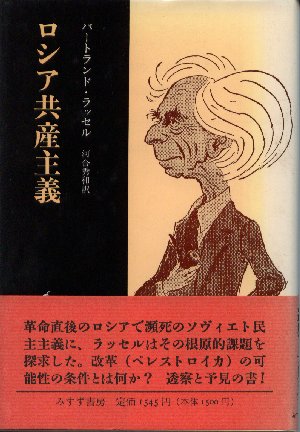 ラッセルの著書の中、最も重大なものと言われるプリンシピヤ・マセマティカ(注:ニュートンのプリンキピアを意識し、ラテン語からとられていることから、「プリンキピア・マテマティカ」)を私は読んでいないが、ラッセルの数ある著作の中で再評価を必要としているものは、第一次大戦直後に書かれた『ボルシェヴィズム-その理論と実際-』(注:河合秀和訳『ロシア共産主義』)であろう。アンドレ・ジイドの『ソヴィエット紀行』は、共産主義にかたむいたジイドが実際にソヴィエットに行ってみて、ソヴィエット共産主義についての賛美に条件をつけてゆくなりゆきを書いたものである。このジイドのソヴィエット論は、第二次世界大戦直前の世界の左翼インテリによって非難されたりはしたものの、主な点で正しいことがスターリン批判以後に左翼インテリにとってもあきらかになった。ジイドにとって、第二次大戦直前まであきらかでなく、知識人一般にとってはフルシチョフの出現まであきらかでなかった、このソヴィエット文明の性格は、第一次大戦直後のソヴィエット文明論であるラッセルの著書に、はっきりととらえられている。現在までのところでみるとソヴィエット文明論としては、同時代のマルクス主義者よりはラッセルの方がはるかに早くするどくソヴィエットを見ていたように思われる。ラッセルはこの著書で、アジア的な伝統をせおった新しい宗教としてのソヴィエット共産主義の役割を全体としては高く評価し、同時にこの中で、ヨーロッパ的な分析的知性をもったトロツキーやゴーリキーたちが、不安定な位置にあることを見ている。イギリス議員団の一員としてわずかの期間の旅行の中で、また革命直後の事件すべてが流動的な時期に、よくもこれだけはっきりしたソヴィエット像をつくれたと思う。このことは、ラッセルの持っているするどい'感'によって支えられてはじめてできたことである。ラッセルが専門の数理論理学からとおくはなれたところにある歴史の問題、現代史の問題を考えるとき、彼を支えるものは、数理論理学によって養われたディダクティヴな(演縄的)方法でもなく、むしろ高度にアブダクティヴ(仮設形成的)な方法であり、このアブダクティヴな方法は根本においてひろい経験によって養われた常識と感によって支えられている。
ラッセルの著書の中、最も重大なものと言われるプリンシピヤ・マセマティカ(注:ニュートンのプリンキピアを意識し、ラテン語からとられていることから、「プリンキピア・マテマティカ」)を私は読んでいないが、ラッセルの数ある著作の中で再評価を必要としているものは、第一次大戦直後に書かれた『ボルシェヴィズム-その理論と実際-』(注:河合秀和訳『ロシア共産主義』)であろう。アンドレ・ジイドの『ソヴィエット紀行』は、共産主義にかたむいたジイドが実際にソヴィエットに行ってみて、ソヴィエット共産主義についての賛美に条件をつけてゆくなりゆきを書いたものである。このジイドのソヴィエット論は、第二次世界大戦直前の世界の左翼インテリによって非難されたりはしたものの、主な点で正しいことがスターリン批判以後に左翼インテリにとってもあきらかになった。ジイドにとって、第二次大戦直前まであきらかでなく、知識人一般にとってはフルシチョフの出現まであきらかでなかった、このソヴィエット文明の性格は、第一次大戦直後のソヴィエット文明論であるラッセルの著書に、はっきりととらえられている。現在までのところでみるとソヴィエット文明論としては、同時代のマルクス主義者よりはラッセルの方がはるかに早くするどくソヴィエットを見ていたように思われる。ラッセルはこの著書で、アジア的な伝統をせおった新しい宗教としてのソヴィエット共産主義の役割を全体としては高く評価し、同時にこの中で、ヨーロッパ的な分析的知性をもったトロツキーやゴーリキーたちが、不安定な位置にあることを見ている。イギリス議員団の一員としてわずかの期間の旅行の中で、また革命直後の事件すべてが流動的な時期に、よくもこれだけはっきりしたソヴィエット像をつくれたと思う。このことは、ラッセルの持っているするどい'感'によって支えられてはじめてできたことである。ラッセルが専門の数理論理学からとおくはなれたところにある歴史の問題、現代史の問題を考えるとき、彼を支えるものは、数理論理学によって養われたディダクティヴな(演縄的)方法でもなく、むしろ高度にアブダクティヴ(仮設形成的)な方法であり、このアブダクティヴな方法は根本においてひろい経験によって養われた常識と感によって支えられている。
ラッセルは、マルクス主義のように歴史を科学として記述するという方法に大きな望みをもたなかった。しかし、数学におけるような分析的知性の拡大適用によって、社会問題、人生問題がすぐさまとけるとも思わなかった。学問の根本は分析的知性にあると考え、それをその適用できる限り適用するとともに、ひろく人生の事実と親しむことによって生じる市民的な常識と感に主としてたよりながら、人生の問題、社会の問題、歴史の問題を考えてゆく他ないと考え、この後の者(常識と感)の養成の場所として市民としての公的・私的諸活動があり、また歴史の学習があると考えた。人生・社会・歴史を科学的にあつかうことについてのラッセルのひかえめな態度が、結局において、これらの問題について、ラッセルを同時代の学者よりもすくなくあやまつことを可能にさせたのである。
このようなラッセルの認識論、方法論が、ラッセルの哲学的著作を支え、マルクス主義者による社会診断ともちがい、論理実証主義者による社会診断ともちがう、独自の性格の社会診断を生みだしている。
ラッセルじしんは、自分の著作の中で、数理論理学に関するもののみが重要な仕事で、あとのものはつけたりで、通俗的なものだと何度か言い、このようなラッセルの評価が、先にのべた室伏の評価の根拠になっているのかもしれないが、私は、ラッセルの自著についての評価をそのままうけいれる必要はないと思う。(評論家)
 バートランド・ラッセルという名前をはじめて知ったのは、昭和十一年に室伏高信(むろふせ・こうしん、1892-1970:「時事新報」「読売新聞」の記者を経て評論家・著述家として活躍。戦時中は軍部批判をし、小田原に隠棲)の本(たしか『青年の書』、『現代文明批判』の合本)を読んだときだった。室伏高信とか、土田杏村、倉田百三のエッセイを通して私は哲学に入っていったので、これらの人々に多くをおうている。室伏の文章は人をひきつける力をもっており、この中に同時代の世界の最もあたらしい思想家達の名前がきらびやかにちりばめられていた。その中にラッセルについての紹介があり、彼がイギリスに行ったときラッセルに会って、フランスに行ったらベルグソンに会いたいと思うが、ベルグソンあての紹介状を書いてくれとたのむ。ラッセルは、ベルグソンとは思想的立場が違うので、紹介状を書きにくいという意味のことを手紙で返事してきた。このラッセルの自筆書簡を室伏は著書の巻頭にファクシミリ版でかかげていた。それからその著書の中では、ラッセルの思想は通俗的なものでおもしろいけれど浅薄であると批判していた。
バートランド・ラッセルという名前をはじめて知ったのは、昭和十一年に室伏高信(むろふせ・こうしん、1892-1970:「時事新報」「読売新聞」の記者を経て評論家・著述家として活躍。戦時中は軍部批判をし、小田原に隠棲)の本(たしか『青年の書』、『現代文明批判』の合本)を読んだときだった。室伏高信とか、土田杏村、倉田百三のエッセイを通して私は哲学に入っていったので、これらの人々に多くをおうている。室伏の文章は人をひきつける力をもっており、この中に同時代の世界の最もあたらしい思想家達の名前がきらびやかにちりばめられていた。その中にラッセルについての紹介があり、彼がイギリスに行ったときラッセルに会って、フランスに行ったらベルグソンに会いたいと思うが、ベルグソンあての紹介状を書いてくれとたのむ。ラッセルは、ベルグソンとは思想的立場が違うので、紹介状を書きにくいという意味のことを手紙で返事してきた。このラッセルの自筆書簡を室伏は著書の巻頭にファクシミリ版でかかげていた。それからその著書の中では、ラッセルの思想は通俗的なものでおもしろいけれど浅薄であると批判していた。