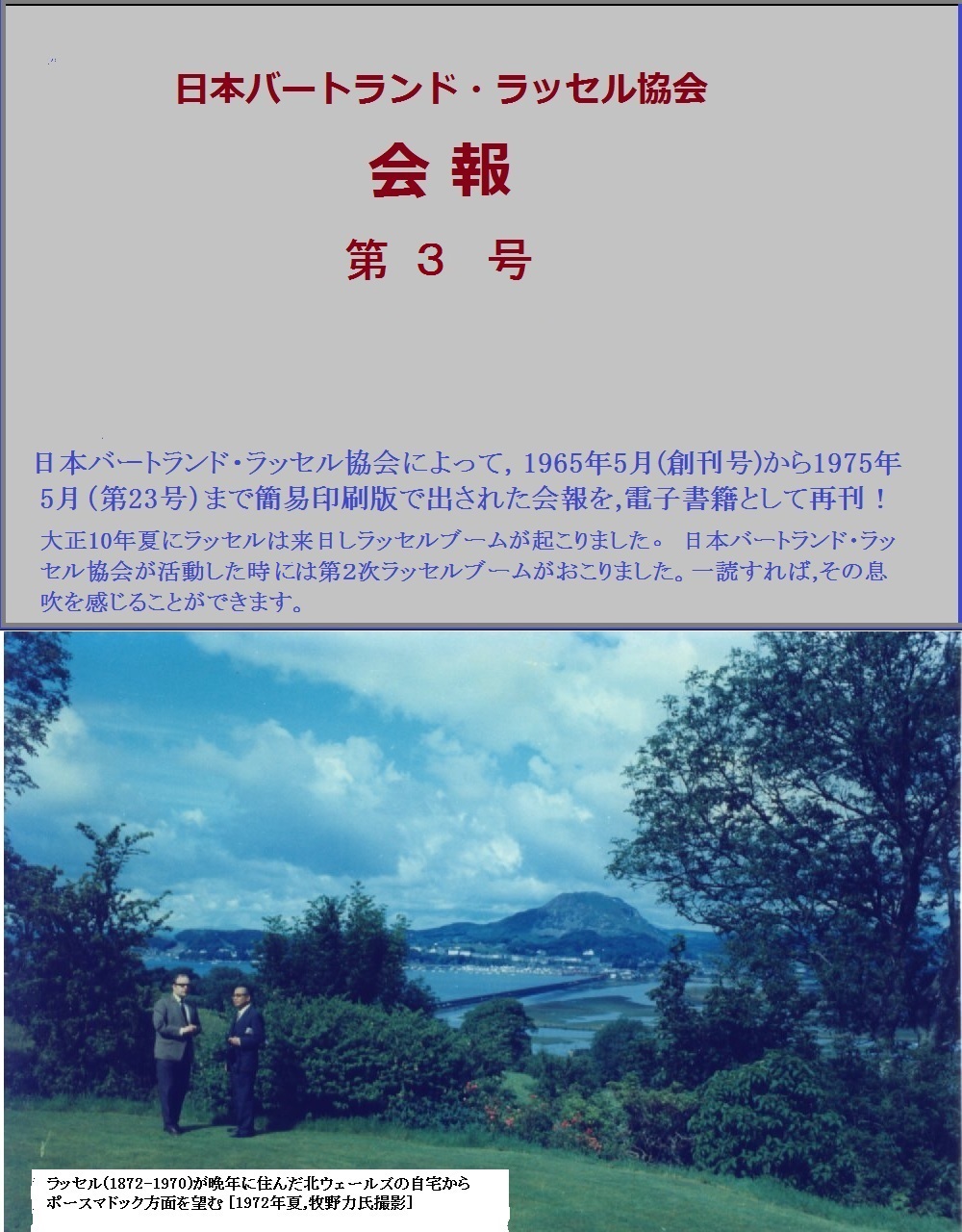
ラッセル協会会報_第3号
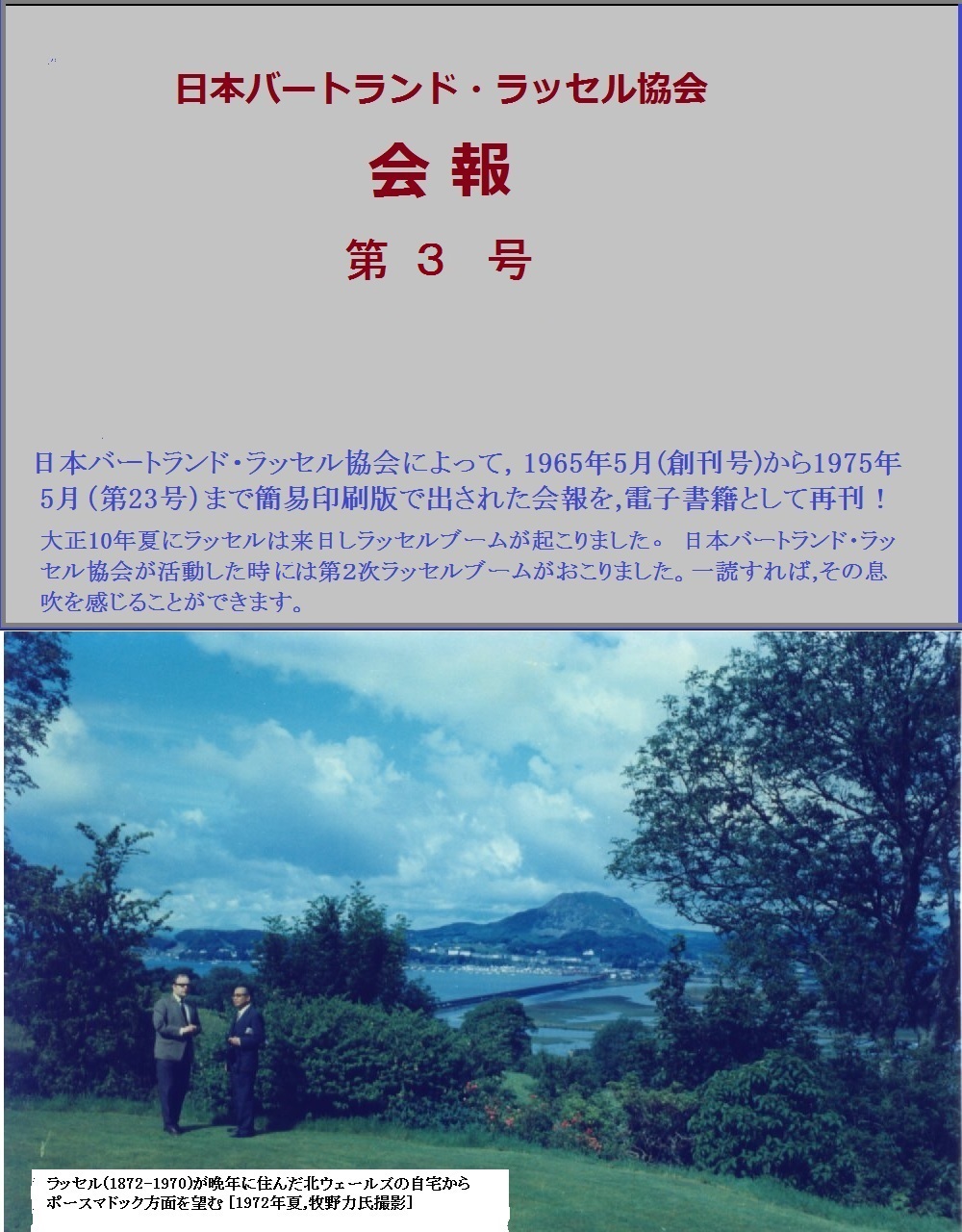 ラッセル協会会報_第3号 |
「ラッセルが専門の数理論理学から遠く離れたところにある歴史の問題,現代史の問題を考えるとき,彼を支えるものは,数理論理学によって養われたディダクティヴな方法でもなく,むしろアブダクティヴ(仮設形成的)な方法であり,このアブダクティヴな方法は根本においてひろい経験によって養われた常識と勘によって支えられている。ラッセルはマルクス主義のように歴史を科学として記述するという方法に大きな望みを持たなかった。しかし,数学におけるような分析的知性の拡大適用によって,社会問題,人生問題がすぐさま解けるとも思わなかった。学問の根本は分析的知性にあると考え,それをその適用できるかぎり適用すると共に,ひろく人生の事実と親しむことによって生じる市民的な常識と勘に主として頼りながら,人生の問題,社会の問題,歴史の問題を考えてゆく他ないと考え,この常識と勘の養成の場所として市民としての公的,私的活動があり,また歴史の学習があると考えた。人生,社会,歴史を科学的に扱うことについてのラッセルの控えめな態度が,結局において,これらの問題について,ラッセルを同時代の学者よりも少なく誤まつことを可能にさせたのである。氏は,「高度にアブダクティヴな方法」,つまり「ひろい経験によって養われた常識と勘」に支えられて,「歴史を科学的に扱うこと」に「控えめな態度」をとったことが,ラッセルを浅薄にしたどころか,かえって個々の歴史事象に対して「あやまつこと」の「より少ない」判断を下すことを「可能に」したと言っているのである。それはラッセルが学問と歴史をはっきり区別したことの指摘である。
|
| |
|
これをアマゾンで購入 |
「時問についてのわれわれの知識には二つの源がある。一つは,(1)見かけの現在の内部での継起の知覚であり,もう一つは(2)記憶である。思い出は,比較的昔か最近かという知覚されることのできる質を持っており,その程度によって私の現在のあらゆる記憶を時間的順序に並べることができる。しかしこの時間は主観的であり,歴史的時間とは区別されなければならない。歴史的時間は,現在に対して「さきだつ」という関係を持ち,その関係を私は見かけ上の現在の内部の変化の経験から知る。歴史的時間の中では,私の現在の記憶はすべて「今」あるが,それらが正しいかぎり,それらは歴史的過去における出来事を指している。どんな記憶も,それが正しくなければならないという論理的な理由はない。論理が示すことのできるかぎりでは,私の現在の記憶はすべて,たとえ歴史的な過去がまったく存在しなかったとしても現在とまったく同じでありうる。従って,過去についてのわれわれの知識は,われわれの現在の記憶の分析だけによっては発見されない或る要請に依存している。」これをもって直ちにラッセルの史観を示すものととることはできまい。しかしそこには,歴史の存立についての積極的肯定はない。「思い出」の「質」は認められているけれども,質を洪水のように溢れさせるものではない。在るのは知性による懐疑的な分析だけである。ラッセルに時としておもしろい歴史を書かせ,あたかもシーリアスでないかのごとき感じのものを書かせるのは,じつは歴史についてのこのような根本観念であり,さらには,へーゲリアニズムのような歴史の壮大な絶対化に対する嫌悪,歴史事象に向けられた知的常識家の眼であると,現在のわたくしは考えている。(終)