竹尾治一郎「あとがき 1997_ バートランド・ラッセルの哲学的主張の変遷」
* 出典:竹尾治一郎『言語と自然』(関西大学出版部、1998年3月刊)pp.299-302.
* 竹尾治一郎((たけお じいちろう、1926年12月31日 -) 氏は当時、関西大学名誉教授(1997年に定年となり、南大阪大学教授/分析哲学・科学哲学が専門)
ラッセルの哲学的主張がよく変わったことはむしろ伝説的と言ってもよく,そのかぎりでは冒頭に引用した C.D.ブロードの批評は正しい。不適当な説の変更は,その連続よりも貴重であるから,必要な情報は,何が変わり何が連続したかである。そこで,ラッセルの哲学のとりわけ重要な変更と思われる点を次に挙げておきたい。
(1)真理論,詳しくは,信念あるいは判断の真理についての分析を挙げることができる。この問題はもちろん「プリンキピア(数学原理)』の領域には含まれない。1906年から1912年までのラッセルは,信念を多項関係と考えた。「AはBがCを愛していると信じる」(たとえば,「オセロはデズデモーナがキャシオを愛していると信じる」)と考えよう。括弧内は,Aが偽な信念をもつ場合である。Aは、BがCをRしていると信じるという場合,「信じる」以外の動詞R(ここでは「愛している」)は二項を関係づける動詞である。しかるに,事実として,判断が偽なときは,それがBとCとを関係づけない。これを説明するために、「信じる」をA,B,R,Cの四項からなる関係と考えるのが「多重関係説」である。そこで,もし,オセロはデズデモーナがキャシオを愛していると信じることが真な信念を表すなら,オセロ,デズデモーナ,愛する関係、キャシオという四項が,信じるという関係で関係づけられる。そこで,もし信じられているような事実が存在し,Aが真な信念をもつなら,信念内容の後の三項の順序づけと,事実においてそれらにそれぞれ対応する存在者の順序づけとが対応する。他方,もしAが偽な信念をもつなら,それらは対応しない。しかしながら,1918年の「論理的原子論の哲学」(第IV講,§3)では,ラッセルはこの説を撤回した。すなわち,(イ)信じられている命題を独立の存在者として扱うこと,および(ロ)「オセロはデズデモーナがキャシオを愛していると信じる」における,「愛している」という動詞を,信念における対象(関係項)の一つとして扱うことを,ともに不適当と彼は認めた。(これについては,私の『分析哲学の発展』(法政大学出版局,1997),pp.49-58を参照されたい。) しかし,信念その他の「命題的態度」(ラッセル,上掲書,§4)についての,最終的に満足すべき解決といえるものは,現在にいたるまで与えられていない。
(2)一般の認識論的立場に関しては,より重要な変更が生じた。最初,1914年,1917年の頃,ラッセルは「可能な場合には常に,推論された存在者は,論理的構成によって置き換えられなければならない」ということを,「科学的に哲学することの最高原則」と考えていた。もしわれわれが対象aを直接に見知るのではなく,その存在を単に推論するだけとするなら,われわれは、いかにしてaが、直接に見知られる対象の集合bからの論理的構成であるか,あるいは,それに還元されるか,あるいは,それから演繹されるかを示そうと試みるべきである。もしこれができれば,aとbとは同じ事実内容をもち,aの知識はbの知識と同じだけ確実である。世界についてのわれわれの知識は,そのようにして確実な基礎の上に再構成されるであろう。このような方法で言語と世界との関係を分析することが,ラッセルの論理的原子論全体の着想にほかならなかった。したがって,有意味な命題とは,原子的命題か,あるいはそれらから真理関数的に構成された命題か,あるいは一般的命題(すなわち,、それらが世界についての原子的事実のすべてであるという「一般的事実」をいう命題)かである。しかしながら,認識論的に確実な原子的命題は,一人称的報告「私の前に赤い斑点がある」のような言明でなければならない。すると,そこで言われるような対象は,直示的に定義される(指差される)対象である。しかし,もし原子的言明の内容が私の経験なら,どうして物理的対象がそうした心的経験から構成されるのであろうか。ラッセルはその構成に満足できなかった。そこで彼は,そうした経験を,どの特定の心にとってのデータである必要もない,だれかによって感覚されることからは独立に存在しうる「知覚対象」と考えるようになった(1921)。しかし最終的には,「感覚データ」という語を用いることを完全にやめ,物理的対象は,普通に科学者がそうしているように,推論された存在者であると考えるようになった(1948)。こうして,論理的原子論のプロジェクトは放棄されたのである(1948,191-97)。これらの変更は重要であるが,またそのどの段階でも,ラッセルは,数学ならびに外部世界の知識(心理学を含む)の確実な基礎があることを確信し,それを合理的に解明することを,終生求めつづけたのである。なお,上の(1)およびこの(2)に見たような真理の考え方はすべて,伝統的な「対応真理説」の上でのヴァリエーションであったということができる。
(3)ラッセルの哲学的主張の一貫性という点からいえば,それが最も明瞭に現れるのは,「プリンキピア』が書かれるまでの初期の著作,『幾何学の基礎』(1897),「ライプニッツ哲学の批判的解説』(1900),「関係の論理」(1901),「型(タイプ)の理論に基づく数学的論理学」(1908)などにおいてである。これらを通じての基本的主張は,(イ)哲学的研究において,ラッセルが関心をもったものが常に「真理」であり,とくに数学や論理学の研究では,彼にとっての最も重要な問題は,数学の真理に基礎を与えること-したがって、相対的に・真理が無矛盾性(整合性)に優先することになる-、そして,(ロ)その際,最初に関係概念を導入し,その関係項として対象を定義するアプローチをとること-たとえば,幾何学では,点が関係の項として定義される-である。『プリンキピア』以後の哲学的著作でも,(イ)はもちろんであるが,(ロ)もまた,しばしば形を変えて繰り返されている。上の(2)の論理的構成も,関係の理論を用いて行われるのである。この点については,C.W.Kilmister,"Russell"(New York; St. Martin's Press,1984)が参考になる。(なお,この時期のもう一つの重要な著作,「指示について」(1905)については,本書の第一論文でやや立ち入った考察を行ったので,参照していだければ幸いである。)
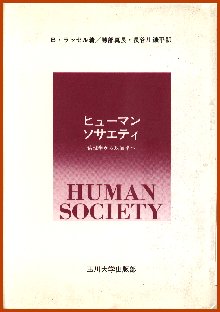 (4)メタ倫理学では,極端な言い方をすれば,ラッセルは「現代倫理学理論の主な理論的立場を,実質的にはすべて採用した」。最初,「倫理学の原理」(1910)においては, G.E.ムーアに従って,直観主義の倫理学を古典的な形に要約し,情動主義が流行するずっと前に,倫理的判断の非認知主義的理論(1935,1938)を採用し,最後に老年にいたって,『倫理と政治について見た人間社会』(Human Society in Ethics and Politics, 1955/*1954のまちがい)において,倫理的自然主義に賛成するようになった。最初と最後の著作によって,ラッセルが倫理学に残した貢献は明らかである。ただ情動主義から自然主義への移行については,ラッセル自身は,「それほど重要な変更をしているという意識がなかった」(書簡)と言っている。これは,ある重要な意味において,もっともなことであろう。事実判断に対する検証手段としての「知覚」に相当するものが,道徳の判断にはない。つまり,倫理学は知識としての基礎をもたない。ヒュームからムーアまで,またラッセルの後では論理実証主義者の何人かによって,受け継がれて来た伝統では,道徳の判断が最終的に訴えるものは,ある種の直観ないしは感情である。『人間社会』が書かれる少し前に(1944),ラッセルは述べている。「なぜすべての欲求の満足が善であると私は考えるのだろうか。ただ,慈愛(benevolence)のような感情の故にである。それ故,欲求の満足が善であるという原理から,慈愛が美徳であることを導くことは循環である」。
(4)メタ倫理学では,極端な言い方をすれば,ラッセルは「現代倫理学理論の主な理論的立場を,実質的にはすべて採用した」。最初,「倫理学の原理」(1910)においては, G.E.ムーアに従って,直観主義の倫理学を古典的な形に要約し,情動主義が流行するずっと前に,倫理的判断の非認知主義的理論(1935,1938)を採用し,最後に老年にいたって,『倫理と政治について見た人間社会』(Human Society in Ethics and Politics, 1955/*1954のまちがい)において,倫理的自然主義に賛成するようになった。最初と最後の著作によって,ラッセルが倫理学に残した貢献は明らかである。ただ情動主義から自然主義への移行については,ラッセル自身は,「それほど重要な変更をしているという意識がなかった」(書簡)と言っている。これは,ある重要な意味において,もっともなことであろう。事実判断に対する検証手段としての「知覚」に相当するものが,道徳の判断にはない。つまり,倫理学は知識としての基礎をもたない。ヒュームからムーアまで,またラッセルの後では論理実証主義者の何人かによって,受け継がれて来た伝統では,道徳の判断が最終的に訴えるものは,ある種の直観ないしは感情である。『人間社会』が書かれる少し前に(1944),ラッセルは述べている。「なぜすべての欲求の満足が善であると私は考えるのだろうか。ただ,慈愛(benevolence)のような感情の故にである。それ故,欲求の満足が善であるという原理から,慈愛が美徳であることを導くことは循環である」。
メタ倫理学におけるラッセルの発展の跡は,彼の哲学全体の特徴を明らかにする。ラッセルは,最後まで,プラグマチズムと,知識の本性についての全体論的説明に対して敵対的であった。そうした立場からの倫理学の擁護は,あらゆる種類の客観的真理を投げ棄てることによってのみ可能となる,とラッセルは考えたからである。したがって,彼はデイヴィドソンの哲学の或る側面や,ローティの,客観性とは最大限の合意にすぎず,合意が事物の本性に一致するか否かを問うことは意味がないという結論には,絶対に同意しなかったであろう。また,真理が哲学にとっての問題であったから,彼が後期ウィトゲンシュタインが示唆したようなことすべてに,深い反感を抱いたのも当然であった。(了)

