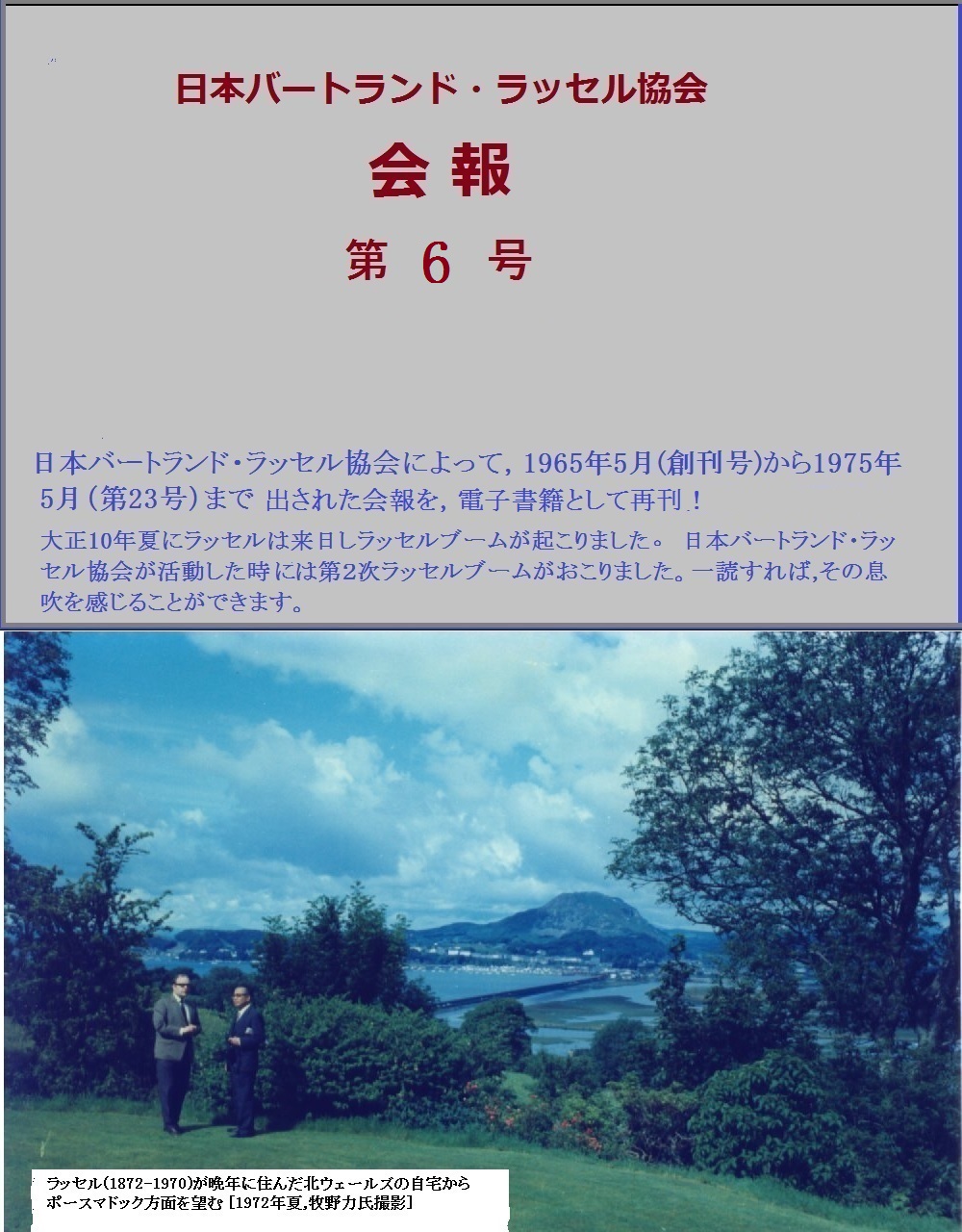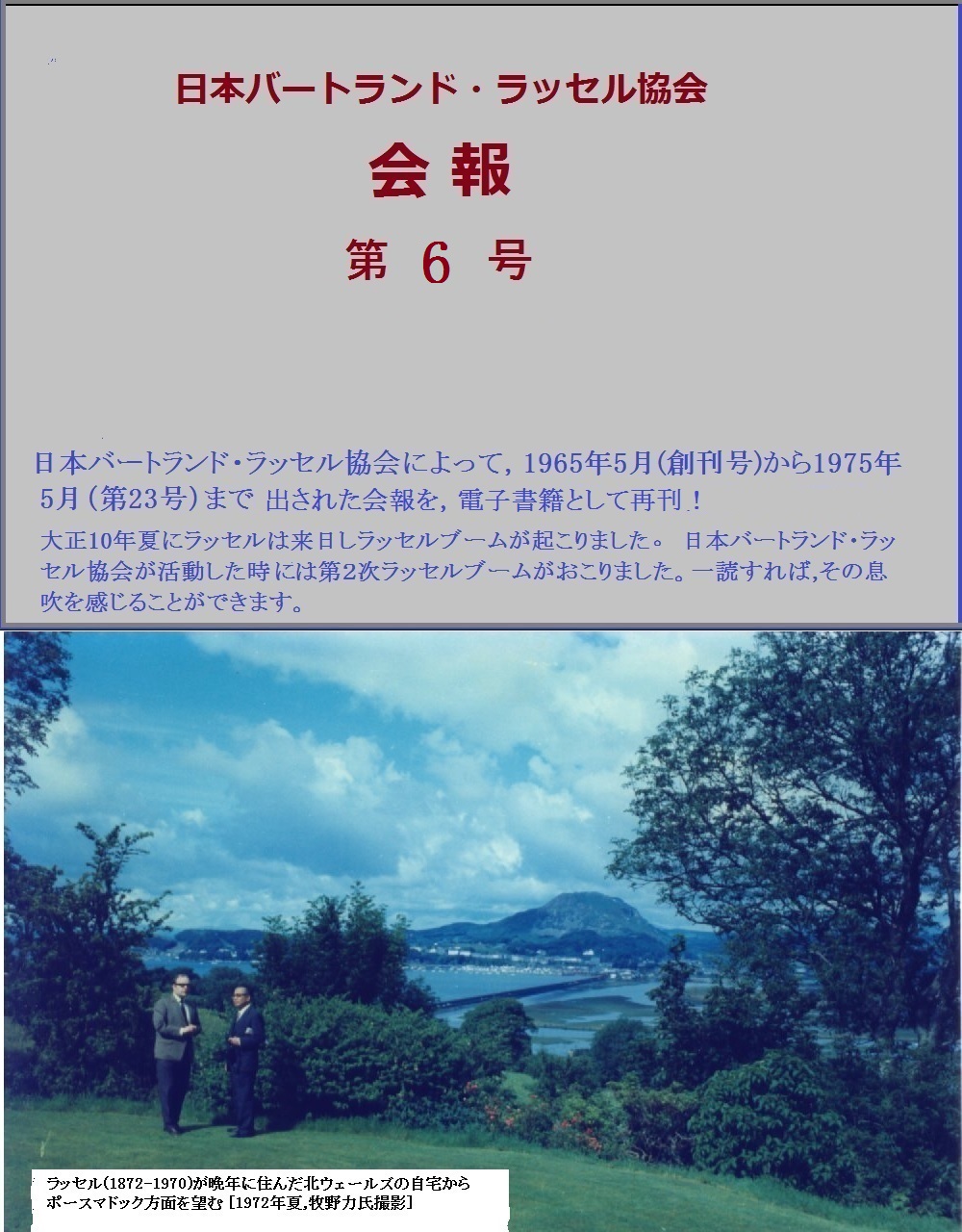高峯一愚「学生とともに(バートランド・ラッセルの)『民主主義とは何か』『自由とは何か』を読んで」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第6号(1966年12月刊)p.9-11.
* 高峯一愚氏(1906~2005.01.18)は当時、東京都立大学教授
1
(八王子の)大学セミナーハウスでのテキストとしてこれ(ラッセルの『民主主義とは何か』『自由とは何か』)を選んだことについては、とり立てて意味はない。昨年は岩波新書の務台理作著『現代のヒューマニズム』を読んだが、ほぼ似たような、一応読んで誰にも何か感想を述べられそうなもので、あまり値段の高くないものをという基準で、たまたまこれをということになったまでである。その結果が成功であったかどうかは、以下の学生諾君の感想その他から読みとっていただきたい。
2
はじめにあらかじめ読んできているところに基づいて、めいめいに感想を述べてもらったのであるが、それらの主要なものは次のようであった。
(1)ソ連体制をナチス的全体主義と同一視しているのは安易にすぎないか。
これはけだし、最初から '民主主義'の意味について、最も直接的実際的に、「鉄のカーテンの西側では、最高権力を社会の成人の過半数が握っている意味だ」といういい方をし、それに対して「東側では、それが '民主主義者'と自称してきた特定の少数の人たちが行なう軍事的独裁政治のこと」(p.3)だと言い、続いて「現在のロシアが民主主義という言葉を使うのは全く例のない恥知らず」などと言われていること、スターリン(1879年12月9日=グレゴリオ暦12月21日-1953年3月5日)の集団農業制度や強制労働収容所の、民主主義政体の下では実行できなかったような残忍さをあげたり(pp.19-20)、「ロシア革命以後、共産主義者の主流派の理論から、どれほど僅少でも逸脱すると例外なしに誰も、死刑か終身刑の憂き目にさらされる」(p.32)といい、『自由とは何か』(What is Democracy, 1953)の「精神的自由」の項では「もし諸君が遺伝問題で軽卒にも、ほとんど全部の有能な遺伝学者たちの説く学説に同意でもしようものなら、北極地方の荒廃地で、奴隷状態の下に、運河掘りか金山で働くように、収容所に送られるだろう」(p.75)とソ連におけるルイセンコ学説を諷刺し、「政治と自由」の項にいたると、明らかに「自由妨害が一人前に本格的になると、どの国もナチス・ドイツやソ連にならざるをえない」といってナチス・ドイツとソ連とを同列におき、さらには「自由の問題についてはソ連は、ナチス・ドイツよりも絶対悪い。ナチス・ドイツはある程度の海外旅行を許し、外国人のドイツ国内旅行をも、特別な反対理由がなければ、入国を許したが、ソ連政府は、ロシア人の国外退去も許さず、外国人のロシア入国許可は、ロシア側がその外国人を無害な、あるいは、だましやすい人物と考えた場合だけだ」(p.86)とまで非難している点等を指すものであろう。(松下注:ラッセルのロシアに対する物言いは、スターリンの死後、かなり変っていく。)
これら以外にも全篇に一貫しているラッセルのソ連体制の独裁主義に対する非難は、彼のイギリス流の民主主義の考え方からすれば当然のことではあろうが、またこれが、平易端的な表現を要求されるラジオ放送であり、かつそのなされた時期が第二次世界大戦後間もない頃で、現在の国際感覚からしては、もはやそぐわなくなっていること、これは本書の「あとがき」で訳者も述べられているように(p.114)、むしろわれわれはそのような「変移の底にあるもの」をこの講演から読みとるべきだといえようが、しかしスターリン時代についての知識をその時代人として知ることのなかった今日の若い世代にとって違和感を抱かしめることは止むをえないところであろう。なお同様の違和感は、「アメリカで、如何なる外国人に入国を許すかは無教育な警官の掌中に握られており」、「その警官は、欧州の物理学者たちは全部、頭のよいアメリカ人たちによって発見された原子爆弾の秘密を頭の悪いロシア人に売りつけるスパイ共だと信じていて、その結果は、科学者の国際会議がアメリカで開催不可能となってしまい、海外旅行の自由を持たないアメリカ科学者たちが欧州で成された価値ある研究結果を視察できず、もしこの次に戦争が起こると、その戦争におけるアメリカの技術的能率が低下するのは、ほとんど確実だ」(p.50)といっているところにも、ローゼンヘルグ夫妻事件の空気のまだ残っていた頃の所論として露呈されている。
「スターリン主義=ソ連の共産主義体制=ナチズム」というこの単純な公式化に対する批判は
(2)ラッセルには社会経済史的観方がない、
という形でもなされ、これと関連してであろうが、
(3)階級闘争観が不徹底だ、
という批判ともなって表明される。
ラッセルは最初からマルクス流の階級闘争観をそのまま認める者ではないであろうが、しかも『民主主義とは何か』の「権力悪」の項等において、「権力を握っている者が、古今東西、恐怖心に駆られている場合を除けば、権力を持たない人間の幸・不幸に無頓着」(p.18)であること、「民主主義の恐らく他のどれにもまさる一つの長所」として、「国民のほとんど半数近い人々が政府を悪党どもの寄り集りだと信ずること」(p.46)をあげ、ラッセルがルーズベルト大統領時代のアメリカにいた頃の経験として、ラッセルの会った人々の多くがルーズベルトを危険な精神異常者と考えていたこと、ラッセルはこの人たちの批評には同意しなかったが、しかし、多数の人々が一国の元首にこういう意見を砲くことは、全く健全なものと考えたと述べている(p.48)。また「民主主義強調論の第一の、かつ最も首肯させる論拠は人間の利己心であり、あるグループの人たちが他のグループに対し権力を握ると、前者はほとんど常に後者を虐待するもので、白人は黒人を、貴族は農民を、男は女を虐待してきた」とし、「珍らしい環境の中での短期間の例を除けば、支配するグループがその相手の支配されるグループに対して寛容慈悲の精神で振舞ってきた事例は発見困難であろう」(p.52)といっていることは、やはり人類社会における階級闘争を認めているとせねばならない。『自由とは何か』(What is Freedom, 1952)の「自由と思想」の項でも、「権力を握っているグループが、権力のない者たちに犠牲を払わせて自分たちが豊かになるのを控えるなどということは、まずないことである」といい、その注目すべき実例をソ連が与えてくれているとして、「マルクスは純然たる考えちがいをして、もし私有財産が廃止されると、経済的不正がなくなると想像したが、財産が権力の唯一の形式であることを(松下注:財産が権力の唯一の形式であるという間違った想定をしており)、また、少数派の掌中に権力を集中しながら私有財産を廃止すると、偏狭な暴君政治を確立することになるだけでなく、最大の経済的不正を必ず招くことなどを彼(マルクス)は認識しなかった」(p.89)としている。こうなるとむしろ、階級闘争観については、ラッセルの方がマルクス以上に徹底していたともいえるようであり、マルクスは過去の支配階級に対してだけはその権力悪によって独裁に陥ることの必然性を強調したが、未来の共産主義社会については、もはや人間の権力悪は出現しないかのような楽天観に立つという誤りを犯していたということになろう。なおマルクスの階級闘争観には暴力革命の是認が含まれているけれども、ラッセルでは、あくまで民主主義という合理性によって権力悪の独裁化を牽制することが強調されているのである。マルクス主義の階級闘争観を公式的に強く印象づけられている今日(1966年頃)の多くの学生に対しては、それを解きほぐすとすれば、一応その立場に立ちながら内在的批判に訴えるのでなければならないように思われる。
(4)イギリスの民主主義を安易に礼讃しすぎてはいないか。
これは、この講演が、最初から「鉄の力ーテン」の西側と東側とを対照させて東側の独裁、西側の自由と、両者をきわ立たせるという構想をとっていることからのおのずからなる結果であろうが、それにしても、人間の権力悪一般に関しては、イギリスの歴史においても露呈された種々の権力悪にもふれており、「イギリスの上流階級が政治権力を独占していた間、彼らはスターリンとそっくり同じ悪事を働いた」(pp.20-21)ことを指摘している点も見逃すべきではなかろう。しかし彼が「第一次世界大戦の罪」について「その最大の罪が、ドイツ、オーストリア、帝政ロシアに分けられるべきであることに、ほとんど誰も異存はないと思う」とし、第二次世界大戦についても、「その全責任は、公正にみて、ヒットラーにかかっていることに疑いない」(p.25)と言っているが、前者についてはイギリスの侵略主義的な植民政策に全く責任はなかったか、後者について第一次世界大戦後の対独賠償案等について連合国側に全く不手際はなかったか等の問題に少しもふれようとしていないところには、やはり冷徹な理論を求める者にとっては物足りないものの感じられることを否みえない。(松下注:もちろんラッセルは、イギリスの侵略主義的な植民政策や第一次世界大戦後の対独賠償案に対する非難をいろいろなところで言っている。『民主主義とは何か』『自由とは何か』はヨーロッパの一般市民向けのラジオ講演であることに注意)
(5)歴史教育を「特定の国の歴史としてではなく、文化の進歩の歴史として教えられるべきだ」とする(ラッセルの)意見には同感である、
ただラッセルがこのような場合にも、歴史を「自分の国だけを不当に強調して教えてはならず、どの国も例外なしに悪いことをやって来たこと」を教えるべきだ(p.35)と言って、「どの国にも立派なことを為した人もあることを」とはつけ加えていない。ここにラッセルに見られる支配者、すなわち権力悪に対する抵抗権という感覚が流れているのであろう。
3
最後に、「現代の民主国家が直面している諸問題の一つ」としての「専門家活用の問題」(p.13)に関して、二院制というわが国の議会制度が参議院に求めたところが、この「専門家活用」の意味を持つものではなかったかということが取り上げられ、参議院の現状に対する種々の批判がなされ、また「英国民は大抵のイギリス人警官を友人とみなしているが、多くの国々では、警官は恐怖の眼でみられている」(p.15)という点に関して、警官がもともと国民の安全を護ってくれるわれわれの友人であることを疑う者はなかったが、デモの警戒に当る際の警官の態度については、全くデモ隊に対する挑発と敵意以外のものを持たない異様な存在としてしか映らないという激しい抗議が一般であった。こうしたギャップをどうして埋めるか、考えなければならない重要な問題であろう。
4
この報告は必ずしもゼミナーにおける諸発言の忠実な記録ではない。散漫たらざるをえなかった諸発言を整理するために、後でわたくしなりに前後の脈絡をつけなければならなかった産物であることを諒とされたい。
一晩と半日をかけてのゼミナーのテキストとして、問題の種切れを心配しないでもなかったが、次々に話に花が咲いて、取り上げる予定の問題を幾つか残すことになった。