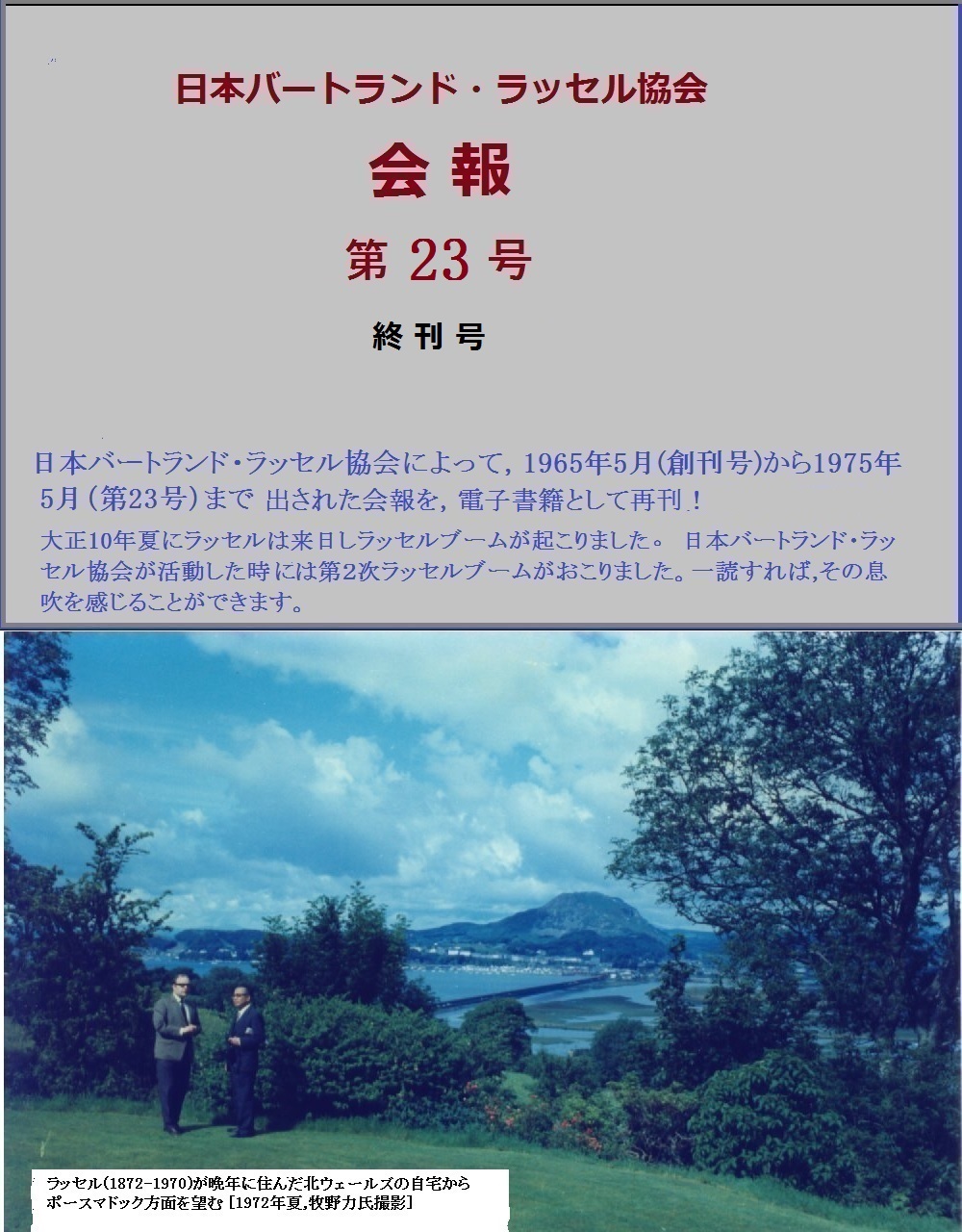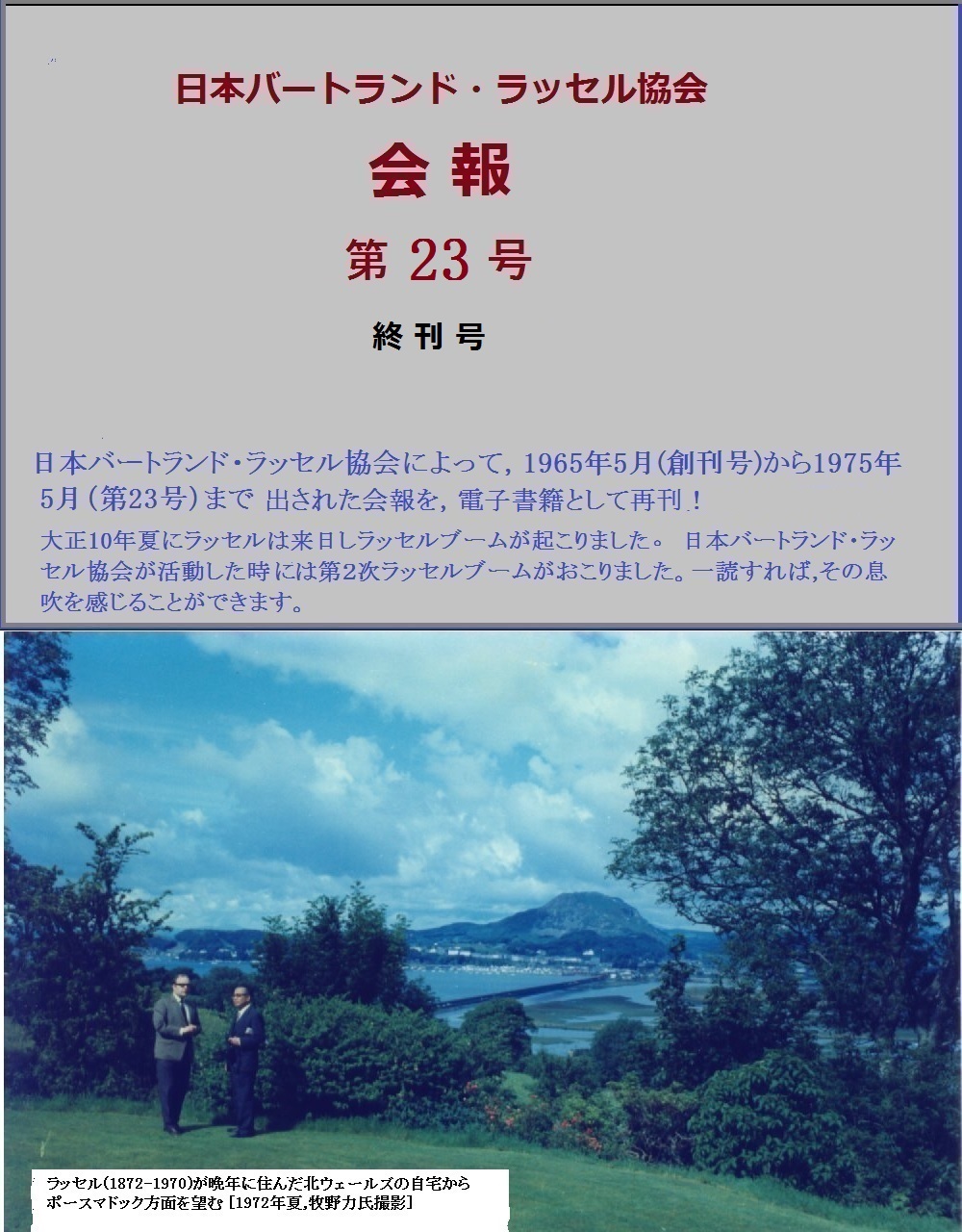鎮目恭夫「死を見つめる心-ラッセル,アインシュタイン,湯川秀樹」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第23号(1975年5月)p.15.
* 鎮目康夫氏(1925~2011.7.28)は,科学評論家。ラッセルの Human Knowledge, 1948 の訳者。
「人は自分の死ならまだしも,肉親や親しい友の死にはたえがたい」というようなラッセルのコトバを,たぶん15年以上前,ラッセルの『人間の知識』の翻訳をしていたころだったと思うが,私はどこかで読んで,ほんまかいなと思い,以来時おり思いだした。他方,数年前に湯川さんがテレビで「私にとっては,他人や人類の死よりは自分自身の死のほうが,やっぱり大問題」だというようなことを語ったのに,私は深い親和感を覚えた。
もちろんラッセルも,自分自身の死をひとごとのように客観的に感じていたわけではない。例えば,80歳ごろ書いた「いかに老いるべきか」という小文(ラッセル著作集第1巻『自伝的回想』みすず書房)のなかに,「死の恐怖を征服する最もよい方法-と少なくとも私に思われるもの-は,諸君の関心を次第に広汎かつ非個人的にしてゆき,ついには自我の壁が少しずつ縮小して,諸君の生命が次第に宇宙の生命に没入するようにすることである」とあるが,これはラッセル自身へのコトバでもあったと読める。しかし,死の恐怖に関しては,アインシュタインのほうが率直だった。彼は死の一年半前(74歳)に-動脈瘤のため余命が短いことをすでに知った時-,ある手紙(英語)で,「死の恐怖は自然が種(しゅ)の生命の保存のために用いる手段の一つ」であり,しかも,そういう理由づけはともあれ,死の恐怖は人間にとって「逃がれようがない(It cannot be helped)」と書いた(ホフマン『アインシュタイン』河出書房)。
自分の死を思うとき,恐怖を感ずる私の気持ちは,今なお,冒頭にあげたラッセルよりは湯川さんやアインシュタインのコトバに近い。にもかかわらず,数年前から私は,冒頭にあげたラッセルのコトバ(私が記憶するもの)への共感をも,かなり実感するようになってきた。これは,私が6年余り前に当時丸1つと5歳半の2児を私1人の手で養育する生活を始めたことと,この4,5年間に自分の体力の明らかな老化を感ずるようになったことのためのようだ。ちなみに,ラッセルも前記の「いかに老いるべきか」の末尾に,「年老いて生命力の減退と共に'ものうさ'がますなら,永遠の憩いという観念を受け容れやすくなるだろう」という意味のことを書いている。ラッセルは50歳近くなって2度目の妻ドーラと結婚し,55歳ごろドーラと共に「自由学園」(=羽仁もと子経営)に似た幼稚園兼小学校のようなものを設立し,以来7,8年間ドーラとの間の2児も含めてたぶん100名ぐらいの子どもの保育と教育に,彼自身も多少は直接にさえたずさわった(アラン・ウッド『バートランド・ラッセル』みすず書房)。アインシュタインは,最初の妻との間の2児に扶養費を送ると同時に2度目の妻との平凡な家庭で,妻とその亡夫との間の2人の娘を愛育した。子育てというものは,単に子のためだけのものではなく,親自身のためのものでもあり,育てる側の人自身の死生観の形成と深化に重要な役割を果たす。アインシュタインやラッセルにとってもそうだったようだが,私も含め世の多くの人々にとってもそうであろう。ただし,男でも女でも自分の血をひいた子をもつか否かは決定的なことではないと私は思うが。