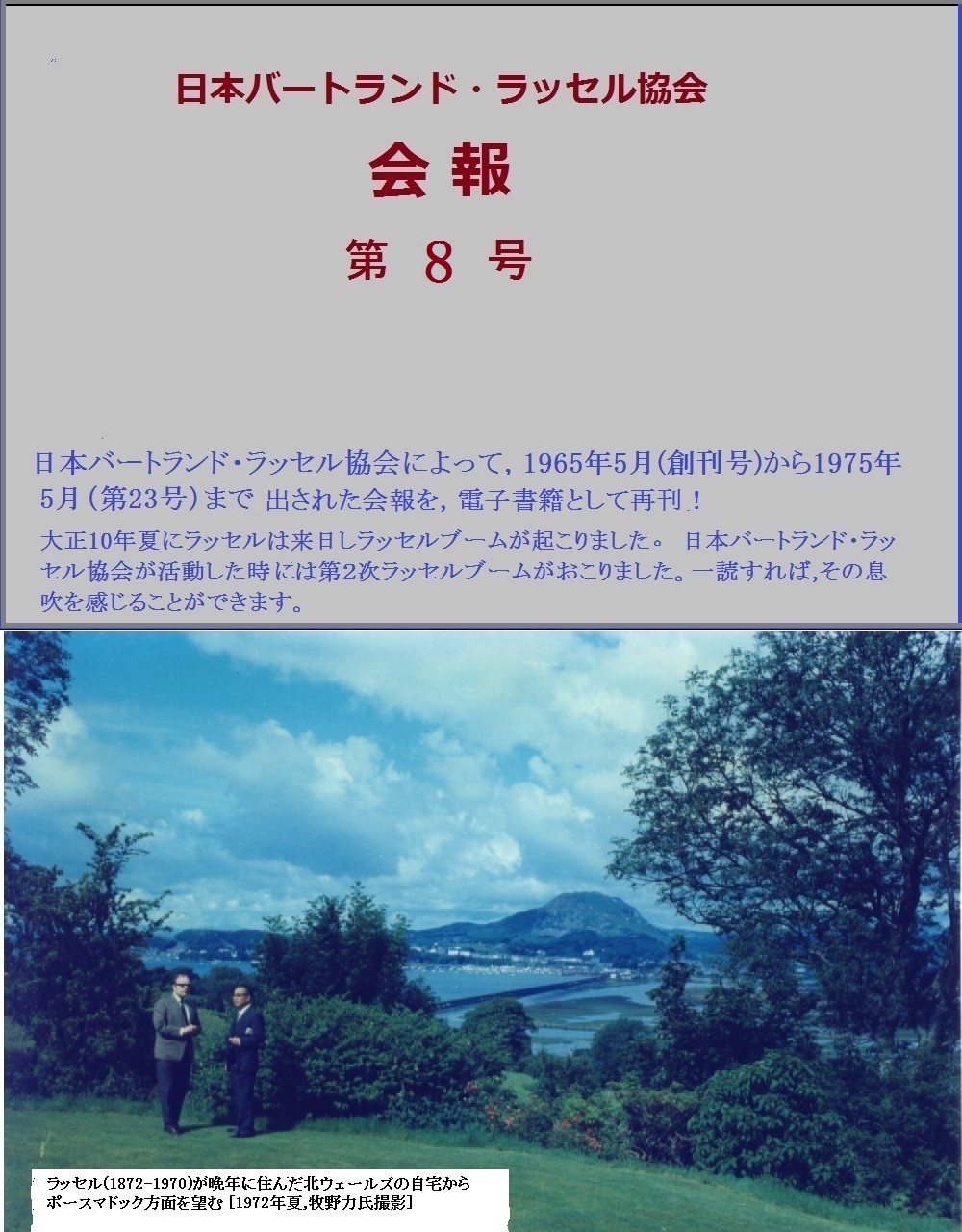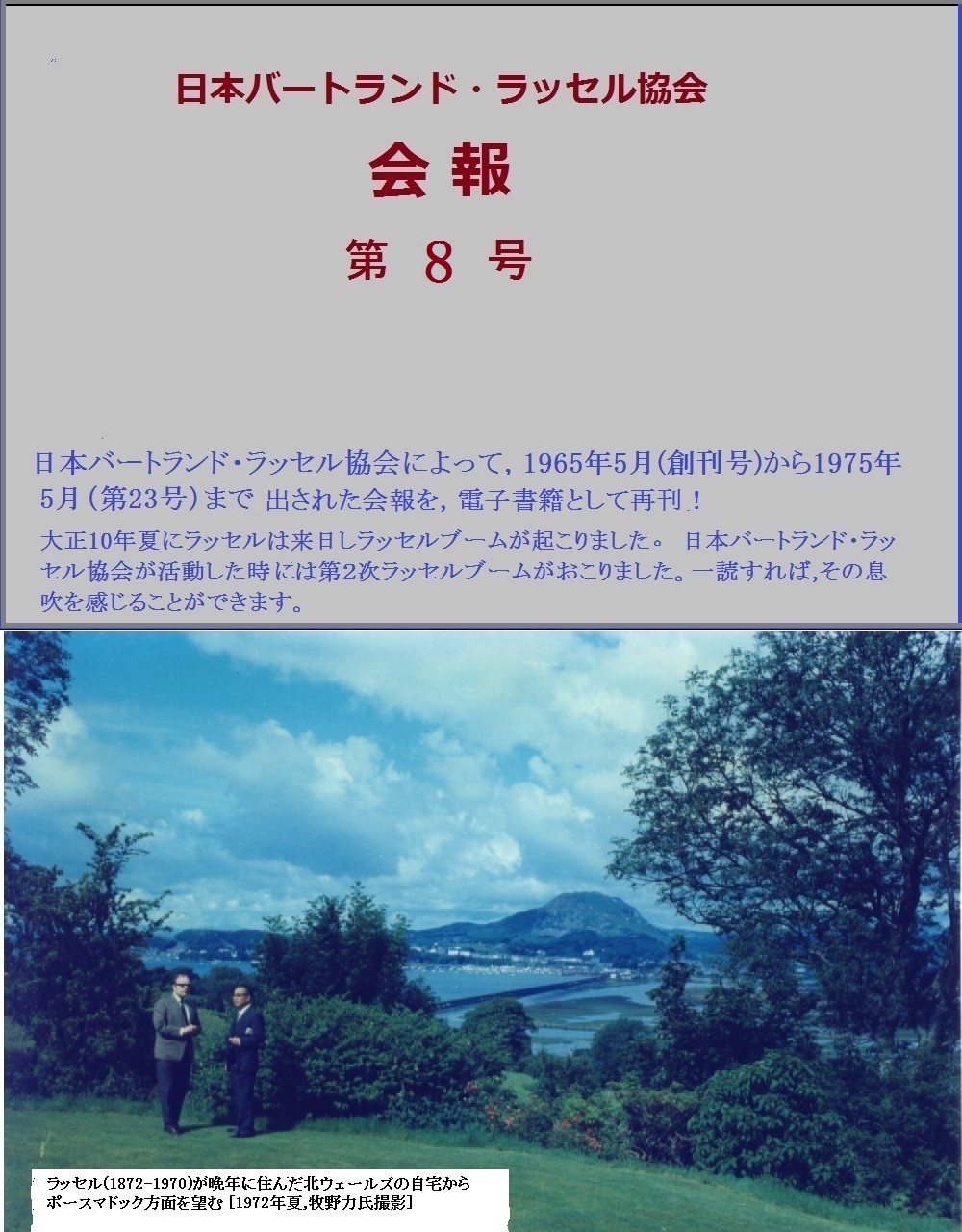関嘉彦「バートランド・ラッセルとイギリス社会主義」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第8号(1967年7月)p.4-5.
* 1967年5月18日,朝日新聞社講堂で開催された「ラッセル生誕95年記念講演会の要旨。
*(故)関嘉彦(1912年~2006年5月4日)氏は当時,東京都立大学教授。参議院議員も務める。
バートランド・ラッセルの時事問題についての発言は,衝動的なところがあって,私は必ずしも賛成ではないが,彼の根本思想には私も賛成するところが多い。特に私は,イギリス労働党の唱える社会主義思想の研究を若干してきたが,そのような社会主義-最近の言葉で云えば民主社会主義の思想には,ラッセルの経験主義的考えが多くの影響を与えていると思う。
従来イギリスの社会主義は,トーマス・ヒル・グリーン(Thomas Hill Green,1836- 1882:イギリスの哲学者)の理想主義哲学の上に立っているといわれてきた。日本では私の恩師河合栄治郎先生がそのように云っておられた。外国でも,例えば「イギリス社会主義の哲学的基礎」を書いたアダム・ユーラムなどはグリーンらの影響を強調している。確かにそのような面がある。例えば1920年代の労働党に大きな影響を与えたリンゼイ卿らは,グリーンの系統に立つ人である。しかしその面のみがイギリス社会主義ではない。他面において,経験主義哲学がイギリス社会主義のいまひとつの柱となっている。そしてその一人の代表がバートランド・ラッセルである。
ラッセルの自伝によると,彼が社会問題について本を書き始めたのは,第一次大戦中からである。もっとも19世紀の終りには,ドイツ社会民主党に関する本を書いているし,その頃からフェビアン協会に入り,ウェッブ夫妻と親交を結んでいた。また1907年には自由党から推されて下院議員の選挙に立候補している。しかし社会主義の立場からの政治参加ではなかった。
ラッセルの生涯に大きな影響を与えたのは,第一次大戦である。彼は,戦争中非戦運動のため投獄されたこともあるが,その時彼は,邪悪な政府が嫌がる民衆をひきずって戦争をおこすと考えていたのに,実際は,民衆が熱狂して戦争を支持しているのを見て,驚いた。そして戦争を防ぐためには,民衆の心を改めねばならぬし,それは社会制度の改革にまで至らねばならぬと考えて,社会主義を主張するようになり,労働党に入党した。当時,イギリスの自由主義者チャールズ・トレヴェリアン,アーサー・ポンソンビー,ノエル・バックストンらが相次いで労働党に入党したが,それらの人々は,大戦中非戦論であったマクドナルドやスノーデンらの独立労働党の主張に共鳴して社会主義者になった。ラッセルもそれらの人と同じく,第一に平和主義者であり,その目的実現の手段として社会主義に賛成した。ラッセルは1922年と1923年に労働党から下院議員選挙に立候補して落選した。この時当選していたら,或は彼の一生は政治家として終っていたかも知れぬが,幸か不幸か落選したおかげで,労働党には入党しつつも側面から社会主義や人生論や結婚問題,更には哲学の本などを書いて,イギリスの世論に多くの影響を与えることになった。
1930年代にイギリスの知識階級は,左傾し,ラスキやコールらはマルクス主義に好意をもち,フェビアン主義の親玉のシドニー・ウェッブはソ連共産主義を礼賛するようになるが,ラッセルは,熱烈な労働党支持者ではないにしても,基本的には,労働党の主張する漸進的社会改革の,立場を離れなかった。第二次大戦後は平和の実現という立場で多くの本を書いているが,労働党の外交政策と常に一致というわけではなかった。2年程前ヴェトナム政策で労働党の政策に不満をもち,遂に長年関係をもった労働党を脱党している。彼はしかし政治的には懐疑主義者で,労働党に入っていた時も,熱心な党員という程ではなかった。
ラッセルは哲学者であるが,彼自身の数理哲学と社会思想との間に直接の関係のないことは彼自身認むる通りである。しかし広い意味では大いに関係がある。彼は「哲学と政治」という論文の中で,プラトンやへーゲルの如き理想主義は,グリーンらの少数の例外を除き,絶対主義に結びつき,デモクリトスやロックの経験主義は民主主義に連なってきたが,それは理論的にも根拠のあることである,科学の理論は仮設的であるが,政治においても仮設的経験主義的立場に立つと絶対確実な善を主張し得ない,しかるに観念論の立場に立つと,哲学者が自分が好ましいと思う目標を歴史的必然という名目で他人に強制する狂信主義になる。自分の信念に科学的証拠を要求し,他方で人間の幸福を何よりも大切に思う人のとりうる哲学は,経験主義的自由主義(民主的社会主義とも矛盾しない)のみである,と述べている。ラッセルがマルクス主義に反対し,ソ連共産主義に反対するのも,それが狂信の上に立つ独裁政治であるからである。
それではどのような理論で彼は社会主義を基礎付けるかというと,第一次大戦後の「社会改造の原理」(Principles of Social Reconstruction, 1916)などで説いていることは,人間の衝動には2つある,すなわち有限なものに対する所有衝動と,精神的なものに対する創造衝動の二つである,徒らに衝動を意志で抑えるのでなく,創造衝動をのばすことで所有衝動を抑えるようにせねばならぬ。ところで資本主義は所有衝動を助長し,それが戦争の原因となっている,従って資本主義を廃止して所有衝動の働きを少なくし,貧困の心配なく創造衝動をのばしうる如く社会を改造せねばならぬと説いている。
しかし国家に産業上の権力を集中するような国家社会主義は,かえって個人の創造衝動を抑えるから反対である。政治的民主主義が政治権力を分散するように,産業上の権力を分散し,産業に働いている全従業員が産業経営に発言権をもつようなギルド社会主義を,最も弊害の少ないものとして主張する。
もっとも,このギルド社会主義の主張は,思想としては立派であっても実行不可能なので,彼も1922年以降はそれを放棄したが,根本の精神はその後も変っていない。多少のニュアンスの差はあるが,1930年代の「権力論」(Power, 1938)や,第二次大戦後の「倫理及び政治における人間社会」(Human Society in Ethics and Politics, 1954)の基本的テーマも,大筋においては同じである。
「倫理及び政治における人間社会」の中の彼の道徳哲学は広義の功利主義である。行為の正邪は,よい結果を産むか否かできまり,善悪は幸福をもたらすか否かできまる。公共の善は人類一般の幸福であり,公益と私益とを一致させるのが法律及び政治の任務である。ところで幸福は,欲求の満足にほかならないから,他人と共存しうる如き欲求を計ることが善である。その欲求の満足のためには,財が必要であるが私有財産の対象となるような財貨例えば食料などについては,その量が不足している限り,公平なる分配が望ましい,第二に私有されるものであり乍ら,誰でもが同じように獲得できないもの,名声とか権力如きものに対しては,その欲求を馴らしていかなければならぬ。例えば民主主義は権力欲をならす方法である。第三に,その所有が他人の享楽を減少させない如きもの,例えば健康,愛などは,誰でもが獲得できるが,ただ貧困などのため,それを獲得できないものに対しては社会保障制度で,その物質的障害を除いていかねばならぬ。すなわち,民主主義の上に立ち,社会保障制度やその他の富の平等化の方策をもつ如き,民主社会主義の社会が彼の理想である。
このラッセルの考えはイギリス社会主義の中でどのような位置をもつか。初期のイギリス労働党の社会主義がフェビアン協会の社会主義の影響下にあったことは正しい。しかしバーナード・ショウとかウェッブ夫妻は,哲学的関心は余りなかった人である。彼らは,過去において民主主義的方法で社会の漸進的改革が可能であったから,将来も可能であると考えて民主主義的改革を主張し,自由競争が非能率的であるという理由で産業の公有化を主張した。それはあくまで能率の点から考えた社会主義であり,人間の自由に対する適切な配慮を欠いていた。
その意味ではそのフェビアン社会主義は,イギリス伝来の自由民主主義の伝統から踏みはずす心配がある。そこに民族の本能的反逆として,初期のフェビアンより一世代遅れて登場したのがG.D.H.コールとかR.H.トーネーとかバートランド・ラッセルである。彼らが強調したのは人間の自由である。なかでもラッセルは,イギリス伝来の経験主義の哲学に立つ社会主義の理論を提供した。勿論この時代には,前述のように理想主義哲学の上に立つ社会主義者も活躍した。しかし,理想主義の陥り易い独断を防いで,民主主義的社会主義にひき戻したのは,ラッセルらの主張する経験主義に立つ考え方である。その意味でラッセルのイギリス社会主義への貢献を忘るべきではない。(終)