笠信太郎「智恵の構造」
『日本バートランド・ラッセル協会会報』第5号(1966年7月)pp.2-3.
* 1966年5月17日,ラッセル生誕94年記念講演会における笠信太郎ラッセル協会会長の講演要旨(『朝日新聞』掲載)* 講演をデジタル録音したもの<
|
|
「知識を得る」という。ところが、知恵については「知恵を出す」などという。知識というものは外にあるらしく、知恵は何でも私たちの内にあるかのようでもある。
その辺のところを、少しラッセルにうかがいを立ててみよう。ラッセルを読むと、随所に知恵のカケラが光っているような思いがする。そこで、おそらくは、どこからはいっても「知恵とは何か」をつかむことはそうむつかしくなさそうに思われるが、いまラッセルが10年ほど前に書いた小さな論文「知識と知恵」(knowledge and wisdom, 1954/要旨訳)を手がかりに、少しばかり考えてみる。ラッセルからは暗示を得ることとして、あとは、まずいながら、私自身の知恵のないところを、ご披露することになろう。
総合的な判断
知恵を考えてみるのに、4つばかりカナメの点があるようである。
第1は、ラッセルもいっている「比率(proportion)の感覚」である。ある事件、ある問題を理解するには、この問題を構成しているいろいろの要素の間のプロポーションを確実につかむことが肝心である。無知はこの比率を大きくゆがませる。高ぶった感情もまた、誤った比率を作りだす。感情をできるかぎりおさえて、各要素について、事実に即した、均衡のある全体の絵が、もしとらえられるならば、それを総合的な判断だといってよいとしよう。
この判断は、それでもまだ「知恵」などと呼ばるべきものではない。それどころか、いろいろの要素が手にはいっても必ず「わからぬ」部分があるものである。問題が大きければ大きいほど、この「不明」の部分は大きいであろう。それでも、私たちが、ここでどうでもこうでも一つの判断を下さねばならぬという場合には、その「不明」の部分のあることをふくめての「判断」になろう。しかし独断に落ちないよう、「懐疑」もいけないとなると、判断者の態度は、慎重の上にも慎重であるほかはない。いわゆる「科学的な気質」が望まれることになろう。
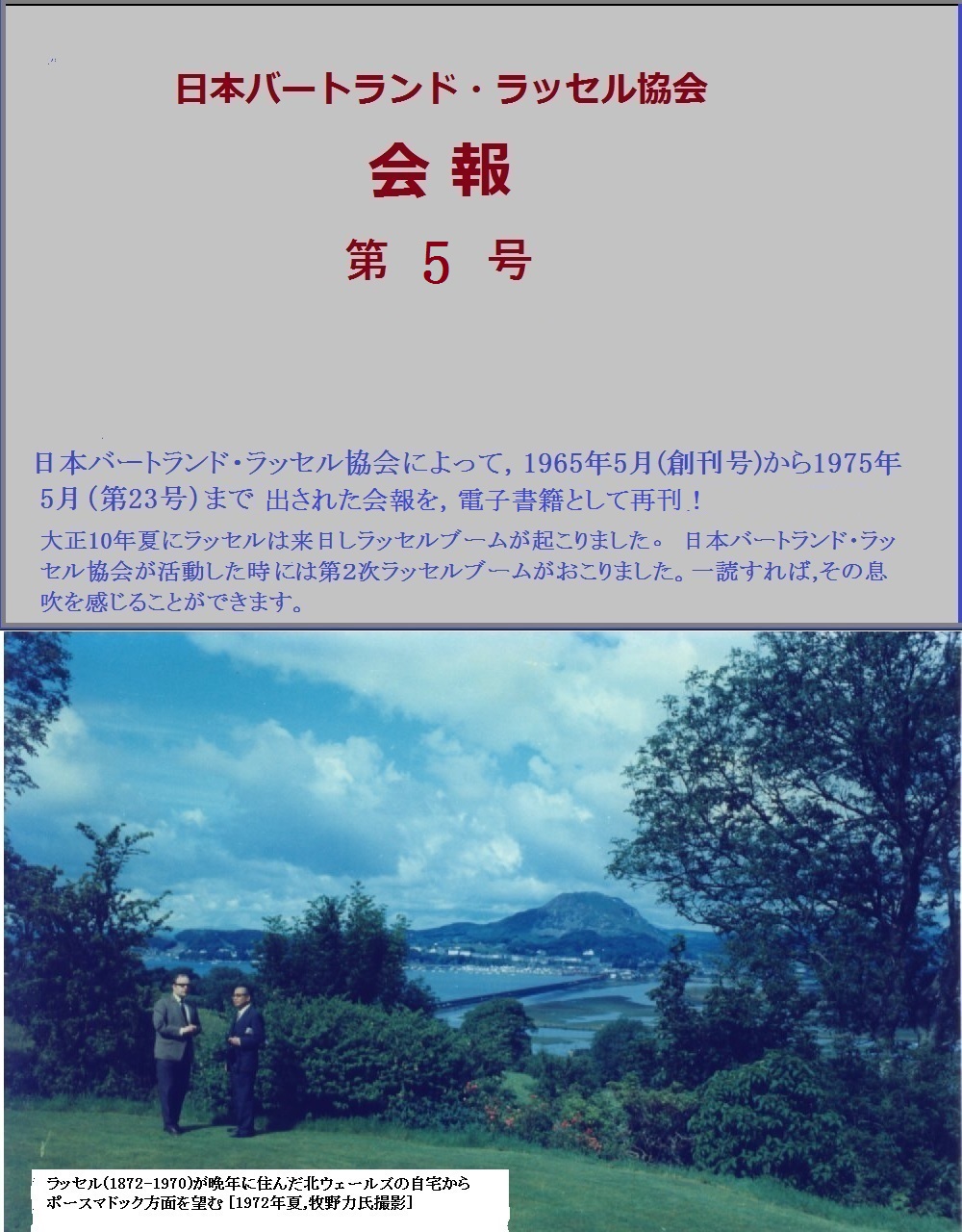 ラッセル協会会報_第5号 |
ところで「事実に即した」とか、妥当な「比率」(proportion)の感覚」とかいっても、それは一体、何を基準とするかという問題が、すでにそこには伏在している。
その基準は一体何であろう? これが第2のカナメの点になる。
この基準として一つの固定した観念とか理念とかをもち出すことは、ご免をこうむらねばなるまい。ナチズムでも、一つの観念の旗印を基準とした。基準は神であろうか。八百よろずの神があるのでは、いろいろの基準が出てこよう。
基準はきわめて普遍的ものを、事実上、私たちは日ごともちいているのではないか。むろん問題が小さかったら、「事業の成功」も基準たりえようが、問題が世界的規模にひろがっているような場合、それは人間的な自覚から生れるもの以外のものではありえまい。自分が生き、人も生かす。より高く、より良く、より豊かに生かすことだ。ヒューマンな目的というよりは、目的がヒューマンなことの高揚、それ自身ではあるまいか。
資治通鑑の著者、宋の司馬光(しばこう:1019-1086)が、あどけない子供のころ、大ガメに石をぶっつけて、噴出する水といっしょに中の子供のいのちを助けたという話、これが知恵だと、私も子供のころ教えられたものだ。知恵は、どこか人間自身と、その生命と、つながっていることを、この少年訓は暗示しているようだ。そうして現代の知恵は福祉国家から世界政府へと、人間の生命の擁護と拡充に、そのツマ先をむけているようだ。
経験との呼応
そうした人間の自分自身に対する自覚だということになると、第3のカナメは、いきおい、さっきの総合的な判断を、人間の生活の長い歴史的経験と相呼応させてみることであろう。過去の史上に浮ぶ幾多の事実が、私たちの総合的判断を、支えたり、修正したりしてくれる。ラッセルの判断の中に、いかに歴史的事実の援用の多いことか。
よい事例とはいえまいが、ベトナムの問題をいま目の前にすえてみる。共産と反共の争いというこの問題の一面は、16世紀の後半、カトリックとプロテスタントの両派が欧州のあらゆる人間を例外なくつかみ、その争いが国際的動乱としてアラシのごとく吹きまくったとき、イギリスをこのアラシから守りぬいたエリザベス一世、それから、宗教戦争の終結をはかって信教の自由を宣したフランスのアンリ四世を思い起させる。この知恵を思うと、いまの問題に知恵の来ることの、いかにおそいかを、思い知らされるではないか。
変化の承認
第4のカナメは、いつも私たちを押しつけている「いま」と「ここ」、その専制主義のいましめからできるかぎりのがれ出ることである。
もう一度、問題のベトナムに帰ろう。この紛争の中で、アメリカ当局の根本信念は、共産主義に「変化」は起らぬという立場のようだ。ところが共産主義の本山のソ連では、フルシチョフ以来一つの変化が出てきた。平和共存は、イデオロギーを固執するかぎりでは考えられないものである。さらに経済問題での考え方の徐々たる推移。他の共産国がモスクワを中心とせず、多中心的に移行したのは、イデオロギー専制からの重大な変化である。新興国は、こうして変ってゆくお手本を仰ぎながら、推移してゆくであろう。そうして、世界全体を見ると、非同盟と中立の国々の数が次第にふえ、次第に力を得てくる。イデオ ロギー的な対立の苛烈さは、次第に色あせてゆくように見えている。(右イラスト出典:B. Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953.)
ところで、1954年のジュネーブ、まだスターリン影響下の世界で、ダレス米国務長官がとった対抗手段には、まだ理由があった。ところが、それからの10年が「変化」の時代であった。変化に対応しないということに、降りてくるエスカレーターを下からのぼってゆくのと同じで、労苦が多く、効果がない。
阿片戦争では、上海も、チーフーも、15分間の戦闘で、事はすべて終った。当時の中国とイギリスとの対比は、いまのアメリカと北ベトナムとの力の対比とほぼ同じようなものであったろう。北爆一週間もすればギャフンと参っても不思議ではないはずだが、どっこいそうはいかなかった。世界の世論の多くが、この小さな国の味方にまわったからであろう。変化を見なかったアメリカは、問題の中に占める自分の側の「正義」の比率も見誤っていたとしか思えない。
支え手は人問
以上の四点、バラバラであって、全構造をしめつけるボルトがないではないか。その通りである。そして知恵は一つの統一である。たくさんの知識を一つの知恵の結晶へと結ばしめるものは、統一ある生きた人間であって、ある原理でも、理念でも、観念でもない。たとえその原理や理念が自分で作ったものであっても、それに身をゆだねてはならない。生きた人間こそ、知恵の支え手である。ラッセルの口ぶりをまねれば「星空がすばらしいのではなく、星空が私たち人間の知覚を通してもつ効果がすばらしいのだ」。(了)

