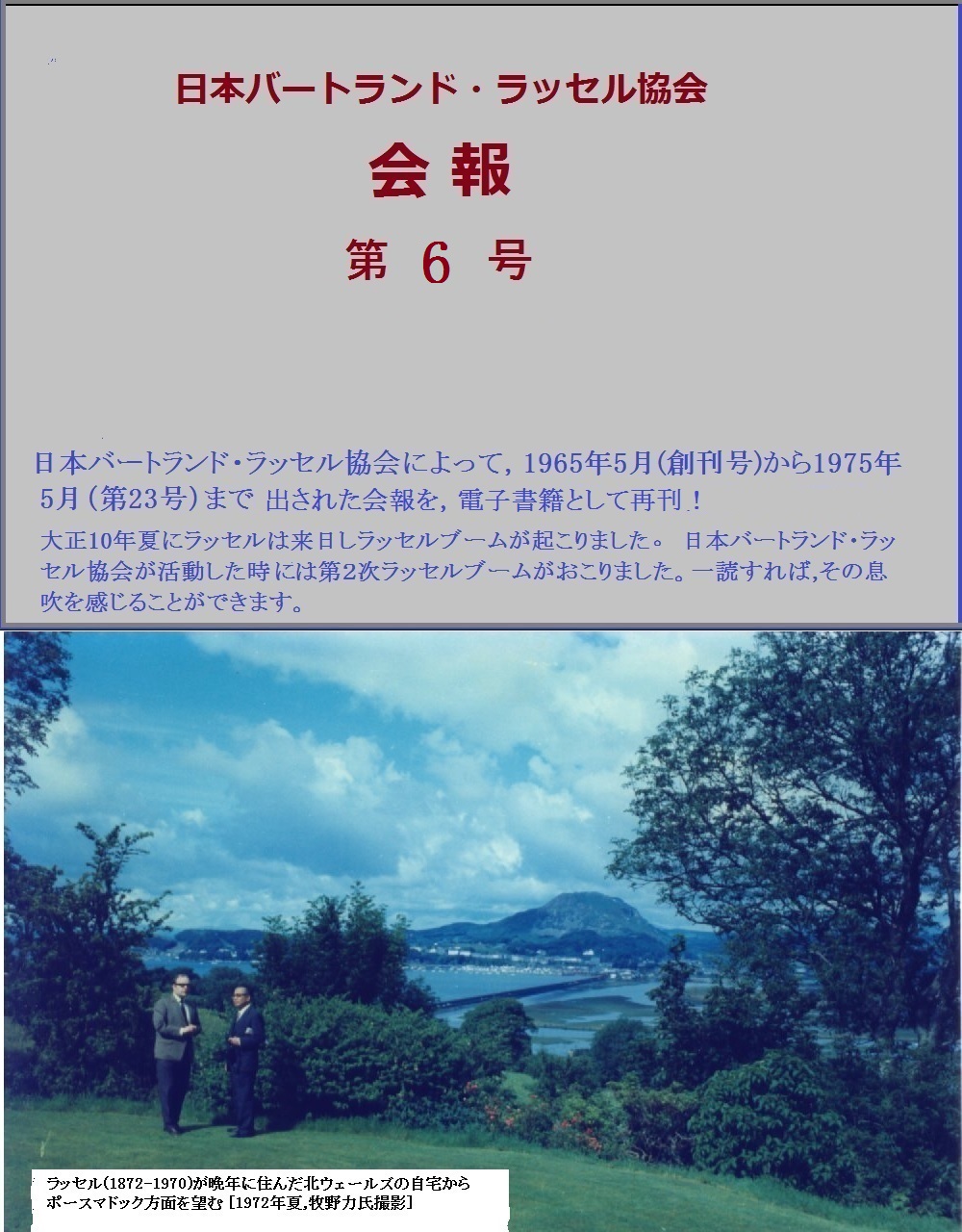 ラッセル協会会報_第6号 |
「もし、ラッセルの政治、社会的著作に歴史的法則の洞察に欠けるところがあるとすれば、それはほかならぬ彼の依って立つ分析哲学の帰結にほかならない。そこに見られるものは、科学と道徳にかんする頑固な二元論であり、人間を社会から切りはなし、孤立した現象としてしかとらえ得ない極端な個人主義的見解である。しかも、科学を単に手段にすぎないと見る彼の見解からは、およそ未来に対する希望など生れてくるはずもなく、そこにはつねに厭世観がつきまとっているのである。彼のとる倫理学説が、価値はすべて主観的情緒的なものによってきまるにすぎない、という見解に立っている以上、そこには客観的な指標は何も示されておらず、彼の言動は、判断の基準を求めるわれわれを徒らに迷妄に導いてゆくばかりである」


