(随想) 野阪滋男「懐疑論者バートランド・ラッセルの一側面- 政治的懐疑にみる」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第23号(1975年5月)p.17-18.
* 野阪滋男(のさか・ますお):現在、茨城大学名誉教授(2004年まで茨城大学人文学部教授)
* 懐疑論者の祈り<
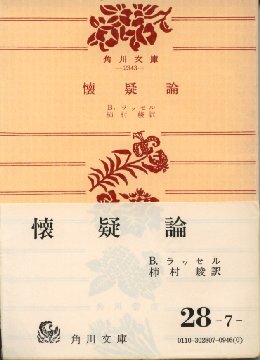 昨年(1974年)の秋、作家の遠藤周作氏は、新聞紙上に、「善魔について」と題する一文を寄せていた。一人よがりの正義感や独善主義を信奉する人を善魔と称し、その特徴を、自分以外の世界を認めず、自分の主義にあわぬ者を軽蔑し裁く点に求めている。「彼等はそのために、自分たちの目ざす『善』から少しずつはずれていく。自分自身でも意識しないうちに、彼等は他人から支持される善き人ではなく、他人を傷つけ、時には不幸にさえする善魔になっていくのである」(朝日新聞、昭49年10月21日タ刊)というのである。
昨年(1974年)の秋、作家の遠藤周作氏は、新聞紙上に、「善魔について」と題する一文を寄せていた。一人よがりの正義感や独善主義を信奉する人を善魔と称し、その特徴を、自分以外の世界を認めず、自分の主義にあわぬ者を軽蔑し裁く点に求めている。「彼等はそのために、自分たちの目ざす『善』から少しずつはずれていく。自分自身でも意識しないうちに、彼等は他人から支持される善き人ではなく、他人を傷つけ、時には不幸にさえする善魔になっていくのである」(朝日新聞、昭49年10月21日タ刊)というのである。
これを読んだ時、わたしは、ラッセルの『懐疑論集』に収められている「善人の及ぼす害」という評論を思い出したのである。彼はここにおいても懐疑的立場から、善・悪という概念に疑いを挾み、善人によってこそ流される害悪について言及している(東宮隆訳『懐疑論集』一八頁)。これにつき、今は多くを語れないが、これを政治の分野に関連づけてみると、ラッセルの以下の言葉は実に面白い。今日のわが国の政治の混迷を招いたのも、こうしたところにあるといえる。
ラッセルは言う。「子供というものは、言われたことをおとなしくきくと『善良』で、きかないと『しようがない』子になる。こんな子が成長して政治的指導者になると、まだ子供時代の考えをなくさずにいて、自分の命令に服従するものは『善良』だと定義し、これを無視するものは『悪い』と定義することになるのであろう。……『善』政はわがグループによる政治のことで、悪政は他のグループによる政治だ、ということにもなる」(東宮訳『権力論』二九五頁〕。
政治的指導者に善魔的人物が多いことを、ラッセルは見事に見抜いている。この善魔、自分の存在をおびやかす反対派を敵としてとらえ、社会の諸悪の根源はすべてこの敵にあると吹聴し、彼等に汚名を着せることにより、自らの存在の必要性と正統性を主張せんとする。それ故にのみ、この反対派の存在もまた必要となる。「われわれは敵を奪い去られることを好まない」とラッセルは人の心に潜む意識にも鋭いメスをいれている。こうした善魔の仕業によって、「英語を話す国民の大部分は、自分たちの悩んでいる病弊も、或る政党が権力の座につけば、いやされるであろうと、真実信じ」てしまう。もっとも、わが国のように議会政治が遅れているところでは、これほどまで政党に対し限りない関心と全幅の信念をもちあわせていないから、善魔の好計も水泡に帰すことになるかもしれない。
かくして、ラッセルは、彼一流の調刺のきいた言葉で、政治的悪党主義の効用を例証している。ある雑誌に載った日本の老政治家の言を引用しつつ、一九二〇年代のシナと日本とを比較している。シナでは政治家が汚職などで不正直であったために商人が政治家を信用できず取引の安全には自らの身を正さざるをえなかったのに対し、(当時の)日本では法的正義の錠があって、政治家は正直であったために商人が不正直にならざるをえなかった、という。
ラッセルは、正直な政治家につき、三つの類型にわけている。要するに、政治の分野でも、単に正直であるだけでは足りないのであって、それどころか「一番高い意味で正直な政治家でも、きわめて有害なことがある」とし、「愚鈍と無意識の偏見とは金銭ずくより大きな害を及ぼす」ことを鋭く指摘している。(東宮訳『懐疑論集』四一頁)
正直はたしかに、個人の生活においては善であり美徳であるかもしれない。しかし、それが社会生活、政治という分野でとらえられるとき、必ずしもこれを善とのみ言ってはおられない。民主主義社会では、ラッセルも言うように、「一見相反する方向に傾くような二つの性質の広く行きわたることが必要」であり、どこまでも、思想の自由市場を最大限に確保し、自覚ある国民が、その正統性と異端性を選択することが望まれる。その際、あまりにも物分かりのよい善魔がはびこる社会も、悪魔のはびこる社会と同様、あるいはそれ以上に、望ましからざる害悪をもたらすことを、懐疑論者ラッセルは見事に示唆している。(大学講師)

