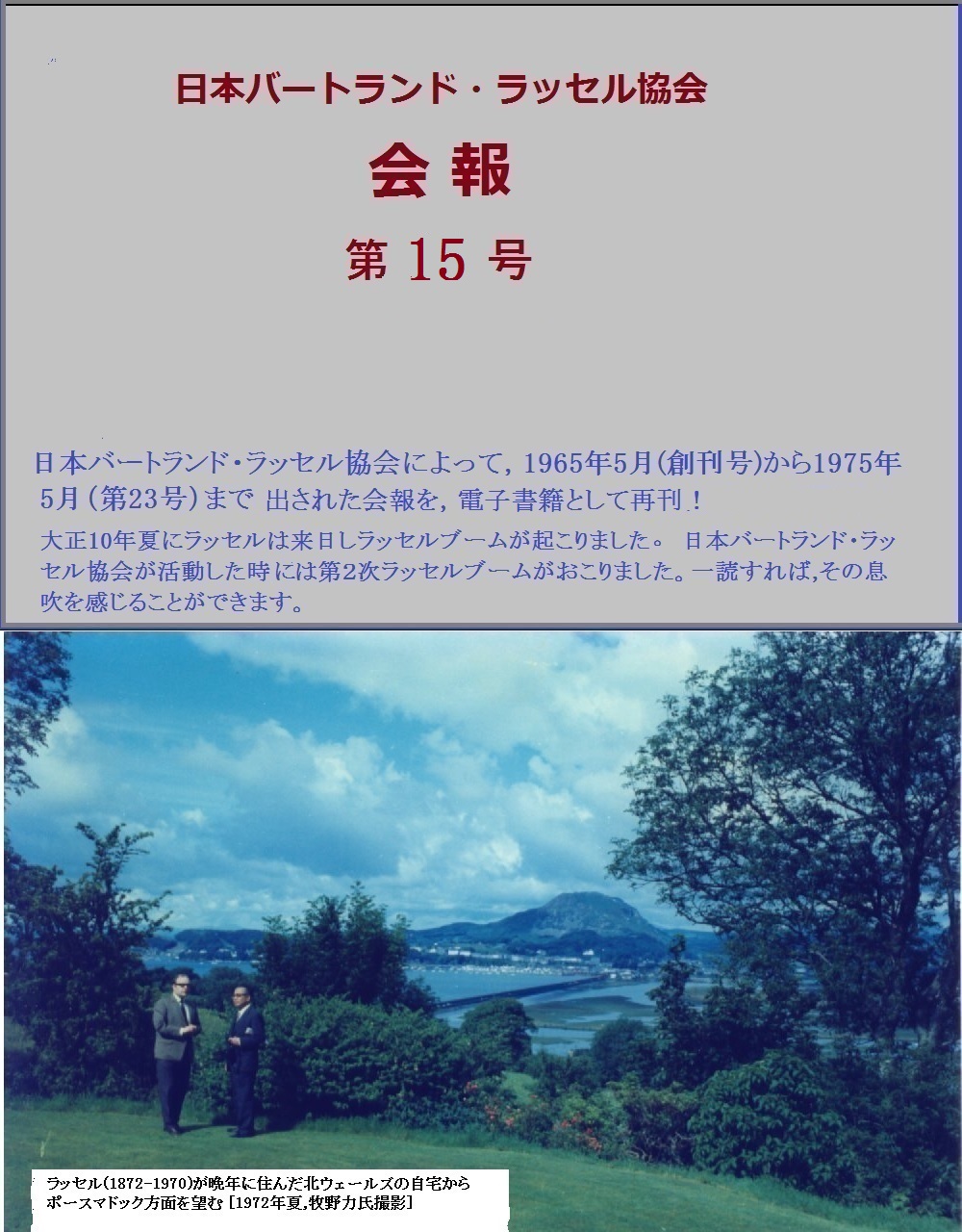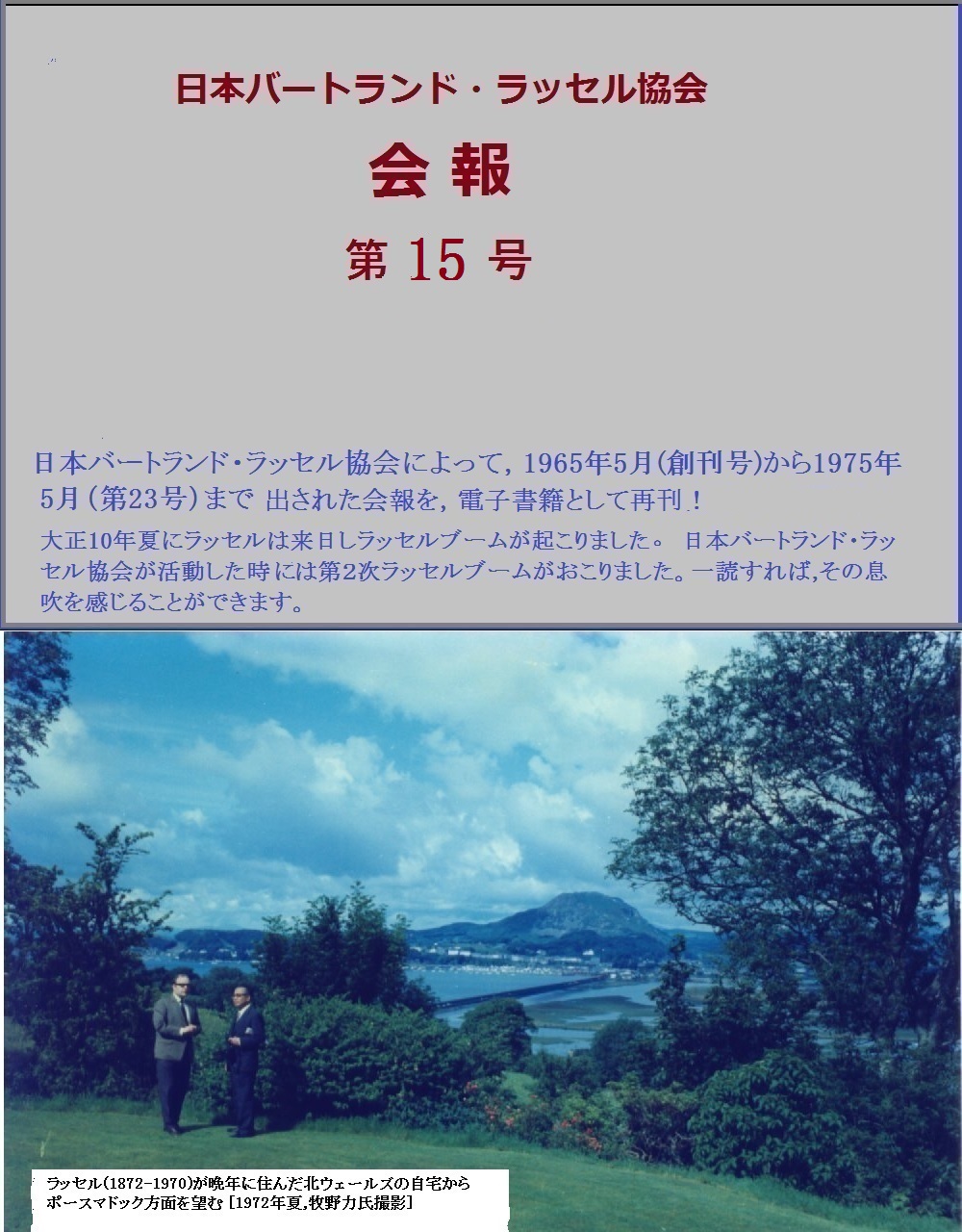永井成男「バートランド・ラッセルから学ぶ」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第15号(1970年5月)pp.5-6.
* 永井成男(ながい・しげお、1921~2005)氏は、東京医科歯科大卒及び早大文学部卒。執筆当時、東洋大教授、日本科学哲学会委員長。その後東洋大学名誉教授。<
ラッセルの訃報に接し、しばらくは信じられぬ思いであった。百才近い高齢ではあるが、万年青年のように、精神的、肉体的に衰えをみせぬラッセルの超人的な活躍ぶりから、百何十才まで元気で活動するラッセルのイメージが私の脳裏に焼付いていたからである。
本協会より、ラッセル追悼号に寄稿するようにとの依頼があったが、私は、ラッセルとは直接の面識はおろか、文通さえも交わしたことがなく、個人的には全く無縁の者であるので、科学哲学者としての私が、ラッセルの思想、人柄、実践から何を学び、また学ぼうとしているかについて、思い出や感想を述べて、追悼の言葉にしたいと思う。
私がラッセルの哲学と本格的に取り組むようになったのは、昭和23年の春頃からであった。早稲田大学の哲学科の卒業論文に、「論理主義における数の定義について」というテーマを選んだ私は、ラッセルの『数学の原理』と、ホワイトヘッドとの共著「プリンキピア・マテマティカ』に挑戦した。文字通りに「挑戦」のつもりだった。それまで、私は西田哲学や田辺哲学に傾倒し、特に、田辺元の数理哲学を通じて、ラッセルの論理主義に批判的な思想をいだいていたので、この線に沿って、論理主義の数の定義を批判的に詳細に検討しようと企てたのであった。卒論は四百字詰で四百枚の大論文となったが、意外な結果となった。ミイラ取りのミイラほどではないが、特に、哲学の研究方法上で、大転換を余義なくされた。記号論理学を使用する論理的分析法を採用しなければならないこと、西田、田辺哲学には、なお、維持すべき真理は含まれているが、それは論理的分析法によってのみ開発できると信ずるようになった。こうした立場から、私は、さらに、カルナップ等の論理実証主義、分析哲学に導かれ、西田、田辺哲学から学び得たものを生かしつつ、論理主義の数理哲学を修正発展させることが、私の生涯の哲学の研究課題の一つとなったのである。へーゲル的な形而上学の色彩の濃厚な西田、田辺哲学から、科学的な分析哲学に導かれる機縁をつくってくれたのが、ラッセルの数理哲学であったことは、私にとってこの上なく幸であった。ラッセル哲学には、古い伝統哲学の要素と新しい分析哲学の要素とが含まれているので、へーゲル的形而上学から脱却する媒介的な役割を果すことができたからである。
私のラッセルヘの関心は、彼の数理哲学や科学哲学にとどまらなかった。彼の社会・倫理思想からも、決定的と言えるほどの大きな影響を受けた。ラッセルの社会・倫理思想への関心は、理論的な側面にとどまらなかった。彼の個人的、社会的な実践活動に示される思想と行動との一致は、日本人にみられがちの立前と本音が一致しない二重構造に、公的、私的な憎悪感をいだいていた私には、素晴しい魅力であった。ラッセルの社会・倫理思想の影響下に、私は、一種の社会主義思想をいだき、実践するようになった。ラッセルと共に私に大きな影響を与えたカルナップの造語である「科学ヒューマニズム」(Scientific humanism)に、私なりの解釈を加えて、その社会主義思想を科学ヒュマニズムとよぶことにしている。それは、マルクス主義の社会主義ヒューマニズムが、とかく、個人主義ヒューマニズムを否定する全体主義的弊害が伴うのに対し、あくまで個人の自由を尊重する個人主義ヒューマニズムとの調和をはかる新しい社会主義的ヒューマニズムである。
マルクス主義が、未だに先進資本主義国において革命に成功し得ないのは、先進資本主義国において、かなり高度に個人主義ヒューマニズムが支配している現実を軽視する非現実的な思想だからであると感じている。マルクス主義の宿命的な教条主義は、今日の行動科学的な社会科学の科学性、社会工学的な社会政策の技術性を十分に生かしきれないでいる。社会主義者は、プロレタリアの不当に不利な階級的立場への愛情と、ブルジョアの不当に有利な階級的立場への憎悪から成るプロレタリア・イデオロギーの意識の点で、極左的でなければならないが、単なる極左的感情論理の非科学からは、革命は生れない。極左的情熱が冷静な科学の論理と融合するところに科学ヒューマニズムの新しい社会主義の道が開ける。この科学ヒューマニズムこそ、真の意味で新左翼であり、私は、ラッセルがこの科学ヒューマニズムヘの道を身を以て開拓、実践した典型的人物であると信じているので、生涯、彼から学ぶことをやめないに違いない。